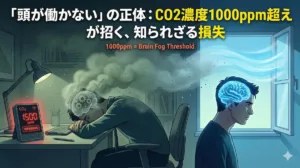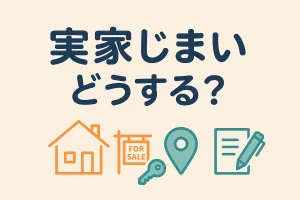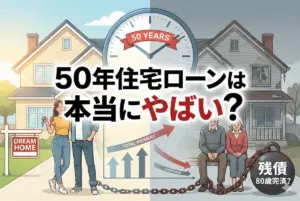相続時精算課税に「年110万円の基礎控除(=非課税で贈与できる枠)」が新しく導入されました。
これ、ひと言でいえば「相続時精算課税でも毎年110万円までなら贈与税がかからず、しかも相続時に持ち戻さない」という強力な使い勝手の改善です。
もともと贈与税の税金がかからない上限が年110万円だったのでそれに合わせた形ですね。
教育費や住宅購入の初期費用など、コツコツ支援したいご家庭にとって追い風になります。
なぜ注目されるのか。理由はシンプルで、これまでの相続時精算課税には暦年贈与のような「年110万円の非課税枠」がなかったため、少額の生活支援に向いていませんでした。
今回の改正で毎年の学費・塾代・頭金準備などに“使い分け”できるようになったからです。
相続時精算課税制度の基本
まずは相続時精算課税制度について基本をみていきましょう。
これまでの仕組みと課題(基礎控除がなかった)
相続時精算課税は、生前に多額のお金を移しても贈与時は原則非課税(特別控除2,500万円)、相続時に合算して清算する制度。
ところがこれまでには基礎控除が存在せず、少額の援助には向きませんでした。
この改正からこの穴が解消された、というのが今回のポイントです。
今回の改正のポイント:新設「年110万円の基礎控除」」
- 2024年1月1日以後の贈与分から、相続時精算課税でも年110万円の基礎控除を創設。
- 相続時の“持ち戻し”も、毎年の110万円分は対象外(=加算する価額は「贈与時価額−110万円」の残額)。
- すでに過去に相続時精算課税を選んでいる人も、2024年分以後は適用。
- ドナー(贈与者)が複数いる年は、110万円をあん分(按分)して使います(=受贈者のその年の110万円は合計で1枠)。
- その年の贈与が110万円以内なら申告不要。
- 相続時精算課税は一度選ぶと、その贈与者との贈与について暦年課税へ戻せない点は従来どおり。
(贈与者は原則60歳以上、受贈者は18歳以上の直系卑属=子・孫。条件等の詳細はタックスアンサー参照
補足:「110万円は“受贈者あたり年1枠”」です。
父と祖父の2人から同年に支援を受けても合計110万円が枠で、各贈与の金額比で按分します。
ここは誤解しやすいので要注意
贈与税の非課税枠との違い
贈与税は「年110万円非課税」が基本。
一方で2024年以後は、被相続人の死亡前7年以内の暦年贈与が原則相続財産に加算されるようになりました
従来3年→7年に延長、ただし4〜7年分の合計100万円は加算除外。
「コツコツ非課税で逃げ切る」効果は弱まりました
「生活資金援助の枠」としての意義
相続時精算課税での年110万円は、贈与税も相続時の加算もかからない“素の非課税枠”として使えます。
相続時精算課税を選択し、年間110万円以内の贈与を行えば贈与税・相続税どちらも発生しません。
教育費や住居関連の細かな費用など、使うたびに意味のある少額支援に相性ピッタリ。
教育資金にどう使える?
それでは具体的にどのように活用すればよいのかを考えて見ましょう。
使いどころのイメージ
- 塾代・予備校費・模試代・受験料などの年々発生する費用
- 大学の学費・入学金・教材費
- 留学費用の一部(授業料・住居費のサポートなど)
これらは年110万円の枠で支援すれば、申告も不要(その年の合計が110万円以内)でシンプル。
祖父母→孫の支援にも使えます(受贈者が18歳以上で相続時精算課税を選択できる関係にあること)。
「教育資金一括贈与非課税」との違い
教育資金には別途、「教育資金の一括贈与(最大1,500万円まで非課税)」があります。
こちらは金融機関で専用口座や管理契約を結び、受贈者が30歳未満、前年合計所得1,000万円以下といった要件があり、期間は2026年3月31日まで。
用途も教育関連費に限定され、使い残しや贈与者死亡時の課税にも注意が必要です。
まとまった進学費用を一気に渡す時に向く一方、日々の塾代などには相続時精算課税の年110万円枠が柔軟です。
住宅資金にどう使える?
次に住宅関連の場合です。
頭金づくり・初期費用の分担
住宅購入まで数年かけて頭金を作るなら、相続時精算課税の年110万円でコツコツ援助がしやすくなりました。
購入年に一気に大金を動かさず、家計の負担分を年ごとに支える使い方が可能です
※同年に複数の直系尊属から受ける場合は合計110万円枠を按分。
「住宅取得等資金の非課税制度」との違い・併用イメージ
住宅には別枠で「住宅取得等資金の贈与の非課税」(2024/1/1〜2026/12/31)があり、省エネ等住宅なら1,000万円、その他は500万円まで非課税。
購入(新築・取得・増改築)の対価に充てる資金が対象で、翌年3/15までの申告と要件書類が必要です。
既存の住宅ローン返済原資に充てるのは対象外と理解してください。
使い分けのポイント
・購入年:住宅取得等資金の非課税(〜1,000万円/500万円)でどんと援助。
・購入前後の年:相続時精算課税の年110万円で初期費用・引っ越し・家具家電など周辺費用をコツコツ。
メリットと注意点
メリットと注意点についてもみていきましょう。
メリット
相続時精算課税に年110万円の基礎控除が新設された最大のメリットは、教育費や住宅関連費のように毎年こまめに発生する支出に対して、贈与税も相続時の持ち戻しも気にせず支援しやすくなったことです。
年内の贈与総額が110万円以内に収まるなら申告も不要で、手続き負担がぐっと軽くなります。
祖父母から孫への支援といった世代をまたぐ資金移転にも使いやすく、実際の暮らしに寄り添った「生活資金援助の年枠」として機能する点が、家計の平準化やライフイベント準備に相性のよいポイントと言えるでしょう。
注意点
注意点はまず、相続時精算課税は“贈与者ごとに一度選ぶと暦年課税へ戻せない”というルールが従来どおり維持されていることでしょう。
どの贈与者についてこの制度を選ぶのかは、長期の贈与計画を見据えて慎重に決める必要があります。
次に、同じ年に父と祖父といった複数の直系尊属から贈与を受ける場合でも、受け取る側の非課税枠は合計で年110万円が上限です。
人数分に増えるわけではなく、各贈与額に応じて按分される点は誤解が生じやすいところです。
また、不動産を相続時精算課税で生前贈与してしまうと、相続時に使える小規模宅地等の特例(宅地評価の大幅な減額)が適用できなくなる可能性があります。
宅地の扱いは相続全体の税負担に大きく影響するため、資産の内訳次第では生前贈与よりも相続時の取得を優先するほうが有利なケースも少なくありません。
さらに、改正後の暦年贈与は持ち戻し期間が原則7年に延長されました。
相続時精算課税の活用がすべてのご家庭で“強い節税”につながるわけではなく、「税メリットはほどほど、家計支援の柔軟さが主役」という性格を理解したうえで活用するのが現実的です。
ケーススタディ
次にケーススタディを見ていきましょう。
A家|祖父母が孫の大学進学時に毎年110万円を援助
まず、A家の例です。
・目的:私立大学の学費・通学費・教材費をカバー
・設計:相続時精算課税を選び、毎年110万円の範囲で支援。合計が110万円以内なら申告不要。祖父と祖母の2人から同年に贈る場合は合計で110万円なので、例えば祖父60万円・祖母50万円のように按分。
・ポイント:教育資金一括贈与のような金融機関での管理契約は不要。用途自由度が高く、少額の継続支援に向く。大きく資金が要る学年だけは一括贈与制度を検討する、など併用の設計も可。
祖父母が孫の大学進学を見据えて、毎年の学費や通学費、教材費をサポートする場面を想像してください。
相続時精算課税を選択し、年110万円の枠の範囲で振り込んでいけば、その年の合計が枠内である限り申告は不要です。
祖父と祖母の双方から支援する場合でも、受け取る側の非課税枠は合計110万円なので、たとえば祖父60万円・祖母50万円のように按分して運用します。
入学年などまとまった費用が必要な年度は、教育資金一括贈与の非課税制度で“ドンと渡す”選択肢もあり、それ以外の年は110万円枠で“コツコツ支える”というハイブリッド設計が現実的です。
いずれの方法でも、贈与契約書や振込記録を整えておくと、後日の確認がスムーズになります。
B家|親が子の住宅購入頭金を数年間にわたり支援
次に、B家の例を見てみましょう。
・目的:3年後の購入に向けて頭金を積み上げ
・設計:購入までの3年間は各年110万円を相続時精算課税で支援。購入年は「住宅取得等資金の非課税」で省エネ等住宅なら最大1,000万円まで非課税枠を活用。ローンの返済資金は原則この特例の対象外なので、購入関連の対価支払いに充てる
・ポイント:購入年の申告・証明書類の準備(翌年3/15まで)を忘れずに。前後の年は110万円枠で引越し・家具家電・諸費用の補助もしやすい。
子どもの住宅購入を3年後に予定しているケースでは、購入までの各年に相続時精算課税の110万円枠を活用し、頭金や初期費用の準備を計画的に進められます。
そして実際に購入する年には「住宅取得等資金の非課税」を使って、対象となる対価(新築・取得・増改築の支払い)に大きく充てるのが王道です。
ローンの既存返済資金は原則としてこの特例の対象外である点に留意し、購入年には必要書類を揃えて期限内(例年は翌年3月15日まで)に申告します。
購入前後の年は110万円枠を家具・家電・引っ越し費用など周辺コストの補助に回すと、無理のない資金計画が描きやすくなります。
どんな家庭にメリットが大きい?
それでは、どんな家庭にこの制度のメリットが大きいのでしょうか。
まず、相続財産の規模が基礎控除内から軽く超える程度で、不動産比率が高すぎない家庭は、教育・住宅といった生活密着の支援を優先しながら、相続時の特例(たとえば小規模宅地等)との相性を個別に点検する価値があります。
次に、現役世代の教育費や住宅費の負担が重く、数年単位で山をならしたい家庭には、110万円の“年枠”が家計調整の強い味方になります。
最後に、祖父母を中心とした三世代の連携が取りやすい家庭では、「一括で大きく渡す制度」と「毎年の110万円枠」を目的・金額・タイミングで使い分けることで、過不足なく資金が届く設計がしやすくなります。
制度は便利になりましたが、資産構成や家族構成、将来の住み替えや事業承継の予定などはご家庭ごとに異なります
最終判断の前には、税理士に試算とシミュレーションを依頼し、税負担と生活設計の両面でブレないプランを固めておくと安心です。
よくある質問
次はよくある質問です。
Q. 相続時精算課税で110万円以内なら毎年“何に使っても”いいの?
A. 法律上、使途制限はありません(教育・生活・住居関連の生活支援として柔軟)。
ただし贈与の事実(贈与契約書・振込記録等)は残しましょう
Q. 110万円枠は“贈与者ごとに”ある?
A. いいえ。受けとり側のその年の合計で110万円です。
同年に父・祖父からもらうときは枠を按分します。
Q. 住宅取得等資金の非課税は、ローン返済にも使える?
A. 原則、購入(新築・取得・増改築)の“対価”に充てる資金が対象。
既存ローンの返済原資は対象外と理解してください。
Q. 宅地を相続時精算課税で生前贈与しても大丈夫?
A. 小規模宅地等の特例(相続時の大幅評価減)は相続や遺贈で取得した宅地が対象。
生前贈与した宅地には適用されません。方針決定前に必ず専門家へ。
まとめ
今回は「相続時精算課税に基礎控除110万円が新設|教育費・住宅費を賢く支援を受けよう」と題して相続時精算課税の基礎控除の話をみてきました。
2024年から相続時精算課税に年110万円の基礎控除が新設。
贈与税も相続時の持ち戻しもかからない“生活支援の年枠”が手に入り、教育・住宅のコツコツ支援が現実的になりました。
教育資金は「一括(〜1,500万円)」と「毎年110万円」の使い分けで無駄なく、住宅資金は「購入年=住宅取得等資金非課税」「前後の年=110万円枠」の二刀流が王道。
ただし、戻せない選択・按分ルール・宅地特例の扱いなど落とし穴もあります。
確実に実施するなら税理士と確認しながら、自分の家計事情・資産構成に合う設計にしましょう。