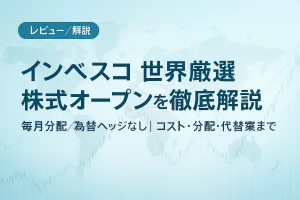またまた、新しい投資信託が登場します。
米国の超大型グロース株だけに“10社均等”で投資するという「ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>」です。
名前のとおり、アメリカのグロース株の時価総額上位10銘柄に等金額で投資をするというかなり尖った商品となります。
今回は新たに登場した「ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>」について詳しく見ていきます。
ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>の概要
まずは「Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)」の概要から見ていきましょう。
| ファンドの名称 | ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし> |
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
| ベンチマーク | Solactive US Growth Mega 10 Select |
| 設定日 | 2025年11月4日 |
ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド<購入・換金手数料なし>はSolactive US Growth Mega 10 Selectとするファンドです。
Solactive US Growth Mega 10 Selectってあまり聞き慣れないと思いますが、主に米国市場に上場するグロース(成長)株のうち、原則として時価総額上位10銘柄を選定し、等金額で投資する、Solactive社提供の株価指数です。
ポイント
・10銘柄均等なので、1社あたり約10%ずつの比率からスタート。
・四半期リバランスで“勝ちすぎた銘柄”の比率を定期的に戻す。
・構成が常に10銘柄とは限らない(スピンオフ等があるため)。
手数料
次に手数料を見ていきましょう。
信託報酬率
年0.385%(税込)。
となっています。
似たコンセプトの商品と比較して低めの手数料となっていますね。(すべて投資対象が違いますので参考程度ですが)
一歩先いく USテック・トップ20インデックス:年率0.495%(税込)
米国大型テクノロジー株式ファンド(マグニフィセント・セブン):年率0.594%(税込)
iFreeNEXT FANG+インデックス:年率0.7755%
Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式):年率0.10725%程度(税込)
購入時手数料・信託財産留保額・為替ヘッジ
すべて
なし
となっています。
どこで買える?取扱金融機関とNISA対応
次にどこで買えるのかを見ていきましょう。
取扱販売会社
ニッセイのニュースリリースでは、
マネックス証券
楽天証券
イオン銀行
SBI新生銀行
が掲載されています。
スタートではこの4社からの取扱となりそうです。
SBI証券についてはリリース時点で記載なしです。
ただし、ニッセイアセットマネジメント株式会社の商品は多くの証券会社で取扱がある傾向にありますので、徐々に増えていくものと思われます。
NISAの対応は?
NISAの成長投資枠の対象と明記されています。
※販売会社により取り扱いが異なる可能性あります。買付先の画面で必ずご確認ください。
「10銘柄均等」の狙いと、メリット・注意点
次にこの商品の狙いとメリット、注意点などを確認しておきましょう。
メリット:物足りない“広さ”より、狙いを絞る潔さ
一番大きいのがAI・プラットフォーマー中心の米国超大型グロースに“ド真ん中”で乗ることができるということでしょう。
ここ数年の値動きは抜群となります。
また、均等配分により、「1社の時価総額が巨大すぎて指数が歪む」現象を一定程度ならすこともできます。
デメリット、注意点
次に注意点です。
10銘柄に賭ける集中リスクと為替影響です。
わずか10銘柄なので、セクターやテーマの偏りは大きくなりがちです。
メリットにも書きましたが、AI・プラットフォーマー中心の米国超大型グロースとなります。
そのため、値動きもかなり似ているんですよ。
大きくコケる可能性も秘めています。
また、為替ヘッジなしゆえ、円高局面では基準価額の逆風になりえます。
さらに信託報酬0.385%は広く分散する低コストインデックス(S&P500等)よりは高め。
意図して“狭く深く”に払うコストと捉えられるかが分かれ目となりそうです。
競合商品との比較
ここ数年、アメリカ株特にAIセクターの株が上がっていることもあり、似たコンセプトの競合商品がたくさん出ています。それらとの比較をみていきましょう。
ひと目で分かる要点
まずは要点を比較してみましょう。
ニッセイ・S米国グロース株式メガ10(愛称:メガ10)
- 投資先:米国の超大型グロースから上位10社
- 配分:等ウェイト(10%×10社)
- 銘柄数:10(入替あり)
- リバランス:年4回(3/6/9/12月)
- コスト:年率0.385%
Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式)
- 投資先:S&P500の時価総額上位10社
- 配分:時価総額加重(勝ち組の比率が自然に肥大)
- 銘柄数:10(S&P側の入替に準拠)
- リバランス:指数ルールに依存(加重は常時変動)
- コスト:年率0.10725%
一歩先いく USテック・トップ20インデックス
- 投資先:米国のテック関連大型20社(ETF: Global X 2244に投資)
- 配分:修正時価総額加重
- 銘柄数:20
- リバランス:年2回
- コスト:年率0.495%(投信0.0825%+組入ETF等の経費を合算の見え方)。
iFreeNEXT FANG+インデックス
- 投資先:ICE FANG+ Index(米大型テック+近縁グロース計10銘柄)
- 配分:等ウェイトが基本
- 銘柄数:10
- リバランス:指数ルールに準拠(定期見直し)
- コスト:年率0.7755%
米国大型テクノロジー株式ファンド(マグニフィセント・セブン)
- 投資先:M7の7社(AAPL/MSFT/NVDA/GOOGL/AMZN/META/TSLA)
- 配分:等ウェイト(半期ごとに等分へ)
- 銘柄数:7(基本固定)
- リバランス:年2回
- コスト:年率0.594%
5本ともかなり似ていますが、投資先と配分、コストが違いますね。
どう選ぶ?――“母集団×配分×濃さ”の三択整理
かなり似たコンセプトとなりますので、難しいですが、選び方のポイントは以下となります。
勝者に素直に
勝者に素直に乗りたいならTracersが有力です。
S&P上位×時価総額加重で勝者の比重が大きくなります。
今ならNVDAの伸びをダイレクトに取りやすいが、1社偏重リスクは受け入れる前提。
また、超低コストが強み。
テックを厚めに
テックをより集めにしたいならUSテック・トップ20(テック限定×20銘柄)。
修正時価総額加重でこちらも“勝ち組”の比率が乗りやすい。
コストは中位。
均等に投資
均等に投資ししたいならメガ10/FANG+/M7(等ウェイト系)。
3つの投資信託の違いのポイントは以下。
・メガ10=グロース上位10を四半期で等分に戻す(入替あり)。濃いが分散は10社。
・FANG+=“看板10社”の等ウェイトでテーマ性が明快(指数固定感が強め)。
・M7=最も濃い7社固定。分散は最薄、相場の波もダイレクト
選び方のまとめ
選び方をまとめると以下のような感じですね。
(1)母集団の違いで“何を持つか”が変わる(S&P上位 vs テック限定 vs M7固定)。
(2)配分ルールで“動き方”が変わる(時価総額加重=伸びに乗る/等ウェイト=偏りを戻す)。
(3)濃さ(銘柄数)でブレ幅が変わる(7社→10社→20社)。
(4)4本とも為替ヘッジなし。円高時は逆風になりやすい点は共通。
まとめ
今回は「米国トップ10社に集中投資。ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド徹底解説」と題して新しい投資信託についてみてきました。
広く薄くでは届きづらい“中枢の成長”を、10社均等×四半期調整で素直に取りに行くのがメガ10の本質です。
万能ではありませんが、役割を理解してポートフォリオに置くなら、NISAの成長投資枠でも面白い選択肢になります。
似たコンセプトの商品も増えてきていますので、最終的には、自分のリスク許容度と他の保有資産との相性で判断しましょう。