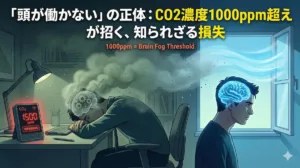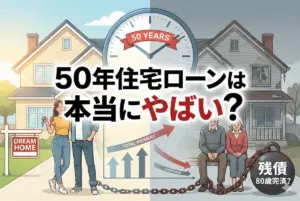梅雨や真夏のジメジメ対策として、まず思い浮かぶのが「エアコンのドライ(除湿)運転」と「家庭用除湿機」。
しかし実際には「何がどう違うのか?」を正しく理解している人は意外と少ないもの。
本記事では 「エアコンの除湿と除湿機の違い」 をキーワードに、性能・電気代・使い分けのポイントを徹底解説します。
再熱除湿や夏型結露などちょっとマニアックな情報も入りますが、家電マニア歴20年の筆者が噛み砕いて説明するのでご安心ください。
エアコンの除湿と除湿機の違い
まずはエアコンの除湿と専門の「除湿機」の違いから見ていきましょう。
同じ除湿なんですが結構違うんですよ。
方式と仕組み
| エアコン(ドライ) | 除湿機 | |
|---|---|---|
| 主目的 | 室温調整+湿度低下 | 湿度低下(衣類乾燥) |
| 水分回収 | ドレン管で屋外に排水 | タンク or 連続排水 |
| 風量 | 冷媒方式で大風量 | 小~中風量(静音設計も) |
| 消費電力 | 再熱除湿>弱冷房除湿 | デシカント>ハイブリッド>コンプレッサー |
一括りにエアコンの除湿と専門の「除湿機」といっても機種によりかなり違いがあります。
まず、一般的なエアコンの除湿(ドライ)は「弱冷房」と同様。
エアコンはもともと「冷房」が本業。
その副産物として空気中の水分を結露させて排出しているに過ぎないんですよ。
だから除湿なのに寒くなってしまうという現象が起こりがちです。
その対策として「再熱除湿」タイプというのもあります。
一方、専用の除湿機も機種によって除湿の仕方が違います。
大きく分けてデシカント式とコンプレッサー式があります。
高額機種だと両方の方式が使える形になっています。
デシカント式とコンプレッサー式の違い
詳しくまとめると以下のとおりです。
| 比較項目 | デシカント式(ゼオライト式) | コンプレッサー式 |
|---|---|---|
| 除湿の仕組み | 吸湿剤(ゼオライト)が水分を吸着 → 内部ヒーターで温めて水分を気体化 → 冷却器で凝縮しタンクへ | 冷媒で空気を冷却し、結露した水分をタンクへ排水(エアコンのミニ版) |
| 得意な季節 | 気温が低い冬でも能力が落ちにくい | 気温が高い夏ほど効率アップ(室温20 ℃以下だと性能低下) |
| 排熱・室温への影響 | ヒーター熱で室温が2〜3 ℃上昇しやすい | 排熱が少なく、室温上昇は小さい |
| 消費電力 | 300〜700 W前後(ヒーター分が大きい) | 150〜350 W前後(冷媒コンプレッサーのみ) |
| 運転音・振動 | ファンのみで静か(40 dB台~) | コンプレッサー振動でやや大きめ(45〜50 dB台) |
| 本体重量 | 軽量モデルが多い(5〜7 kg) | 冷媒・コンプレッサー搭載で重め(10〜15 kg) |
| メンテナンス | フィルター清掃のみ | フィルター清掃+年1回の冷却フィン掃除推奨 |
| 主な用途 | 冬場の結露・カビ対策、寝室の静音運転 | 夏の部屋干し、広いリビング・高湿度空間 |
ざっくりいうと梅雨〜夏のカラッと速乾派 → コンプレッサー式がおすすめ。
高温多湿ほど高効率&省エネで排熱が少なくリビングに置きやすいです。
ただし、室温15 ℃以下だと霜取り運転が増え、能力&電気代ともにロスします。
オールシーズン派はデシカント式がおすすめ
外干しできない冬場でもパワフル。静音で夜干し向き。
ただし夏は室温が上がるので冷房併用が前提って感じですね。
高めの機種だと両方の仕組みが使えるハイブリット式というのもあります。
再熱除湿とは?
再熱除湿は「一度冷やして水分を取り、その空気をヒーターで再加熱して室温を保つ」高度なドライ運転。
- 長所:室温を下げずに快適。梅雨寒・冬の乾燥対策に◎
- 短所:ヒーター使用で電気代が高い
ちなみに「再熱除湿」は三菱、日立の比較的高額機種などに搭載されています。
ダイキンなど他のメーカーも上位機種だと再熱除湿としては言ってないけど「冷えすぎない除湿」として似た仕組みを導入していたりします。
エアコンで除湿をしたい方は「冷えすぎない除湿」の機能はついていた方が良いでしょう。
除湿量の違い
一番違うのは実際の除湿量かもしれません。
例えばうちも使っているコンプレッサー式除湿機の上位モデル(三菱「MJ-PV250SX」など)は 1日24 .5L 以上を回収。
30畳クラスのリビングでも対応可能です。
ジメジメとした季節だと1時間もつけておくと数リッターの水が貯まっててびっくりするんですよ。
エアコンの除湿量は能力2.2 kWクラスでおおむね0.5〜1 L/h
除湿量のスペックだけ見ればそれほど差がない感じですが、エアコンはある程度冷えると稼働しなくなったりしますし、寒くなりすぎるので除湿メインで考えると除湿機にかなり部があります。
電気代の違い
電気代も比較してみましょう。※機種によりかなり違いますので参考程度です。
エアコン除湿の電気代
| 運転モード | 1時間 | 1日(8h) | 1か月(30日) |
|---|---|---|---|
| 弱冷房除湿 | 約 8〜13円 | 約 64〜104円 | 約 1,920〜3,120円 |
| 再熱除湿 | 約15〜25円 | 約120〜200円 | 約 3,600〜6,000円 |
除湿機の電気代
| 方式 | 1時間の目安 |
|---|---|
| コンプレッサー式 | 約 3.9〜12.4円 |
| デシカント式 | 約 9.1〜15.8円 |
| ハイブリッド式 | 約10.0〜20.5円 |
夏場はエアコン弱冷房除湿の方が安い場合も。
ただし再熱除湿は高コストです。
冬場〜梅雨の衣類乾燥はコンプレッサー式除湿機がエコって感じですね。
個人的には湿気が気になる時は専用の除湿機で一気に除湿してしまうのが好きですね。
夏型結露とエアコンの落とし穴
エアコンで除湿をする場合に気をつけたいのが夏型結露です。
夏でも窓や壁、壁の中がビショビショになる「夏型逆転結露」。
外気温30 ℃以上で湿度高めという日本の夏で、室内を24 ℃以下に冷すと発生しやすいと言われています。
断熱性の高い新築ほど要注意。
特に再熱除湿でないエアコンで長い間、低い設定温度でエアコンを付けたり、除湿をすると夏型結露になりやすいんですよ。
うちも引き渡し時にこの話を注意されています。
とくに新築1年〜2年の間は基礎コンクリートや木材から水分が出ているそうなので、湿度高めなんですよ。
だからより夏型結露が起こりやすくなっています。
見えない壁の中で結露が発生しまくり、カビだらけになった家なども実際にあるそう。
除湿をするときに室温を下げ過ぎないように気をつけましょう。
最近、断熱性の高い家だと1台のエアコンを24度設定にして風量弱運転で家中を冷やすみたいなやり方が流行っています。
電気代だけを考えれば非常に効率が良いのですが、夏型結露はちょっと怖い気がしますね・・・
除湿機の選び方のポイント
それでは除湿機を買う際のポイントを見ていきましょう。
用途を明確に
部屋干し or 部屋全体の湿度管理か
除湿方式を選ぶ
前述したように除湿方式によってかなり用途が異なります。
それを踏まえて選びましょう。
- 梅雨、夏メイン→コンプレッサー式
- 冬も使う→デシカント式
- オールシーズン&電気代重視→ハイブリッド式
除湿量(L/日)
除湿量も機種によって異なります。
一般的な目安は
部屋の畳数×0.5〜1L
ですね。
例えば18畳のリビングなら9L〜18Lくらいはほしい感じです。
タンク容量 & 連続排水
タンク容量も確認しておきましょう。
容量が少ないとこまめに水を捨てないといけなくなります。
機種によってはホースを繋いで連続排水できるものもあります。
その他機能
衣類乾燥モード、チャイルドロック、空気清浄機能、など必要に応じて機能を確認しましょう。
また、寝室などで使うなら音もチェックしておきましょう。
私が選んだ機種
ちなみに前述したようにうちは除湿機として評判の良い三菱製を選びました。
容量も多く、インバーターなので電気代も比較的低め。
コンプレッサー式ですが、冬も使える仕組みなのがGOOD
まとめ
今回は「エアコンの除湿と除湿機の違い|除湿量・電気代・再熱除湿・夏型結露対策まで完全ガイド」と題して除湿について考えてみました。
まとめると
って感じですね。
この記事が 「エアコンの除湿と除湿機の違い」 を理解し、最適な一台を選ぶ助けになれば幸いです。
快適でカラッとした夏をお過ごしください!