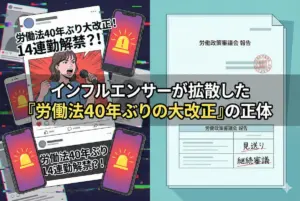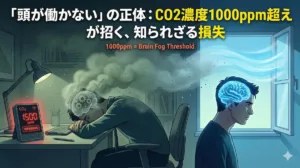先日、隣地の土地所有者からの依頼を受けたという「土地家屋調査士」の補助者を名乗るものが訪ねてきました。
どうやら隣の土地の測量をするのに境界立会をするので参加しろって話のようです。
しかし、こちら側がお願いした話でもないのに非常に横柄。
境界立会をするのは義務との主張で、こちらの予定も聞かずに日時も指定もしていきました。
非常に腹がたったので境界立会について調べてみました。
同様な方のためにその結果を残しておきましょう。
結論:境界立会に法的な参加義務は原則ない。
まずは結論から見ておきましょう。
境界立会は、隣接地の境界(筆界/所有権界)の確認のために行う現地確認です。
基本的に法的な参加義務はありません。
所有者の協力は慣行的に求められますが、出席・署名押印は任意という扱いが実務上一般的です。
受けるメリットと受けないデメリット
いっぽう、受ける合理的メリットとして「自分の土地の境界認識が明確になる」「測量成果(図面)を得られる」「将来の売却・改築での不確実性が減る」などが挙げられます。
依頼側の費用負担で測量が進み、結果的に自分の資産価値の不確実性が下がる点は看過できません
受けないデメリットとしては隣地の所有者との関係性悪化が挙げられるでしょう。
境界立会をしないと売却することもできないケースがあるんですよ。
ちなみに私のケースは隣地の所有者は会ったこともありませんし、そもそもどんな人かも知りません。(名前すら知らないです)
揉めるようなややこしい境界でもないんですけどね。
「義務ではない」根拠と“登記実務のいま”
それでは義務ではない根拠を見ておきましょう。
登記所が常に「隣接地の立会・署名」を要求するわけではない
法務省は表示登記の実務で、実地調査や既存資料から筆界の確認が可能な場合は、隣接地の筆界確認情報の提供を求めない扱いを明確化しています。
したがって「立会いがない=直ちに手続不能」とは限りません。
「協力が事実上の近道」になるケースも
例えば分筆・地積更正等の登記や売買前の確定測量では、隣接所有者の協力があるほうがスムーズです。
相手が用意する測量成果を共有でき、将来の係争予防にも資するため、費用負担なしで自分も恩恵を受ける側面があります。
横柄な土地家屋調査士への「上手な受け方・断り方」
うちのケースでは境界や境界立会の有無が問題ではなく、横柄な「土地家屋調査士」の補助者の態度が問題でした。
その点についても考えてみましょう。
身分証の提示を求める
まず、その「土地家屋調査士」及び、その補助者という人物が本当に存在するのか、詐欺ではないのかの確認をしましょう。
土地や家屋の権利を奪うような詐欺も実際ありますので、本人確認は必須でしょう。
本人確認をちゃんとしたうえでも横柄な態度である場合はそういう人なのでしょうね・・・
事前に書面と根拠資料を求める
次に依頼趣旨・対象境界・立会日時・当日の流れ・署名押印の有無、書類の提出先を書面でもらいましょう。
また、既存資料(公図・地積測量図・確定測量図・分譲当時の図面)の事前提示を依頼。
成果物(図面写し)提供の可否とタイミングを確認。
当日の説明責任を明確に
測量方法・基準点・復元根拠(地積測量図・境界標・旧分筆図 等)の整合性説明を求める。
筆界と所有権界の違い、越境物の扱いなど誤解しやすい論点は口頭と書面で説明してもらう。
態度がひどい場合の選択肢
立会の同意はするが、「担当者変更」や同席者追加(第三者の土地家屋調査士・家族)を要請。
また、「現時点では書面不足につき保留」とし、代替日程を提示。
こちらの代替え日程を飲まず、相手の都合で特定の日に限定するなら立会料(日当)を請求するのも手。
立会を完全拒否の選択肢
①別日での再依頼、②法務局に相談して資料主導で登記実務を進める、③筆界特定、④境界確定訴訟の順でエスカレーションするのが一般的。
拒否は可能でも、関係性の悪化と時間的コストを招く点は織り込みたいところです。
ただし、完全拒否する場合は、筆界特定や裁判等の代替手段に進まれてもやむなしという認識が必要。
また、自分たちが土地を売却する際に、境界立会が必要になった際に拒否されるリスクが上がるのも覚悟は必要でしょうね。。。
“署名押印だけは拒む”という中間解
境界そのものに異論はないが、確認書への署名押印だけはしたくないという中間解も実務上あります。
事案によっては、立会なし・署名なしでも登記が進む可能性があるため(表示登記実務の運用や資料完備のケース)、法務局へ相談してもらうのも手。
「境界立会 できない場合」どうなるのか?
それでは境界立会できないようなケースではどうなるのでしょう?
以下のようなパターンがあります。
① 隣地所有者が不在等(行方不明/高齢で判断不能 等)
家庭裁判所で不在者財産管理人選任を申立て、手続を進める道があります。
② 感情的対立で立会が決裂
第三者の土地家屋調査士を介し事実の提示に専念。
それでも進まなければ、筆界特定制度の申請で公的第三者の判断を仰ぐ。
ちなみにそれが終わるまで売却等ができません。
③ そもそも境界帰属で深刻な対立
境界確定訴訟で最終判断を得る。
共有地が絡む場合は共有者全員が当事者となる必要があるのが実務上のルールです(必要的共同訴訟)。
まとめ
今回は「境界立会は義務?拒否できる?—横柄な土地家屋調査士への対応と「受けるメリット・断るリスク」完全ガイド」と題して境界立会についてみてきました。
境界立会は原則任意です。
ただし、受ける合理的メリットもあります。
最終的には拒否のリスク(時間・関係悪化)と天秤にかけて考えましょう。
私は「土地家屋調査士」の補助者の態度への抗議と日程はこちらが決めるとのメールを補助者を雇う「土地家屋調査士」に打つことにしました。
その対応次第でどうするかを考えます。