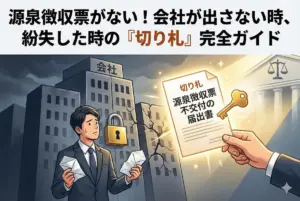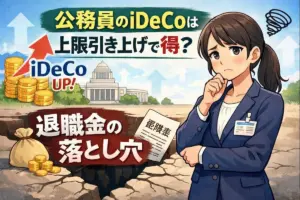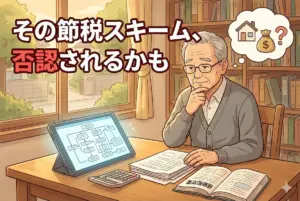先日から社労士界隈、税理士界隈で大騒ぎとなっている事案が発生しました。
大阪の税理士が社会保険労務士法違反の疑いで逮捕されたのです。
しかも告発したのが報道によると大阪府内の社労士団体とのこと。
おそらく社会保険労務士会です。
税理士と社会保険労務士は境界問題でいろいろありますので、今回の件が仁義なき戦いに勃発する可能性まで示唆されています。
今回は社労士と税理士の境界について解説していきます。
社会保険労務士法27条違反
まずは今回の逮捕の発端となった社会保険労務士法についてみておきましょう。
社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行ってはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。
出典:社会保険労務士法 第27条
社労士は、就業規則、労働・社会保険の申請書類の作成・提出代行、帳簿作成などを業として行えます。
これらは「独占業務」で、社労士でない者が報酬を得て反復継続して行うことは原則禁止ということ。
違反は懲役または罰金の対象になります。
1年以下の拘禁刑(懲役)または100万円以下の罰金です。
今回の大阪の税理士の事件の概要
今回の事件の概要は日経新聞によると以下の通り。
府警によると、池上容疑者は2022年4月〜25年8月、自身が運営する税理士事務所(大阪市中央区)で社労士の業務を1件5000円〜10万円で請け負い、少なくとも約400万円を売り上げていたという。
出典:日経新聞
逮捕容疑は6〜7月、社労士資格を得ずに顧客3社から報酬を受け取り、労働保険の申請に必要な書類を提出するなどした疑い。
有償で反復継続して社会保険業務をやっていますので、たしかにアウトな内容です。
ただし、罰則の内容を考えると割に合わない報酬金額ですね・・・
ちなみに拘禁刑以上の刑が確定すると、刑の執行が終わった日、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、税理士となる資格を有しないと定められています。
税理士資格まで失ってしまうリスクがあるのです。
悪いことをしている認識がなかったのかもしれませんが。
どこまでが「税理士の付随業務」か
なお、社労士法27条に「他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。」という文言があります。
税理士業務と社会保険労務士業務はかなり繋がっている部分がありますので、それに該当するのでは?という論点もあります。
ちなみに2002年に日本税理士会連合会と全国社会保険労務士会連合会が共同で出している税理士又は税理士法人が行う付随業務の範囲に関する確認書では
1.税理士の付随業務としてできる社労士法2条1項の事務は、「租税債務の確定に必要な事務」に限る。
2.事務代理(2条1項1の3)は付随業務ではない
3.年末調整は税理士業務。社労士が年末調整を行うと税理士法52条に抵触。
とされています。
つまり、税理士が行える“社労士っぽい事務”は「租税債務の確定に必要な事務」の範囲に限るということ。
具体的なイメージとして、出勤簿・給与データなど“年末調整をするための前提データ”を整える行為はあり得るが、社会保険の申請作成・提出の“代行”まで踏み込めばアウトという意味合いでしょう。
逆に年末調整は社会保険労務士がやったら違法だよっていう線引です。
このあたりの給料に絡む書類作成の話はすべて一連の流れですから、一箇所に頼みたいのは事業者からしても当然なんですが、士業の境界があるためそれぞれ別になってしまうのです。
給料に絡む話を社労士に頼むと社会保険手続きも一連の流れとしてやってくれますが、年末調整は対象外。
税理士に頼むと年末調整までやってくれますが、社会保険手続きは対象外という・・・
年末調整は社労士 税理士 どちらの業務なのか?
今回の社会保険労務士会告発の税理士逮捕で大きな問題となりそうなのが年末調整業務です。
給料計算、社会保険計算の流れでそのまま年末調整までやっている社会保険労務士もいますが、「税理士又は税理士法人が行う付随業務の範囲に関する確認書」でも明確に年末調整は税理士業務と明記されています。
これが今後、税理士会から問題視される可能性があるのです。
税理士法の基本
税理士法についても確認しておきましょう。
税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
出典:法令リード 税理士法 52条
社会保険労務士法との大きな違いが、「報酬を得て反復継続」という文言がないことです。
つまり、無償でも単発でもやっちゃ駄目ってことです。
ちなみにこちらの罰則は2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。
社会保険労務士が関与できる範囲
年末調整は、所得控除の適用可否や控除額の計算など税務判断が連続する仕事です。
このため、年末調整は税理士業務と明確化されています。
社会保険労務士でも給与計算システムの入力や従業員からの書類回収といった補助的な周辺作業自体は問題ありませんが、「控除の要件判断」「税額計算」などの年末調整の核心の判断は税理士の職域となります。
法定調書などの書類も当然そうなりますね。
まとめ
今回は「業界騒然。税理士が社労士法違反で逮捕。今こそ確認しておきたい社労士と税理士の境界」と題して税理士と社会保険労務士の境界についてみてきました。
まとめると
・年末調整は税理士。
・労働・社会保険の申請作成・提出代行・帳簿作成は社労士。
・付随業務は極めて限定。
ってことですね。
行政書士と司法書士、行政書士と弁護士の争いなんかもよく見ますが、他にも士業同士の境界(グレーゾーン)はたくさんあります。
事業者がそれらを理解するのはなかなか難しいです。
実情に合わせてもう少し緩和してほしいな・・て思うところはありますね。