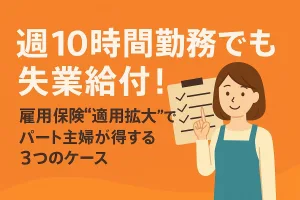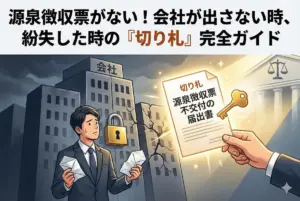2025年11月16日、金融業界に大きな動きがありました。
金融庁が暗号資産を金融商品取引法の対象として位置づける方針を固めたのです。
この決定は、ビットコインやイーサリアムなど国内の暗号資産交換業者が取り扱う105銘柄を対象としており、2026年の通常国会への法改正案提出を目指しています。
この制度改正は単なる法律上の変更以上の意味を持ちます。
現在最大55%という重い税負担から、株式投資と同様の20%分離課税への道が開ける可能性があるためです。
また、情報開示の義務化やインサイダー取引規制の導入により、より透明性の高い市場環境が整備されることになります。
本記事では、金融庁が公表した一次資料や金融審議会の議事録をもとに、この歴史的な制度改正の全容を詳しく解説していきます。
金融商品取引法への移行が意味するもの
まずは、今回の金融商品取引法への移行の意味を考えてみましょう。
資金決済法から金商法へ転換する背景
現在、暗号資産は資金決済法に基づいて「決済手段」として規制されています。
しかし実態として、
- 口座数は1,200万超、預託金残高は3兆円以上とされる規模まで拡大
- 実際には「決済」よりも「投資・投機」として使われるケースが圧倒的に多い
こうした状況を踏まえ、金融庁は
金融審議会の暗号資産制度に関するワーキング・グループにおいて公表されたデータによれば、国内の暗号資産取引において決済目的の利用は一定の需要があるものの、投資目的が圧倒的多数を占めています。
この現実と法規制の乖離を解消するため、金融庁は暗号資産を「金融商品」として位置づける方針を固めました。
「実態が投資商品なのだから、金商法で一元的にルールを定めたほうが筋が良い」
ということです。
金融商品取引法は、株式や債券などの有価証券取引に適用される法律であり、投資家保護や市場の公正性確保を主な目的としています。
暗号資産をこの枠組みに組み入れることで、より実効性のある投資家保護策が講じられることになります。
すでに責任準備金が義務化される話も出ていますね。

有価証券とは異なる新たな金融商品カテゴリー
重要な点として、暗号資産は有価証券とは別の金融商品カテゴリーとして位置づけられる予定です。
暗号資産はブロックチェーン技術を基盤として駆動し、発行の仕組みや用途、取引形態において有価証券とは本質的に異なる特徴を持っています。
特に発行や流通の形態において、技術的な性質の異なるものが混在している点が有価証券との大きな違いです。
ビットコインのように発行者が存在しない暗号資産もあれば、特定のプロジェクトによって発行され管理される暗号資産も存在します。
金融庁は、こうした暗号資産の多様性を踏まえ、有価証券とは別の新しい金融商品としての法的枠組みを構築する方向で検討を進めています。
対象となる105銘柄の詳細と選定基準
今回のニュースで多くの投資家が気にしているのが、検索キーワードにもなっている「105銘柄一覧」という言葉です。
国内交換業者が取り扱う暗号資産の現状
金融庁のワーキンググループでは、日本暗号資産取引業協会(JVCEA)のデータをもとに、「2025年度上期の時点で、国内で取り扱い可能とされた暗号資産は105銘柄」と説明されています。
つまり、
- JVCEAの審査を通り
- 国内交換業者が取り扱うことが認められている暗号資産
の数が、現時点で105ということです。
今回報じられている「105銘柄に金商法を適用」という話は、この“取り扱い可能銘柄”をそのまま金融商品として位置付ける案だと考えられます
105銘柄一覧はどこで見られるのか
ここが重要なポイントですが、金融庁が「この105銘柄です」と公式に一覧を公表しているわけではありません。
現時点で投資家ができる現実的な確認方法は、次のようなやり方です。
- 金融庁や財務局が公表している「暗号資産交換業者登録一覧」で、登録済み業者を確認する
- それぞれの交換業者のサイトで、取り扱い暗号資産の銘柄一覧をチェックする
- JVCEAが公表する「会員が扱う暗号資産一覧」資料を参照する(ワーキンググループ資料など)
報道ベースでは、ビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)、リップル(XRP)など、国内主要取引所に上場しているメジャー銘柄はほぼ含まれているとみられます。
ただし、「105銘柄一覧」という形で一つのページにまとまった公式リストがあるわけではないため、
「○○サイトの105銘柄一覧」といった非公式のリストを鵜呑みにしない
という姿勢も大切です。
詐欺も買い煽りに使われそうな予感もあります。
105銘柄から外れたらどうなるのか
海外の取引所でのみ取り扱われている暗号資産や、国内での取引量が極めて少ない銘柄については、別途のルール整備や将来的な制度改正の中で議論されていく見通しです。
ただし、どの取引所で取引していても、日本の居住者としての申告義務は変わりません。
規制対象外の銘柄であっても、取引による所得が発生すれば適切に申告する必要があります。
暗号資産が「金融商品」になると何が変わるか
投資家目線で気になるのは、「金商法の金融商品になると、自分たちにどんな影響があるのか」です。
大きく分けると、ルールが厳しくなる部分と、環境が良くなる可能性がある部分の両方があります。
情報開示が増え、銘柄ごとの「見える化」が進む
金融庁の資料や報道によると、金商法適用後は、対象銘柄について次のような情報開示が求められる方向です。
- 発行者の有無や、プロジェクトの性質
- どのブロックチェーン・どんな仕組みの上に成り立っているか
- 価格変動リスクや流動性の状況
- 取扱い開始・廃止、ハードフォーク、破産など、投資判断に影響する重要事実
イメージとしては、株式の目論見書やファンドの運用報告書に近い情報を、各暗号資産について整備していく形です。
これにより、いままで「名前とチャートくらいしか分からないアルトコイン」が多かった状況から、少なくとも105銘柄については、最低限の説明書が揃う方向に向かうと考えられます。
インサイダー取引や相場操縦への規制が強化
金商法の金融商品になると、インサイダー取引や相場操縦に対するルール適用がはっきりします。
従来も、明らかな「ポンプ&ダンプ」や風説の流布は証券取引等監視委員会などが問題視していましたが、暗号資産についてはグレーな部分も少なくありませんでした。
金商法適用後は、
- 未公表の重要情報を知った内部関係者による売買
- 自分や関係者で価格を吊り上げてから売り抜ける行為
- SNSで虚偽の情報を流しつつ取引する行為
などが、より明確に「違法」として扱われやすくなります。
短期的には「これまでのような派手な値動きが出にくくなる」可能性もありますが、中長期の投資家にとっては、市場の信頼性が上がる方向と見ることもできます。
某国の大統領の関係者とかは国外の話なので対象にはならないでしょうが・・・
販売・勧誘ルール:断定的なセールストークに歯止め
金商法の世界では、
- 「必ず儲かる」「損はしない」といった断定的な勧誘
- 顧客の意向を無視した過度な勧誘
- 深夜・早朝の迷惑な電話勧誘
などが厳しく制限されています。
暗号資産が金融商品として位置付けられれば、こうした販売・勧誘ルールが暗号資産にも適用される方向です。
これにより、将来的には
- 高齢者に対する過度な暗号資産勧誘
- 「年金より安全」「元本保証」などの不適切なセールストーク
といった行為にも、今より踏み込んだ対応が取られることが期待されます。
レンディングやステーキングも金商法の対象に?
金融庁はすでに、暗号資産レンディング(貸し出し)サービスなどについても、金商法の規制対象に含める案を提示しています。
これが実現すると、レンディングやステーキングのサービス提供者は
- 契約内容の明確化
- 元本割れリスクや信用リスクの説明
- 説明義務違反があった場合の責任
などについて、今よりも重い責任を負うことになります。
投資家にとっては、
- 「利回りだけを強調したレンディング広告」が出にくくなる
- その代わり、利用できるサービスが一時的に減る可能性もある
といったプラス・マイナス両面を意識しておきたいところです。
交換業者の負担は増え、取扱い銘柄の選別が進む可能性
一方で、金商法の枠組みは、交換業者にとってかなり重いものです。
- 情報開示のための文書作成・更新
- 内部管理体制の整備
- コンプライアンス人員の増強
など、コスト増は避けられません。すでに金融審議会では、
「規制が重厚すぎると業界が存続できない」
という悲鳴に近い声も上がっています。
その結果として、
- 取扱い銘柄を105銘柄からさらに絞り込む
- 将来性はあるが情報開示が難しい銘柄を上場させない
といった動きが出る可能性もあります。
投資家としては、単純に「105銘柄一覧に入っているから安心」というより、むしろ選別が進む過程で、上場継続が難しくなる銘柄が出てくるリスクも意識しておきたいところです。
暗号資産税制はどう変わる?「最大55%」から「20%」へ
今回のニュースで、個人投資家にとって最もインパクトが大きいのは、暗号資産税制の見直しです。
現行の暗号資産税制(~2025年分のイメージ)
今の日本の暗号資産税制をざっくり言うと、次のような特徴があります。
- 利益は「雑所得」として総合課税
- 給与など他の所得と合算され、最高税率は55%前後
- 株式・投信と違い、損失の繰越控除ができない
- 暗号資産同士の交換でも課税が発生する
たとえば、年収900万円の会社員が暗号資産で300万円の利益を出した場合、税率は40%前後に達しうる、という試算もよく紹介されています。
この「高い税率」「損失を翌年に持ち越せない」という点が、暗号資産税制への不満の大きな理由でした。
金融庁などが要望している新しい暗号資産税制
こうした状況を受け、金融庁や業界団体は「暗号資産を他の金融商品と同じく申告分離課税にしてほしい」という要望を続けてきました。
2026年度税制改正要望では、金融庁が正式に
- 暗号資産取引について20%前後の申告分離課税
- 株式等との損益通算と損失繰越(3年間程度)
- 暗号資産同士の交換は課税せず、法定通貨に換金した時点で課税
といった方向性を打ち出しています。
各種解説記事や試算でも、「最大55%→20.315%」への税率引き下げと、損失繰越導入のメリットが具体的に紹介されはじめています。
投資家の税負担はどれくらい変わるか(イメージ)
例として、年収800万円の会社員が暗号資産で300万円の利益を得たケースを考えます。
- 現行制度:給与と合算され、税率は30~40%台、税額は約90~100万円前後になるイメージ
- 分離課税20.315%になった場合:利益300万円×20.315%で、税額は約61万円程度
単純化した例ですが、数十万円単位で税負担が軽くなる投資家が多いと考えられます。
また、今は「去年大きく損をして、今年は利益が出た」場合でも、損失を繰り越せないため、税金だけが重くのしかかります。
損失繰越が導入されれば、この“税金だけ勝ち”のような状態が改善されることが期待されます。
ただし、暗号資産税制はまだ「決定」ではない
注意したいのは、これらはあくまで要望・検討段階であり、まだ国会で法律が成立したわけではないという点です。
- 与党税制調査会の議論
- 2026年度税制改正大綱
- 金商法改正案の国会審議
といったプロセスを経て、ようやく具体的な条文や施行時期が確定します。多くの解説では、実際の適用開始は早くても2027年からという見方が有力です。
したがって、現時点では
「2026年から税率20%になるから、今年は利益をいくら出しても大丈夫」
といった安易な前提で動かないことが大事です。
少なくとも2025年・2026年分の確定申告は、現行ルールを前提に準備する必要があります。
いつから変わる?今後のスケジュール感
現時点で公表されている情報や有識者の解説を整理すると、おおまかなスケジュール感は次のようになります。
- 2025年:金融審議会ワーキンググループで制度設計の議論を継続。資金決済法から金商法への移行案を詰める。
- 2026年:通常国会に、金商法改正案と関連税制改正案を提出することを目標。
- 2027年ごろ:法案成立後、1年前後の準備期間を経て、暗号資産の金商法化と新しい暗号資産税制が本格施行というシナリオが有力。
もちろん、国会審議の状況次第では前後しますが、少なくとも2025年中に一気にルールが変わることはない、という点は押さえておいてよさそうです。
まとめ
金融庁が進める暗号資産の金融商品取引法への移行は、日本の暗号資産市場にとって歴史的な転換点となります。
- 投資家保護を強め、市場の透明性を高める
- 税制を株式並みにし、国内からの資本流出を防ぐ
という意味で、長期的にはプラスの側面が大きいと考えています。
一方で、
- 業者側の負担増により、サービスや取扱い銘柄が一時的に縮小する
- 「105銘柄一覧に入っているから安全」という誤解が広がる
- 税制改正を過度に織り込んだ投資判断をしてしまう
といった落とし穴もあります。
暗号資産はあくまでハイリスク資産であり、金融商品化しても値動きが穏やかになるとは限りません。
むしろ、「金融商品になったから安心」と油断した投資家ほど、思わぬ値動きに振り回される可能性があります。
だからこそ、今のうちから
- 一次情報(金融庁資料や公式の税制改正要望など)にあたる習慣
- 税務・法制度の変化を自分の言葉で説明できるレベルの理解
- 無理のない投資額と、長期の視点
を意識しておくことが、これから数年の暗号資産市場を乗り切るうえでの“最大の防御力”になってくるはずです。