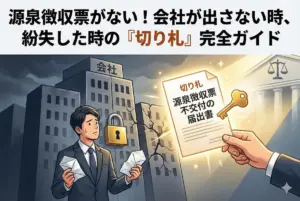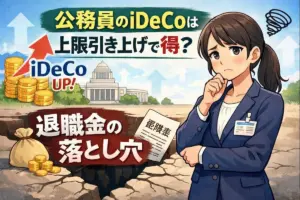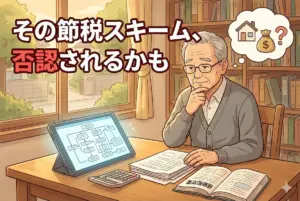長らく据え置かれていたマイカー通勤などの通勤手当の非課税限度額が11年ぶりに変更となりました。
しかも、これからの話だけではありません。「過去に支払った分」まで戻ってくる可能性があるのです。
とくにマイカー通勤の方と経理担当者にとっては、「知らないうちに損をしていた」「年末調整で慌てた」という事態になりかねない改正となります。
まずは今回のポイントをおさえつつ、「通勤手当の非課税限度額の改正はいつからなのか」「マイカー通勤にどう影響するのか」を順番に整理していきます。
通勤手当の非課税限度額の改正をざっくり概要
まずは今回の変更内容をざっくり確認していきましょう。
2025年11月19日に所得税法施行令が改正され、「自動車や自転車などの交通用具で通勤している人」に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
ポイントは次の2つです。
- 対象は マイカー・バイク・自転車などで通勤している人の通勤手当
- 電車・バスなど公共交通機関のみを利用している人の非課税枠(1か月15万円まで)は変更なし
もともと、マイカー通勤の非課税限度額は2014年にも一度引き上げられており、今回が約11年ぶりの見直しです。
なぜ今、マイカー通勤の非課税枠だけを引き上げたのか
背景としては、ここ10年ほどでガソリン価格が大きく上がり、地方を中心にマイカー通勤者の負担が増えていたことがあります。
資源エネルギー庁のデータでも、この10年でレギュラーガソリンの全国平均価格が約1.3倍になっていると紹介されています。
一方で、非課税限度額は長く据え置かれていたため、「実際の通勤コストに比べて税制が追いついていない」という状態になっていました。
今回の改正は、そのギャップを少し埋めるための見直しと考えるとイメージしやすいと思います。
通勤手当の非課税限度額の改正はいつから?(いつ適用されるのか)
今回一番混乱するのがいつから適用されるかです。
改正の施行日と適用時期の整理
今回の話でよく検索されているのが「通勤手当の非課税限度額の改正 いつ」というキーワードです。
ここは少しややこしいので、整理しておきましょう。
今回の改正(所得税法施行令の一部改正)は、以下のスケジュールで動いています。
- 公布・施行日:2025年(令和7年)11月20日
- 適用開始日:2025年(令和7年)4月1日以後に支払われるべき通勤手当
ここが今回の改正の最大のポイントです。
法律が変わったのは2025年の11月ですが、「2025の4月1日まで時計の針を戻して適用する(遡及適用)」というルールになっています。
つまり、つまり、法律としては11月から動き出しますが、2025年4月以降のマイカー通勤手当について「本当はこう計算すべきだった」という基準が、あとから決まったイメージです。
なぜ「遡及適用」なのか?
「なぜ4月なのか?」と疑問に思うかもしれません。
これは、国の会計年度や多くの企業の事業年度の始まりに合わせるという意味合いに加え、近年の急激なガソリン価格上昇に対し、少しでも早く税制面での手当てを行う必要があると判断されたためです。
つまり、「4月から11月までの間に、これまでの古い基準で税金を引かれすぎていた人」が発生していることになります。
この「払いすぎた税金」を取り戻す手続きが、今年の年末調整の最大のトピックとなるわけです。
実務上のイメージ(2025年の年末調整との関係)
国税庁の解説例では、片道50kmのマイカー通勤者に毎月3万円の通勤手当を支払っているケースが示されています。
- 1〜10月の給与計算では、旧限度額(28,000円)を使って、毎月2,000円を課税扱い
- しかし、改正により、4〜10月分については新しい限度額(32,300円)を使って計算し直すことになります
結果として、4〜10月の7か月分で課税扱いにしていた通勤手当の一部が「本当は非課税だった」と判明し、その金額を年末調整でマイナス調整して、所得税を還付します。
経理担当者目線で言うと、
- 2025年11・12月分は、給与計算の段階から新限度額で処理
- 2025年4〜10月分は、年末調整で「課税し過ぎていた分」を精算
という二段階対応が必要になる、というイメージです。
企業によってはすでに年末調整の手続きが始まっているところも多いでしょうが、急に言われて大混乱でしょうね・・・
通勤手当の非課税限度額の改正とマイカー通勤の具体的な金額
次に、具体的な金額の変化を見ていきましょう。
今回の改正は、電車やバスなどの公共交通機関利用者(最高限度15万円)には変更がありません。
影響があるのは、自動車、自転車などで通勤している方々です。
距離ごとにいくらまで非課税になるのか
自動車や自転車などの交通用具を使用して通勤する給与所得者の通勤手当については、片道の通勤距離に応じて非課税となる限度額が定められています。
今回の改正では、この距離区分ごとの限度額が引き上げられました。
片道距離別・改正前後の非課税限度額(1か月あたり)
| 片道の通勤距離 | 改正後(2025年4月1日以後適用) | 改正前 |
|---|---|---|
| 2km 未満 | 全額課税(非課税枠なし) | 全額課税 |
| 2km 以上 10km 未満 | 4,200円(変更無し) | 4,200円 |
| 10km 以上 15km 未満 | 7,300円(+200円) | 7,100円 |
| 15km 以上 25km 未満 | 13,500円(+600円) | 12,900円 |
| 25km 以上 35km 未満 | 19,700円(+1,000円) | 18,700円 |
| 35km 以上 45km 未満 | 25,900円(+1,500円) | 24,400円 |
| 45km 以上 55km 未満 | 32,300円(+4,300円) | 28,000円 |
| 55km 以上 | 38,700円(+7,100円) | 31,600円 |
電車・バス通勤の非課税限度額(1か月あたり「合理的な運賃等の額」上限15万円)は改正なしです。
今回の改正で実際に数字が増えたのは、片道10km以上のマイカー通勤者です。片道10km未満の人は金額の変更はありません。
マイカー通勤者の手取りはどれくらい変わるのか
ここからは、イメージしやすいように具体例で見ていきます。
(税率は分かりやすくするため、所得税5%・住民税10%=合計15%と仮定します)
ケース1:片道20km・通勤手当月1万5,000円の場合
片道20kmは「15km以上25km未満」の区分です。
- 改正前の非課税限度額:12,900円
- 改正後の非課税限度額:13,500円
毎月1万5,000円支給しているとすると、
- 改正前:1万5,000円 − 1万2,900円 = 2,100円が課税対象
- 改正後:1万5,000円 − 1万3,500円 = 1,500円が課税対象
課税対象が 月600円減る ことになります。
これが1年間続いたと仮定すると、
600円 × 12か月 = 7,200円分の通勤手当が新たに非課税になります。
税率15%で考えると、
7,200円 × 15% = 約1,000円 程度、年間の税負担が軽くなるイメージです。
ケース2:片道50km・通勤手当月3万5,000円の場合
片道50kmは「45km以上55km未満」の区分です。
- 改正前の非課税限度額:28,000円
- 改正後の非課税限度額:32,300円
毎月3万5,000円支給しているとすると、
- 改正前:3万5,000円 − 2万8,000円 = 7,000円が課税対象
- 改正後:3万5,000円 − 3万2,300円 = 2,700円が課税対象
課税対象が 月4,300円減る ことになります。
これが1年間続いたと仮定すると、
4,300円 × 12か月 = 5万1,600円分の通勤手当が新たに非課税です。
税率15%で考えると、
5万1,600円 × 15% = 約7,700円 程度、年間の税負担が軽くなります。
距離が長く、もともと限度額ぎりぎりまで支給されていた人ほど、影響も大きくなるイメージです。
経理・給与担当者が対応すべき実務ステップ
次に経理・給与計算担当者の話を見ていきます。
パターン別対応フローチャート
対応は、自社の給与規定や支給実態によって異なります。
パターンA:通勤手当を「非課税限度額と同額」支給している場合
- 状況:規定で「非課税限度額を支給する」と定めている会社。
- 対応:
- 差額の追加支給が必要です(4月分〜現在まで)。
- 追加支給額は全額「非課税」となるため、所得税の徴収は不要です。
- 社会保険(随時改定)の対象になるか確認が必要ですが、数百円〜数千円の差であれば、固定的賃金の変動があっても2等級以上の変動にはなりにくいため、月変(随時改定)には該当しないケースが大半でしょう(要確認)。
※社会保険は通勤手当を加えて計算するんですよ。詳しくはこちらの記事を御覧ください

パターンB:通勤手当を「一律固定額」支給している場合(実費支給含む)
- 状況:独自のルールで距離に関わらず月2万円支給、あるいはガソリン代実費で月3万円支給、など。
- 対応:
- 支給総額を変える必要はありません(規定改定しない限り)。
- 「課税区分」の修正が必要です。これまでは「課税」として処理していた部分の一部が「非課税」に変わります。
- 4月〜11月(改正前)に徴収しすぎた源泉所得税を、年末調整で精算(還付)します。
具体的な精算手順(年末調整)
次に実際の精算処理について考えてみましょう。
ステップ1:対象従業員の洗い出し
まず確認したいのは次の2点です。
- マイカー・バイク・自転車で通勤しているか
- 片道通勤距離が10km以上かどうか
通勤距離が10km未満の従業員や、電車・バス通勤のみの従業員は今回の改正の影響を受けません。
勤怠システムや通勤届の情報から、対象者を一覧にしておくと後工程がスムーズです。
ステップ2:給与計算ソフト・通勤手当マスタの見直し
多くの給与ソフトは、アップデートで「新しい非課税限度額」に対応する予定だと案内しています。
- ソフト側で自動対応される範囲
- 会社側で手動設定が必要な項目
を事前に確認しておくと安心です。
とくに「通勤手当の支給額=常に非課税限度額の範囲内」という前提で設定している会社は、マスタの見直しが必要になるケースがあります。
ステップ3:2025年分年末調整での精算方法
国税庁は「年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例」を公表しています。
基本的な考え方は、次のような流れです。
- 2025年4〜10月分について、旧限度額を使って課税した通勤手当のうち「新制度なら非課税だった金額」を集計
- 源泉徴収簿の「非課税となる通勤手当」として、その金額を総支給額から控除
- 控除後の金額をもとに、改めて年末調整を行う
2025年に退職した人については、年末調整ではなく本人の確定申告で精算する必要が出てくるケースもあります。従業員への案内文もセットで準備しておくと親切です。
ステップ4:就業規則・通勤手当規程の確認
就業規則や賃金規程で
- 「通勤手当は非課税限度額の範囲内とする」
- 「人事院勧告に準じて改定する」
といったルールにしている会社も多いと思います。
その場合、
- 会社として通勤手当そのものの支給額を増やすのか
- あくまで支給額は据え置きで、税計算だけ変えるのか
をあらためて整理する必要があります。
「非課税枠が増えたから、必ず手取りも増える」とは限らない点には注意が必要です。
マイカー通勤者が知っておきたいポイント
次にマイカー通勤者の話を見ていきます
自分の通勤手当がどう変わるかをチェックする手順
マイカー通勤をしている従業員の立場では、次の3点を確認しておくと安心です。
- 自分の片道通勤距離(会社に届け出ている距離)
- 毎月支給されている通勤手当の金額
- その金額が、新しい非課税限度額を超えているかどうか
もし「支給額が限度額を超えていて、今までも一部課税されていた」のであれば、今回の改正で課税対象が少し減る可能性があります。
会社に聞くときの聞き方
「通勤手当の非課税限度額の改正って、うちの会社はどうなりますか?」と聞くときは、感情的にならず、
- 改正後の非課税限度額に合わせて、支給額や税計算の見直しをする予定はあるか
- 2025年分年末調整で還付が出る可能性があるか
といった点を、冷静に確認するイメージがよいと思います。
通勤費は会社のコストでもあるため、支給額を増やすかどうかは経営判断です。
そもそも通勤費を出すのか出さないのかも会社の自由なんですよ。
一方で、すでに支払った通勤手当について「本来非課税でよかった部分」まで課税され続けるのは適切ではありません。
この点は会社側も意識しておく必要があります。
よくある質問(Q&A形式)
最後に、現場でよく聞かれる疑問にお答えします。
- 3月分として4月10日に支払われた通勤手当は対象ですか?
-
対象です。
今回の改正は「2025年(令和7年)4月1日以後に支払われるべき」ものが対象です。
給与の締め日ではなく「支給日」基準で判断されます。
4月1日以降に支給日が到来する給与に含まれる通勤手当であれば、たとえ計算対象期間が3月であっても新基準が適用されます。
※ただし、厳密には「4月1日以後に支払われるべきもの」という文言の解釈で、3月勤務分を4月に払う場合も対象となるケースが一般的ですが、実務上は国税庁Q&A「令和7年4月1日以後に支払う給与等から適用」を確認してください。通常、4月支給給与から適用します
- バイクや自転車も対象ですか?
-
「交通用具」を使用している場合が対象ですので、マイカーだけでなく、オートバイ、原付、自転車も含まれます。
- 過去に退職した人の分はどうすればいいですか?
-
再計算して源泉徴収票を再交付する必要があります。
4月以降に退職し、既に源泉徴収票を発行済みの元社員についても、税金を納めすぎていたというケースがでてきます。
その場合は、原則として退職者本人の確定申告で調整することになります。
会社側は本人に連絡をとり、差額分も支給し、再計算(準確定申告等の還付手続きの基礎となる修正)を行い、新しい源泉徴収票を送付するというのが誠実な対応かもしれません。
- 電車・バス通勤の非課税限度額も変わるの?
-
いいえ、変わりません。
電車・バスなどの交通機関のみを利用する場合は、これまでどおり「1か月あたりの合理的な運賃等の額(上限15万円)」が非課税枠です
- 会社は通勤手当の支給額を必ず増額しないといけない?
-
いいえ、法律上「支給額を増やせ」という義務はありません。
今回の改正はあくまで「いくらまでなら所得税をかけなくてよいか」という上限の話です。
会社が通勤手当の支給額そのものを増やすかどうかは、就業規則や賃金方針に基づく経営判断になります
ただし、
- 「通勤手当は非課税限度額の範囲内で支給する」と就業規則に書いている
- 人事院勧告に合わせて通勤手当を改定すると明記している
といった場合には、規程との整合性を取る必要があります。
- 通勤距離が2km未満の人は、何も変わらない?
-
通勤距離が片道2km未満のマイカー通勤者については、改正前と同様に全額課税のままです。
「少しだけ近い距離だから車で」というケースでは、そもそも通勤手段としてマイカーを認めるかどうかも含め、会社側の就業規則や安全面のルールを合わせて検討する余地があるかもしれません。
まとめ
今回の「通勤手当の非課税限度額の改正」は、
- いつからか:2025年11月20日施行だが、2025年4月1日以後に支払われるべき通勤手当にさかのぼって適用
- 誰に関係するか:片道10km以上のマイカー・自転車通勤者
- 何が変わるか:距離に応じた非課税枠が最大月7,100円引き上げられ、年末調整で税金が還付される可能性がある
という3点を押さえておけば、大きく迷うことはありません。
経理担当者にとっては、
- 対象者の洗い出し
- 給与システムの設定変更
- 2025年分年末調整での精算
という手間は増えますが、その分、従業員の「知らない間に損をしていた」という不満を抑えることができます。
マイカー通勤者にとっても、今回の改正は「実質負担が少し軽くなるチャンス」です。
自分の通勤距離と通勤手当の支給額を一度見直し、必要なら会社に確認しておきましょう。