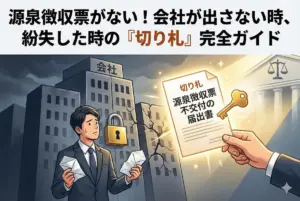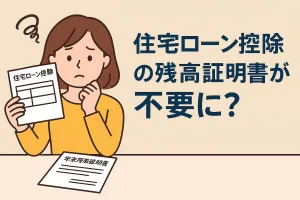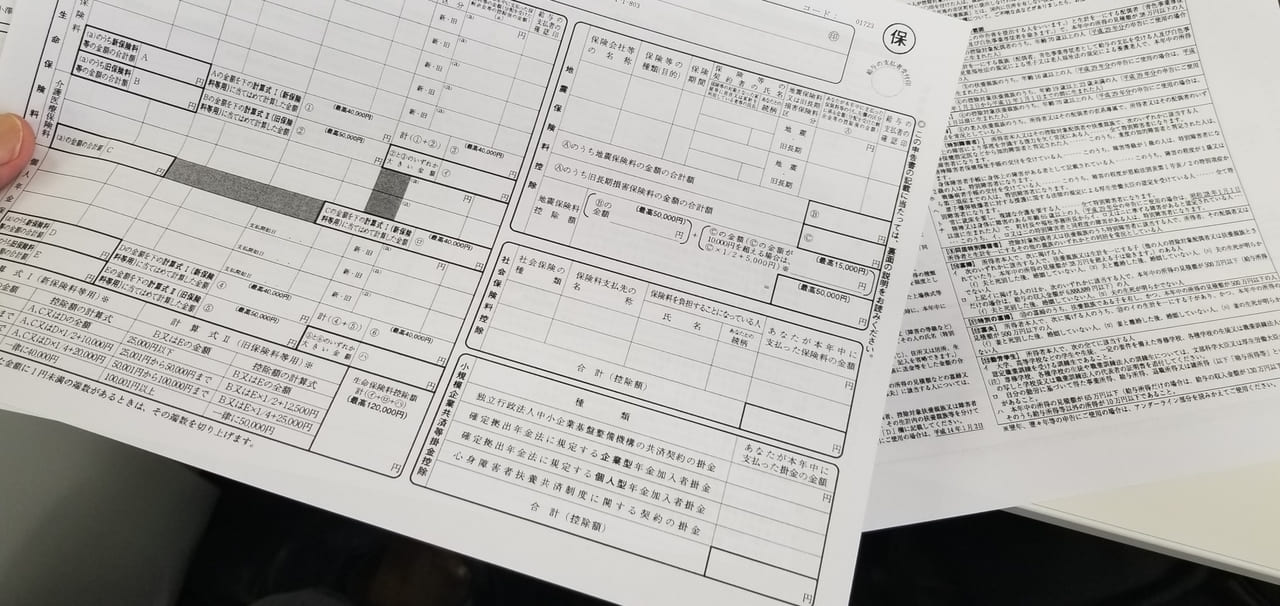働き方改革の一環で副業を許可する企業が増え始めています。
副業をすることで毎月の生活費の足しになるのはもちろん、将来の独立や転職に有利に働く可能性もあるでしょう。
しかし、副業をしていると気になってしまうのが確定申告のこと。
今回は副業をしている方のための確定申告の話を見ていきたいと思います。
副業と確定申告
会社員で働いているだけならば所得税は月々の給料や賞与から源泉所得税が引かれます。
そして年末に年末調整を行うことで所得税を確定し1年間の所得税を確定することができます。
ですから本人は年末調整の書類を用意するだけであとは勤務先がやってくれます。
そのため特に多額の医療費や住宅ローン借り始めた方以外は確定申告は必要ありません。
しかし、副業があるとそうはいかなくなります。
確定申告が必要となる副業の条件
副業をしていても条件を満たしていなければ確定申告は不要です。
副業で確定申告が必要な基準としては20万円の壁があります。
副業の所得が20万円以下の場合には確定申告が不要となるのです。
ただし、お仕事の内容にもよります。
正社員とアルバイトやパートを掛け持ち
副業がアルバイトやパートの場合にはアルバイト・パート先からもらった収入が20万円以下の場合には、確定申告不要です。
複数掛け持ちしている場合にはその合計です。
また、アルバイトやパートとそれ以外の収入がある場合にはそれらも合わせて20万を超えるようならば確定申告が必要となります。
ただし、短期間で一気に稼いだような場合にはアルバイトやパートの収入から源泉所得税が引かれているとおもいます。
収入や控除によっては確定申告をすればその源泉所得税の全部もしくは一部が戻ってくる可能性がありますので一度計算してみるとよいでしょう。
アルバイトやパート代が報酬として支払われている場合
アルバイトやパートの内容によっては給与ではなく、報酬や手数料のような名目で支払われている場合があります。
この場合には請負のような形となりますので、少し計算が変わります。
売上ー経費=所得。
このケースの場合の売上げは報酬や手数料のことを指します。
そこからその副業に掛かった経費を差し引いた金額が所得です。
所得が20万円以下ならば確定申告が不要です。
副業がアルバイト・パート以外
アルバイトやパート以外の場合は、前述の報酬として支払われていた場合と同じルールとなります。
所得が20万以下ならば確定申告が不要です。
所得とは
所得と収入とは少しニュアンスが違います。
売上ー経費が所得となります。
つまり、例えば副業で100万円の売上げがありました。でも経費が90万円かかっていれば所得は10万円となります。
所得が20万円以下となりますので確定申告が不要となるってことです。
経費とは
経費とはその仕事に必要な費用のことです。
例えば副業専用で8万円のパソコンを買いました。
これは経費となります。
専用ってところがポイントですね。
プライベートでも使っている場合は全額経費とは出来ません。
事業に利用した割合を経費とします。
例えば半分副業・半分プライベートならば購入金額の50%が経費となります。
今回のケースの場合には4万円が経費として認められます。
また、その仕事をするために必要な旅費、仕事で使う車のガソリン代、高速代、自宅のインターネット回線代、家賃、電話代、電気代なども仕事とプライベートを按分して経費にすることができます。
税金が発生しない場合
また、もう一つ確定申告不要のケースがあります。
それは税金計算したら納める税金がない場合です。
この場合も確定申告は必要ありません。
所得税の計算ルール
所得税は下記のルールで計算します。
まず、所得金額を求めます。
売上ー経費ですね。
その所得金額から所得控除を引きます。
その差に税率を掛けることで所得税が計算されます。
ポイントとなるのは所得控除です。
所得控除とはたくさんあります。
例えば誰でも該当する基礎控除、扶養者がいれば該当する扶養控除
生命保険などを払っていた場合に該当する生命保険料控除
iDeCoに加入していると該当する小規模企業共済等控除などがあります。
それらの合計が所得金額を超えていれば所得税がかからなくなります。
そのため確定申告は不要なのです。
副業の人も知っておきたいどの申告方法がよいのか
副業で確定申告をする際に覚えておきたいルールとして申告方法があります。
具体的には事業所得(青色申告・白色申告)で申告するか、雑所得で申告するかです。
それぞれメリット・デメリットがありますが税金金額が変わってきますのであらかじめ知っておいてほしいルールです。
事業所得として申告
まずは副業を事業所得として申告する場合です。
この場合には3つのやり方があります。
1つは青色申告(65万控除)
2つ目も青色申告(10万円控除)
3つ目は白色申告
ちょっとややこしいですね(笑)
噛み砕いてみていきましょう。
青色申告とは
まずは青色申告です。
青色申告とはちゃんと経理処理をする代りに所得控除が受けられる制度でそのレベルに応じて65万控除と10万円控除があります。
青色申告のメリットはたくさんありますが、抜粋してご紹介すると
65万もしくは10万円の所得控除が受けられる。
赤字の場合に他の所得と相殺できる
赤字の場合、それの繰り越す事ができる
家族に仕事を手伝って貰ったときに支払った給料を経費にできる(専従者給与)
特に大きいのが赤字の繰越でしょうね。
今年は赤字だけど来年はたくさん利益が出る予定のような場合に今年の赤字を相殺して計算できるようになるってことです。
これは地味ですがかなり大きいですよ。
専従者給与も大規模に副業を行う場合には大きいでしょうね。
ちなみに専従者給与を出すためにはあらかじめ届け出が必要ですので押さえておいてください。
青色申告の条件
青色申告はメリットも大きいですが、適用するためにはいろいろな条件が付与されています。
青色申告承認申請書を提出
帳簿付けが必要(複式簿記)
発生主義によること
損益計算書と貸借対照表作成
簿記を勉強したことがない人にはなんだこれ?って用語が並んでいるかもしれません。
まず、青色申告承認申請書の提出はそのままですが青色申告しますよって書類を税務署に提出しておくってことです。
簡単な書類を出すだけですのでなんら難しくないと思います。
詳しくは下記国税庁の該当ページをご覧ください
次に帳簿付けが必要(複式簿記)です。
これは簿記のルールにそって書類を作っておくってことです。
65万控除を選択する場合にはこちらの帳簿付けが(複式簿記)が必須となります。
10万円控除ならばもう少し簡単な単式簿記もOKです。
なんかすごいハードルが高そうですが現在はAIの進歩により会計ソフトがかなり進歩していますのでほとんど簿記の知識がなくてもこちらの書類を作ることは可能です。
特にクラウド会計というクラウドを使った会計ソフトがおすすめです。
どちらも会計処理が劇的に改善することでしょう。
専門的な話をすると仕訳処理(日々の取引を記録する処理)がほぼ自動で可能となっています。
とくに預金やクレジットカードの取引はほぼ正確に自動仕訳が可能です。
そのため労力もかなり少なく会計処理が可能となっています。
ちなみに私はMFクラウド使ってます。
どちらも1月程度無料で使えますので一度試してみると良いと思います。
発生主義とは取引が発生した時点で帳簿に記載するルールのことです。
これもクラウド会計を利用すれば難しいことではありません。
なお、10万円控除の場合には現金主義(お金が動いたら処理)も認められています。
損益計算書と貸借対照表作成もハードルが高そうですが、クラウド会計で日々の仕訳を行っておけばほぼ自動で作られますので全く難しくありません。
10万円控除だと損益計算書のみも認められています。
つまり、青色申告はなんだか難しそうですがクラウド会計を利用することで難なくクリアできますのである程度の副業をやるならばぜひ届け出をして青色申告しておきたいものです。
65万円の控除と赤字の繰越は魅力的ですね。
青色申告65万控除と10万円控除の違い
青色申告の65万控除となるのか10万円控除となるのかは、65万円控除の要件を満たしている否かによります。
65万控除の要件は下記の通り。
所得の種類が山林所得のみでないこと、
不動産所得の場合、事業として行われていること
複式簿記で記帳していること
現金主義でないこと
損益計算書・貸借対照表を添付
確定申告の法定期限を守る
満たせない場合には10万円控除となります。
65万と10万では55万円も控除が違いますので大きいですよね。ぜひ65万控除の条件を満たしておきたいところ
白色申告とは
白色申告とは単式簿記による収支内訳書(損益計算書)を作って申告する方法です。
クラウド会計や会計ソフトを利用しない場合はこちらを利用するケースが多いかと思います。
青色申告に有るような赤字の繰越や所得控除は受けられません。
赤字の場合に他の所得と相殺はこちらも可能となっています。
また、白色申告でも専従者給与は支払うことができます。(上限あり)
雑所得として申告
処理的には1番簡単なのが雑所得として申告することです。
確定申告には収入金額と経費の合計額を記入するだけですからかなり簡単です。
ただし、青色申告のメリットは全て受けられませんし、赤字の場合に他の所得と相殺も不可です。
まとめ
今回は副業の方向けに確定申告の基本ルールを見てきました。
特に副業でも程度の収入を見込みならやはり青色申告にしてもらった方が圧倒的にメリットが大きいとおもいますのでぜひ挑戦して見てくださいね。
おすすめの副業はこちらをご覧ください。
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://ideco-ipo-nisa.com//12717]
また、会社が副業を許可してくれないときはこちらをご覧ください。
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://ideco-ipo-nisa.com//9747]
読んでいただきありがとうございました。