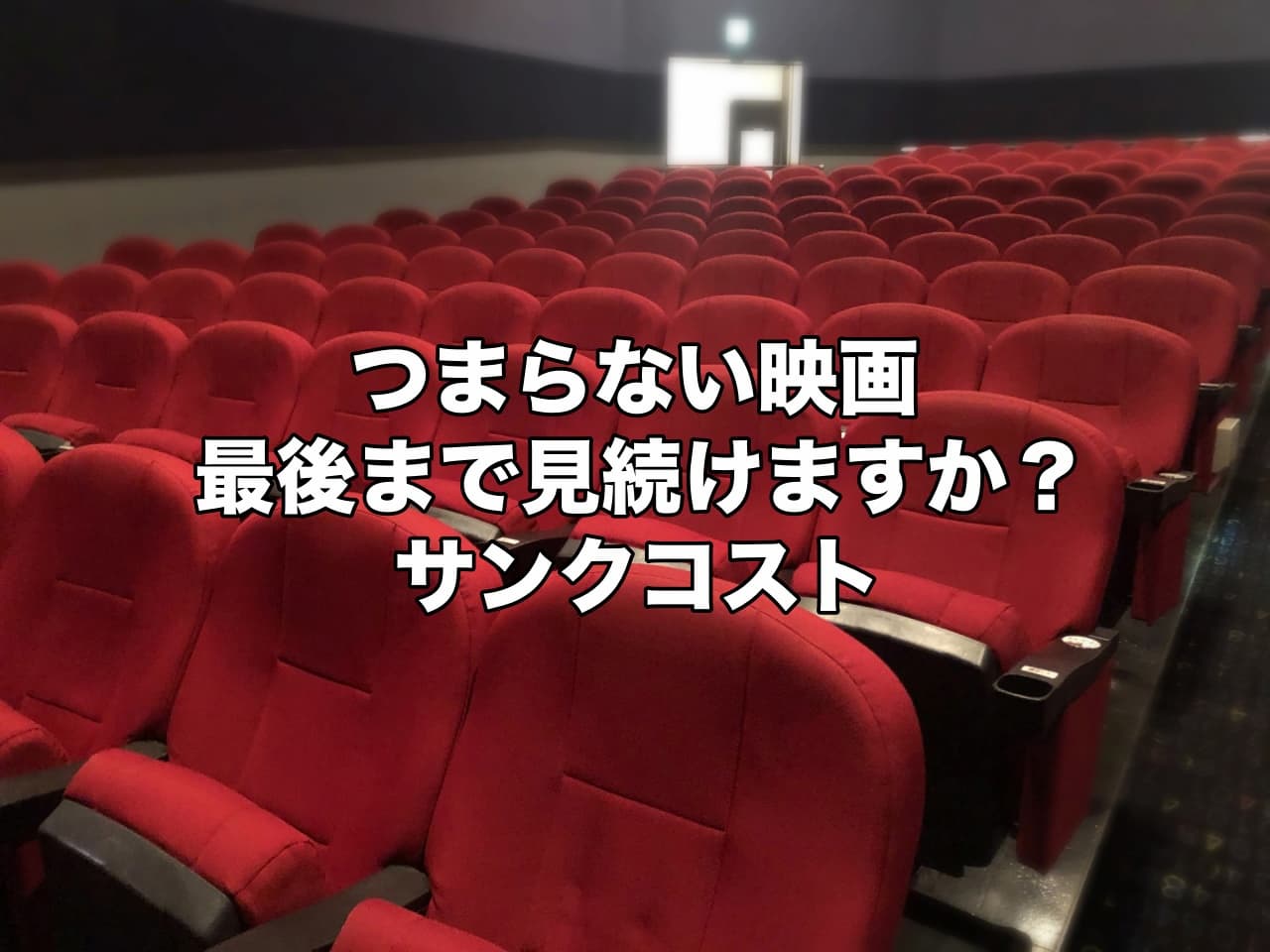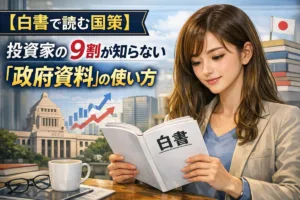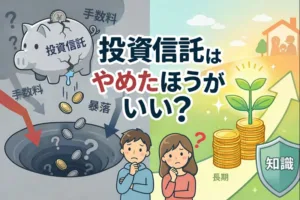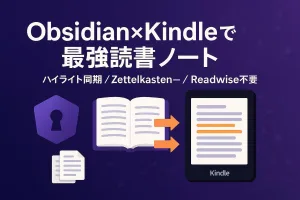投資で負ける大きな要因は人間の心理面にあります。
今回はそんな投資の足かせになってしまう心理的効果の「サンクコスト」について解説していきます。
サンクコストは投資だけに限らず、恋愛など普段の生活でも大きな影響のある話なんですよ。
意識しているのとしてないのでは全然違いますのでぜひ知っておきたいところです。
サンクコストとは
サンクコストとは日本語では埋没費用といいます。
既に回収が不可能であるコストを意味します。
本来はサンクコスト部分の費用はもう戻ってきませんし、今後の判断をするときに関係ありませんから無視すべき事項なのです。
しかし、それができない人や企業が多いんですね。
サンクコストの事例
サンクコストは投資だけに限らず様々な局面で発生します。
映画を見始めたが・・・
例えば2,000円だして映画を見始めたとします。
本当につまらなかったとしても途中で抜けて来る人はそれほど多くありません。
これはすでに支払ってしまった2000円がお金が勿体無いという心理が働いているのです。
これがサンクコスト効果です。
合理的な判断をするならば、つまらない映画を見るのに2時間使うよりもその時間を有意義に使う方法はいくらでもあるはずなのにです・・・。
しかし、すでに回収不能は2000円が判断を狂わせてしまうですね。
これができない人がほとんどなんですよ。
同じようにつまらない漫画、つまらない小説なんかも同じですね。
サブスクやレンタル、漫画喫茶ならば途中まで読んでつまらないならその場で止めるでしょうが、購入したらなんとか最後まで読む人が多いんですよ。
これもサンクコストによる影響ですね。
ただし、映画も小説も最後までみると面白くなるケースもあるのでなんとも言えませんけどね笑
例えば私がとても好きな映画で99年アカデミー賞で外国語作品賞を受賞した「ライフ・イズ・ビューティフル」。
この作品は映画館でみましたが、前半はチャップリンみたいな感じで合わないわ、帰ろうと思うくらいつまらなかったですが、途中から急に良くなりましたからね・・・
ダメ男に貢いだが・・・
ダメ男にいろいろなプレゼントやお金を貢いだケースも同じですね。
そのダメ男との関係は冷めきっていても、ダメな人だとわかっていても今までの貢いだ金額が足かせとなって関係を終わらせれないようなケースは多いです。
プレゼントはすでに回収が不可能であるコストなんですけどね。
アイドルやホストへの貢ぐようなケースも考え方は同じですね。
このサンクコストで危険なのはストーカーなどの犯罪につながるケースもあることです。
サンクコストは非常に怖い部分も持ち合わせているのです。
スマホゲームのガチャ
スマホゲームはゲーム会社にとってかなりのドル箱だそうです。
それはガチャの仕組みがあるから。
ガチャもサンクコストなんですよ。
例えば1回100円のガチャを100回回したとしましょう。
すでに1万円使っています。
あくまでガチャはランダムですからいくら使っていても次の確率は同じです。
しかし、1万円使っていると次こそは。。。ってなってしまうんですよ。
パチンコなんかもおなじような心理的な部分がありますよね。
赤字を出しても・・・
企業においても同じです。
すごい赤字を垂れ流している事業でも過去に多額の資金を投じると引くに引けなくなりそのまま続けているって話はよくあります。
その投資は既に回収が不可能であるコストですから、本来はその時点で辞めるのが正解だったりするのですが・・・
株で損切りできないのはサンクコスト
株式投資でも同じです。
サンクコストが働いてしまうケースが多くあります。
例えばある株を1,000円で買いました。
その後、不祥事がありその株は500円に落ちます。
しかし、1,000円で買ったという買値を気にするため損切ができません。
1,000円になるまで塩漬けをしてしまうのです。
不祥事があった時点でその会社の価値は大きく変わっているのに買値に縛られているのです。
たぶんもう1,000円の価値はないとわかっていてもサンクコストを考えてしまうため動けないのですね。
コンコルドの誤りも同じ意味
ちなみにサンクコストのことをコンコルド効果とかコンコルドの誤り、コンコルドの誤謬と言うこともあります。
意味はほぼ同じです。
コンコルドは飛行機を作っている会社ですが、あるとき新型の飛行機を開発する際に多額の投資をしました。
しかし、途中で開発が難航し利益を出すのは難しいとわかっていたにも関わらず、過去の投資金額が無駄にしたくないという心理が働いてそのまま開発をしてさらに大きな損失を出した事例から名付けられました。
どことは言いませんが、なんか日本でも同じような話を今も聞きますね・・・(笑)
サンクコストは大企業ほど陥りやすい
サンクコストは頭が良い人、プライドが高い人ほど陥りやすいと言われています。
また、企業で言えば大企業ほどサンクコストにハマる傾向が本当に強いのです。
過去の過ちを認めたくない、責任を取りたくなのでしょう。
7Payを損切りできたセブンイレブンはすごい
ここ数年の事例ではセブンイレブンの7Payなんかはサンクコストを考えずによく撤退できたな、って思います。
セブン&アイ・ホールディングスグループが鳴り物入りではじめた同社のスマホ決済の「7Pay(セブンペイ)」
2021年7月1日からサービス開始したものの、不正利用が相次いだこともあり、2021年9月末で終了するとの発表がありました。
当然、失敗ですから批判が多かったですが、個人的にはセブン&アイ・ホールディングスの評価が上がった今回の判断でしたね。

サンクコストに打ち勝つには
それではサンクコストに打ち勝つためにはどうすればよいのでしょう?
今を意識する
最大のポイントは過去の投資などは忘れてしまい、今を意識して最善の策を常に考えることです。
前述のようにサンクコストはすでに戻ってこない部分です。
それを意識していては足かせになるだけなんですよ。
ですからその部分は忘れて今で常に判断できるようにすることが大事です。
成功している投資家の多くは含み損とか含み益とかあまり考えないそうです。
今その銘柄が今いくらでそれは買いなのか、売りなのか、ホールドなのかを判断しているだけなんですよ。
自分の買値、売値を意識するとその判断が歪んでしまうためです。
有名投資家のcisさんも自著の中にサンクコストについて書いてますね。
機会費用を意識する
サンクコストと対になってよく使われる言葉に「機会費用」というものがあります。
機会費用とはある選択を行うことで選択しなかったものの価値のことです。
例えば前述に映画の話。
2000円払ってしまったからとつまらない映画を2時間見続けます。
もし、はじめの30分でこりゃダメだと判断すれば残りの1時間30分は他のことに使えます。
そのほかの事が機会費用です。
その時間に勉強したり、遊んだりすればもっと有意義だったのかもしれません。
そうった機会費用を意識することでサンクコストに打ち勝ちやすくなるのです。
株でも同じですね。
投資資金が100万。
ある銘柄に捕まってサンクコストで損切りできないようなケース。
もし、すぐに損切りして他の銘柄に乗り換えれば利益がでるかもしれません。
その利益をサンクコストで捕まっているために得られないのです。
そういった判断ができるようにしたいところ・・・
タイパを意識
最近はタイパ(タイムパフォーマンス)というコトバが使われるようになりました。
コスパ(コストパフォーマンス)の時間(タイム)バージョンです。
時間をより有効に活用しようってことです。
「タイパが良い」とは、使った時間に対して満足度が高いことを意味となります。
タイパを意識すればサンクコストも生まれにくいでしょうね。
まとめ
今回は「つまらない映画を最後まで見続ける人は株式投資に向いていない?【サンクコスト】」と題してサンクコストについて見てきました。
サンクコストにハマらないように意識しておきたいところですね。
なお、他にも投資に関しては心理が働いています。
以下の記事も合わせて御覧ください。