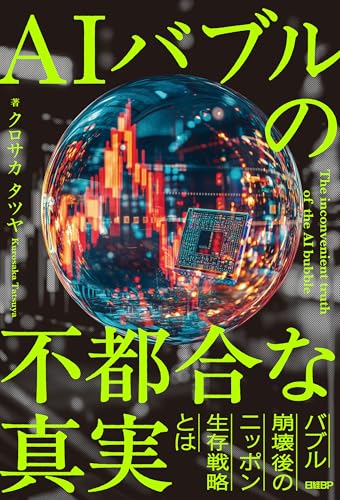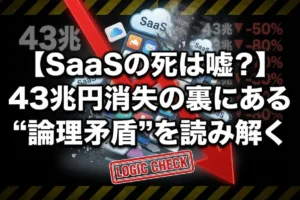生成AIブームの中心にいるOpenAIやエヌビディア(NVIDIA)のニュースは、日々、期待をかき立てます。
しかし、昨今心配される声も出ています。
業界内の資金がぐるぐる回る「循環投資」の色合いが強まっているからです。
相場が崩れた時の連鎖は大きくなってしまうんですよ。
今回は循環投資の落とし穴について考えてみましょう。
循環投資とは何か:株式の世界で起きる「需要の前借り」
循環投資は難しく聞こえますが、実態はシンプルです。
以下のような流れなんですよ。
目立つリーダー企業(例:GPU供給者)が、周辺のAI新興企業へ出資する
↓
出資を受けた企業は、性能競争で先行したいがゆえに、出資元の高価な半導体・サービスを積極的に購入する
↓
売上が伸びたリーダー企業の株価・信用力が上がり、さらなる投資余力とPR効果が生まれる
↓
市場全体の「期待」が一段引き上がり、同様の取引・提携が広がる
これ自体は違法でも不当でもありません。
ただし、需給の土台が「実需の拡大」より「資金の循環」に寄りすぎると、利益の裏づけが弱いまま評価が上積みされやすく、逆風で一気にしぼむ危うさをはらみます。
AIの足腰が“本当に”強いのか、それとも“循環の熱”で大きく見えているのか。
ここを見抜くのが投資家の腕の見せどころです。
言葉が似ていますので循環取引と混同しないようにしましょう。

いまAIで起きている「循環」の具体像
実際今起きている循環投資に見ておきましょう。
エヌビディアの積極投資と買い手の同時拡大
エヌビディアは2024〜2025年にAI関連の出資・提携を多数実行。
社外のAI企業に資本参加しつつ、その企業群は学習・推論のためにNVIDIA製GPUやDGXなどのシステム、あるいはNVIDIAエコシステムに依存を深める。
この循環が疑念と期待を同時に膨らませています。
こうした“循環的”な構図への懸念はセルサイドの著名アナリストからも挙がっています
OpenAIの前のめりな設備需要と巨額ディール
OpenAIは推論サービスの拡大と次世代モデル開発で、前例のない計算資源と電力を必要とします。
設備・電力需要の桁が大きすぎるため、資本提携や長期の調達契約が連鎖的に生まれ、投資の“輪”がいっそう太くなる。
報道では、NVIDIAとOpenAIの超大型資本・供給提携が取り沙汰され、規模・相互依存の大きさから競争政策(独禁)面の視点まで言及される状況です。
また、OpenAIのサム・アルトマン氏自身が、より多くの製造・資金パートナーをグローバルに探し回っているとの報道もあります。
足元のキャッシュフローより先に、将来の供給網・電力網を確保しにいく“前のめり”の動きです
タイムライン
直近でもこのような投資が行われています。
- 2023/1/23
Microsoft→OpenAI 約100億ドル出資。以後、OpenAIはAzureを大量利用=出資と購買が同じ輪で回り始める。 - 2025/8/27
NVIDIA FY26 Q2:売上466.7億ドル、うちデータセンター411億ドル。上流(GPU/DC)に需要集中。 - 2025/9/22
NVIDIA→OpenAI 最大1,000億ドルの覚書。初回100億ドル拠出/10GW規模のNVIDIAシステム導入前提=出資⇄購買の結合がさらに強化。 - 2025/10/4
報道:OpenAIのサーバー賃料見込み2025年160億ドル → 2029年4,000億ドル。需要前提が桁違いに拡大。 - 2025/10/15
BlackRock・NVIDIA・MicrosoftなどがAligned Data Centersを約400億ドルで買収へ。自己資本300億→最大1,000億ドル動員想定、電力5GW規模のDC確保。
MS→OpenAI、NVDA→OpenAIの例のように、資本注入⇄長期調達コミットがセットで回っているんですよ。
IMFや大手運用の「過熱」シグナル
過熱懸念は、いまや投資界隈の雑音にとどまりません。
IMFはAI投資ブームが景気を押し上げている一方、ドットコム期との比較で“バブル様相”のリスクに言及しています。
「ITバブル」と「AIバブル」は同じか
昨今の株価はAIバブル、半導体バブルといっても良い状況です。
しかし、まだAIの成長はこれからでバブルは始まっていないという話もあります。
そんなAIバブルと比較されがちなのがITバブルです。
比較してみましょう。
論点① バリュエーションの偏り
S&P500上位銘柄の割高感は、ドットコム期以上だとする見方があります。
金利水準、指数の構成、ハイテク比率の上昇を踏まえると、「上位の超大型に集中した高バリュエーション」という点で当時より偏りが強いとの分析です
論点② 実体投資の厚みと収益モデル
一方で、1999年〜2000年頃と違い、今は半導体・データセンター・電力など“実体インフラ”への投資が先行・併走しています。
利益を出す中核企業も多く、ITバブル時の「広告収入頼みの赤字新興」とは土台が違う、という逆張りの見方も根強い。
論点③ 需給ショックと価格破壊のリスク
それでも、モデルの性能競争や新規参入(例:低コストで高性能をうたう新興モデル)が“価格破壊”を起こすリスクは見逃せません。
2025年序盤には、中国勢の台頭報道をきっかけに、AI関連の時価総額が大きく揺れた局面もありました。「循環の熱」で拡大した売上期待が、一瞬で尻すぼみになるのがこの相場の怖さです。
ITバブル崩壊から学べること
ITバブルの崩壊から2つのことが言えます。
1つ目は、「指数全体に居続ければ、時間が解決してくれた」では済まなかったという点。
2000年初頭の時価総額上位ハイテクを長期保有した投資家の多くは、その後15年超のトータルでも市場平均に届かなかったという検証があります。
上位集中が進む時ほど、“優勝劣敗”の見極めが効きます。
2つ目は、「バブルの遺産」が次の繁栄を作ったこと。
ITバブル崩壊は痛かったけれど、当時の過剰投資が光ファイバー網やサーバー普及を加速し、のちのクラウド・スマホ経済を支えました。
現在のAIバブルでも、データセンター・電力・モデル基盤への投資が“過剰”で終わるのか、“次の成長土台”になるのか、バブルでないのかは今がちょうど分かれ道かもしれません。
「サム・アルトマンのマイダスタッチ」の功罪
サム・アルトマン氏を“マイダスタッチ”と称える論調が各所に見られるようになっています。
マイダスタッチとはギリシャ神話のミダス王に由来し、「触れたものを金に変える力」を指す言葉で、サム・アルトマン氏が動けば巨大な資金と供給網が動き、関連銘柄が大きく反応するところから比喩されるように。
物語としては魅力的ですが、投資の世界では「物語先行」が過熱を生みます。
国内の解説・コラムでも、アルトマン氏を中心とした巨額の“循環”の描写が増え、読者を引きつけています。
投資家としては、物語の熱と現実のKPIを意識的に切り分けたいところですね。
循環投資の「引火点」はどこにあるか
投資家としては引火点となりえるポイントを意識しておきましょう。
相互依存の強まり(供給も資本も同じ輪)
供給者(GPU・電力・クラウド)と需要者(AIサービス)が、資本提携・オプション契約・長期の売買契約で太く結び付くほど、輪は強固になります。
しかし、どこか一社に利益失速・規制・訴訟などのショックが来ると、輪の全体にストレスが回ります。
エヌビディアとOpenAIの関係強化が独禁面で注目されるのも、相互依存の強さゆえです。
収益化の“タイムラグ”
AIの社会実装は進んでいるものの、社内のPoC(実証実験)段階が長引き、ROIが見えないまま投資が先行している企業も多いとの指摘があります。
これは、需給の輪が“お金の循環”で保たれている部分があるということ。
企業の投資回収が遅れれば、発注が減速し、上流の設備サプライヤーの計画修正につながります。
マクロの冷や水(金融環境・政策・規制)
IMFの懸念にある通り、AI投資が景気統計を押し上げている間はよくても、金利・電力制約・対中サプライチェーンなどの“現実の制約”がボトルネック化すれば、評価は見直されます。循環の輪は、マクロの冷や水で一気に冷えます。
まとめ
今回は「「循環投資」の落とし穴:サム・アルトマン“マイダスタッチ”とAIバブル崩壊リスクを実例で検証」と題して生成AI界隈の循環投資の危うさについて見てきました。
AIは、人材・設備・電力・規制の“重い現実”を伴うテーマです。
そこに巨額の資金と物語が絡み、循環の輪が太くなっています。
私たち投資家がやるべきは、「その売上・受注は、資金の輪が生んだ“前借り”ではないか?」と常に自問すること。
バブルは“熱”で測れませんが、キャッシュフローと投下資本、契約の質、在庫・受注のタイミングは測れます。
熱に浮かされず、この“測れるもの”を見る。
これが、崩れたときに致命傷を避ける一番の近道かもしれません。
にほんブログ村