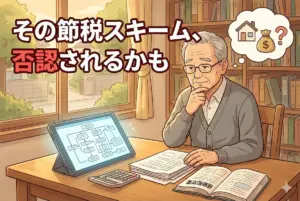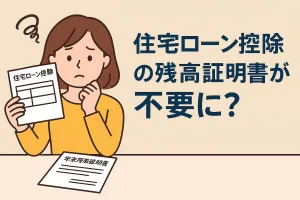働き方改革がどうやら可決されそうな感じですね。
働き方改革は1億総活躍社会に向けての制度ですが、その中に非正規社員と正社員の格差是正というのが盛り込まれています。
具体的には同じ仕事をした人には立場に関係なく同じ賃金を払うべきという同一労働同一賃金があります。
速攻性があるルールではなさそうですが今後はこの方向に是正されていくことは間違いないでしょう。
そうなると可能性が広がるのが主婦の方です。
能力はあるけどちょうどよい仕事が見つからず、生産性の高くない仕事についている人たちも活躍できる場が広がるのです。
しかし、日本の制度にはいくつか問題があります。
それが壁です。税金面、社会保険面など様々な壁があり、中途半端に働きすぎてしまうと損をしてしまう可能性もあるのです。
今回はこの壁と主婦の働き方改革について考えてみたいとおもいます。
※加筆修正をしました。
主婦の働き方の壁(扶養、配偶者控除など)について考える
主婦の方の壁はいろいろな部分であります。
まず、壁として考えられるのが税金、次に社会保険、さらに家族手当、住民税、他にも保育園の費用などです。
つまり、どれだけ稼いだらよいのかは様々な面から考える必要があるのです。
まずは税金面からみていきましょう。
税金面の壁:103万円、150万円
配偶者控除はこれにより主婦の社会進出を減らす要因になるということで一時期は廃止の議論が活発にされていました。
しかし、結局は配偶者控除の金額が少し改正(2018年から)されて決着しています。
詳しく見ていきましょう。
配偶者控除とは
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。
これを配偶者控除といいます。
簡単に言えば配偶者(妻)がいる人をで妻の収入が少ない人は生活大変でしょうから少し税金面で優遇してあげましょうってことです。
配偶者控除の金額
配偶者控除の控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額、及び控除対象配偶者の年齢により次の表のとおりになります。
| 控除を受ける方の合計所得金額 | 控除額 | |
| 控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
| 900万円以下 | 38万 | 48万 |
| 900万円超950万円以下 | 26万 | 32万 |
| 950万円超1000万円以下 | 13万 | 16万 |
老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます
控除を受ける方の合計所得金額は給料額と違う
控除を受ける方の合計所得金額は給料の額面ではありません。
そこから所得税計算上の控除等を引いた金額(所得)のことです。
ですから給料のみで収入を得ている場合、年収1120万円の方で所得900万となります。
つまり、年間の給料(額面)が1120万円以下だと38万円控除が受けられる。
1120万円超〜1170万円以下だと26万円控除が受けられる
1170円超〜1220万以下だと13万円控除が受けられる
1220万超だと控除が受けられないということになります。
103万円の壁とは
配偶者控除の条件で「年収103万円以下」って話を聞いたことある方が多いと思います。
これに基づいて働き方をセーブしている話はよく聞きますね。
ある意味一番有名な主婦の働き方の壁かもしれませんね。
でもこれは正確には少し違うのです。
正確に覚えておきましょう。
正確には「合計所得金額が38万円以下」です。
前述の控除を受ける方の合計所得金額と同様に控除を受けたあとの金額が38万円以下ということです。
パートやアルバイトの給料のみ受け取っている方は逆算すると「年収103万円以下」ということになりますので数字は間違えていませんが・・・。
もし、パートやアルバイトなどの給料所得以外の収入を得ている場合は計算が異なり103万円とはなりませんのでご注意ください。
これ以内に押さえれば夫が「配偶者控除」を最大限に適用できます。
つまり、夫の節税につながるということですね。
さらに、これに加え、妻は社会保険料の負担がない、所得税が非課税というメリットがあります。
配偶者特別控除
主婦の方の所得が38万円(パートのみの給料なら103万円)を超えた場合にはまったく控除がなくなるかと言えばそうではありません。
(ここを勘違いしている方が多い気がします。)
配偶者特別控除というものがあります。
配偶者特別控除の控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額、及び控除対象配偶者の年齢により次の表のとおりになります。
| 控除を受ける方の合計所得金額 | |||||
| 900万円以下(年収1120万円) | 900万円超950万円以下(年収1170万円) | 950万円超1000万円以下(年収1220万円) | 1000万円以上(年収1220万円) | ||
| 配偶者の合計所得金額 | 38万超〜85万円以下(年収150万) | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 0円 |
| 90万円以下(年収155万) | 36万円 | 24万円 | 12万円 | 0円 | |
| 95万円以下(年収160万) | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 0円 | |
| 100万以下(年収166.8万) | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 0円 | |
| 105万以下(年収175.2万) | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 0円 | |
| 110万以下(年収183.2万) | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 0円 | |
| 115万以下(年収190.4万) | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 0円 | |
| 120万以下(年収197.2万) | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 0円 | |
| 123万以下(年収201.6万) | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 0円 | |
| 124万超(年収201.6万 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
税金面なら150万円が目安
103万円の壁を意識してちょうど103万円までにおさえるよりも余分に働いたほうが家計として生活費が増える可能性があるのです。
例えば、旦那さんが900万円以下(年収1120万円)の家庭で103万円に押さえた場合と150万円まで働いたケースを考えてみましょう。
この場合、どちらも旦那さんの控除額38万円と同じです。
しかし、妻の収入が47万円増えますので家計は楽になるはずです。(実際には税金等もありますのでそのまま増えるわけではありません)
だったら、余裕があるなら150万円まで働いた方が得となるはずです。
今後は税金面を考えるなら150万円が一つの目安となります。
社会保険の壁:106万円、130万円
もう一つ意識をしておくと良いのが社会保険の壁です。
社会保険では通勤費込みで106万円と130万円にそれぞれ壁があります。
ちょっとややこしいのが130万円の壁は社会保険は通勤費も含めることになっているところですね。
106万円の壁は含みません(笑)
勤め先の社会保険加入の壁:106万円
まずひとつ目が社会保険の壁106万円(月額8万8千円)です。
これは大企業にお勤めの方に該当するルールです。
具体的には下記の条件を満たす場合、勤め先の健康保険、厚生年金に加入することになります。
つまり、旦那さんの扶養に入れなくなるのです。
2. 給料が月額8万8000円以上
3. 社会保険の対象となっている従業員(被保険者)数501人以上の企業に勤めていること。
4. 雇用期間が1年以上の予定
5. 学生以外(夜間・定時制は除く)
「従業員数(被保険者)が501人以上」の条件は事業所ではなく会社単位で判断します。
該当しているかどうかは勤め先に聞くのが1番早いですね。
大企業の店舗でアルバイトしている場合にはこちらに該当することが多いでしょう。
ただし、これ一概に損とは言えません。
たしかに勤め先の社会保険に入ることになると旦那さんの社会保険の扶養になれなくなります。
また、社会保険を払うことになりますので手取りは減るでしょう。
しかし、社会保険に加入すると将来の年金が増えます。
また、遺族年金や障害年金なども手厚くなり、怪我等で働けなくなったときも傷病手当がもらえるようになります。
そのため一概にどちらが得とは言えないのです。
※追記:厚生労働省が従業員数(被保険者)が501人以上の制限を撤廃しさらに現状月額8万8000円以上の条件を月額6万8000円以上に改定する案を検討始めましたね。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://ideco-ipo-nisa.com//17493]
扶養者の壁:130万円
次は旦那さんの扶養に入れるかどうかの壁です。
こちらはこんな条件となります。
見込み年収が130万円未満、かつ、被保険者の年収1/2
つまり、これから1年間の収入が130万円以上になりそうかどうかで判断されます。
こちらは会社から支給される通勤費も加算して計算します。
細かい算定のルールは旦那さんが加入している健康保険組合等により微妙にことなりますので確認しておきましょう
もし、これを超えると旦那さんの扶養に入れなくなるため、国民健康保険、国民年金に加入する必要が出てきます。
国民年金も国民健康保険もかなり高いので、少しだけ超えてしまうと手取りがマイナスとなります。
ちなみに平成30年4月からの国民年金保険料は月額16340円です。(平成31年4月からの国民年金保険料は月額16410円)
つまり、年間19万6千円にもなります。
国民健康保険は県によってかなり金額が違いますので県のWEBページでご確認ください。
結構負担が重くなりますよね。
そのため俗にいう160万の壁を意識するとよいでしょう。
160万円の壁
160万円(通勤費込み)の壁とは旦那さんの扶養を抜けた場合に手取りが増える境目です。
つまり、中途半端に130万を超えると手取り面でみればかなり損ですが、160万円を超えてしまえば夫婦を合算した場合の手取りが増えることになります。
その辺りも考えて調整する必要があります。
その他の壁
他にも壁があります。順番に見ていきましょう。
住民税非課税の壁:100万円
住民税にも壁があります。
それは非課税の壁です。
住民税非課税なのは100万円-65万円(給与所得控除)=35万円となります。
これを超えると住民税が課税対象となります。
家族手当、配偶者手当の壁
旦那さんの会社に家族手当や配偶者手当がついている場合にはご注意ください。
働きすぎるとこの手当が無くなる可能性があります。
これは会社によりルールがまちまちですから、一度就業規則等で確認しておくと良いしょう。
保育園、幼稚園の壁
保育園や幼稚園にも注意しておきましょう。
自治体により料金が家族年収で計算するところがあります。
自治体により計算方法が違いますのでこちらはあらかじめ確認をおすすめします。
壁を特に意識しなくてよい人
基本的に壁を意識しなくて良い人もいます。
それは旦那さんが自営業者や年金受給者などの方です。
この場合には前述した所得税の控除は意識したほうが良いでしょうが、社会保険の106万、130万、160万円の壁は意識しなくて良いです。
自営業者などの場合にはそもそも社会保険の扶養という制度がないため、国民健康保険、国民年金に加入する必要があります。
そうなればたくさん働いた方が家庭は潤うはずです。
ちなみに、自営業者でも法人化していれば給料もらっている方と同じですから壁は意識する必要があります。
まとめ
今回は主婦の働き方改革について考える。いくつもある壁を意識するといくら稼ぐのがよいのかというテーマで見てきました。
ややこしいところもありますが、まとめるとかんな感じです。
特に意識したいのは税金面の壁である103万円、150万円、そして社会保険の壁である106万円、130万円です。
それらを意識してどれだけ働くとよいのかを考えましょう。
(1)配偶者控除適用により夫の節税になる
(2)社会保険料の負担なし
(3)所得税非課税
(1)配偶者特別控除適用により夫の節税になる
(2)社会保険料の負担なし
(1)配偶者特別控除適用により夫の節税になる
(2)社会保険料の負担なし(106万の壁対象外の場合)
(1)配偶者特別控除適用により夫の節税になる
150万ちょい超えくらいがかなり割に合わないかもしれませんね。
夫の配偶者特別控除適用が少なくなり、社会保険の負担が多くなりますので130万未満で働いたほうが夫婦間の手取りは多くなる可能性があったりします。
ある程度フルに働けるならば160万を超えて働いたほうが、こういう細かいことを考えるよりもたくさん働いたほうが家計面ではプラスになりますね。
またプチ起業の場合はこちらの記事を御覧ください。
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://ideco-ipo-nisa.com//20455]
読んでいただきありがとうございました。