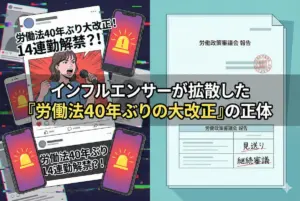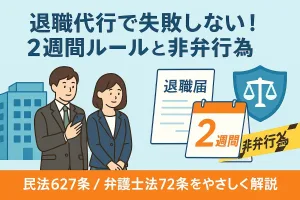最近、毎日のようにSNS で「開示請求します」という言葉を見るようになりました。
法律的にかなり開示請求のハードルが下がったことが大きいのでしょう?
今回はSNS で頻出する開示請求の仕組み・費用・期間・成功率・された側の正しい対応まで初心者向けにわかりやすく整理します。
ちなみに私も開示請求を真剣に検討をしたことがあったりします笑
「開示請求」は2種類ある
ちなみに開示請求といっても大きく分けて二種類あります。
こちらを混同しないようにはじめに見ておきましょう。
本来の意味の“開示請求”とは
開示請求の本来の意味はこちら。
行政機関が保有する自分の個人情報の開示を求める制度です。
国税庁を例にすると、所定様式で申請し、本人確認・手数料の納付(1件200~300円のレンジ)等を経て開示を受けます。
近年は e-Tax 等によるオンライン申請の整備も進みました。
SNSで言う“開示請求”=「発信者情報開示」
一般的にSNSなどでよく見かける開示請求の意味はこちら。
正式名称は「発信者情報開示」なんですが、なぜか開示請求という言葉が一般的に使われてしまっていますね。
SNSや掲示板で名誉を傷つけられた等の権利侵害を受けた被害者が、投稿者を特定するためにプラットフォームやプロバイダへ発信者の情報(IP アドレス、タイムスタンプ、氏名・住所など)の開示を求める手続です。
2022年10月施行の改正により、「発信者情報開示命令」という新しい非訟手続が導入され、従来より迅速な救済が図られるようになりました。
法的背景:プロバイダ責任制限法の改正と、侮辱罪の厳罰化
最近、SNSで「開示請求します」というのをよく見るようになったのは2つの法律が改正されたことが大きいと思われます。
発信者情報開示命令の創設(2022年10月施行)
1つ目は発信者情報開示命令の創設です。
従来はプラットフォーム→アクセスプロバイダと二段階の裁判が必要で時間・コストがかかるのが難点でした。
改正により、コンテンツプロバイダ(SNS等)とアクセスプロバイダを同一手続の中で扱える新手続が創設され、要件やフローが整備されています。
裁判所サイトには申立書式・フローチャート・チェックリストが公開されています
侮辱罪の厳罰化(2022年施行・時効延長)
もう一つが侮辱罪の厳格化です。
SNS上の悪質な誹謗中傷が社会問題化したことを背景に、侮辱罪の法定刑が引き上げられ、公訴時効も1年→3年に延長されました。
これによりインターネットでの中傷に対する刑事上の抑止力が強化されています。
ただし、Xなどでは今でも侮辱は当たり前のように見かけますね・・・
「アホ」や「馬鹿」などでも侮辱に該当する可能性があります。
ちなみに侮辱罪の法定刑は
一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
です。
ネットの開請求の基本的な流れ
次に開示請求の基本的な流れを見ていきましょう。
ステップ1:証拠保全(最優先)
削除される前に、URL・投稿全文・アカウントID・日時・スクショ等を保存。
弁護士へ早期相談すると保存の抜け漏れを防げます。
WEB上の誹謗中傷・侮辱の場合はWEB魚拓を取るサイトがありますので、そういうのを使うのも一般的
ステップ2:削除依頼・送信防止措置の申出
多くのサイトはオンラインフォーム等で削除依頼や送信防止措置を受け付けており、発信者への照会期間が7日程度とされる運用もあります。
削除依頼と並行して、IPアドレス等の開示請求(任意開示)を行うこともあります。
ステップ3:裁判所の「発信者情報開示命令」申立て
任意で進まない場合、発信者情報開示命令を申し立てます。
あわせて提供命令(ログの保全)を組み合わせ、特定不能を防ぐ運用が行われます。
書式・フローは前述の裁判所サイトが充実しています。
ステップ4:アクセスプロバイダから契約者情報の開示
SNS 事業者から得た IP・タイムスタンプを基に、接続プロバイダへ契約者情報の開示を求め、氏名・住所等を取得します(非訟手続の中で連続的に処理できるのが改正のポイント)。
ステップ5:その後の対応(民事・刑事)
特定後は、損害賠償請求・謝罪広告請求等の民事手続、または名誉毀損・侮辱等の刑事告訴を検討します。
この時点ではあくまで相手がだれかわかっただけなんですよ。
慰謝料の相場感は事案により幅がありますが、10万~70万円程度が目安とも言われています。
弁護士費用との兼ね合いで裁判をするかを検討しましょう。
裁判前に示談で決着をつけるケースも多いです。
開示請求の期間の目安と“タイムリミット”
次に期間の目安とタイムリミットをみていきましょう。
全体の期間感
実務では、従来型の二段階ルートで半年~1年程度、新設の発信者情報開示命令ルートで3~4か月程度がひとつの目安とされます(事案・運用で前後)。
裁判まで含めると1年程度はかかる見込みです。
開示請求までのタイムリミット
アクセスプロバイダが通信ログを長期間保存しているとは限らないため、手続が遅れると特定不能になるリスクが上がります。
専門サイトでも、手続開始から10か月前後かかるケースがある旨が示され、早期着手の重要性が強調されています。
費用の目安:弁護士費用・実費・担保金
次に費用の目安を見ておきましょう。
弁護士費用・実費
発信者情報開示に関する裁判所手続の実費が数万円、弁護士費用は数十万円~100万円程度が相場とされます(事案の難易・手続の数で上下)。
仮処分を併用する場合は担保金(概ね10~30万円)が別途必要になることがあります。
費用倒れリスクと損害賠償の相場観
慰謝料の一般的レンジ(10万~70万円程度)を踏まえ、「費用>回収額」となるおそれもあります。
つまり、足が出てしまうんですね。
抑止・再発防止・謝罪の獲得を重視するか、金銭回収を重視するかで戦略が変わります。
弁護士なしで開示請求できる?
前述のように開示請求→裁判になった場合、足が出てしまうケースが多くなっています。
それを回避するためには弁護士を使わないという方法もあります。
開示請求も裁判も弁護士を使わなくてもできるんですよ。(時間は取られます)
東京地裁の公式ページには申立書のWord様式、記載例、チェックリスト、目録の選び方、フローチャートまで用意されており、個人でも辿れる導線が整っています。
手数料や郵便物の扱い(レターパックの予納)も明記されています
ちなみに私は敷金の裁判で弁護士を使うと足が出てしますので、使わず自分で戦いましたね。

費用の目安(本人申立て)
本人申し立ての場合の費用は開示命令・提供命令・消去禁止命令は収入印紙を各1,000円/1申立て。
相手方や申立人が複数ならその人数分が必要です。
申立書の1枚目上部に貼付します。
レターパックライトを相手数分予納(切手の一括予納ではなく、必要段階での予納方式)
全部合わせても1万円で収まるくらいでしょう。
私がやった敷金裁判でもそんなもんでしたね。
本人でやるメリット/デメリット
ただし、本人でやるデメリットもあります。
デメリットとしては記載不備で補正・却下リスク(主文/目録の設計ミス、要件事実の不足など)。
争点が複雑(複数プラットフォーム、海外事業者、刑事手続との並行等)なケースだと準備が素人には大変ってことですね。
私が裁判したときはわからない部分は、裁判所に問い合わせて教えてもらいながらやりました。
敷金の裁判は自分でやっている方も多いので、ネットで情報もそれなりにありましたから、そこまで困ることはなかったですけどね。
一番のデメリットは準備が大変だったりや裁判日にいかないといけないという時間的な部分でしょう。
メリットとしては前述したように費用を大きく抑えられる(印紙・郵便の実費中心)という部分です。
開示請求の成功率は?
開示請求をしても開示されないというケースも少なくありません。
どのくらいの成功率なのでしょう?
公開データは限定的
プラットフォーム別・手続別の成功率(開示率)は一般に公開されていません。
一方、近年は事業者側の協力姿勢が高まり、成功率が上がる傾向にあるとの実務家の指摘があります。
成功可否を左右する要素
成功率に影響する要素として、権利侵害の明確性(名誉毀損・侮辱・プライバシー等)、証拠の確実性、迅速性(ログ保全)、申立書の構成(要件事実の充足)などが挙げられます。
このあたりは本人訴訟の場合にはノウハウがないので難しいところではあります。
「開示請求されたら」どうする?
逆に「開示請求された」側の話もみておきましょう。
SNSのレスバ(レスバトル)で開示請求まで発展という話は少なくないんですよ。
通知(意見照会)に落ち着いて対応
開示請求されるとサイト運営者から意見照会(多くは7日程度の回答期限)が届くことがあります。
事実関係を整理し、真実性・公益性・違法性阻却の主張があり得るか、弁護士に相談しましょう。
削除・訂正・謝罪の判断
誤解・過失が明らかな場合は早期の削除・訂正・謝罪で紛争リスクを下げられます。
反対に、故意・悪質性が高い投稿は、民事・刑事の責任(侮辱罪の厳罰化も踏まえる)を負う可能性があります。
「反撃の開示請求」や“濫訴”への注意
根拠の薄い報復的開示請求は、相手方・裁判所・プロバイダの負担を増やし、場合によっては不法行為的評価を招きかねません。
感情的に動かず、一次情報・法的要件で判断する姿勢が重要です。
まとめ
今回は「開示請求とは?SNS時代に増える開示請求のやり方・費用・期間・成功率等を解説」と題して開示請求についてみてきました。
開示請求自体のハードルはかなり低くなっています。
しかし、判例を見る限り、弁護士費用を賄うのも難しいというのが実情です。
コストと時間、抑止効果などの部分を天秤にかけて考える必要はありそうです。