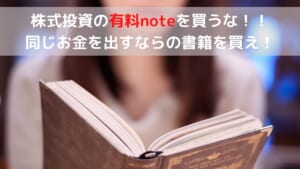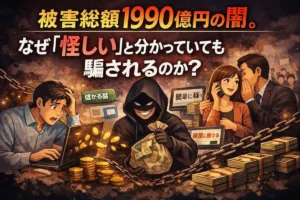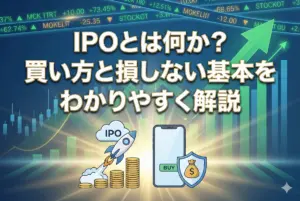最近、メタプラネットなどのビットコイントレジャリー企業のMSワラントの発行が増えています。
しかし、SNSなどを見ているとMSワラントの影響をよく理解していない方がかなり多いように感じます。
昔から株をやっている人はMSプラントを発行する企業はかなり敬遠するんですけどね・・・
今回はMSプラントの仕組み、株価への影響、発行企業の狙いなどを詳しく解説していきます。
MSワラントとは
まずはMSプラントとはなにか?からみていきましょう
まずはここだけMSワラントの基本
MSワラントは正式名称「行使価額修正条項付きの新株予約権」です。
簡単に言えば新しい株を発行して投資家などから資金調達をする方法ですが、発行後に行使価額(新株に変える時の価格)が株価に合わせて下がることがあるのが最大の特徴。
これにより、引受側は株価が下がっても行使しやすい一方、既存株主には希薄化(株が増える)や需給悪化の懸念が生まれやすい——これが“嫌われやすい”理由です。
金融庁も発行件数の増加や、メリット・デメリットの丁寧な説明不足を課題視し、モニタリングすると明記しています。
普通のワラントとなにが違う?
通常のワラント(新株予約権)との違いもおさえておきましょう。
通常のワラントは行使価額は原則固定です。
MSワラントは行使価額に下限(フロア)を設けつつ、株価連動で下方修正されます。
この差が、株価下落局面でも新株が継続的に市場へ出やすい構造につながります。(=需給が緩みやすい)。
論文でも、MSワラント発表時の株価反応は有意にマイナスで、下限行使価額が低い・発行予定株式数が多いほど下落が強まりやすいと検証されています。
MSワラントを行使すると株価はどうなるのか
基本的にMSワラントが行使されると株価にマイナスに働くケースが多いです。
そのメカニズムも知っておきたいところ。
MSワラントで株価が下がりやすい理由(需給×希薄化×シグナル)
下がりやすい理由は大きく3つあります。
需要の悪化
1つは需要の悪化です。
引受側が行使→株を市場で売却する流れが続くと、売りが増えやすいのです。
希薄化
2つ目は希薄化です。
これはワラントでも同じですが、新株が増えると1株あたり利益は薄まる形となります。
つまり、単純に1株あたりの株の価値が下がるのです。
会社全体でみれば変わらないというのがポイント。
シグナル
3つ目はシグナリングです。
前述した論文でも書かれていますが、MSワラントは資金繰りや負債負担が重い企業が“ラストリゾート”として使う傾向があり、市場がネガティブに受け止めやすいということです。
私もですが、昔から株をやっている人は特にこの印象が強いですね。
業績不振などで金融機関などから資金調達がうまくできない会社が利用するイメージがあります。
前述の論文(2002–2019年、325件対象)では、発表日にマイナスの株価反応、下限行使価額が低いほど下落が強い、発行株数が多いほど下落が強いことなどが確認されています。
3つのシナリオ
MSワラントを発行した場合の3つのシナリオをあらかじめ意識しておきましょう。
需給悪化が続く:平均12カ月24.1%、24カ月39.4%下落のデータも
ほとんどがこれ。
行使→売却のサイクルが続くと、上値が重いレンジ相場もしくは下落相場になりやすいです。
行使株数が大きい/フロアが低いほど、重さは長引きがち。
実際に株価が下がるというデータもあります。
一橋大学の論文です。
2004–2018年、505社・847件を分析したところMSワラントの発表日に平均−2.6%の下落、発表後12カ月で−24.1%、24カ月で−39.4%の超過収益(市場調整後)と報告しています。
事業の進展で需給を吸収
滅多にありませんが、プラスに働くシナリオもあります。
資金使途が業績に結びつき市場が成長加速を織り込んで、悪材料を吸収することもあります。
このパターンでは特にR&D集中の企業で、資金制約が緩み→投資が進み→業績回復というケースが多いよう。
設計・運用で副作用を抑制
行使停止条項やロックアップ、売却制限、行使上限など設計で売り圧の“速度”を落とす工夫もあります。
MSワラントの発表がされたらIRで条項をしっかり確認しましょう。
MSワラントの発行企業は何を狙っているのか?
それではMSワラントを発行する企業の狙いを考えて見ましょう。
発行側のメリット
一番大きなメリットは株価水準が定まらない局面でも、投資家は行使価額が修正されるため、MSワラントを行使しやすく、企業は安定して資金を調達できるという部分です。
また、行使の進捗に応じて資金が入ることや(ただし裏返すと完遂しないリスクも)、通常の借り入れと違い、負債ではなく自己資本が厚くなるという部分もあります。(財務体質の改善)。
投資家(既存株主)のデメリット
逆に既存株主はデメリットが多くなります。
まずは、発表時点から需給悪化懸念で売られやすいという株価下落リスクがあります。
また、行使が進むほど株数が増えるため、希薄化が進んでしまうというデメリットもあります。
つまり、発行側には大きなメリットがあるけど、既存株主側にはデメリットが大きいというのがMSワラントなんですよ。
MSワラントを発行する企業の特徴
発行企業の共通点はレバレッジが高い/ROAが低い/規模が小さい/株価変動が大きいなどです。
前述したように金融機関等からの資金調達がうまくできないケースに使われるパターンが多い傾向。
また、タイミングとして株価が高い局面で出しやすい傾向もあるようです。
過去には発行前の株価吊り上げが疑われた事例も多かったですね。
MSワラントの発表がされたらチェックしたいポイント
次にMSワラントが発表されたらチェックしておきたいポイントを羅列しておきます。
チェックリストとしてご利用ください。
条項
- 下限行使価額(フロア)の水準:低すぎないか
- 行使割合の上限・日次上限:過度な連続行使を抑える仕組みがあるか
- 行使停止条項:価格急落や一定条件で止まるか
- 売却制限/ロックアップ:実効性ある制限か
- 月次の行使・残数の開示:可視化されているか
(これらはIR資料やQ&Aで確認可能。メタプラネットのようにQ&Aを出す例も)
需給と株主構成
- 発行済株式数に対する潜在株比率(どれだけ希薄化し得るか)
- 大株主の保有・ロックアップ
- 同時期の他手段(公募・CB等)との重なり(売り圧増幅の可能性)
経営の姿勢(金融庁の指摘に照らして)
- なぜMSワラントか?他の調達手段との比較説明が丁寧か
- 資本政策・中期計画との整合
- 既存株主への配慮(還元方針・対話)が見えるか
金融庁は証券会社によるメリット・デメリットの説明徹底を要請しています。
企業側の説明の質も重視ですね。
まとめ
今回は「メタプラネットで話題のMSワラントとは?仕組み・株価への影響・発行企業の狙いをやさしく解説」と題してMSワラントについてみてきました。
発行企業の狙いと、既存株主のデメリット。
株価が下がりやすい理由あたりはしっかり認識しておきたいところですね。
今後その株に投資をしようとする方もIRの条項/Q&A/行使進捗を追い、フロア・発行規模・上限・停止条項を丹念に確認しましょう。
また、リスクが高いと判断したら、「その後」を待って判断でも遅くありませんよ。