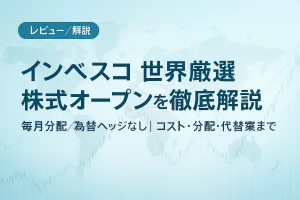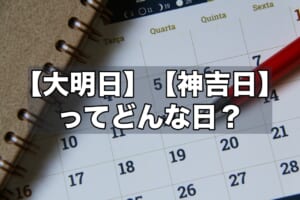2025年夏に発売された『引き寄せの法則を全部やったら、効きすぎて人生バグりかけた話』(角由紀子 著)がAmazonで「本」総合1位・発売3週間で6刷などかなりの話題となっています。
引き寄せの法則自体はかなり古くからオカルト好きの人には知られた話ですが、こちらの本で知った方も多いと思います。
あらためて引き寄せの法則について解説していきましょう。
引き寄せの法則とは(定義と来歴、科学的な位置づけ)
まずは、引き寄せの法則とはなにか?という話からみていきましょう。
シンプルな定義
引き寄せの法則は単純なオカルトではなく、「強く意識したことに、行動や選択が引っ張られて結果が近づく」という自己啓発の考え方に近いものですね。
日本では「思考は現実化する」「ポジティブに考えると良いことが起きる」「自分の思っていることが現実になる」といった説明が広く流通しています。
つまり、思考が現実を引き寄せるという意味で「引き寄せの法則」と言われています。
古くは仏教でも言われているような話です。
なりたい自分を手に入れるための自己宣言「アファメーション」にも近いですね。
思考は現実化するはナポレオン・ヒルなどでも有名ですね。
ザ・シークレット
引き寄せの法則はかなり前にも大流行したことがあります。
ロンダ・バーンの『The Secret(ザ・シークレット)』が大ヒットしたことです。
スピリチュアルやオカルトというよりも世界的な自己啓発ブームの文脈で拡散しました。
映画化までしているんですよ。
私もこの本を読んでいて、何となくレベルではありますが実践してたりします。
科学的根拠は?
引き寄せの法則は学術的には実証が不十分で疑似科学とされるとの整理が一般的です。
一方で、「目標を明確にすると関連情報に気づきやすくなる」という人間の注意の仕組み(RAS=網様体賦活系)で説明できる部分もあります。
RASは脳の覚醒・選択的注意に関わる仕組みとして知られています。
“気づきやすさ”が上がれば、行動や意思決定が変わるのは自然です。
朝のテレビの占いで赤がラッキーカラーとか言われると、無意識に赤いものを意識していしまうという「カラーパス効果」という心理学の理論もありますが、それにも近いですね。
まとめると
・「思考が宇宙のエネルギーで現実を引き寄せる」という説明 → 科学的根拠に乏しい。
・「明確な目標が行動と選択に影響し成果に近づく」 → 心理・脳科学的に説明しうる部分あり(選択的注意・習慣形成など)
現実的な引き寄せの法則のやり方
次に引き寄せの法則のやり方をまとめておいましょう。
ポイントは目的は“都合よく願う”ことではなく、“行動を増やし判断の質を上げる”こと。
以下は、自己啓発界隈で一般的な手順を、実務向けに調整したものです。
意外とここにまとめてあることって会社などでもやっていたりするんですよ。
ゴールを“数字と期限”で一行にする(RASを起動する)
- 例:「年末までに現金100万円の緊急資金」「半年で月3万円の配当」
- RAS(選択的注意)に“何を拾わせるか”をはっきり決めます
「現実のレバー(てこ)」を3つだけ書く
- 収入(本業・副業)/支出(固定費)/運用(積立・配当)の3レバー。
- 引き寄せノートに行動レバーを書き、毎日1つだけ進めます。
1日5分の“視覚化”と“アファメーション”は行動文で
- 「私は〜になった」より「私は毎朝30分、銘柄メモを更新する」のように行動が増える言い回しにします。
- アファメーションや視覚化は自己暗示の一種。怪しげな科学語りは排除し、行動設計の補助輪と割り切ります。
否定形を使わない(注意の向き先を間違えない)
「失敗したくない」ではなく「試算→小さく試す」と書く。注意は向けた先に集まると理解する。
見える化”トリガーを置く
- ホーム画面に目標画像/リマインダー。
- 手帳やデスクトップに短い行動文(例:朝は市場メモ→出社前に積立チェック)。
こうした環境づくりは選択的注意のゲート(RAS)を通りやすくします
よくある誤解と落とし穴
次によくある誤解と落とし穴を見ていきましょう。
「思えば叶う」は順番が逆
思考→行動→選択→結果、の順。
行動が増えない“引き寄せ”は空回りです。
「損失回避」で判断が歪む
人は利益より損失の痛みを強く感じます(プロスペクト理論)。
願望が強いほどその傾向が強くなります。
株で言えば「含み損の放置」や「ナンピンでの正当化」に走りがち。
これは投資的にも大きなマイナスとなりますが、引き寄せの法則的にもマイナスなんですよ。
落とし穴:全部やる=燃え尽きる
断食や過度な習慣化は生活や健康を崩すリスク。
話題書のレビューでも適度な距離感”が強調されます。
引き寄せの法則を全部やったら、効きすぎて人生バグりかけた話レビュー
最後に『引き寄せの法則を全部やったら、効きすぎて人生バグりかけた話』は私も読んでみましたので簡単なレビューを。
著者の角由紀子さんはオカルト系編集者、YouTuber。
瞑想・断食・各種スピリチュアル実践までオカルト的に語られる手法を盛り盛りでやってみた体験記です。
良い変化もあれば、やり過ぎの副作用や生活バランスの崩れも描かれるタイプの作品で、“適度な距離感”の重要性が示唆されます。
やり過ぎと反省を含む“実験記”として読むのが吉。
「効いた要素は、注意の向け方が変わり行動が増えたから」「効きすぎ=優先順位が暴走」と翻訳して捉えると実用的かもしれませんね。
体験記としての読み物も十分リターンがあります。
まとめ
今回は「今話題の引き寄せの法則とはなにか?やり方、効果、科学的根拠などを解説」と題して引き寄せの法則について見てきました。
引き寄せの法則はオカルト的に考えられがちです。
しかし、自己啓発や脳科学(RAS)や心理学(カラーパス効果)などの意味合いでも無視できないものなんですよ。
引き寄せの法則に興味の出た方はまずはこちらの本を読んでみると良いでしょう。