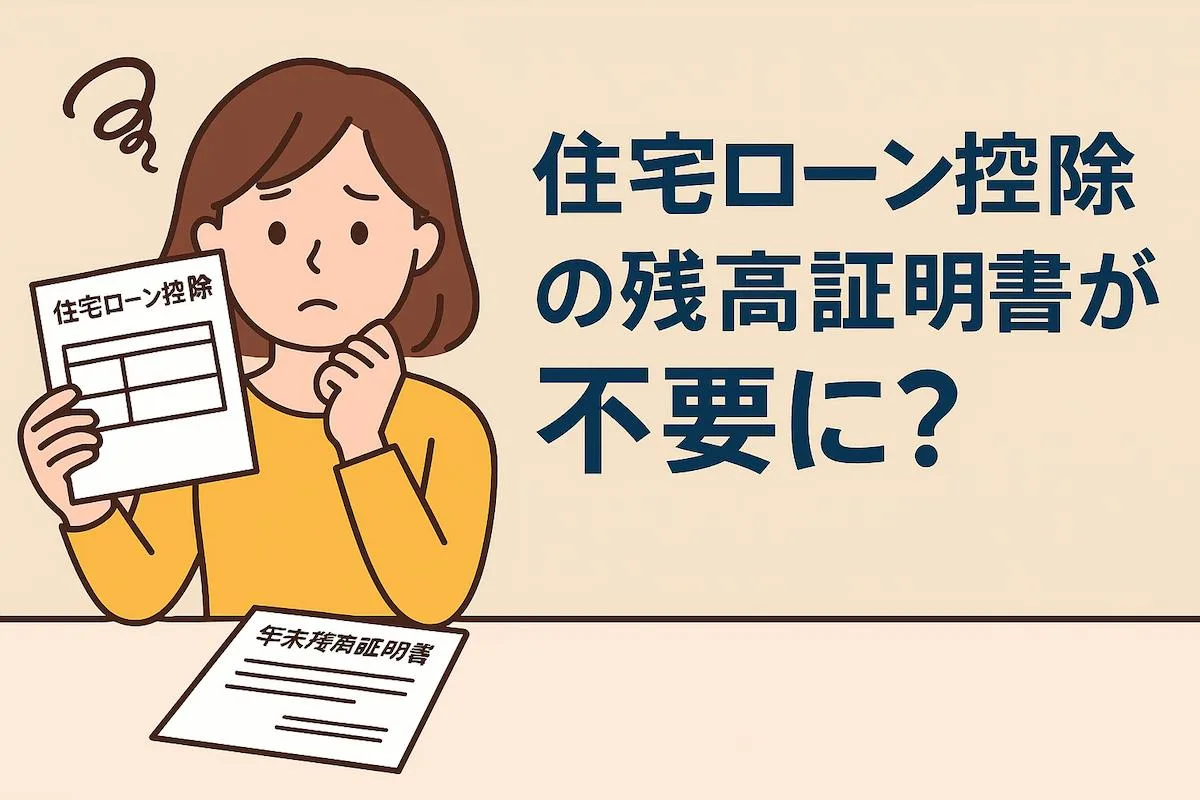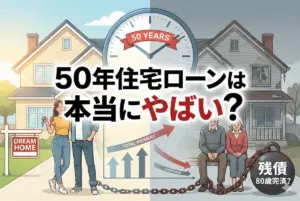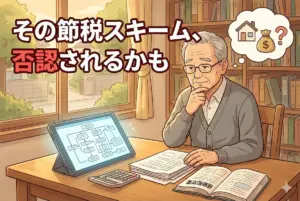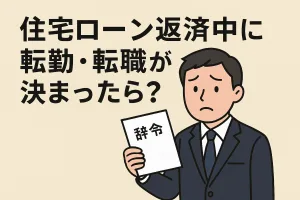「また今年も住宅ローンの残高証明書が届いた…」
10月末ころになると金融機関から届く、住宅ローン控除のための年末残高証明書。
確定申告や年末調整のたびに提出しなければならず、紛失や提出忘れに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
実はこっそりと住宅ローン控除の残高証明書提出が不要になる制度が始まっています。
今回は、住宅ローン控除で残高証明書を不要にする具体的な方法と、知っておくべき注意点をすべてお伝えします。
残高証明書提出の煩わしさ
住宅ローン控除の残高証明書は、従業員にとっても経理担当者にとっても大きな負担となっています。
従業員側
10月末ごろに金融機関から郵送される残高証明書。
年末の忙しい時期に届きますし、多くはハガキ一枚なので他の郵便物に紛れて紛失してしまうケースが後を絶ちません。
また、再発行には時間がかかり、年末調整や確定申告の期限に間に合わないこともあります。
会社側
会社側も負担が大きいです。
従業員が提出する残高証明書の内容確認、金額の転記、書類の保管。
さらに、提出忘れの従業員への催促や、再発行の手配など、年末調整業務を複雑化させています。
放置すると生じる問題
面倒とはいえ放置すると問題が生じてしまうのが住宅ローンの残高証明書です。
住宅ローン控除を受け損ねるリスク
残高証明書を紛失したり提出を忘れたりすると、その年の住宅ローン控除を受けられなくなります。
仮に年間20万円の控除額であれば、それがそのまま損失となります。
投資家の視点で考えれば、20万円を年利5%で運用すれば、10年間で約258万円にもなります。
書類管理のミスで、これほどの機会を失うのは避けたいところです。
確定申告や修正申告の手間
年末調整で住宅ローン控除を受け損ねた場合、自分で確定申告をする必要があります。
普段は確定申告をしない会社員にとって、これは大きな負担です。
「確定申告の仕方がわからない」「時間がなくて申告できなかった」という声を多く聞きます。
実際問題、住宅ローン控除を諦めてしまう方も少なくありません。
残高証明書を不要にする方法
それでは残高証明書を不要にする方法をみていきましょう。
新たに導入された調書方式
令和4年度税制改正により、住宅ローン控除の手続きについて、従来の年末残高証明書を用いる「証明書方式」から、年末残高調書を用いる「調書方式」への変更が行われました。
証明書方式(従来の方法) 金融機関から納税者に残高証明書が交付され、納税者が確定申告や年末調整の際に税務署または勤務先に提出する方式です。
調書方式(新しい方法) 金融機関が直接税務署に「年末残高調書」を提出し、国税当局から納税者に住宅ローンの「年末残高情報」を電子データで提供する方式です。
調書方式を利用すれば、年末残高等証明書の添付は不要となります。
残高証明書を不要にする具体的な手順
具体的な手順を段階的に説明します。
ステップ1:金融機関の対応状況を確認
調書方式に対応した金融機関については、国税庁ホームページで公表されています。
まず、自分の住宅ローンを借りている金融機関が調書方式に対応しているか確認してください。
国税庁ホームページの「調書方式に対応した金融機関の一覧」で検索できます。
令和7年時点では、大手銀行を中心に対応が進んでいますが、すべての金融機関が対応しているわけではありません。
ステップ2:住宅ローン控除の適用申請書を提出
調書方式に対応した金融機関からの借入れについて住宅ローン控除の適用を受ける場合には、住宅ローン控除の適用申請書を金融機関に提出する必要があります。
申請書には、氏名、生年月日、住所、マイナンバーを記載します。
各金融機関で様式が異なるため、借入先の金融機関に確認してください。
多くの金融機関では、インターネットバンキングや窓口で申請できます。
ステップ3:e-Taxの利用者識別番号を取得
マイナンバーカードを持っていない場合や、マイナンバーの提供を希望しない場合は、e-Taxの利用者識別番号を申請書に記載することも可能です。
e-Taxの利用者識別番号は、国税庁のe-Taxウェブサイトまたはマイナンバーカードがあればe-Taxにログインして取得できます。
ステップ4:マイナポータル連携の設定
確定申告でマイナポータル連携を利用する場合は、居住を開始した年内に、e-Taxからの情報取得を希望する事前準備が必要です。
マイナポータルにログインし、「もっとつながる」から国税庁を選択して、情報連携の同意を行います。
この設定により、年末残高情報が自動的にマイナポータル経由で取得できるようになります。
対象となる人・ならない人
なお、この制度は対象となる人、ならない人がいます。
その点も確認しておきましょう。
対象となる人 :令和6年1月1日以降に住宅に居住を開始した方
令和6年1月1日以降に住宅に居住を開始した方が原則的な対象です。
ただし、借入先の金融機関が調書方式に対応しており、適用申請書を提出していることが条件となります。
具体的には、令和6年以降に住宅を購入または新築し、居住を開始した方で、住宅ローン控除の要件を満たしている方です。
対象とならない人 :令和5年以前に居住を開始した方
令和5年以前に居住を開始した方は、原則として従来の証明書方式のままです。
ただし、金融機関によっては令和5年以前の居住者にも調書方式への移行を認めている場合があります。
また、借入先の金融機関が調書方式に移行していない場合は、従来どおりの証明書方式での対応となります。
金融機関が対応していない場合は従来の方式
令和6年から調書方式に対応していることを公表している金融機関は、当初は限定的でした。
2025年現在は大手銀行を中心に対応が進んでいますが、地方銀行や信用金庫の中には、まだ対応していないところもあります。
国税庁ホームページの「調書方式に対応した金融機関の一覧」で、自分の借入先が掲載されているか必ず確認してください。
掲載されていない場合は、従来どおり残高証明書の提出が必要です。
調書方式の落とし穴と対処法
便利なようですが、今の時点では調書方式は落とし穴もあります。
すべての金融機関が対応しているわけではない
この新しいシステムは、全ての金融機関で一斉に導入されているわけではなく、システム対応が間に合わない金融機関については、従来の残高証明書を交付する経過措置が設けられています。
つまり、令和6年以降に居住を開始した方でも、借入先の金融機関が調書方式に対応していなければ、従来どおり残高証明書の提出が必要なのです。
複数の金融機関から借入れている場合
一つの金融機関が調書方式に対応していても、もう一つの金融機関が対応していない場合があります。
この場合、対応していない金融機関からの借入分については、従来どおり残高証明書の提出が必要です。
すべての借入先の対応状況を確認し、どの方式で申告するのが最も効率的か検討してください。
勤務先が電子データでの年末調整書類の受付に対応していない
また、勤務先が電子データの提出を受付できず、書面でしか受領できない場合は、QRコード付証明書等作成システムを利用して、書面で出力して提出する必要があります。
事前に勤務先の経理部門に確認し、電子データで提出できるか、それとも書面での提出が必要かを把握してください。
書面での提出が必要な場合でも、マイナポータルから情報をダウンロードし、QRコード付き書面として出力できるため、残高証明書の原本を保管・提出する必要はありません。
よくある質問と回答
次にみなさんからよくある質問について回答をしていきましょう。
Q1:令和5年以前に居住を開始した場合は使えないのですか
原則として、調書方式は令和6年1月1日以降に居住を開始した方が対象です。
ただし、借入先の金融機関の判断により、令和5年以前の居住者にも調書方式への移行を認めている場合があります。
まずは借入先の金融機関に問い合わせて、調書方式への移行が可能か確認してください。
Q2:マイナンバーカードを持っていないと利用できませんか
マイナンバーカードがなくても、e-Taxの利用者識別番号を取得すれば、調書方式を利用できます。
申請書にe-Taxの利用者識別番号を記載して金融機関に提出してください。
ただし、マイナポータル連携を利用した自動入力機能を使うには、マイナンバーカードが必要です。
より便利に使いたい場合は、マイナンバーカードの取得をお勧めします。
Q3:勤務先が電子データを受け付けてくれない場合は
勤務先が電子データでの提出を受け付けていない場合は、QRコード付証明書等作成システムを利用して、マイナポータルからダウンロードした電子データを書面として出力してください。
この書面は、従来の残高証明書と同様に勤務先に提出できます。金融機関からの原本の提出は不要です。
Q4:途中で住宅ローンを借り換えた場合はどうなりますか
借り換え後の新しい金融機関が調書方式に対応している場合は、新たに適用申請書を提出する必要があります。
借り換え前の金融機関への申請とは別に、借り換え後の金融機関にも申請してください。
借り換え後の金融機関が調書方式に対応していない場合は、その金融機関から従来どおり残高証明書が交付されます。
Q5:証明書方式しか使えないときのe-Taxは?
申告送信後にPDFイメージで添付できます。
紙提出よりも後追いが効くので、紛失時は借入先で再発行→スキャンで代替可能です。
まとめ
今回は「住宅ローン控除の残高証明書が不要に?e-Tax連携で書類提出を省略する方法」と題して住宅ローン控除の残高証明書についてみてきました。
金融機関が限定されていたり、入居日により使えなかったりとまだまだ課題は多いですが、対象となる方は残高証明書の提出を原則不要になりました。
正直、残高証明書が不要になったからそこまで劇的に変わるわけではありませんが、今後のことを考えて試してみてもよいでしょう。
税務手続きのデジタル化は、今後も加速していきます。
早い段階で対応しておけば、将来の手間を大幅に削減できます。
また、マイナポータルやe-Taxの使い方に慣れておくことで、今後導入される新しいサービスにもスムーズに対応できますしね。