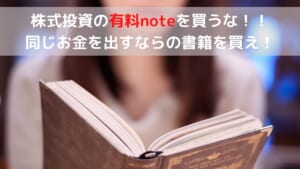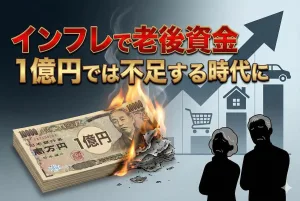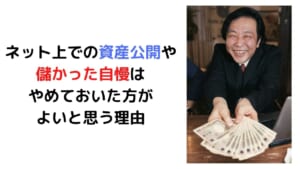2024年以降、物価高騰と金利上昇を背景に、賃貸住宅の家賃値上げ通知が急増しています。
国土交通省の調査によれば、2024年の賃貸住宅の家賃改定率は前年比で約1.8倍に増加しました。
「突然、家賃を5,000円上げると通知が来た」「値上げを断ったら退去を迫られそう」──そんな不安を抱えている方も多いでしょう。
結論から言えば、家賃値上げは必ず応じる必要はありません。
借主には拒否する権利があり、法律で守られています。
結論:家賃の値上げは「合意がないと成立しない」
まずは結論から見ておきましょう。
借主側は拒否も交渉も可能です。
法律上は、借地借家法32条(賃料増減額請求)により、相場・税金・経済事情の変動などで賃料が不相当なら、将来に向かって増減を請求できるとされています。
これは貸主側だけじゃなく借主にも認められているんですよ。
つまり、大家が一方的に「来月から○万円アップ」と通知しただけでは、法律上、自動的に新しい家賃に切り替わるわけではないのです。
「一方的に通知=自動で値上げ」ではありません。
借主側は、
- 根拠を確認する
- 内容に納得できなければ交渉する
- 場合によっては拒否する
ことができます。
まず値上げの根拠資料の提示を求め、周辺相場や現状(設備老朽化など)を踏まえて冷静に交渉しましょう。
ポイント:時期の決まりは法律に明文なし(更新時に多いが、時期の定めはない)ため、通知が来た時点で根拠確認→交渉が基本。
借地借家法32条「賃料増減額請求権」とは
家賃の値上げ・値下げのルールは、借地借家法32条で定められています。
ポイントは以下の点。
- 賃料が「不相当」になった場合、将来に向かって増減を請求できる
- この権利は貸主だけでなく借主にも認められている
- 「不相当」の判断基準は、土地・建物価格、公租公課、経済事情の変動など
- 効力は請求の意思表示が到達した時点から発生(原則、過去には遡らない)
つまり、値上げ通知が来ても、それが「相場や経済事情から見て妥当か」を検証する権利があるということです
大事なのは、
- 権利は 貸主だけでなく借主にもある
- あくまで「請求」であって、相手が自動的に従う義務があるわけではない
という点です。
「請求→話し合い→合意できれば新家賃、合意できなければ調停・裁判へ」というのが、法律上の基本的な流れになります。
効力は“将来に向かって”発生。
また、効力は将来に向かって発生するということも覚えて起きましょう。
原則、過去に遡っての増減はできないのです。
効力を発揮するタイミングは、請求の意思表示が相手に到達した時点からとなります。(「◯月分から」等の指定があればその時点)
ただし、値上げ請求→裁判等で相当額が確定すると、到達時点に遡って差額の精算が必要になることがあります。
このあたりは後述する交渉するうえでも重要な論点ですので覚えて起きましょう。
定期借家契約の注意点(特約があると32条が外れることも)
定期借家(借地借家法38条)では、賃料改定の特約があれば32条の適用を外すことができます(38条9項)。
その場合、契約の特約が優先されます。
契約書の賃料改定特約を必ず確認しましょう。
具体的には以下の項目です。
- 契約書が「普通借家契約」か「定期借家契約」か
- 定期借家の場合、賃料改定の特約があるか
- 特約がある場合、その内容(改定時期、改定方法など)
普通借家と定期借家で扱いが異なるため、拒否・交渉の戦略も変わります。
本来は賃貸借契約を結ぶ際にしっかり確認するのが良いんでしょうけどね。
下記の記事のような事例もありますので難しいところではあります。
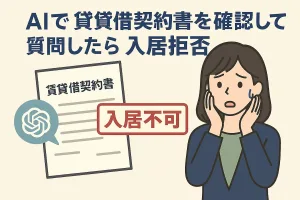
なお、借地借家法の条文を読まれたい方は以下のe-Gov法令で確認できます
>>e-Gov法令
家賃の値上げは「何%までOK?」という誤解
よくある誤解があります。
家賃の値上げは「◯%までならOK」というものです。
結論から言うと
- 「10%まではOK」
- 「○円までは合法」
といった一律のルールは、借地借家法にも民法にも存在しません。
これを理由に値上げを迫ってくる大家や管理会社も多いそうなので、知っておきたい部分です。
おそらく大家や管理会社側もそんな法律がないことは知っていて、こちらが知識がないだろうことを良いことに承諾させるために言っているのでしょう。
では、何を基準にするのかというと、裁判例などでは、
- 周辺の賃料相場との比較
- 物件の立地・築年数・設備などの属性
- 税金・物価など経済事情の変化
といった要素を総合的にみて、「客観的にみて妥当な額かどうか」が判断されています。
つまり、「○%なら絶対問題ない/絶対アウト」といった線引きはできず、個別事情ごとの判断になる、というイメージを持っておくのがおすすめです。
大家や管理会社から「法律で○%まで認められている」と言われた場合は、その発言自体を疑ってかかるくらいでちょうどいいでしょう。
ちなみに給料の減額には限度が設定されていたりします。
それとの勘違いを狙っているのかもしれません。

家賃値上げ通知が来たときのチェックリスト
では、実際にポストに値上げ通知が入っていたら、何から手をつければよいでしょうか。
焦って返事をしたり、感情的に電話をかけたりする前に、次のポイントを落ち着いて確認していきましょう。
通知の内容と「根拠」が書かれているか
まずは、通知の内容を丁寧に読みます。
- いつからいくらに上げたいのか
- 値上げの理由・根拠が書かれているか
ここで、よくあるのが
「周辺相場の上昇に合わせて家賃を見直します」
とだけ書かれていて、具体的な資料が何も添付されていないケースです。
この場合、
- どんな相場データを見ているのか
- 固定資産税など公租公課の増減はどうなっているのか
- 物件の老朽化・未修繕箇所などは考慮しているのか
など、具体的な根拠資料の提示を求めるのが基本です。
自分でも周辺相場や物件状況を確認する
貸主側の資料を待つと同時に、借主側でもできる範囲で相場を調べておきましょう。
- 同じエリア・似た築年数・広さ・設備の募集賃料をポータルサイトで確認
- 自分の部屋に不利な条件(駅から遠い・日当たり・騒音・共用部の劣化など)がないか洗い出す
「今の家賃が高すぎる/それほど高くない」の感覚を、数字と客観的な情報で持っておくと、後の交渉がかなりやりやすくなります。
契約書・特約のチェック
先ほど触れたように、
- 普通借家か定期借家か
- 賃料改定に関する条項・特約がどう書かれているか
によって、取れる戦略が変わってきます。
- 「更新時に双方協議のうえ賃料改定」程度の一般的な記載なのか
- 「消費者物価指数等の変動に応じて改定する」といった具体的ルールが書かれているのか
契約書のコピーを手元に置きながら整理しておくと、その後に弁護士や相談窓口に持ち込む際にもスムーズです。
家賃値上げの「断り方」と交渉の進め方
値上げの内容や根拠を見ても納得できない場合は、きちんとした形で「いったん増額には応じられません」という意思表示をしておきましょう。
断るときの基本スタンス
ポイントは、
- 感情的にならず、あくまで「理由付き」でお断りすること
- 電話よりも、メールや書面など「記録が残る方法」で伝えること
です。
話し合いが長引いたときに、「言った/言わない」で揉めないよう、やり取りの履歴はできるだけ残しておきましょう。
メール・書面の例文、イメージ
細かい文面は状況によって調整が必要ですが、イメージとしては次のような内容です。
- 値上げ提案を受け取ったことへのお礼
- 値上げの根拠資料を求める一文
- 自分でも周辺相場や物件状況を確認した結果の簡単な説明
- 現時点では増額には応じられない旨
- 今後も円滑な関係を希望する、という一言
こうした形で「一方的な拒絶」ではなく、「根拠が確認できれば検討はするが、今の情報だけでは合理性に疑問がある」というスタンスを示すと、相手も強引に押しにくくなります。
例えばこんな感じのメールや書面を送ると良いでしょう。
〇〇(物件名・部屋番号) 借主の△△と申します。
このたび家賃増額のご提案を拝受しました。
つきましては、増額の根拠資料(近傍同種の賃料比較、固定資産税等の増加、経済事情の変動の具体資料)のご提示をお願いできますでしょうか。
当方で周辺相場を確認したところ、現状の賃料は近隣相場と大きな乖離は見受けられませんでした。また、室内設備の老朽化や未修繕箇所(例:給湯器の度重なる不具合等)もあり、現状では増額の合理性に疑問がございます。
誠に恐縮ですが、現時点では増額には応じかねます。
今後も円滑な関係を希望しておりますので、根拠資料のご提示とあわせて、必要であれば現地確認や修繕のご相談もさせてください。
それで大家側からでてきた内容に納得できれば承諾すればよいだけです。
交渉を有利にするための材料
交渉をするうえで以下の証拠資料を用意しておくと有利となります。
- 近傍同種の募集賃料(駅距離・築年数・専有面積・間取り・設備)
- 物件の不利益要素(日照・騒音・結露・共用部の劣化・未修繕の記録)
- 公租公課や経済事情の変動の資料提示を求める(貸主側根拠)
交渉のコツは数値と一次情報で話すことです。
相場表・修繕履歴・設備交換見積など「根拠」を添付しましょう。
また、こちら側から代替案を出すのもおすすめです。
今すぐの大幅増は困難なら段階増額・共益費見直し・修繕実施を条件など。
また、できるだけ感情論を避け記録を残しましょう。
交渉は言った言わないの話になりかねないので、メールなど履歴が残るメディア中心が良いでしょう。
要点は箇条書き、期限を区切るのも重要です。
交渉に入る時点で撤退ラインをある程度決めておくのも良いでしょう。
もし、撤退ラインを超えるようなら転居も含めて検討しましょう(事前に転居先や転居コストも見積もりしておきましょう)
住まいダイヤル(国交大臣指定の住宅相談窓口)などで相談を事前にしておくのもおすすめです。
>>住まいダイヤル
非弁行為に注意
なお、交渉は基本的に管理会社を通さず大家と直接がおすすめ。
管理会社ができるのは事務手続きや伝達(伝書鳩)のみ。
具体的な交渉まで管理会社がやっている場合は、非弁行為(弁護士じゃない人が法律行為しちゃだめよ)となる可能性があります。
管理会社はこのあたりかなり緩いので指摘してあげるのも効果的です。

逆に自分が交渉をするのではなく、他の人(弁護士以外)に頼む場合も非弁行為として指摘される可能性がありますのでご注意ください。
代理が必要なら弁護士に依頼しましょう。
話し合いでまとまらない場合:調停前置と裁判の流れ
それでも折り合いがつかない場合、いきなり訴訟というわけにはいきません。
賃料増減額は「調停前置」
まず民事調停(簡易裁判所)が原則となります。(民事調停法24条の2)。
つまり、
- まず簡易裁判所で「民事調停」を申し立てる
- そこで話し合いによる解決を試みる
- それでもまとまらなければ訴訟へ進む
という順番が原則になります。
調停と聞くと構えてしまうかもしれませんが、
- 手続き自体は書式に沿って申立書を書く形で、個人でも十分対応可能
- 調停委員(弁護士や不動産の専門家など)が間に入って調整してくれる
ので、「いきなり法廷で対決」というイメージとはかなり違います。
調停書式や費用・提出物の案内例は各地裁HPに掲載されています。
それほど難しいものではありませんので、弁護士等に依頼しなくても可能です。
判決・調停成立後の「差額精算」と利息
調停や裁判で最終的な家賃額が決まると、
- 値上げ通知が相手に届いた時点
までさかのぼって、「本来払うべきだった家賃との差額」を精算するのが一般的です。
ここで注意したいのが、不足分に対する利息の扱いです。
借地借家法32条には、差額の不足分について「年10%」の利息特則が置かれています。一般的な民法上の法定利率(2025年時点では年3%)よりも高い水準です。
このため、
- まったく支払わずに放置する
- 「値上げに納得いかないから0円しか払わない」
という対応を取ると、後からまとめて差額+利息を支払うリスクが大きくなってしまいます。
「払わない」はNG。係争中の支払い方
トラブル時の原則は、
「自分が妥当と思う額は払い続ける」
というスタンスです。
- 現行家賃だけは払い続ける
- 相手が一方的に通知してきた増額分までは払わない
といった対応をとっておけば、「滞納」を理由に契約解除・明渡しを迫られるリスクを一定程度抑えられます。
調停でも不成立なら訴訟へ。
それでもまとまらない場合は訴訟となります。
家賃値上げ相当額を裁判所が判断します。
私も弁護士を使わず裁判したことがありますが、難しそうに見えますが意外と敷居は低いんですよ。

Q&A:家賃値上げのよくある質問
最後に、ニーズの多い疑問をQ&A形式で整理しておきます。
Q1. 家賃値上げを拒否したら、更新拒否や退去を迫られますか?
値上げに納得できず、合理的な理由をもって交渉・拒否しているだけであれば、それだけを理由に直ちに更新拒絶・退去とはなりません。
ただし、
- 長期にわたる滞納
- 誠実な交渉を拒み続ける
など、信頼関係を損なう事情が重なると、更新拒絶や明渡し請求の材料にされる可能性もあります。
感情的に対立する前に、第三者(相談窓口や弁護士)を間に入れるのがおすすめです。
Q2. 「口頭での家賃値上げ通知」だけでも有効ですか?
法律上、口頭での意思表示でも足りるとされますが、後々のトラブル防止のためにも、
- できれば書面やメールでの通知を求める
- 自分のメモにも日付・内容を残しておく
など、記録を残しておくべきです。
Q3. 値上げ幅が「相場より少し高いかな?」という程度なら、争うだけ損ですか?
係争にかかる時間や精神的な負担を考えると、「多少の増額なら割り切る」という判断も現実的な選択肢の一つです。
- 転居コスト(敷金・礼金、引っ越し費用、家具家電の買い替えなど)
- 転居に伴う生活上の負担
も含めて、「今の家に住み続けるメリット」と比較し、自分なりのラインを決めておくと迷いにくくなります。
まとめ
今回は「大家から家賃の値上げ通知が来たら?「家賃値上げ 拒否・断り方・法律」完全ガイド」と題して賃貸の家賃値上げ通知が来た場合の話を見てきました。
ポイントは値上げ通知の根拠をしっかり確認することですね。
そしてそれで納得できるかです。
できなければ交渉、退去、調停、裁判などの選択となります。
物価高や金利上昇の局面では、今後も家賃値上げの話は増えていくかもしれません。
いざというときに慌てないよう、借主として押さえておきたいポイントを、ぜひ頭の片隅に置いておいていただければと思います。
今のうちに知識を蓄えておきましょう。