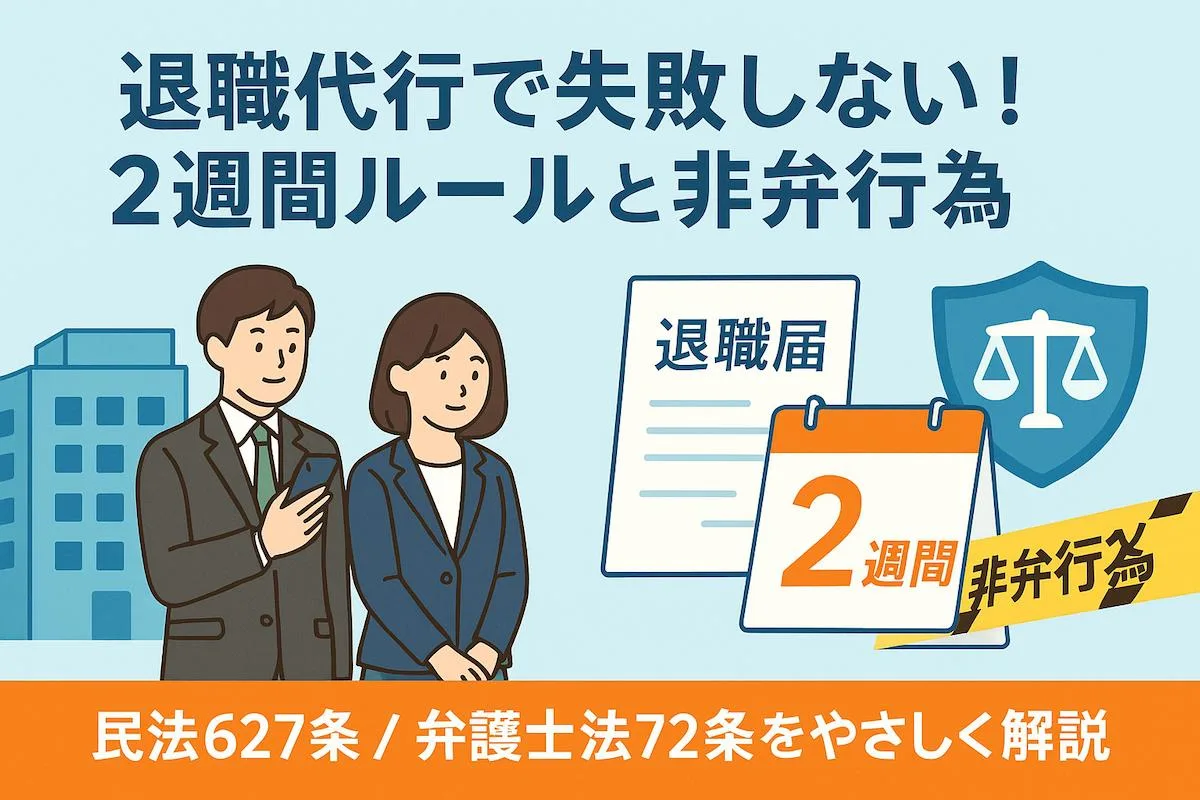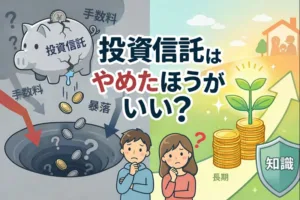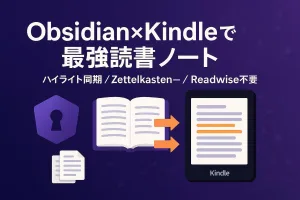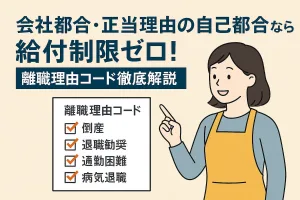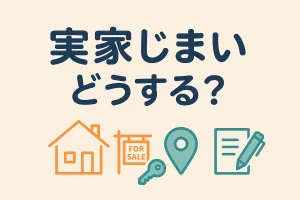「会社が怖くて言い出せない」「交渉ごとは任せたい」――そんな時に頼りになるのが“退職代行”。
最近はやっていますね。
でも、法律の線引きを知らずに依頼すると逆にトラブルを呼ぶことも。
この記事では、民法627条の“2週間ルール”と弁護士法72条の“非弁行為”を中心に、退職代行を安全に使うための法律知識をわかりやすく解説します。
※追記:退職代行大手のモームリに家宅捜索が入りましたので追記しました。
退職代行とは?まずはサービスの正体を理解しよう
退職代行とは、労働者本人に代わって「退職したい」という意思を会社へ伝えるサービスです。
単なる“連絡代行”だけの業者もあれば、弁護士が交渉まで担うタイプも存在します。
ポイントは以下の3つ。
・意思表示の伝達:退職届を提出・電話やメールで退職意思を伝える
・手続きのサポート:貸与物返却や書類のやりとりを代行
・交渉の可否:退職日の調整、有給消化、残業代請求など“交渉”
「退職は申し出後2週間で自由」— 民法627条のルールを整理
退職代行を利用する前にまず知っておきたいのは退職に関する法律です。
民法627条1項が定める“2週間ルール”
期間の定めのない雇用契約は、退職の申入れから2週間で終了します。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
出典:民法第627条1項
言い換えると、会社の同意がなくても2週間経てば辞められる、というのが原則です。
つまり、退職を申し入れてから2週間が経てば、使用者の承諾がなくとも退職できるってことですね。
ですから、自分で言えるなら退職代行を利用しなくても2週間で辞められるのです。
ちなみに会社側は「すくなくとも30日前にその予告を」とされていますので、従業員側が有利な条件となっているのです。
就業規則に「1カ月前申告」とある。その場合どうなる?
就業規則では「退職の申し出は1カ月前申告」とある企業が多いです。
この場合、どうなるのでしょう?
結論を言えば民法の強行規定ではなく任意規定と解されるため、原則“法が優先”と考えられています
つまり、前述した「会社の同意がなくても2週間経てば辞められる」というのが原則ってことです。
ただし、基本的には民法の方(2週間)を優先されるとの判断ですが、過去の判例の中には就業規則の規定を優先する旨を認定したものもあります。
ですから揉めたくなければ就業規則等のルールにしたがったほうが無難でしょう。
有期契約社員・試用期間中は?
契約社員の方や試用期間の場合はどうなるでのでしょう?
簡単にまとめるとこんな感じとなります。
- 有期契約:期間満了前の退職は原則できませんが、やむを得ない事由があれば解除可能(民法628条)。
- 試用期間:無期雇用と同様に扱われることが多く、2週間ルールが適用されるケースが一般的。
※詳細は個別契約・就業規則・判例により異なるため、専門家へ確認しましょう。
非弁行為とは?弁護士法72条が禁じる“越えてはいけない線”
次に退職代行を使うなら必ず知っておきたい超えてはいけない線について見ていきましょう。
弁護士法72条の概要
弁護士または弁護士法人でない者が、報酬目的で“法律事件に関する法律事務”を業として行うことを禁止しています。これがいわゆる「非弁行為」です。
・弁護士法72条
弁護士又は弁護士法人でない者は,報酬を得る目的で訴訟事件,非訟事件及び審査請求,再調査の請求,再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定,代理,仲裁若しくは和解その他の法律事務を取扱い,又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし,この法律又は他の法律に定めがある場合は,この限りでない。
非弁行為は意外と使える知識ですから覚えておいて損はないですよ。
実はいろいろなところで問題になる話です。

罰則規定
違反すると「2年以下の懲役または300万円以下の罰金」(弁護士法77条4号)という重い罰則対象になります。
ここまでOK/ここからNG 早見表
この非弁行為を退職代行にあてはめるとこんな感じの判断になります。
| 行為例 | 法律判断の目安 | 根拠・解説 | 退職代行業者(非弁)がやると? |
|---|---|---|---|
| 本人の退職意思を“伝えるだけ” | 使者行為=OKの可能性 | 単なる伝達で交渉なし | 原則OK。 |
| 退職日や有給消化日数を交渉 | 代理交渉=非弁行為の恐れ | 法律上の権利義務調整 | NG。弁護士or労働組合に依頼を |
| 未払い残業代・退職金額の計算と折衝 | 法律事務・交渉=アウト | 弁護士法72条該当 | 完全NG(東京弁護士会も具体例で指摘) |
| 退職届の作成サポート(テンプレ提供) | グレー(単なる書式提供なら) | 内容チェック・助言で線引き注意 | 注意。個別法的助言は非弁リスク |
弁護士 or 労働組合なら交渉できる理由
弁護士:法律事務の独占業務。退職金・残業代など金銭請求交渉も合法。
労働組合:労働組合法に基づき、団体交渉権を持つため、退職条件に関する交渉が可能と解されます。実際、労働組合に加盟した退職代行サービスは交渉可能とうたう例も
モームリの事例
捜査関係者によると、家宅捜索したのは同社本社など複数箇所。退職を希望する依頼者が企業側と交渉する必要が生じた際、依頼者を弁護士に紹介し、紹介料として弁護士側から違法に報酬を得ていた疑いがある。
出典;日経新聞 「退職代行モームリ」を家宅捜索、報酬目的で弁護士紹介疑い 警視庁
モームリの家宅捜索された理由は、弁護士から紹介料を得ていたという部分ですね。
これも禁止されています。
退職代行業者を選ぶチェックリスト
退職代行業者はたくさんあります。
以下の点を確認したうえで検討してください。
- 運営主体の確認:弁護士事務所か、労働組合か、ただの民間企業か
- 契約書・委任状の有無:代理権の証明は必須。ない場合、会社が相手にしないことも。
- 対応範囲の明確化:交渉は不可/可を明示しているか
- 料金体系の透明性:追加料金・成功報酬の有無
- 返金保証・アフターフォロー:連絡がつかない等のトラブル対策
- 個人情報保護体制:プライバシーマーク等、情報管理の仕組み
よくあるQ&A
次によくある質問を見ていきましょう。
- 会社が退職届を受け取らないと言ってきたら?
-
到達主義なので、内容証明で到達させればOK。
2週間後に退職は成立します(無期雇用の場合)。
- 有給消化を拒否された…交渉してもらえる?
-
有給は権利ですが、具体的な消化日数の調整は“交渉”です。
弁護士や労組に任せましょう。(もしくはそれらが運営する退職代行業者)
- 「損害賠償請求するぞ」と脅されたら?
-
適法に退職申出をしていれば原則損害賠償義務は生じません。
ただし例外もあるので専門家に相談を。
- 試用期間中でも辞められる?
-
多くは無期契約扱いで2週間ルール適用。
ただし就業規則や契約内容で異なるため要確認。
- バイト(有期契約)の途中退職は?
-
やむを得ない事由があれば解除可
例えばハラスメント・健康悪化などです。
それらの証拠を残すことが重要。

まとめ:法律を押さえれば“静かに・安全に”退職できる
今回は「退職代行業者を使う前に必読!「2週間ルール」と「非弁行為」の法律知識まとめ」と題して退職代行業者に関わる法律の話をみてきました
退職代行=意思表示の伝達サービスです。
弁護士法72条が禁じる“非弁行為”を理解し、違法業者を避けるのが吉でしょう。
罰則も重いですしね。
弁護士・労働組合なら交渉OKです。
交渉が必要なら弁護士が運営する代行業者を使うのがトラブルリスクを下げることに繋がりますね。