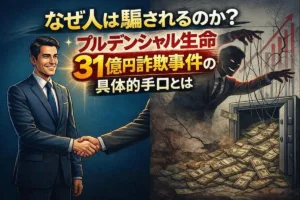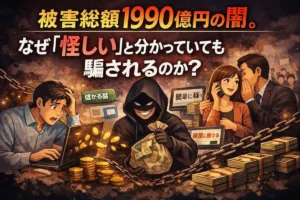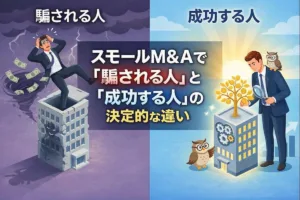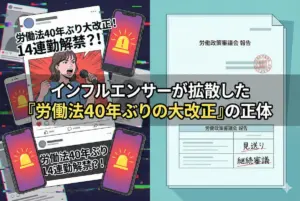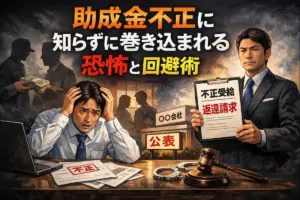2025年になってから生成AIが急激に進歩し、普及してきました。
それに伴い「AI動画で稼ぐ」「ノースキルで月○万円」といったSNS投稿がかなり目立つようになってきました。
ところが、実態は安易な“稼げる系”情報商材や、そこから誘導される高額コンサル契約が少なくありません。
消費者トラブルの公的データでも、情報商材→高額な副業コンサルやセミナーに勧誘というケースが目立つと報告されています。
この手の情報商材屋は手を変え、品を変え時流に乗ったサービスで展開してくるので注意が必要なのです。
今はそれがAI動画なのです。
数年前は暗号資産でしたよね・・・

今回は「AI動画で稼ぐ」は本当?というテーマでその手の情報商材等の注意喚起をしていきたいと思います。
先に結論
先に結論を出しておきましょう。
“AI動画で誰でも簡単に稼げる”とうたうnoteなどで販売されている商材は、購入後に高額コンサルへ誘導される事例が多く、返金トラブルも発生。
自殺者も出るなど社会問題化し始めています。
そもそも素人が書いた有料note買うくらいなら本を買うのをおすすめします。
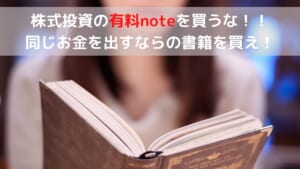
「AI動画副業」情報商材の典型パターン
次にAI動画で◯◯円とかうたう副業の情報商材の典型的なパターンを確認しておきましょう。
これを知っておくだけでもその手の商法にひっかかるリスクはかなり減るはずです。
よくある導線
よくある導線は以下です。
XなどのSNSで不幸な人生だったけどと発信→
AI動画に出会って一発逆転できた等の発信→
「いいね」と合言葉「◯◯」でマニュアルを無料でプレゼントと見込み客を集めと拡散を狙う→
noteなどで比較的安価な商材を販売→
限定コミュニティ(サロン)へ誘導→
高額コンサル(情報商材の売り方の指導)→
自分も情報商材屋に→
結局多くの人はうまくいかないか、情報商材屋にならないと儲からないという流れがほとんどです。
だいたい「先着○名」「24時間限定で無料」などで焦らせるパターンが多いです。
また、返金条件が曖昧。
公的相談でも情報商材→高額契約という流れの被害が多数確認されています。
心理テクニック
また、情報商材屋は心理テクニックを駆使してきます。
「今やらないと置いていかれる」不安の煽り、「1日30分」「誰でも」の簡単アピール、“限定感”や“成功例”の演出がテンプレ化。
実績証明の不在や景品表示法違反の二重価格(いまなら30万円→3万円など)も定番です。
家など高額商品の販売にも使われる心理テクニックも使っているんですよ。

掲示板、SNSで違和感
「買ったけど中身が薄い」「結局、別の高額講座へ」などの体験談・嘆きがSNSなどで並んでいるケースも多いです。
それと同様に儲かったとか絶賛する投稿も出てきます。
個別投稿は玉石混交ですが、絶賛投稿はステマも多いので、マイナスの投稿をよく読み火のない所に煙は立たない。複数の独立情報源を突き合わせる姿勢が重要でしょうね。
悪徳な情報商材屋の見分け方
AI動画に限らず悪徳な情報商材屋の見分け方を確認しておきましょう。
コンテンツの中身
一次情報の出典(YouTube公式サポート等)を示しているか?
示さない場合は危険な信号がでていると思いましょう。
また、収益の根拠(確定申告書、アナリティクス画面の検証可能提示)があるか?
スクショだけであればいくらでも捏造可能です。
販売者・運営の透明性
過去の制作実績と失敗例の開示があるか?をチェックしましょう。
そこがぼやかしていれば怪しいと思ってください。
また、その手のコンテンツを販売するなら義務になっている特定商取引法の表示(所在地・連絡先)があるかを確認してください。
ない場合はほぼアウトです。
また、あっても嘘である可能性があります。
住所や名前を検索してみると見破れるケースも。
返金情報などの具体性も確認しましょう。
さらにはSNSで批判コメントを即ブロックするなど、議論拒否の態度は要注意ください。
契約・支払い
契約を「今だけ」「人数限定」と急かすケースは怪しいです。
また、はじめの金額が低くても後から“別料金”を追加してくるケースもありますのでご注意ください。
そもそも「AI動画で稼ぐ」は可能か?
それではそもそもAI動画で稼ぐことは可能なのでしょうか?
結論から言えば簡単ではないでしょうが、アイデアと努力次第で可能だと思います。
変な情報商材屋に捕まるとかなりの遠回りになってしまいそうですけどね。
YouTubeなどで「AI動画は収益化できない」わけではない
まず知っておきたいのが、2025年7月、YouTubeは反復・大量生産=非真正コンテンツ”の定義を明確化したこと。
“AI動画だから禁止”ではなく、オリジナル性・付加価値の乏しい量産物を排除する狙いです。
人間の視点や編集、解説、教育的・娯楽的価値の追加があれば、収益化の道は残ります。
以下の点がポイントですね。
- 人の解説・批評・教育的価値を明確化(台本の骨子に自分の視点)。
- 素材のライセンスと著作権を厳守。寄せ集め・自動読み上げだけは避ける。
- 反復量産のテンプレ依存をやめ、企画の深さを優先。
つまり、鍵は“オリジナルであること”。
自動音声を載せただけのスライドショーなどは対象外になり得ます。
情報商材屋が教えている内容は自動音声を載せただけのスライドショーってケースが多いらしいんですよ。
そもそも本当に簡単に作れて儲かるなら、それを人に教えることで対策されるリスクがありますので教えてないでしょうね。
収益化の“土台”を整える
どんなビジネスでも基本は同じですが、成功するなら以下の点を意識しましょう。
- 領域選び:得意分野×市場需要(自分の得意な分野で需要がある分野を探す)
- 差別化軸:独自の切り口・検証・数字を足す(ニュース要約だけは避ける)。
- 制作フロー:台本→素材権利確認→編集→自分の声や解説を加える→字幕・サムネ最適化。
- YouTube方針の順守:開示が必要なAI利用は開示し、“本物感”(オリジナル性)を担保する
近道をしようと高額な情報商材に手を出さずに、自分の専門×AIで地に足のついた運用をするのをおすすめします。
トラブルに遭ったら——返金・相談・証拠化
ここからはすでに被害にあってしまった場合の対応を考えてみましょう。
まずやること
まずやることは契約書・販売ページ・広告キャプチャを保存してください。
また、決済履歴も残しましょう。
そして返金条件(クーリング・オフ対象か、表記内容)を確認。
情報商材はネット通販のデジタル提供が多く、法的取り扱いが複雑です。
そのため、なかなか返金が受けにくく、摘発もされないというのが実情なんですよ。
相談先
主な相談先は以下です。
相談内容によって他の相談先をご紹介してくれます。
消費生活センター/消費者ホットライン188
また、国民生活センターのFAQ/事例集で同型トラブルの先例が公開されています。
ケーススタディで学ぶ「危険信号」
次によくあるパターンをおさえておきましょう。
無料note→安価なnote→高額コンサルへ
「無料→1,980円→“伸びしろあり”とDM→コンサル30万円」とだんだん金額を上げて誘導していくパターン。
約束のサポートがほぼない、返金できないと揉める典型例。
“AI動画は収益化不可”を餌にした別売り講座
AI動画は収益不可だからと「この方法ならOK」と更に高額講座を販売。
一次情報に基づかない断定は危険。
公式は“AI利用そのものは問題なし”と明言しています。
SNSでの“成功談”の見せ方
SNSで成功談を見せるのはよくある常套手段です。
多くの場合証拠はアナリティクス画像のみ、人物はイニシャル、証憑がありません。
まずは不幸な人生を見せ、AI動画で一発逆転。
今ではこんないい暮らしをしていますなんて見せるのも典型的なよくあるパターンです。
昔からあるマルチ商法でもよく使われた流れなんですよ。
詐欺の手口は昔からほとんど変わっていないという話もあります。

まとめ
今回は「AI動画で稼ぐ」は本当?“情報商材屋”の罠。手口・見分け方・返金対応を解説と題してAI動画に絡んだ情報商材やが増加しているという話を見てきました。
“誰でも簡単に”をうたう商材には、基本的に怪しいと思って一次情報を確認しましょう
困ったときは188に相談。
情報弱者にならない最短の道は、急がず、検証し、相談することです。