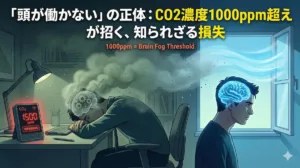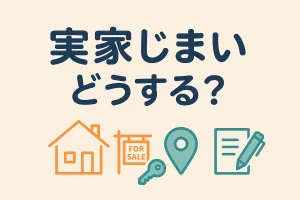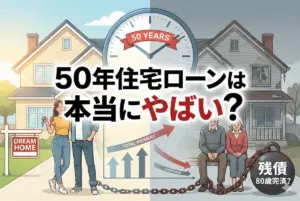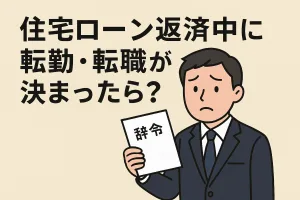「親の土地に家を建てれば、土地代が浮いてコスパ最強では?」——そう考える方は少なくありません。
実際、土地取得費ゼロは大きな魅力です。
一方で、農地転用の許可や届出が必要な「田んぼ・畑」問題、親名義のまま建てると後で揉めやすい名義・権利関係、固定資産税や不動産取得税、贈与税・相続時精算課税の選択、住宅ローン審査(無償借地だと厳しい)など、知らないと損する落とし穴が山のようにあります。
本記事では、共働きで忙しい家づくり初心者のあなたでも迷わないように、メリット・デメリット、税制・手続きの全体像、典型的なトラブル事例まで、やさしく・実務的に整理しました。
「親の土地に家を建てる」前に読むべき保存版ガイドとしてお役立てください。
親の土地に家を建てる「3つの大きなメリット」
まずはメリットから見ていきましょう。
土地取得費がかからない(or極小化できる)
最大のメリットは土地取得費が掛からないことでしょう。
主要都市ならで数千万円かかる「土地代」を節約できます。
「親の土地 無償借地」や「親の土地に家を建てる」キーワードに惹かれるのは、この費用インパクトが圧倒的だからこそですね。
実家の近くで子育て・介護の連携が取りやすい
共働き世帯には特に大きいのは子育てや介護の連携が取りやすいことでしょう。
送迎・体調不良時のサポートなど、頼れる距離は生活の安定に直結します。
おそらく親が自分の土地で家を建てさせたいのはこの部分が大きいでしょうね。
地域や行政の支援策を使える可能性
三世代同居・近居支援、自治体によっては住宅取得補助・固定資産税の軽減措置などがあるケースもあります。
たたし、制度の有無やルールは自治体ごとに異なるため要確認。
親の土地に家を建てる「7つのデメリット・リスク」
次にデメリットやリスクをみていきましょう。
あまり知られていませんが、かなりデメリットが多いんですよ。
うちも親所有の田んぼに家を建てることを勧められたんですが、デメリットを考えて断りました笑
農地(田んぼ・畑)なら農地転用が必要
田んぼや畑に家を建てようとするとあらかじめ農地転用が必要となります。
農地法(第5条等)に基づき、市街化区域なら原則「届出」/市街化調整区域なら「許可」
許可が下りなければ建築不可。
“田んぼに家を建てた友人がいるから大丈夫”は危険です(自治体・区域で全然違う)。
地域によってはなかなか許可が降りないことがあります。
名義・権利関係が複雑化しやすい
親名義のまま家を建てると、相続発生時に兄弟間でトラブルになりがちです。
また、無償使用貸借(タダで使わせてもらう契約)だと、親が亡くなった後に使用貸借が終了しうる点も要注意。
つまり、揉めやすいってこと。
住宅ローン審査が厳しくなることがある
土地が本人名義でない場合、銀行は土地所有者(親など)を連帯保証人・担保提供者に求めるのが一般的。
無償借地では評価が低く、借入が難しい・金利条件が悪化するケースも。
贈与税や不動産取得税、登録免許税など“目に見えないコスト”が発生
土地を贈与してもらえば贈与税が掛かります(対策として相続時精算課税という選択肢も)。
また、贈与でも不動産取得税・登録免許税は(原則)かかります。
固定資産税の負担問題
固定資産税は土地の所有者に課税されます。
親が負担し続けるのか?将来あなたが相続したら?「親の土地 固定資産税」問題は家族会議が必須。
地盤・インフラの追加費用
田んぼや畑は軟弱地盤の可能性が高いです。
そのため、地盤調査・改良費で数百万円になることも。
また、排水・上下水道・道路(接道義務)など、“宅地で当たり前”がここでは当たり前ではないので追加費用がかかるケースも。
将来の資産価値・売却しづらさ
農地転用した元農地は、周辺環境や規制により、売却が難しい・値が付きにくいケースがあります。
また、権利関係も複雑となりますので売るときも大変。
税制・費用で“見落としがち”なポイント
親の土地に建てるといってもいろいろなパターンがあります。
ここが一番ややこしいので、パターン別に表で整理します。
| パターン | 典型的な使い方 | 税金(主に) | 住宅ローン | リスク/注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 無償使用貸借(親名義の土地をタダで借りる) | 親名義のまま、子の家を建てる | 贈与税は基本不要(使用貸借は無償利用なので贈与とみなされにくい)/固定資産税は親 | 融資ハードル高め(担保設定・親の同意が必須) | 親死亡後、相続人が契約解除を主張する可能性。兄弟間で将来揉めやすい |
| 賃貸借(親に地代を払う) | 借地契約を締結し登記 | 贈与税回避の色合い強い/地代収入に親の所得税/固定資産税は親 | 借地権の登記があれば銀行は比較的融資しやすい | 地代の妥当性(相場)や契約内容の整備が重要 |
| 共有名義(親と子で土地を共有) | 共同購入・持分で登記 | 取得持分分の不動産取得税・登録免許税 | 共有者全員の同意が必要で売却・担保設定が面倒 | 将来、共有の“出口”で揉める典型 |
| 贈与(親→子に土地を贈与) | 家を建てる前に名義を子へ | 贈与税(高額)・登録免許税(2%)・不動産取得税(3%※土地) | 子が100%所有で住宅ローンは通りやすい | 贈与税負担が重くなりがち |
| 相続時精算課税(2,500万円控除) | 生前に子へ移転しつつ、贈与税を抑える | 贈与時は非課税でも、将来相続で精算/不動産取得税・登録免許税は発生 | 所有権が子へ移るので融資しやすい | 将来の相続税が増える可能性あり。相続税対策にはならないことも |
税率は原則・一般的な目安です。
個別の特例や軽減措置、タイミングで変わるため、税理士への相談はマストです。
代表的な税金・費用の整理
親の土地に家を建てると言ってもお金はそれなりに掛かるんですよ。
代表的な税金、費用を整理しておきましょう。
贈与税
親から土地をもらうと贈与税の対象。
相続時精算課税制度(2,500万円まで贈与税0円、超過分は一律20%)を選ぶ選択肢あり。
ただし将来の相続で合算されるので“税金繰り延べ”に過ぎない点に注意。
不動産取得税
贈与・売買で土地を取得すると原則課税(標準税率3%)。
登録免許税
所有権移転登記にかかる税。**贈与は評価額の2%**と重い(売買は1.5%など)。
固定資産税
原則、土地の所有者に課税。親の土地に家を建てる場合、誰が負担するか事前に合意しておく。
印紙税
契約書を作成する場合に発生(契約金額等に応じて)。
名義・権利関係と住宅ローンの壁
親名義の土地に家を建てる際の注意点の肝となる点がこちらです。
銀行が気にするのは「担保と返済可能性」
土地の所有者=親、建物の所有者=子というケースでは、銀行は土地に対して担保を設定できないため、融資判断が厳しくなりがち。
よって、親を担保提供者・連帯保証人にする/賃貸借契約を結び借地権を登記するなどの対応が必要となるケースも
代表的な設計パターン
土地は親名義のまま「賃貸借契約(借地権設定)」→登記
- 銀行が担保評価をしやすい。
- 地代の妥当性を示す資料(路線価や近隣相場)があるとベター。
土地を相続時精算課税で子名義へ移す
- 贈与税は抑えられるが、将来の相続税への影響は要確認。
- 住宅ローンは比較的スムーズ。
共有名義(親子)にして、親も担保提供者に
ローンの柔軟性は高まるが、将来の共有解消コストや意思決定リスクが増します。
つまり、仲が悪くなったときに揉めやすいってことですね。
農地転用の手続きとデメリット
前述したように田んぼや畑に家を建てようとすると農地転用という手続きが必要です。
ここからはその点について詳しく見ていきましょう。
市街化区域か、市街化調整区域かで“重さ”が全然違う
まず、その土地の場所が市街化区域か市街化調整区域なのかをしらべましょう。
難易度がかなり違うんですよ。
簡単に解説すれば
・市街化区域:市街化を図ろうとしている区域
・市街化調整区域:市街化を抑制すべき区域
と市町村が地域ごとに指定しているのです。
市街化区域
原則「届出」でOK(農地法第5条の届出)。
比較的スムーズに農地転用が可能です。
市街化調整区域
原則「許可」が必要で、難易度が高い。
住宅を建てる目的の転用は厳しく制限されることが多い。
市町村からすれば市街化を抑制しようとしている地域なので当然と言えば当然ですけどね・・・
地目変更登記も必要
農地転用の許可が下りたら田・畑から宅地へ地目変更登記も必要です。
固定資産税評価が上がる可能性もあるので、「親の土地 固定資産税」問題として家族内で分担を決めておく必要がありますね。
地盤・インフラ・接道のチェック
田んぼ・畑=軟弱地盤の可能性が高く、地盤改良費100万〜300万円超になるケースも珍しくありません。
また、その他にも注意すべきポイントがありますので、あらかじめチェックしておくとよいでしょう。
- 地盤調査結果と改良の要否・費用
- 排水・水捌けの状況(農地特有の水路や暗渠など)
- 上下水道・ガスの引込費用
- 建築基準法上の接道要件(原則4m以上)を満たしているか
- 農業用施設・水利権などの権利関係
- 周辺のハザードマップ(洪水・液状化)
農地転用の申請窓口
一般的に農業委員会(市区町村)が窓口。
書類の要求レベルは自治体で差があります。
ハウスメーカーによっては手続きを代行してくれるところもありますが、お任せにしすぎず、早い段階で自分でも確認をするとよいでしょう。
よくあるトラブル事例
親の土地に家を建てる方は意外と多いですが、揉め事もあるんでしょ。
よくあるトラブル事例もあらかじめ知っておきたいところ。
親名義の土地に家を建て、相続後に兄弟と紛争
親の厚意で無償使用貸借で建築。
親が亡くなった後、相続人(兄弟)が「土地を売りたい/地代を払え」と主張。
最初から賃貸借契約&借地権登記をしておけば、ローンも組みやすく、法的安定性も高かった。
仲の良かった兄弟姉妹でもお金(相続)が絡むと大揉めするのは本当によくあります。
農地転用を甘く見て計画が白紙に
「近所も家を建ててるから大丈夫」と思い込み、市街化調整区域で転用許可が下りず。
ハウスメーカーのプラン・ローン事前審査まで進んでいたが全てやり直しに。
これも実際によくある話です。
無償借地で建てて、借り換えに失敗
金利が下がり借り換えを検討したが、土地の担保が設定できず金融機関が難色なんてケースも実際に多いですね。
まとめ
今回は「親の土地に家を建てるメリットと落とし穴」と題して親の土地に家を建てる話をみてきました。
「親の土地に家を建てる」——土地代が浮く分“得をした気分”でスタートしがちですが、農地転用・税金・名義・住宅ローン・固定資産税……と、検討すべき論点は想像以上に広く深いのが実態です。
逆にいえば、早い段階で“専門家を巻き込んで”全体設計できれば、コストもリスクもグッとコントロールできます。
ハウスメーカーだけでなく、税理士・司法書士・金融機関、不動産屋を早めに並走させて、あなたの家族にとってベストな形を作っていきましょう。
知らずに損をしないための第一歩は早めに確認することです。
土地を買うという選択肢も含めてしっかり検討するのが良いでしょう。