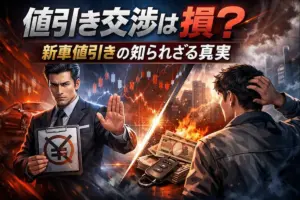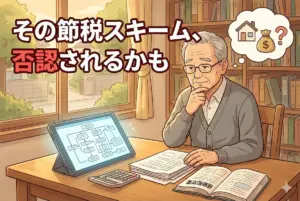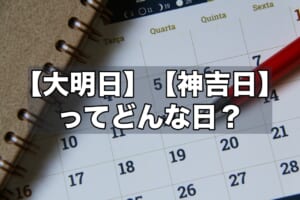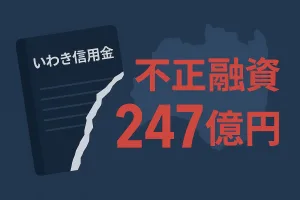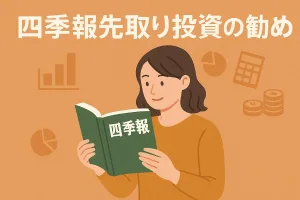日本維新の会・藤田文武共同代表をめぐり、秘書企業への発注と領収書の扱いが報じられ、印紙の貼付や領収書の「適法性」に世間の目が集まりました。
事件の真偽や全体像は今後の検証に委ねるとしても、「領収書に印紙が要るのはいつ?」「貼り忘れのペナルティは?」といった基本を、押さえておく価値は大きいです。
報道の経緯を手がかりに、印紙税の実務ルールを一次情報で整理し直します。
報道の一例では「公金を原資とする支出」「領収書の適否」が取り上げられましたが、論点は広く“正しい領収書の作り方・受け取り方”にも及びますね。
収入印紙とは
収入印紙は、契約書や領収書など「課税文書」に貼って、印紙税を納めるための切手状の証票です。
郵便切手に似た見た目をしていますが、用途は全く異なります。
印紙税法では20種類の「課税文書」が定められており、これらの文書を作成する際には、定められた金額の収入印紙を貼付し、消印することで納税義務を果たします。
収入印紙には1円から10万円まで、全部で31種類の額面があります。
最も使用頻度が高いのは200円の収入印紙で、5万円以上100万円未満の領収書に使用されます。
領収書の印紙税
領収書は、受取金額が5万円以上になると収入印紙の貼付が必要です(例外は後述)。
「5万円未満は非課税」という規定のため、49,999円までは収入印紙が不要ですが、5万円ちょうどからは200円の収入印紙が必要になります。
この金額基準には重要なポイントがあります。
原則として消費税額は含まれないという点。
つまり、領収書に消費税額が明記されている場合は、本体価格(税抜)のみで判断します。
例えば、税込50,600円の領収書でも、内訳として「税抜金額46,000円・消費税額等4,600円」と記載されていれば、本体金額が5万円未満のため収入印紙は不要です。
しかし、内訳が記載されていない場合は、総額で判断されるため5万円以上と扱われ、200円の収入印紙が必要になります。
この違いは、領収書の記載方法によって納税額が変わることを意味します。
金額帯ごとに税額が決まっており、代表的な区分は次のとおりです。
- 5万円以上100万円以下:200円
- 100万円超200万円以下:400円
- 200万円超300万円以下:600円
- 300万円超500万円以下:1,000円
- 500万円超1,000万円以下:2,000円
1,000万円超の領収書は「第5号〜第20号文書」の一覧に細かい区分があります。
高額取引が多い方は、国税庁の一覧表で最新の資料を必ず確認しましょう。
最高額は10億円を超える領収書で20万円となります。
契約書の印紙税
不動産・請負・金銭消費貸借などの契約書は、記載された契約金額が1万円以上になると課税され、帯に応じて税額が上がります。
たとえば請負契約書は「1万円以上100万円以下=200円」「100万円超200万円以下=400円」…と段階的に上がる設計です。
契約金額の記載がない書類は一律200円など、例外もあるので前述の国税庁の一覧表を参照ください。
地方公共団体は収入証紙
ちなみに「収入印紙」は国に対して支払う税金で、「収入証紙」という地方公共団体へ納めるものも別にあります。
第二種電気工事士の登録のために県の「収入証紙」が必要でしたね。

収入印紙が不要なケース
また、5万円以上の領収書を発行する場合でも、収入印紙が不要になるケースがあります。
これらを正しく理解することで、不要なコストを削減できます。
電子発行の領収書
印紙税は紙で作成した課税文書に対して課税される税金です。
そのため、電子データ(PDFメール送付など)は課税文書とみなされないため、収入印紙は不要なんですよ。
電子契約システムの普及により、この仕組みを活用して印紙税のコストを削減する企業が増えています。
ある意味、時代遅れの企業にだけ課せられる税金と言えるかもしれません。
クレジットカード決済の場合
クレジットカード決済やキャッシュレス決済は、現金の直接的な授受を伴わない「信用取引」です。
そのため、領収書を発行した時点では金銭を受け取っていないことになり、印紙税の課税対象外となります。(カード会社の立替構造等による)。
ただし、領収書に「クレジットカード利用」などの記載がない場合、現金取引と区別できないため収入印紙が必要になります。
一方、電子マネー決済(nanaco、WAONなど)や商品券での支払いは、現金取引と同様に扱われるため、5万円以上であれば収入印紙が必要です。
営業に関しない領収書
個人間の取引など、営業活動に関係しない領収書については、金額にかかわらず非課税となります。
日本維新の会 藤田文武共同代表の収入印紙問題から学ぶ
日本維新の会の藤田文武共同代表をめぐる公金還流疑惑が報じられました。
共産党機関紙「しんぶん赤旗日曜版」の報道によると、藤田氏側が公設第1秘書が代表を務める会社に約2000万円を支出していた問題で、領収書17枚に収入印紙が貼られていなかったことが明らかになりました。
この問題は単なる事務的ミスでは済まされません。
収入印紙の貼付は、領収書を発行する側の法的義務であり、これを怠ると重大な罰則が科されます。
そもそも収入印紙の貼付なんてビジネスをやっていれば当たり前の話なので、これを藤田氏宛だけで17枚も怠っているというのは本当に業務実態があったのか?という疑問も出てきてしまっても仕方ないレベルの話なんですよ。
政治家による公金の取り扱いという文脈だけでなく、一般的なビジネスにおいても、収入印紙のルールを正しく理解し遵守することの重要性を示す事例です。
収入印紙を貼り忘れた場合のペナルティ
収入印紙が必要な文書に貼付しなかった場合、または貼付したが消印をしなかった場合は、「過怠税」というペナルティが科されます。
原則の3倍のペナルティ
課税文書を作成したのに印紙税を納めなかった場合、本来の印紙税額+その2倍=合計3倍の過怠税が課されます。
本来納めるべき印紙税の3倍のペナルティーとなるんですよ。
例えば、200円の収入印紙が必要だった領収書に貼り忘れた場合、600円(200円×3)の過怠税を徴収されます。
しかも過怠税は損金・必要経費に算入不可。
これは企業にとってはかなり効きますね。
自主申告なら“1.1倍”へ軽減
ただし、税務調査前に自ら申出(「印紙税不納付事実申出書」の提出)をすれば、1.1倍まで軽減されます。
気付いたら速やかに手続を。
申出の手順は国税庁サイトの案内が詳しいです。
収入印紙がない書類を受け取った側
なお、収入印紙が貼られていない領収書を受け取った側にペナルティはありません。
また、領収書としての法的効力も失われません。
しかし、発行側の法令違反となるため、気づいた場合は指摘することが望ましいでしょう。
今回の日本維新の会の藤田文武共同代表のケースだと藤田氏側にはペナルティーがないということになります。
ただし、発行したのが秘書の会社ですから道義的部分は残りますね。
「消印漏れ」の扱い
印紙を貼ったのに消印していない場合は、印紙額面と同額の過怠税(=実質“2倍”相当のダメージ)になります。
収入印紙の正しい貼り方
収入印紙を貼付する際には、いくつかの重要なルールがあります。
貼付位置
法律上、収入印紙を貼る位置に特別な規定はありません。
領収書に収入印紙の貼付欄が設けられている場合はその枠内に、ない場合は余白に貼り付けます。
文字や記載内容に重ならないよう注意しましょう。
消印の方法
収入印紙を貼っただけでは、納税したことになりません。
必ず「消印」をする必要があります。
消印とは、収入印紙と文書にまたがって印章または署名をすることで、印紙の再使用を防ぐ目的があります。
消印は、文書の作成者または代理人、使用人、その他の従業者が行えます。
印章は会社印でも個人印でも構いませんし、署名やイニシャルでも有効です。
重要なのは、収入印紙と文書の両方にかかるように押印または署名することです。
消印をしなかった場合も、貼付しなかった場合と同様に過怠税が科されます。
貼り過ぎた・間違えたときのリカバリー
未使用の収入印紙で誤った額面を購入した場合、郵便局で他の額面の収入印紙と交換できます。
ただし、1枚につき5円の手数料が必要です。
誤って文書に貼付してしまった場合(消印済みでも)、税務署で還付を受けることができます。
ただし、現金での払い戻しは原則としてできません。還付請求の期限は、文書を作成した日から5年以内です。
汚損や破損した収入印紙については、偽造防止の観点から交換できない場合があります。
収入印紙はどこで買えるか
収入印紙を購入できる場所は複数あり、それぞれに特徴があります。
郵便局
郵便局は収入印紙の購入先として最も確実です。多くの郵便局では31種類すべての収入印紙を取り扱っています。
ただし、簡易郵便局や出張所では全種類を扱っていない場合もあります。
郵便局の窓口は平日9時から17時までが一般的ですが、「ゆうゆう窓口」がある郵便局では24時間購入可能です。
高額な収入印紙や特殊な額面が必要な場合は、規模の大きい郵便局を訪れることをおすすめします。
コンビニエンスストア
最も身近で便利な購入先がコンビニです。
セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキなど、大手チェーンでは収入印紙を取り扱っています。
コンビニの最大のメリットは24時間いつでも購入できることです。
ただし、取り扱っている収入印紙は基本的に200円のみです。
400円や1,000円などが必要な場合は、200円の収入印紙を複数枚組み合わせて使用することも可能ですが、高額な印紙が必要な場合は郵便局や法務局で購入する方が効率的です。
注意点として、駅構内のコンビニや個人経営の店舗では収入印紙を取り扱っていない場合があります。
購入前に「収入印紙」または「切手」の表示があるか確認するか、店舗に問い合わせることをおすすめします。
コンビニでの購入は基本的に現金のみですが、セブンイレブンではnanaco、ミニストップではWAONで購入可能です。
ただし、ポイントは付与されません。
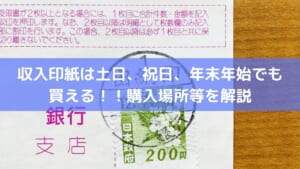
法務局・役所
法務局では、登記などの手続きで収入印紙が必要になることが多いため、窓口や売店で全種類の収入印紙を購入できます。
営業時間は平日8時30分から17時15分が一般的です。
役所でも収入印紙を取り扱っている場合がありますが、すべての役所で扱っているわけではないため、事前に確認が必要です。
金券ショップ
金券ショップでは、使用されなかった収入印紙を額面よりも安価で購入できる場合があります。
ただし、在庫は不安定で、必要な額面が常にあるとは限りません
売っていれば1%〜10%程度割引で買えますので、少しでも安く収入印紙を買いたい場合は金券ショップを覗いてみるのもよいでしょう。
ちなみに金券ショップで収入印紙を買うのにはもう一つメリットがあります。
それは消費税の節税ができることです。
郵便局などで収入印紙を買うと消費税は非課税の扱いとなります。
しかし、金券ショップで収入印紙を買うと消費税は課税対象なんですよ。(例外措置されていないため)
まとめ
今回は「いまさら聞けない収入印紙のルール|「貼り忘れ」の代償と正しい金額の見極め方」と題して収入印紙についてみてきました。
収入印紙は、日常的なビジネス取引において避けて通れない重要な税務事項です。
領収書に収入印紙が必要なのは受取金額が税抜5万円以上の場合で、金額に応じて200円から段階的に印紙税額が増加します。
電子発行の領収書やクレジットカード決済の場合は収入印紙が不要になるなど、コスト削減の方法も存在します。
一方で、収入印紙の貼付を怠ると本来の納税額の3倍という重い過怠税が科されるため、正確な理解と適切な対応が求められます。
藤田共同代表の事例が示すように、収入印紙のルール違反は脱税とみなされる可能性があります。
収入印紙の基本ルールを正しく理解し、コンプライアンスを遵守した事業運営を心がけることが重要です。
収入印紙は郵便局やコンビニで手軽に購入できますが、それぞれの購入先の特徴を理解し、必要な額面や枚数に応じて適切な場所を選択しましょう。
また、今回の話を機会に電子契約システムの導入など、デジタル化による印紙税の削減も検討する価値がありますね。