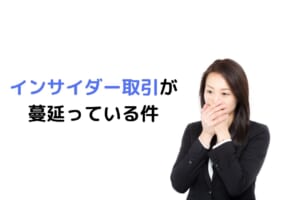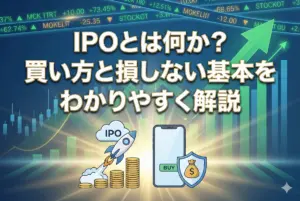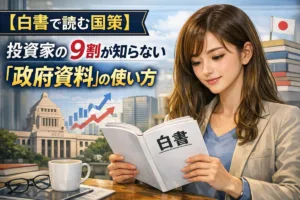「ヒンデンブルグ・オーメン(Hindenburg Omen)が点灯」。この一文だけでSNSがざわつき、メディアが「暴落シグナル」見出しを並べるのは毎度の風物詩です。
実際、NY市場では2025年7月31日と8月11日に点灯報が流れ、SNS上でも話題になりました。
ただし、点灯=即大暴落と短絡的に結びつけるのは早計。
オーメンは「市場の内部断裂」を警告する早期の赤信号であって、確定的な“予言”ではありません。
過去研究では的中率は20~25%程度との評価もあり、誤報(フェイクシグナル)が多いことが知られています。
では、点灯後の翌日・1週間・1か月・3か月で、実際に市場はどう動きやすかったのか。
過去の点灯事例や外部統計を突き合わせ、リスク管理の実務まで整理していきます。
ヒンデンブルグ・オーメンとは?
まずはヒンデンブルグ・オーメンとはなにかについてみていきましょう。
名前の由来と歴史
名前は1937年の飛行船事故「ヒンデンブルク号」に由来。考案者は数学者ジム・ミーカで、背景にはノーマン・フォズバックの「High-Low Logic Index(新高値・新安値ロジック)」があります。
市場の“健全な上昇”なら新高値が優勢、同時に新安値が多発するのは“内部が割れている”サインという発想です。
点灯条件
ヒンデンブルグ・オーメンの点灯条件は一般に次の4条件(細部は流派で差)が同日に成立すると点灯とみなされます。
・NYSEで新52週高値・新52週安値が一定比率以上(代表値:2.2%または2.8%)。
・指数が上昇局面(10週移動平均が上向き、または50日ROCがプラス)。
・McClellan Oscillator(騰落オシレーター)がマイナス。
・新高値の数が新安値の2倍を超えない。
なお、一度点灯すると30営業日有効とする定義が主流です。
暴落シグナルとされる理由
上昇相場の外見に反して内部で新高値と新安値が同時多発するのは市場の二極化(bifurcation)。
上昇の広がり(breadth)が痩せ細り、脆さが増すため、短期的な調整~下落に“なりやすい”という理屈です。
ただし単発点灯の信頼性は低く、“クラスター(短期に複数回)”のほうが意味を持ちやすい。
これが現在の実務的コンセンサスです。
過去の点灯事例と市場の動き
それでは過去に点灯した時はどのような事態になったのでしょう?
リーマンショック前の点灯例
2007~08年の金融危機局面では、大きな下落の前にオーメンが現れていたとされます。
「大クラッシュの前に点灯していたことは多い」一方、点灯しても暴落しないケースも多い。
この二面性が最大の特徴です
コロナショック前の点灯例
2019年末~2020年初にかけても、内部劣化を示すシグナルとして言及が増え、結果的にコロナ相場の急落につながりました(因果ではなくリスク環境の悪化を先取りしたという理解)。
その他の主な点灯事例
2010年のフラッシュクラッシュ前後や、2015年の中国発ショック夏場急落など、“クラスター的に点灯”していた局面がたびたび記録されています。
個別イベントが直接の引き金でも、内部断裂を事前に映した可能性があるわけです
直近の点灯状況
直近では2025年7月31日と8月11日に「点灯」報(NY市場ベース)。
まずは単発かクラスターか、他指標を落ち着いて確認。
点灯後の株価推移
短期1~3か月は平均/勝率ともにやや弱めという研究が複数。
6か月先の平均はマイナスを示した例もあります。
ただし単発点灯の説明力は低く、クラスターの有無で有意性が変わります。
日経平均・NYダウ別のパフォーマンス統計
厳密な全履歴のオープンデータは限られるため、信頼できる公開研究の範囲で“期間別”の要点を要約します。
- ナスダックでオーメン点灯日のその後6か月:平均-5.5%、上昇確率41%(=勝率低下)。※SentimenTrader Backtestより。
- 一般的評価:オーメンの的中率は20~25%前後、誤報が多い。ただし大崩れの前に出ていることも多い。
メディアやSNSで語られる「的中率80%」は、定義が甘い/母集団が小さい事例を含むことが多く、権威ある解説では20~25%程度がむしろ一般的評価。
“大崩れ前に点灯していた”というリコールバイアスに注意しましょう。
時期・相場環境による違い
流動性の潤沢さ/ETF比率上昇は新高値・新安値のカウントを歪ませ、誤報を増やす要因に。
クラスター(30日内に複数回)は弱気リスクの持続を示しやすい。
単発はノイズで終わることも多い
ヒンデンブルグオーメンの確認方法
次にヒンデンブルグ・オーメンの確認方法をみてみましょう。
データの集め方(無料ソース中心)
- NYSEの新52週高値/安値の件数
- WSJ / Barron’s / MarketWatchのマーケットダイアリーでNew Highs / New Lowsを確認。
- BarchartのHighs/Lowsでも一覧確認可。
- 指数の上昇判定
- NYSEコンポジットの10週MAまたは50日ROCがプラスか。定義はInvestopedia/ChartSchoolを参照。
- McClellan Oscillator(MCO)
- 無料版でも掲載するサイト多数。マイナス圏かどうかをチェック。
- 新高値が新安値の2倍を超えない
- 1)で得た件数でHighs ≤ 2×Lowsを確認。
自分の“閾値セット(2.2%/2.8%)”を固定し、30営業日内のクラスター数をトラッキング。
クラスター化のほうが有意性を持ちやすい。
ネット証券会社などが表記してくれると良いのですがね・・・
SBI証券や楽天証券など「要望を叶えました」みたいな改善進捗を公開しているところに要望を送っているといつか叶えてくれるかもしれません。
個人的なやり方
私は毎回計算するのは面倒なので「ヒンデンブルグ・オーメン」「Hindenburg Omen」などのキーワードをヤフーのリアルタイム検索アプリに設定。
Xなどで急激に盛り上がったときなどに通知が来るようになります。
そこでチェックする形にしています。
投資戦略への活かし方
前述のようにファイクシグナルが多いヒンデンブルグ・オーメン。
どのように活用すればよいのでしょう?
点灯後のリスク管理
個人的には以下のようなことを実践しています。
・ポジション縮小:裁量余地がある部分から軽く。決算前・材料待ちを優先的に見直し。
・ボラの高い銘柄は巻き戻しも想定して段階的に外す。
・損切りラインを再設定
・セクター中立化:景気敏感の過度集中を避ける
他の指標との組み合わせで信頼度を高める方法
他の指標と組み合わせるのも有効です。
特に逆イールドはトランプさんが言及するなど注目されている指標です。
過去に検証もしました。

まとめ
今回は「ヒンデンブルグ・オーメンが点灯。点灯後どうなるのか?過去のデータを分析」と題してヒンデンブルグ・オーメンについて見てみました。
まず知っておきたいのは点灯=暴落確定ではないということ。
単発点灯の説明力は弱い一方、クラスター化や他指標の同意で下振れ確率が高まるというのが最近言われていること。
誤報率が高いが、大崩れの前に点いていることも多く、市場の内部が割れてきたことを教えてくれる早期警戒の赤信号としては使えます。
点灯=全降りではなく、ポジションの重さ・期間・ボラの当て方を整える合図として活用しましょう。