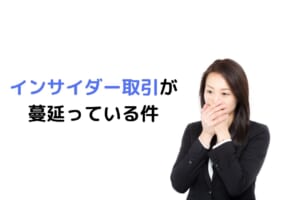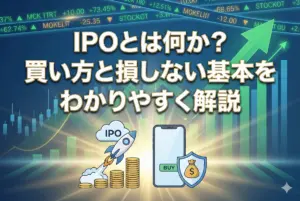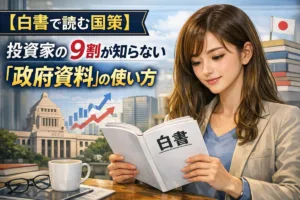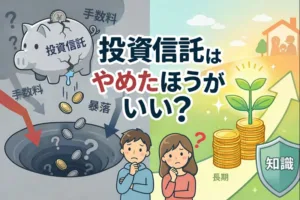2025年9月26日、東京証券取引所はグロース市場の上場維持基準を「上場から5年経過後に時価総額100億円以上」へ引き上げる制度要綱を公表しました(現行は「10年経過後に40億円以上」)。
適用は2030年3月1日以後最初に到来する事業年度末から。
未達となった企業には原則1年間の改善期間が与えられますが、適合計画を開示すれば“猶予期間”による継続上場も可能という“出口の選択肢”も整備されます。
今回は制度の骨子・タイムライン・影響を解説します。
グロース市場「上場維持基準」の何が変わるのか
それでは具体的にどのように変わるのかを確認していきましょう。
新基準の中身:5年・100億円・改善1年
まず、現行基準は以下のとおりでしたが。
上場から10年経過後で時価総額40億円以上(平均終値方式)。
それが以下のように変更されます。
上場から5年経過後の事業年度末で時価総額100億円以上(平均終値方式)。
未達時は1年の改善期間→不適合なら監理・整理指定を経て上場廃止が原則
いつから適用?——「制度施行」と「基準適用」の2段階
制度施行(予定)は以下のとおり。
2025年12月目途。
この施行日以降、スタンダードへの市場変更審査で「利益額1億円以上」の形式要件を適用除外(後述します)
維持基準の適用開始は5年後からとなり、以下のとおり。
2030年3月1日以後、各社の最初に到来する事業年度末から。
ここで100億円基準の判定が始まります。
“例外(猶予)”の設計:計画を開示すれば継続上場の道も
例外として猶予のルールもあります。
そちらも確認しておきましょう。
改善期間:基準未達となった日の翌日から1年間。
猶予期間:改善期間満了後も、「上場維持基準への適合計画(適合計画)」を開示すれば、計画期間の末日まで上場継続を猶予(期限の上限は設けず、必要最小限の設定を推奨)。
このルールは期限等が定められてないことから抜け道にならないことを祈りたいところ。
なお、見直し後の適用フェーズで旧基準(10年経過後40億円)に不適合となった場合は、改善のための期間は設けず上場廃止と明示。
旧・新の二重基準期での運用ルールも明確化されています。
2030年適用年以降の流れまとめ
2030年適用以降の流れをまとめると以下の通り。
- 2030/3/1以後最初の事業年度末で100億円基準を判定
- 未達 → 改善期間1年
- なお改善期間終了後も、適合計画を開示すれば計画期間の末日まで猶予(継続上場可)
- ただし、旧基準(10年・40億円)に適合しない場合は改善期間なく廃止
「スタンダード市場への変更」ルールも同時に見直し
また、スタンダード市場への変更のルールも合わせて変更されます。
形式的な利益要件の“足切り”を緩和
グロース上場会社がスタンダードへ市場変更を申請する場合、「直近1年の利益1億円以上」という形式要件を適用除外になります。
これにより、成長投資を抑えて形式要件を作るイビツな行動を避け、実質審査では「企業の継続性」を中心に評価する方針が示されました。
プライム→スタンダードの変更でも同様の取扱いです(新規上場基準は不変)。
施行は2025年12月目途以後の申請から。
なぜ今基準の“引き上げ”なのか:政策目的と市場機能
なぜこのような変更が実施されるのでしょう?
「機関投資家が投資対象とみる規模」への早期成長を促す
東証は、グロース市場を「高い成長を目指す企業が集う市場」として再定義し、投資対象としての規模を早期に求めることで、投資家の資金循環を促進、M&Aや再挑戦(起業家のセカンド起業)の活性化、市場の新陳代謝を狙うと説明しています。
経過措置の終了と地ならし
2025年3月1日基準日以降、市場区分見直し(2022年4月)に伴う経過措置が終了し、本来の維持基準へ段階的に回帰済みです。
今回の見直しは、経過措置後フェーズにおけるさらなる機能発揮を狙った設計変更と位置付けられます。
企業・投資家にとっての影響
それでは我々投資家や企業にとってどのような影響があるのでしょう?
影響1:上場5年目以降の「資本政策・IRの集中点」が100億円へ
グロースに残るなら、5年目の年度末までに持続的に時価総額100億円を示せる筋肉が必要となります。
需給対策だけでなく、PL/BS/CF、実績KPIを開示し、価格持続性を裏付けるのが鍵となりそうです。
また、時価総額を100億円にするために株価を手っ取り早く上げようとすれば株主優待や配当金の拡充なんかが有効です。
そういうのも各所でみられそうです。
ただし、過去にはトンデモナイ株主優待を発表しておいて、一度も実施しない企業なんかもありました。
その継続性にも注目が必要ですね。

影響2:市場変更(グロース→スタンダード)が現実解に
利益要件の適用除外により、赤字だが継続性が高い成長企業でも、スタンダード市場への道が開けます。
ただし実質審査は継続性中心。
資金調達計画、顧客基盤、解約率、プロダクトの粘着性など、事業の“持ち”を論理で示す必要があります
影響3:未達企業のアクションは“3択”
現在未達の企業は以下の3つの選択肢に収れんされてくるでしょう。
- 100億円達成を狙う(成長投資・収益性改善・需給是正)
- スタンダードへ市場変更(継続性を重視した審査に臨む)
- M&A・再編(売却・統合で企業価値最大化)
投資家としてはそのあたりの見極めが重要となりますね。
企業のIRを丁寧にみることが必要となりそう。
上場維持基準が未達企業の一覧(改善期間該当銘柄等一覧)
なお、上場維持基準が未達の企業は、日本取引所グループの「改善期間該当銘柄等一覧」で見ることができます。
グロースの時価総額基準については、毎月中旬に前月末基準の該当状況が更新される運用とのこと。
なお、媒体によっては「抵触企業一覧」「未達一覧」といった表現でリスト化することがありますが、最終的な事実確認は日本取引所グループの一次情報にあたるのが安全です。
参考として、民間媒体の網羅記事もありますが、抽出基準や更新タイミングが異なるため、投資判断では公式を優先しましょう
投資家がやるべきチェックリストとシナリオ
それでは今回のルール変更投資家がチェックすべきポイントはどこになるのでしょうか?
定点観測のKPI
定点観測をしたいのは以下の3点です。
- 時価総額の持続性:判定は「直近3か月平均終値」。イベント高騰の一瞬ではなく平均水準を観る。
- 開示姿勢:「事業計画および成長可能性に関する事項」で100億円適合を意識した記載が求められる。ロードマップとKPIの整合性を評価。
- 資本政策:浮動株・ロックアップ・主要株主の売買方針(流通株式定義の取扱い見直しも要確認)。
時価総額が100億円未満なら、成長戦略への記載(100億円適合を意識)の開示要件が課されますのでそちらを注目しましょう。
株価シナリオ
株価シナリオもある程度想定しておくとよいでしょう。
- 強気シナリオ:中期で「100億円達成の筋」が見える→需給改善+成長投資継続でレーティング再評価
- 中立シナリオ:スタンダード変更で継続性の裏付け→割安放置修正
- 弱気シナリオ:適合計画が抽象的、KPI進捗乏しい→改善期間終了接近でディスカウント(監理指定リスク)
銘柄探索の入口
改善期間該当銘柄一覧をベースに、適合計画の質・更新頻度、IR説明会の粒度、継続性を横比較。
“猶予”を有効活用できる企業を見極めます。
まとめ
今回は「【グロース市場改革】上場維持基準の引き上げはいつから?ルールと未達リスクとチャンスを解説」と題してグルースの上場維持基準引き上げの話をみてきました。
企業側からみれば5年で100億円は簡単ではありませんが、猶予の設計や市場変更オプションが同時に提示されたことで、多様な対策が現実解になりました。
投資家としては、KPIと資本政策、開示の質、そして継続性を軸に、「計画 ≒ 価格」の整合性を冷静に追うことが大事でしょうね。
この上場維持基準引き上げで株価が大きく化ける企業も出てきそうですのでチェックしておきましょう。