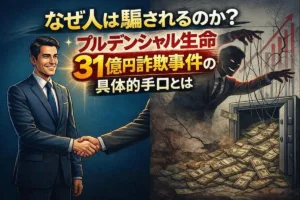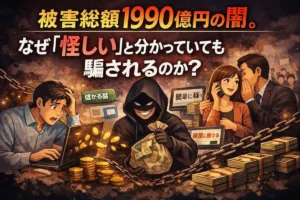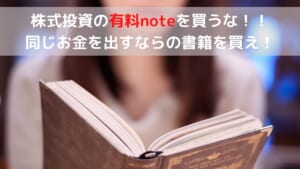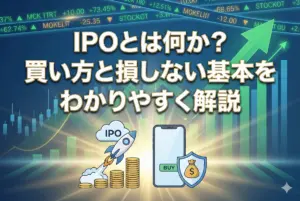日経新聞に興味深い記事が載っていました。
コーポレートガバナンス・コード(企業統治指針)が2026年半ばに5年ぶりに改訂される予定とのこと。
その中に上場企業が現預金をため込みすぎず適切に活用しているか、説明を求める方向で検討されているそうなんですよ。
この手のルールが動くと株価にも大きな影響がありますので、今回はキャッシュリッチ企業の話をみていきましょう。
「説明できる現金の持ち方」が評価される時代へ
それでは今回の話の影響等を考えてみましょう。
まず、結論から言えば説明できる現金の持ち方が評価される時代となりそうです。
背景には、東証の「資本コストや株価を意識した経営」の要請に対し、プライムの92%が対応するなど開示が進んだ一方、現預金はなお積み上がりがちという課題感があります。
最近はアクティビストや企業がキャッシュリッチ企業(現金をたくさん保有している企業)にTOBを仕掛けたり、株主提案をするケースも多くなっていますしね。
政策サイドは「守りのガバナンス」から「攻めのガバナンス」への転換を促しています。
投資家目線でも、“たくさん現金を持っている”より“どう使うかが語れている”会社が、持続的に評価されやすい。
この流れに、相場テーマとしての「キャッシュリッチ」が再点火しやすい地合いも重なります。
高市政権で「現預金課税」「内部留保課税」も
また、コーポレートガバナンス・コードの改定とは別に、キャッシュリッチ企業には気になる点もあります。
それは高市早苗氏が下記の書籍で言及していた「現預金課税」や同列に語られがちな「内部留保課税」の可能性が高市政権の誕生で出てきていることです。
こちらもキャッシュリッチ企業のリスクとして合わせておさえておく必要がありそうです。
現預金課税や内部留保課税とは
企業の手元資金(現預金)や内部留保(利益剰余金)に税を掛ける発想です。
野党系の議員がよく発言している内容ですね。
大企業はお金を沢山溜め込んでケシカラン!!!と叩いてその対策として出していた案です。
しかし、今回それを唱えていた人が総理大臣になるという・・・
個人的にはこれら課税には大反対。
そもそもこれらを唱えている議員は簿記が理解できていないか、理解しているけど世論を誘導しようとしています。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。

キャッシュリッチ株が今後評価される3つの“使い道”
コーポレートガバナンス・コードの改定と現預金課税の可能性がでてきたことで、多くのキャッシュリッチ企業は、お金の使い道を考える必要がでてきます。
評価されるお金の使い道は以下の3つのパターンです。
このあたりも事前に知っておきたいところ。
株主還元(配当・自社株買い)
一番、即効性があり容易にできるのがこれ。
多くの企業はこちらを選択する可能性が高そうです。
特に経営陣がたくさん株を持っているケースだとその可能性がさらに高くなります。
これらは需要供給の改善で短期的に株価を押し上げやすいですね。
ただし単発は割安解消に至りにくいため、中期経営計画にひも付いた累進配当や還元方針の明文化が重要です。
これは「一過性を期待しない」という金融庁側のメッセージにも合致しています。
成長投資(設備・研究、人材・無形資産、M&A)
二番目が成長投資です。
ROIC>資本コストの案件に資金を振り向けるほど長期の適正価値が切り上がります。
金融庁も人的資本・知財など無形資産投資を企業戦略と関連付けて開示する方向を明示しています。
人への投資を語れる会社は評価が上がりやすいですね。
ただし、成長投資をしたからといって業績にすぐ反映されるわけではありません。
短期的に見れば業績は悪化する可能性が高いので(費用が増加)、長い目でみる必要があります。
事業ポートフォリオ再編
資本効率の低い資産を現金化→成長再配分する動き。
アクティビストの関与で進むケースも多く、日本株の構造テーマとなっています。
今回のコーポレートガバナンス・コード改定でこの動きはさらに加速しそうです。
キャッシュリッチ銘柄ランキングは“鵜呑み”にしない
キャッシュリッチ企業の探し方もみておきましょう。
キャッシュリッチ企業の定義
まず、そもそもキャッシュリッチの正式な定義というのは存在していません。
一般的に借入金が少なく、現金や預金などの流動性の高い資産を豊富に保有している企業がそう言われます。
ただし、具体的な数字の定義がないんですよ。
また、無借金企業などもキャッシュリッチ企業と言われることがあります。
ですから紹介している媒体によってかなり違いがあるんです。
最近ではネットキャッシュがプラスであることが条件としている場合や、企業の時価総額をネットキャッシュで割ったネットキャッシュ倍率、総資産に占めるネットキャッシュの割合を示すネットキャッシュ比率で判断されることもあります。
ネットキャッシュ:現預金+短期保有有価証券−有利子負債−前受金。
ネットキャッシュ倍率:時価総額÷ネットキャッシュ
ネットキャッシュ比率:ネットキャッシュ÷総資産
個人的にはネットキャッシュ倍率が一番わかりやすいですかね。
ちなみに先日でていたブルームバーグの記事では、
・ネットキャッシュの総資産に対する比率(ネットキャッシュ比率)が30%以上
・自己資本比率50%以上
でランキング形式にしていましたね。
>>高市政権でキャッシュリッチ企業に圧力も、過去に現金課税検討
有名どころだとオービックビジネスコンサルタント、任天堂、スクウェア・エニックス、シマノ、しまむらなどが挙げられていました。
ランキングの使い方
ですから各社の発表しているキャッシュリッチ企業のランキングなどはそのまま鵜呑みにせず、材料として使うと良いです。
例えばこんな感じです。
- ランキング→候補抽出(“多い順”でざっと把握)
- 資本配分の説明力でふるい(中計・IR資料・決算説明会で「何に・いつ・いくら」を語っているか)
- ROICとWACCの関係(ROIC>WACCを持続できる前提の投資・還元設計か)
- 需給とイベント(中計改訂・上方修正・人件費方針の明確化・大型還元のタイミング)
例えばSBI証券はネットキャッシュ/時価総額≧30%、流動比率≧200%、ROIC≧10%などの条件で“金利上昇にも耐性”という観点のスクリーニングを提示しています。
構造的な強さを兼ね備えた“現金の持ち方”を探すのに有用です
「説明責任」が強まると、株価はどう動く?
それでは今回の「説明責任」が強まることでの株価の影響を考えてみましょう。
いくつかのパターンが予想されます。
“説明できる大型還元+成長投資”で再評価の階段を上る
累進配当と継続的な自社株買いを中計のKPIとしてコミット。
人材・無形資産投資の金額と効果指標を併記。
金融庁の意図(攻めのガバナンス)に合致し、PBR是正→PERの適正化という二段階で株価が上向きそう。
“単発の特別配当だけ”で短期は上がるが、持続せず
金融庁は一過性対応を期待しないと明言しています。
翌期以降の資本配分絵姿が乏しいと、一時的に株価が上がってもすぐに剥落しそうです。
“説明なくため込む”でディスカウント継続+外圧上昇
現金の山=安全という昭和的発想は通用しにくくなります。
また、高市政権が現預金課税等を実施した際に暴落しそうな予感・・・
アクティビスト関与や買収リスクも高まりやすい。
ただし、TOB期待で上がるというケースはありそう。
まとめ
今回は「キャッシュリッチ企業の現預金は宝か呪いか?「現預金の使い道の説明責任」で株価はどう動く?」と題してキャッシュリッチ企業について考えてみました。
今後、キャッシュリッチ企業は「説明責任」のやり方で株価は大きく動きそうな予感。
注目していきたいと思います。