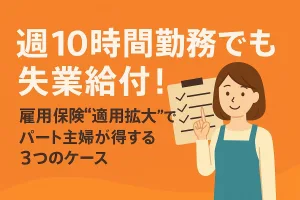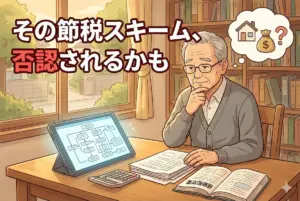2024年11月25日、金融庁が暗号資産交換業者に対し、不正流出などに備える「責任準備金」の積み立てを義務付ける方針 であると報じられました。
背景にあるのは、国内外で相次いだ暗号資産取引所の不正流出・ハッキング事件です。
今回の「責任準備金」義務化は、こうした事件が起きた際に、顧客の損失をできるだけ早く、確実に埋め合わせるための「バッファ(緩衝材)」を、法律であらかじめ用意させようという動きです。
責任準備金とは何か
責任準備金は、ざっくり言うと「万一の事故に備えて事業者が積み立てておくお金」です。
もともと証券会社など第一種金融商品取引業者には、証券事故などが起きたときの賠償をスムーズに行うため、責任準備金の積立義務があります。
ただし、現行の金商法では「業者側の違法・不当な行為による損害」以外で責任準備金を使うには、個別に行政の承認が必要です。
そのため、ハッキングのように「違法行為は外部の攻撃者だが、顧客資産が失われた」というケースでは、迅速な補償に使いにくいという課題が指摘されてきました。
今回の見直しでは、暗号資産交換業者向けに、ハッキングなど不正流出時にも承認なしで責任準備金を使えるようにする方向で議論が進んでいます。
インターネット接続状態にある資産への対応
これまでも日本の暗号資産交換業者は、世界的に見ても非常に厳しい規制の下に置かれてきました。
顧客資産の「分別管理」はその最たるものです。
しかし、今回の改正案ではさらに一歩踏み込みます。
具体的には、インターネットに接続された状態(ホットウォレット)で管理している顧客の暗号資産と同種・同量の暗号資産を、事業者自身の資産としてコールドウォレットなどで保有することを義務付ける方向で調整が進んでいます。
なぜ「同種・同量」であることが重要なのでしょうか。
価格変動リスクへのヘッジとしての現物保有
仮に、480億円分のビットコインが流出したとします。
もし事業者がその補填用として「日本円」で480億円を用意していた場合、どうなるでしょうか。
ビットコインの価格が暴騰していた場合、日本円での準備金では買い戻しができず、顧客への完全な補償(現物返還)が不可能になるリスクがあります。
いわゆる「ショート(売り持ち)」の状態と同様のリスクを事業者が負うことになるのです。
今回、「履行保証暗号資産」として、顧客が預けているのと同じ暗号資産を事業者自身も保有することを義務付けるのは、この価格変動リスクを排除し、いつ何時ハッキングが起きても、確実に顧客へ資産を返還できる財務体質を強制するためです。
逆に言えばそれだけの暗号資産を用意しておかなくてはならないとなると体力があるところしか暗号資産取引所を続けられなくなりそうです。
暗号資産取引所が潰れたらどうなる?現在の補償ルール
「暗号資産取引所が潰れたら自分たちの暗号資産はどうなるのか?」という不安は、投資家なら一度は考えるのではないでしょうか。
銀行が破綻した場合は「預金保険制度」により元本1,000万円までと利息が保護されます。
証券会社が破綻した場合は「投資者保護基金」により1,000万円までが補償されます。
では、暗号資産取引所が潰れたらどうなるのでしょうか。
ここで、いまの日本のルールを整理しておきます。
優先弁済権という強力な権利
改正資金決済法により、暗号資産交換業者が破綻した場合、顧客が預けている暗号資産は、他の債権者(オフィスの大家さんやシステムのベンダーなど)に優先して、顧客に返還される権利(優先弁済権)が認められています。
これは非常に強力な権利です。
しかし、この権利が行使できるのは、あくまで「そこに資産が残っている場合」に限ります。
ハッキングで根こそぎ資産が盗まれた上に、事業者自身も破産してしまった場合、優先弁済権があっても、返すものがなければ絵に描いた餅になってしまいます。
分別管理と信託保全の仕組み
また、日本の暗号資産交換業者は、資金決済法などにより、顧客の暗号資産や日本円を、自社の資産と分けて管理することが義務付けられています。
多くの業者は、顧客から預かった日本円を信託銀行などに信託し、破綻時にも顧客に返還できる枠組みを採用しています。
暗号資産についても、「ホットウォレット(オンライン)」と「コールドウォレット(オフライン)」を組み合わせながら、一定割合以上をコールドウォレットで管理することが自主規制ルールとして求められています。
ただし、これはあくまで「破綻しても預かり資産は基本的に返せるようにしておきなさい」という枠組みであり、すべてが完全に守られると約束されているわけではありません。
実際の返還には時間もかかりますし、破綻の原因や資産管理の実態によっては取り戻せない部分が発生するリスクもゼロではありません。
預金保険のような公的保護はない
銀行預金にはペイオフ(預金保険制度)があり、1,000万円+利息までは「預金保険機構」が保護してくれます。
一方で、暗号資産には、このような公的な「保険」はありません。あくまで
- 事業者の分別管理・信託保全体制
- 事業者自身の財務体力(自己資本)
- 今回議論されている責任準備金や保険加入
といった「民間での仕組み」によって守られるイメージです。
だからこそ、「暗号資産 補償」を考えるときには、どの取引所に、どれくらい預けておくのかを冷静に設計する必要があります。
責任準備金が埋める最後の穴
そこで今回の「責任準備金(履行保証暗号資産)」の意義が出てきます。
ホットウォレットで運用せざるを得ない(顧客の送金利便性のために必要な)分量に関しては、事業者が自己資産として別途コールドウォレットに確保しておく。
これにより、万が一ハッキング被害に遭っても、その別枠の資産を取り崩すことで、顧客資産への毀損を防ぐことができます。
つまり、これまでは「分別管理」によって「事業者の使い込み」は防げましたが、「外部犯による盗難」に対しては財務的なバッファが不十分でした。
今回の改正は、この「外部からの攻撃による損失」をカバーするための財務的義務付けと言えます。
金融商品化するのも大きな要因となっていそうです

責任準備金義務化の背景──繰り返される流出事件
今回の改正の背景も考えてみましょう。
コインチェック事件が残した教訓
2018年1月、コインチェックから約580億円相当の仮想通貨NEMが不正流出しました。
この事件は暗号資産業界に大きな衝撃を与え、26万人もの利用者が被害を受けました。
コインチェックは事件後、約460億円の補償を完了しましたが、これは同社の高収益体質があったからこそ可能でした。
暗号資産交換業特有の利ざやは最大10%とも言われ、株式やFXの1%未満と比べて格段に大きいビジネスモデルが、結果的に補償資金の捻出を可能にしたのです。
しかし、すべての交換業者が同様の対応ができるわけではありません。
事件当時、コインチェックはホットウォレットで管理しており、マルチシグにも対応していなかったというセキュリティ上の問題が指摘されました。
DMMビットコイン流出とその後
2024年5月31日、DMMビットコインから482億円相当のビットコインが不正流出する事件が発生しました。
同社はグループ会社の支援のもとで全額補償する方針を即日表明しましたが、事件を受けて2024年12月2日に取引所の閉鎖を決定し、資産と顧客口座はSBIVCトレードに移管されることとなりました。
チェイナリシスの分析によると、攻撃者は北朝鮮のサイバー攻撃グループと見られ、盗取した資産は複数の中間アドレスを経由させた後、CoinJoinミキシングサービスを利用して資金の追跡を困難にした とされています。
これらの事件が示すのは、どれほどセキュリティ対策を講じても、ハッキングのリスクをゼロにすることはできないという現実です。
責任準備金が導入されるとどう変わる?
次に責任準備金が導入された後の話を考えてみましょう。
不正流出時に“素早く”補償しやすくなる
金融庁の検討資料や報道では、責任準備金は、ハッキングや不正流出が起きた場合にも、行政の個別承認なしで使えるようにする方向で議論が進められています。
これは、
- まず責任準備金で迅速に一次補償を行い
- その後、原因究明や責任追及を行う
という流れを想定していると考えられます。
これまでのように「事業者が自腹やグループ支援でなんとかする」スタイルよりも、事前にルールで枠を決めておいたほうが、投資家から見ても透明性が高くなります。
責任準備金+保険+分別管理の三本柱
報道では、責任準備金だけでなく、保険加入も認める方向で検討されているとされています。
今後は、
- 顧客資産と自己資産の分別管理(+信託保全)
- 責任準備金の積み立て
- サイバー保険などの民間保険
といった三本柱で、暗号資産取引所のリスクに備える設計が主流になっていくはずです。
一方で、責任準備金や保険の水準は、どの程度の被害額を想定するかによって大きく変わります。
投資家への影響と懸念点
規制強化は投資家保護の観点からは歓迎すべきことですが、経済的な側面、特にコストの観点からはデメリットも想定されます。
事業コストの増加と手数料への転嫁
交換業者が自己資金で多額の暗号資産を購入し、それを塩漬け(コールドウォレットで保管)にしなければならないということは、莫大な資本が必要になることを意味します。
中小規模の交換業者にとっては、資金調達コストが経営を圧迫する可能性があります。
規制対応コストが増加すれば、企業はそれを収益でカバーしようとします。
暗号資産交換業者の主な収益源はスプレッド(売値と買値の差)や送金手数料です。
今回の義務化によって、スプレッドが拡大したり、各種手数料が値上げされたりする可能性は否定できません。
業界再編の加速
体力の乏しい交換業者は、この規制に対応できず、撤退や大手への吸収合併を選択する可能性があります。
用している取引所が今後も存続できる財務基盤を持っているか、親会社の信用力はどうか、といった点も選定基準の一つになってくるでしょう。
まとめ
金融庁による責任準備金義務化の方針は、コインチェック事件から約7年、DMMビットコイン流出から約半年という節目で打ち出されました。
相次ぐ流出事件の教訓を制度に反映し、投資家保護の水準を引き上げようとする姿勢は評価できます。
ただし、規制強化が過度になれば、イノベーションを阻害し、暗号資産市場の発展を妨げる可能性もあります。
これからの暗号資産投資では、
- 規制や制度の動きを追いながら
- 取引所のリスク管理と補償体制を冷静に見比べ
- 自分のリスク許容度に合わせて「どこに・どれくらい」預けるかを決める
というスタンスがより一層重要になってきます。
「預けっぱなしは危ない」という感覚を忘れずに、制度で守られる部分と、自分で守るべき部分を切り分けながら、暗号資産との付き合い方を考えていきたいですね。