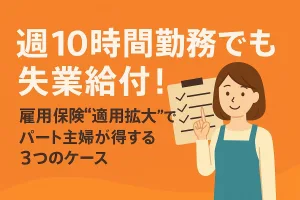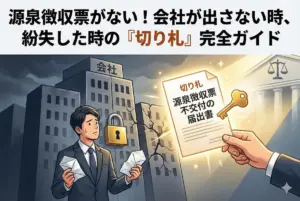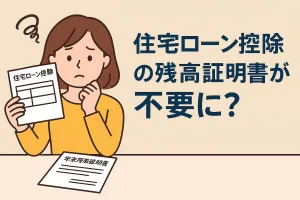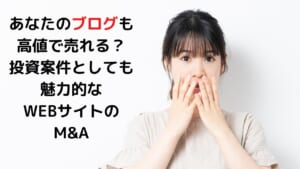2018年から配偶者の扶養や控除に関してのルールが少し変わっています。それに伴い年末調整に必要な書類(配偶者控除等申告書)が追加されています。
先日、読者様からこの配偶者控除等申告書についてのご質問がありましたので、今回の配偶者の控除に関するルール変更についてもう少し詳しく見て行きたいと思います。
簡単にいえば主婦が働いた場合に150万円の壁が新たにできたと思ってもらえば良いでしょう。ただし、150万まで働いた方が得かというとそうでもなく。。。
配偶者控除等申告書の書き方については下記記事をご覧ください。
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://ideco-ipo-nisa.com//19947]
主婦の方に新たな150万円の壁が登場
今回新しく登場した150万円の壁について見て行きましょう。
簡単にいえば配偶者特別控除が拡大されたということです。妻の年収が103万円超150万円以下なら、夫は配偶者特別控除として38万円の所得控除が受けられるようになったのです。150万円を超えると控除額の減額が始まるが、妻の収入が201万円までは控除を受けられます。
昨年まで妻の年収が103万円までは38万円控除というのは同じですが、それを越えると控除額は妻の収入に応じて数万円刻みで減っていき、妻の年収が141万円以上となると控除がなくなってしまっていたのです。
そのため103万円未満の収入に抑える主婦の方が多く、女性の社会進出の妨げとなっていました。配偶者特別控除を拡大することでそれを緩和することにしたのです。
控除の上での103万円の壁は実質無くなったが。。。
今までは103万円の壁がありましたのでそれを意識して働かれていた方が多いでしょう。しかし、今回の改正で税金面だけを見れば150万円まで働いても控除額(控除の種類は変わりますが)は同じとなるのです。(ここを勘違いしている方が多い気がします。)
配偶者特別控除の控除額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額、及び控除対象配偶者の年齢により次の表のとおりになります。
| 控除を受ける方の合計所得金額 | |||||
| 900万円以下(年収1120万円) | 900万円超950万円以下(年収1170万円) | 950万円超1000万円以下(年収1220万円) | 1000万円以上(年収1220万円) | ||
| 配偶者の合計所得金額 | 38万超〜85万円以下(年収150万) | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 0円 |
| 90万円以下(年収155万) | 36万円 | 24万円 | 12万円 | 0円 | |
| 95万円以下(年収160万) | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 0円 | |
| 100万以下(年収166.8万) | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 0円 | |
| 105万以下(年収175.2万) | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 0円 | |
| 110万以下(年収183.2万) | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 0円 | |
| 115万以下(年収190.4万) | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 0円 | |
| 120万以下(年収197.2万) | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 0円 | |
| 123万以下(年収201.6万) | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 0円 | |
| 124万超(年収201.6万 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
主婦本人の税金は・・・103万円の壁健在
103万円の壁は前述のように夫の控除の面を見れば実質的に無くなった形となります。しかし、主婦本人が無税となる範囲は、今までと同様に103万円までなんですね。つまりこちらの面では「103万円の壁」は健在ということです。例えば150万円まで働くことで所得税と住民税が発生することになります。
社会保険の壁は健在
主婦の方が働く上でもう一つ意識をしておくと良いのが社会保険の壁です。社会保険では通勤費込みで106万円と130万円にそれぞれ壁があります。
ちょっとややこしいのが130万円の壁は社会保険は通勤費も含めることになっているところですね。
106万円の壁は含みません(笑)
勤め先の社会保険加入の壁:106万円
まずひとつ目が社会保険の壁106万円(月額8万8千円)です。
これは大企業にお勤めの方に該当するルールです。
具体的には下記の条件を満たす場合、勤め先の健康保険、厚生年金に加入することになります。
つまり、旦那さんの扶養に入れなくなるのです。
1. 1週あたりの所定労働時間が20時間以上
2. 給料が月額8万8000円以上
3. 社会保険の対象となっている従業員(被保険者)数501人以上の企業に勤めていること。
4. 雇用期間が1年以上の予定
5. 学生以外(夜間・定時制は除く)
「従業員数(被保険者)が501人以上」の条件は事業所ではなく会社単位で判断します。
該当しているかどうかは勤め先に聞くのが1番早いですね。
大企業の店舗でアルバイトしている場合にはこちらに該当することが多いでしょう。
ただし、これ一概に損とは言えません。
たしかに勤め先の社会保険に入ることになると旦那さんの社会保険の扶養になれなくなります。
また、社会保険を払うことになりますので手取りは減るでしょう。
しかし、社会保険に加入すると将来の年金が増えます。
また、遺族年金や障害年金なども手厚くなり、怪我等で働けなくなったときも傷病手当がもらえるようになります。
そのため一概にどちらが得とは言えないのです。
※厚生労働省が従業員数(被保険者)が501人以上の制限を撤廃しさらに現状月額8万8000円以上の条件を月額6万8000円以上に改定する案を検討始めましたね。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://ideco-ipo-nisa.com//17493]
扶養者の壁:130万円
次は旦那さんの扶養に入れるかどうかの壁です。
こちらはこんな条件となります。
見込み年収が130万円未満、かつ、被保険者の年収1/2
つまり、これから1年間の収入が130万円以上になりそうかどうかで判断されます。
こちらは会社から支給される通勤費も加算して計算します。
細かい算定のルールは夫が加入している健康保険組合等により微妙にことなりますので確認しておきましょう
もし、これを超えると旦那さんの扶養に入れなくなるため、国民健康保険、国民年金に加入する必要が出てきます。
国民年金も国民健康保険もかなり高いので、少しだけ超えてしまうと手取りがマイナスとなります。
ちなみに平成30年4月からの国民年金保険料は月額16340円です。(平成31年4月からの国民年金保険料は月額16410円)
つまり、年間19万6千円にもなります。
国民健康保険は県によってかなり金額が違いますので県のWEBページでご確認ください。
結構負担が重くなりますよね。
夫婦トータルの手取り金額で考えよう
主婦の税金面や社会保険を考えるとなんだ、今までと一緒じゃん。と思う方も見えるかもしれません。
しかし、これは夫婦トータルの手取り額で考える必要があります。
税金面だけを考えるなら150万円が一つの目安となりますが、社会保険まで考えると扶養を抜けないギリギリライン130万円の壁を超えないあたりが得となります。
ちなみに社会保険が旦那さんの扶養を抜けた場合に手取りが増える境目は160万円を超えたあたりとなります。ですからそのあたりまでになるなら130万円に抑えるのが正解。160万円を超えてしまえば夫婦を合算した場合の手取りが増えることになります。
つまり、150万円ギリギリあたりだと社会保険までを考えると損になる場合もあるってことなんですよね。
その辺りも考えて調整する必要がありますね
まとめ
今回は「2018年の【年末調整】で知っておきたい新設された150万円の壁【配偶者控除等申告書】」と題して今年から変わった配偶者特別控除を中心に見てきました。
今まで見てきたように税金面だけ考えれば150万の壁となりますが、社会保険などをトータルで考えるとそうともいえないケースがあることがわかっていただけたと思います。
トータルで考えて検討して見てくださいね。
また他にも壁はあります。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
[sitecard subtitle=関連記事 url=こhttps://ideco-ipo-nisa.com//13527]
最後まで読んでいただきありがとうございました。
フェイスブックページ、ツイッターはじめました。
「シェア」、「いいね」、「フォロー」してくれるとうれしいです