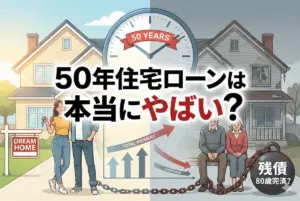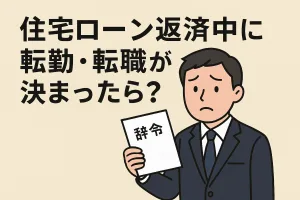最近、共働き夫婦が増えてきたこともあり、夫婦で住宅ローンを借りるペアローンの利用者が増えているそうです。
しかし、このペアローンにはメリットだけでなくデメリットもあるんですよ。
また、ペアローンと似た仕組みで収入合算というものもあります。
今回は夫婦どちらか単独借り入れの場合も含めてペアローン、収入合算のメリット・デメリットを見ながらどれが良いのかを考えて見たいと思います。
ペアローンとは
まずばペアローンとはなにかについて見ていきましょう。
ペアローンとは同一の物件に対して複数人でそれぞれローン契約を行い、お互いに連帯保証人になる借入方法です。
ペアローンが組める対象は銀行によって異なりますが、同居の夫婦や親子が条件となっているケースが多いですね。
例えば3,000万円の借り入れをする場合に一人で3,000万円借りるのではなく夫が1,500万円、妻が1,500万円ずつ借ります。
そしてお互いに連帯保証人となるのです。

出典:ソニー銀行 住宅ローン
ペアローンのメリット
ペアローンを組み事によるメリットは主に3つあります。
大きな借り入れがしやすい
まずひとつ目は単独で借りるよりも大きな借り入れをしやすくなるということです。
それぞれの借入枠を利用するイメージですね。
最近、住宅金額が高騰しているため、単独では住宅ローンだけでは足りず買えないというケースも増えているそうです。
しかし、ペアローンでなら手が届くというケースもあります。
つまり、一人では手が届かない高額な家もペアローンを使えば選択に入れることができるってことですね。
住宅ローン控除を二人で
もう一つのメリットは住宅ローン控除を二人で享受できるという点があります。
住宅ローン控除には以下のような金額の上限がありますので、一人で借りる場合には高額な家なら上限に到達して満額受けられないというケースもあります。
※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください。
| 居住年 | 借入限度額 | 控除率 | 控除期間 | |
| 認定住宅 | 令和4年・令和5年 | 5,000万円 | 0.7% | 13年 |
| 令和6年・令和7年 | 4,500万円 | |||
| ZEH水準省エネ住宅 | 令和4年・令和5年 | 4,500万円 | ||
| 令和6年・令和7年 | 3,500万円 | |||
| 省エネ住宅 | 令和4年・令和5年 | 4,000万円 | ||
| 令和6年・令和7年 | 3,000万円 | |||
| 上記以外 | 令和4年・令和5年 | 3,000万円 | ||
| 令和6年・令和7年 | 2,000万円 | 10年 |
しかし、ペアローンなら一人あたりの残高に応じて住宅ローン控除が受けられるのです。
令和4年・令和5年に居住する認定住宅(認定長期優良住宅または認定低炭素住宅)なら一人5,000万円までが限度額となりますので、合計最大で1億円まで住宅ローン控除の対象にすることが可能となります。
これは大きいですね。
夫婦ふたりとも団信保険に加入が可能
最後は団体信用生命保険(団信)にペアローンなら夫婦でそれぞれ加入できることもメリットです。
団信とは住宅ローンを組んでいる人用の生命保険で、お亡くなりになった場合に住宅ローンが0になったり、団信の種類によっては「がん」が発見されたら0円になるなんてものもあります。
通常の生命保険より有利なものが多いのですが、住宅ローンを単独で組んでいればその方だけしか加入できません。
ですから団信に加入していないほうが亡くなった場合に住宅ローンの返済が困難になるということも実際に多かったそうです。
しかし、ペアローンならそれぞれが住宅ローンの名義人ですから両方とも団信に加入できるのです。
このあたりもメリットですね。
ペアローンのデメリット
一方、ペアローンにもデメリットはあります。
諸費用が倍かかる
まず、大きいのが諸費用が倍近くかかるというものがあります。
2つの借り入れをするのと同じ扱いとなりますので、手続きに必要な登記費用や司法書士報酬、印紙代などがそれぞれ2倍かかってくるのです。
これも地味に大きいですね。
団信はそれぞれの借入分だけが対象
メリットで団信にそれぞれ入れるのがメリットとお伝えしましたが、デメリットでもあります。
実はペアローンで入る団信はそれぞれの借り入れ分だけが対象となるのです。
例えば夫が1,500万円、妻が1,500万円ずつ借りた場合には、夫がなくなったら夫の借入残高1,500万円は消えますが、妻の分の1,500万円は残る形となります。
ですからその分は返し続ける必要があるのです。
夫の単独加入なら全額が団信で保証されます。
この違いは大きいですね。
このあたりはデメリットにもなりえるでしょう。
離婚時のトラブルの元
また、離婚時にはトラブルになりやすいのもペアローンです。
離婚するなら住宅の名義を変えたい、住宅ローンの返済やめたい。連帯保証から外れたいと思うと思います。
しかし、これはペアローンだとなかなか難しいのです。
売却したりしてローンを返してしまうか、借り換えなどで名義を移すことになりますが、当然金融機関の審査も再度必要でハードルは高いんですよ。
建てたばかりの新築物件が中古として出回っていることをたまに見かけますが、多くは離婚案件だそうです。
マンションならそうでもないでしょうが、一戸建ては中古だとよほど駅チカ等条件が良くないとすぐに売れるなんてことはありませんので困っている方が多いそうです。
離婚のリスクが少しでもよぎるならペアローンは少し危険かもしれませんね。
贈与税が掛かりやすい
また、意外な盲点となりそうなのが贈与税です。
夫婦間でも贈与税の対象となるんですよ。
例えば妻が退職して収入がないからと夫が妻の住宅ローンを返済したようなケース。
この場合には金額によっては贈与税が発生します。
繰り上げ返済なども同じですね。
また、借り換えで夫名義に変えるようなケースも同様に贈与税が発生する可能性があります。
ペアローンの場合、それぞれの持ち分という契約になっていますので、返済金額や贈与税が掛かる可能性も考えて割合を検討すべきでしょう。
収入合算とは
次は収入合算です。
収入合算とは名前の通り、片方の借り入れの際に収入を合算してローン審査を受けるやり方となります。
ペアローンと違い一人が借り入れをする形になります。
なお、収入合算は金融機関や住宅ローンの種類によって2つのパターンがあります。
収入合算には連帯債務型、連帯保証型があり
それぞれを簡単に解説すると以下の通りとなります。
- 連帯債務型:一人が主債務者。残りが連帯債務者となる。主債務者が返済不能の有無に関係なく、主債務者と同じ返済義務あり
- 連帯保証型:一人が主債務者。残りが連帯債務者となる。主債務者が返済不能の際に連帯債務者は返済責任が生じる
この文面だけみると連帯保証型のほうが良さそうですが、実は連帯債務型のほうがおすすめだったりします。
連帯債務型とは

出典;ARUHI 住宅ローン用語集 連帯債務
連帯債務型は名義は一人ですが、夫婦ふたりで返していくイメージですね。
片方も主債務者と同じ返済義務が生じてきます。
その代わりに持分比率により住宅ローン控除も利用ができます。
また、上記図では団体信用生命保険(団信)は☓となっていますが、金融機関によっては加入できるものもあります。
例えば三井住友銀行ではどちらかに万一のことがあった場合、住宅ローン残高が0円になるという「クロスサポート」という団信を提供していますね。
フラット35でもデュエット(夫婦連生団信)という団信が提供されています。
連帯保証型とは
次は連帯保証型です。

出典;ARUHI 住宅ローン用語集 連帯債務
こちらは主債務者が返していく。
返せなかったら連帯保証人が返済しなければならないってものですね。
連帯保証型は主債務者のみが住宅ローン控除、団信が受けられます。
収入合算のメリット
収入合算のメリットは以下です。
大きな借り入れがしやすい
まずひとつ目は単独で借りるよりも大きな借り入れをしやすくなるということです。
これはペアローンと基本的に同じですね。
希望金額を借り入れできる可能性が高まることに繋がります。
契約する住宅ローンは1本
もう一つはペアローンと比較して住宅ローン契約に掛かる手数料等が抑えられるという点にあります。
1本の契約となりますので、手続きに必要な登記費用や司法書士報酬、印紙代が1回分で済むのです。
ペアローンと比較して大きいですね。
連帯債務型なら・・・
連帯債務型なら住宅ローン控除を持分割合に応じて利用できるメリットがあります。
団信も金融機関や住宅ローンの種類によっては利用が可能です。
このあたりも大きなメリットになりますね。
収入合算のデメリット
次に収入合算のデメリットを見てみましょう。
こちらも一部ペアローンと同じようなデメリットが生じる可能性があります。
離婚時
まずは離婚時の話です。
ペアローンと同様ですね。
売却などをして住宅ローンを完済してしまうか、新たな条件で借り換えをする、金融機関に相談して連帯保証や連帯債務などの保証条件、人を変更してもらう必要があります。
しかし、なかなかこれもハードルが高いんですよ。
こちらも離婚のリスクが少しでもよぎるなら少し危険かもしれませんね。
ただし、ペアローンよりは借り入れが1本ですから対応しやすいかもしれません。
連帯債務型の団信で一時所得になる?
団信についても考える必要はあります。
片方だけ団信に入っている場合にはもう片方が亡くなった場合には住宅ローンはそのままとなります。
ですから別途生命保険をかけるなど対策は必要でしょう。
また、連帯債務型でデュエット(夫婦連生団信)やクロスサポートに加入する場合も注意が必要な点があります。
それは税務上、一時所得として所得税が課税される可能性があるということです。
自分の持分割合の住宅ローンも消えることになるので課税対象となってしまうんですよ。
かなり小さく注意書きはあるのですが、ここまでなかなかみれないですよね・・

出典:住宅金融支援機構 デュエット チラシ より
結論:ペアローンと収入合算、単独借り入れどれが良い?
ペアローンと収入合算の特徴を今まで見てきましたが、どちらが良いのかわからないって方が大半かと思います。
どちらもメリット、デメリットがあるからです。
主なポイントをまとめると以下の通り。
※スマートフォンの方はスクロールしてお読みください
| ペアローン | 収入合算(連帯債務) | 収入合算(連帯保証) | |
| 契約上の立場 | ふたりとも債務者 | ローン契約者が主債務者、もう片方は連帯債務者 | ローン契約者が債務者、もう片方は連帯保証人 |
| 連帯保証 | ふたりとも | ー | 片方 |
| 返済義務 | ふたりとも | ふたりとも | 片方 |
| 事務手数料等経費 | 2契約分 | 1契約分 | 1契約分 |
| 住宅ローン控除 | それぞれの借入金残高に応じて | それぞれの借入金残高の持ち分割合に応じて | 債務者のみ |
| 団体信用生命保険 | それぞれ加入 | 商品によってはふたりとも加入が可能 | 債務者のみ |
ここからは私が考えるどの借り方がよいのかを見てみましょう。
単独借り入れが向いている人
まず単独借り入れがおすすめの人です。
収入の大半を片方が担っているケースは単独借り入れがおすすめです。
まずは単独借り入れで仮審査などを試してみて希望額まで借りられるか試してみましょう。
それで借り入れ希望額までいくならわざわざ収入合算やペアローンを使ってリスクを増やす必要はないかと思います。
また、離婚がよぎる人も単独借り入れの方が無難です。
収入合算やペアローンは離婚時により大変となる要因となります。
その可能性があるならはじめから避けておくのが良いでしょうね。
フラット35の方は収入合算
ちなみにフラット35はそもそもペアローンという仕組みが利用できません。
ですからフラット35を利用するケースで単独借り入れの条件に合致しないなら、必然的に収入合算となるでしょう。
フラット35の収入合算は連帯債務型なので割合に応じて住宅ローン控除が利用できたりメリットが大きいですね。
なお、フラット35ってなに??って方はこちらの記事で解説しておりますので合わせてご覧ください。
ペアローンが向いている人
次にペアローンが向いている人です。
こちらはふたりとも今後もそこそこ稼いでいけるようなケースにおすすめです。
「今後も」というのがポイント。
住宅ローン控除をフル活用できますしね。
逆に途中で出産退職して育児に専念したり、パートになったりする方はあまりおすすめできません。
住宅ローン控除をあまり活かせませんし、デメリットでご紹介した贈与税の兼ね合いもありますからね。
また、もう一つポイントとなるのはペアローンのデメリットにあった団信の部分。
片方が亡くなっても自分の分は債務が残るので、その部分を自分だけで返せるかどうかです。
なお、それぞれの借入金額は半々でなくても構いませんので、片方が亡くなっても自分だけで返せる金額を設定してあげるのも重要ですね。
収入合算が向いている人
それ以外のケースは収入合算となってきます。
ただし、収入合算は前述したように連帯債務なのか連帯保証なのかによりかなり違いがあります。
自分が借り入れをする住宅ローンはどちらかなのかはあらかじめ確認しておくと良いでしょう。
ちなみにフラット35以外の通常の住宅ローンは連帯保証のみの扱いが多かったりします。
連帯保証型の場合は、住宅ローン控除が片方しか使えないのはちょっと痛いですので、単独借り入れ、ペアローンという選択肢を含めてよく検討してください。
まとめ
今回は「夫婦で住宅ローンを組むならペアローン、収入合算、単独借り入れのどれがよいのか?メリット・デメリットを解説」と題してペアローンなど夫婦ふたりで住宅ローンを返していく仕組みについてご紹介しました。
それぞれメリット・デメリットがありますのでよく考えて利用してみてくださいね。
住宅ローン比較サイトなんかをつかうのもおすすめですよ。
お知らせ:You Tubeはじめました。
You Tube「お金に生きるチャンネル」をはじめました。
You Tubeでも少しでも皆様のお役に立てる動画を定期的に発信していきますのでチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。
最後まで読んでいただきありがとうございました。