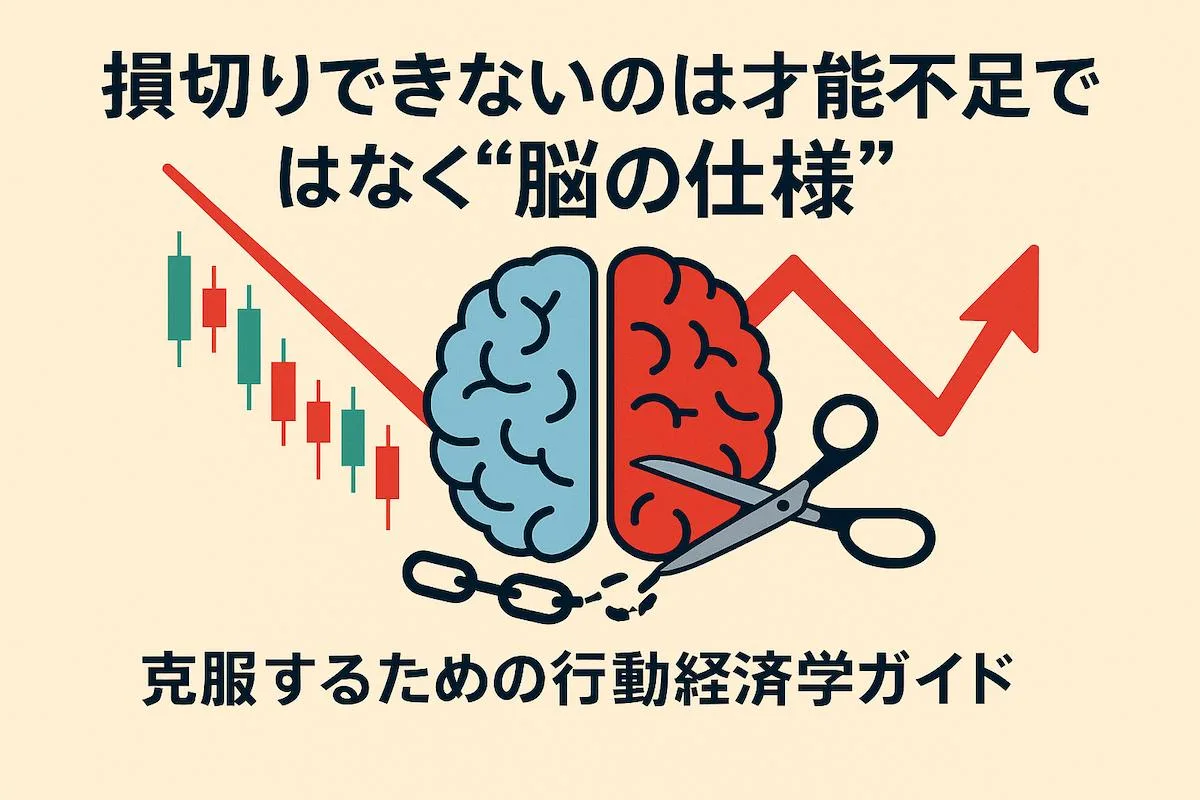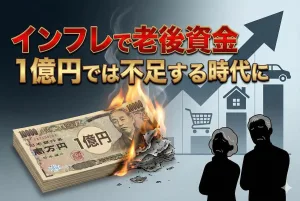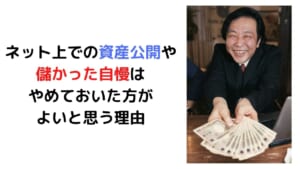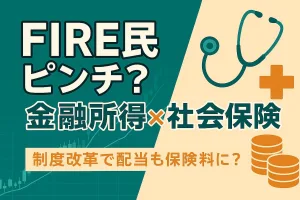「株価が戻るまで待てばいい」「あと少しでプラ転するはず」
そんな淡い期待が損切りできない状況を長引かせ、ポートフォリオ全体のリターンを蝕みます。
本記事では行動経済学の視点から典型的な心理バイアスを解説し、実践的な克服ステップを提示。日本株・米国株の失敗事例も交え、損失回避の罠にハマらない具体策を示します。
行動経済学が解き明かす「損切りできない」本当の理由
行動経済学によれば、人は利益より損失を約2倍強く感じる「損失回避」傾向を持つと言われています。
さらにサンクコストの誤謬が「ここまで塩漬けしたのだから」と撤退を遅らせるのです。
まずは2つの理論を中心に、投資家が損切りを躊躇するメカニズムを整理していきます。
プロスペクト理論と損失回避
「プロスペクト理論」ってあまり聞いたことがない方も多いかもしれません。
しかし実はプロスペクト理論は行動経済学最大の成果とも言われるもので、2002年にはダニエル・カーネマンがノーベル経済学賞を受賞した権威ある理論だったりします。
プロスペクト理論とは難しく言うと「選択の結果得られる利益もしくは被る損害および、それら確率が既知の状況下において、人がどのような選択をするか記述するモデル」です。
これだとわかりにくいですが、株式などに当てはめると少しでも利益がでれば利益確定して、少しでも損があると損失を現実にしたくなくて損切りできない。
つまり、投資の基本である損小利大の逆なんですよね。。。。
具体的には人は損失回避は利得より損失を約2.25倍重く評価するとされています。
チャートが含み損ゾーンに入った瞬間、脳は“痛み”を回避しようとポジションを維持し、 損切りできないトリガーになってしまうのです・・・
詳しくはこちらの記事を御覧ください。

サンクコストの誤謬が判断を曇らせるメカニズム
サンクコストは比較的メジャーな理論ですが、投資にも大きな影響を及ぼします。
サンクコストは日本語で埋没費用といいます。
すでに損失が出ていることが分かっていても、それまでの投資を惜しんで事業を継続してしまう、超音速旅客機コンコルドの開発事例から「コンコルド効果」とも呼ばれます。
既に回収が不可能であるコストを意味します。
本来はサンクコスト部分の費用はもう戻ってきませんし、今後の判断をするときに関係ありませんから無視すべき事項なのです。
しかし、多くの方はそれができません。
既に払ったコスト(時間・含み損)を「回収したい」と考え、合理的判断を拒むのです。
それがサンクコストの誤謬です。
サンクコストの誤謬は損切りできず「塩漬け株」を生み出す大きな要因です。
デイトレなどがうまい投資家はゲーム感覚で投資をしているとよく言われますが、ゲームのスコアくらいの感覚だとサンクコストは働きにくいからよいのでしょうね。
サンクコストについて詳しくはこちらを御覧ください。
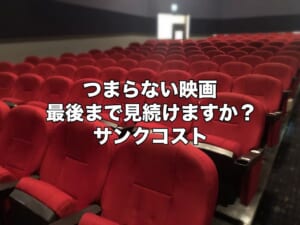
投資家を惑わす代表的なバイアス6選
「損切りできない」現象は複数バイアスが重なって起こります。
ここでは確証バイアス/群集心理/アンカリング効果/保有効果/代表性ヒューリスティック/過信バイアス の6つを取り上げ、影響と対策を具体的に整理していきましょう。
確証バイアス
自説に都合の良い情報だけ集めて含み損を正当化。
損切りできない延命装置となります。
次に紹介する群集心理なんかも絡んでくる話ですね。
逆張りニュースを意識的に検索し、意見表の左右列を埋めてから判断することが重要です。
群集心理(バンドワゴン効果)
群集心理も重要な心理です。
SNSや掲示板で「まだ握るべき」という空気に流されてしまうんですよ。
とくに最近のSNSはSNSのアルゴリズムは「あなたが好む情報」を優先表示します。
そのため、同じ意見ばかり浴びると、異論を遮断する “エコーチェンバー” が完成しちゃうんですよ。
結果としてデマでも「周りが言っているからまだ上がる」と錯覚しがちです。
ポジション管理を個人の投資計画に紐づけ、数量と期間を機械的に決定すると良いでしょう。
また、損切りの話だけでなく、群集心理により高値で買いたくなってしまうという現象もよく起こります。
「デイトレード」という本でバンドワゴン効果を株式投資で失敗する例として以下のように説明されていますね。
今どの状況なのかを考えると効果的です。
バンドワゴンで最初に楽しそうに数人が音楽を奏で踊っている
↓
それをみた人たちが釣られて集まってくる
↓
最初の人たちは離脱
↓
楽しそうな様子を見た人がさらに集まって道が激混みになる
↓
バンドワゴンが停止、バックして多くの人が大怪我
アンカリング効果
アンカリングとは船の錨(いかり)のアンカーからきた言葉です。
最初(同時)に提示された数値や情報が、印象に残ることで基準(アンカー)となり、その後の判断に強く影響を及ぼす現象のことです。
最初に提示された情報が錨(アンカー)のように頭に引っかかりができてしまうんですね。
買値や過去高値を基準(アンカー)として考えてしまい、それに固執し、「そこまで戻るまで売らない」って感じになるのが株式投資によるアンカリング効果です。
値動きではなく期待リターン/リスク比を新しいアンカーに置き換える。
アンカリング効果は買い物など様々な場面で影響があります。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。

保有効果
一度保有した銘柄は“自分のもの”という所有感で過大評価しがち。
これも損切りできない大きな要因となりますね。
現金化した場合の代替案(他銘柄やキャッシュ運用利回り)を書き出し比較。
代表性ヒューリスティック
物事のそれらしさに引っ張られ、その起こりやすさや確率を判断してしまう現象を代表性ヒューリスティックと呼びます。
これも投資に非常に邪魔になるんですよ。
例えば「この銘柄は◯◯業界でトップだから将来性抜群」と、少数情報だけで全体を推測しまうときなどがそうです。
木を見て森を見ずという状態ですね。
投資はむしろ森から入るべきなんですよ。
セクター平均PERや競合のEPS成長率など、統計比較を必ずセットにする。
過信バイアス
「自分は相場を読める」という過度な自信でロスカットを遅らせる。
年間パフォーマンスを市場平均(TOPIXやS&P500)と比較し、謙虚さを維持。
心理バイアスを克服するための5つの実践ステップ
心理バイアスは“知るだけ”では克服できません。
ここでは行動経済学の知見を踏まえ、具体的に行動を変える5ステップを提案していきます。
システムトレード派・裁量派どちらでも応用可能な枠組みとなっています。
事前コミットメントと損切りルール
エントリー時点で損失許容幅(%)と撤退条件を明文化。
これはとても重要な話ですが、心理バイアスの影響でなかなか難しいんですよ。
機械的に撤退条件を設定し、実行するかが大事です。
対策としては以下ですね。
・SNS等で宣言「破ると恥ずかしい」環境を作る。
・逆指値を入れておく
こんな感じで3層のストップロス・モデルを設定しておくとより心理的バイアスに対抗しやすいです。
| ストラテジー層 | 設定例 | 狙い | 想定バイアス |
|---|---|---|---|
| テクニカル層 | 20日移動平均-3% | 短期トレンド崩れを即切り | 損失回避先送りを防止 |
| 資金管理層 | ポジション総損失▲2% | 口座保全 | 群集心理の暴走抑制 |
| システム層 | 年間MAXDD▲10% | ルール全体見直し | サンクコストの誤謬リセット |
投資日記等を書き客観視
エントリー理由・感情・市場環境を記録し投資心理 バイアスを可視化する。
月1回まとめて振り返ることで確証バイアスを検出できます。
機械的ポジションサイズ管理
1トレード損失上限=総資産×1%などと定量化することも重要です。
群集心理からの衝動売買を物理的に抑えることができます。
デジタル・デトックス
含み損銘柄を一時的に非表示にしアンカリング効果を解除。
外部チェックリストの導入
行動経済学的エラーを列挙したチェックリストを決算発表前に読む。
まとめ
今回は「損切りできないのは才能不足ではなく“脳の仕様”。克服するための行動経済学ガイド」と題して損切りと行動経済学の話を見てきました。
「損切りできない」問題の根源は脳の仕様なんですよ。
行動経済学が示すバイアス連鎖。理論を学び、具体策を“仕組み”として実装することで克服できます。
意識して取り組んでみましょう。
行動経済学を学びたいかたはまずこちらがおすすめですね。
私が行動経済学にはまったきっかけとなった本です。