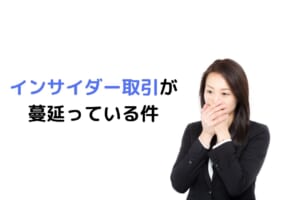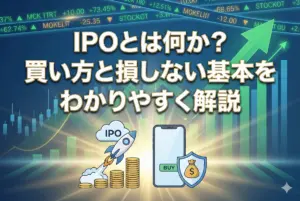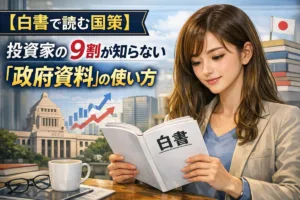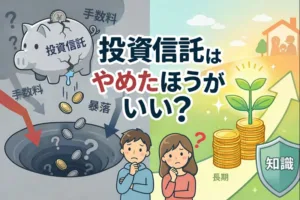「教育資金は何となく毎月余ったら…」では、高校~大学で一気に資金需要が跳ね上がる現実に追いつきません。
この記事では、(1)必要額の目安(最新公的データベース)、(2)貯め方(貯金×投資×保険の設計)、(3)制度活用(児童手当・NISA・贈与・奨学金/教育ローン)を、20〜40代の共働き世帯向けに今日から動ける形で整理します。
※なお、本記事は2025年8月時点のルールで執筆しています。制度は定期的に更新されるため、申請・契約前に最新情報を必ず確認してください。
教育資金はどれくらい必要?年代別・学校別の目安額
まずは今回の話の前提となる教育資金はどれくらい必要となるのかから見ていきましょう。
文部科学省「子供の学習費調査(令和5年度)」によれば、幼稚園(3歳)~高校3年までの15年間に保護者が支出した学習費総額は以下のとおりです。
小~高の「学習費」:オール公立596万円、オール私立1,976万円
ケース1(全て公立):約596万円
ケース2(幼稚園のみ私立、他は公立):約647万円
ケース3(幼稚園・高校が私立、他は公立):約776万円
ケース4(全て私立):約1,976万円
小~高の「学習費」はオール公立で596万円。オール私立の場合には1,976万円となります。
出典:令和5年度 子供の学習費調査(保護者負担。学校教育費+給食費+学校外活動費)
※今後高校無償化などが実施される予定なのでもう少し減ります。
大学の学費:国立は標準53.58万円/年、私大は平均95.9万円/年
大学は以下のとおり。これはあくまでの学校に払うお金の部分だけです。
これ以外に通学費や下宿すればその費用もかかります。
国立大学:標準授業料535,800円/年、入学料282,000円(多くの国立でこの水準)。
ただし一部は引き上げの動きがあり、東京大学は2025年度以降入学者で642,960円/年に。
私立大学(学部):授業料平均930,943円/年、入学料平均245,951円、施設設備費平均165,271円など。初年度納入金は学部・大学で差が大きいので見積もりを。
出展:文部科学省「私立大学等の令和3年度入学者に係る学生納付金等調査結果について」
小学生からをまとめるとこんな感じですね。
| 学年帯 | 公立(年) | 私立(年) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 小学校 | 336,265円 | 1,828,112円 | 学習費総額(家庭負担) |
| 中学校 | 542,475円 | 1,560,359円 | 同上 |
| 高校(全日制) | 597,752円 | 1,030,283円 | 同上 |
| 大学(授業料) | 535,800円(国立標準) | 930,943円(私大平均) | 入学料:国立282,000円/私大平均245,951円。東大は授業料642,960円へ改定(25年度入学者)。 |
つまり、まとめると「小~高は公立想定、大学は国立」→ 約600万円+(入学金28.2万円+授業料合計約214.3万円)が最低金額の目安となります。ですので約850万円は少なくとも学校に払う必要があるってことですね。
塾や通学費や下宿などを考えると少なくとも1,000万円くらいの用意はいるってことですね。
さらに「高校から私立」「大学は私立理系」など、高校以降の選択が費用に大きく変わってきます。
教育資金の賢い貯め方(定期預金×NISA×学資保険の役割分担)
それでは具体的にどのように教育資金を貯めればよいのかを考えてみましょう。
積立貯金(定期預金・財形):短期用途・非常時の現金クッション
直近1~3年に使うお金(受験料、私立併願の入学金“キープ”、塾・模試の増加分)は価格変動のない現金、預金で持つのが現実的です。
「月ベースの固定化」がコツ。
児童手当の入金口座=教育資金口座にし、偶数月の入金→即積立にすると続きます。
最近のネット銀行ではバーチャル口座で用途別に分けることができたりしますので、そういうのを使うとわかりやすいですね。
投資型(新NISAの活用):10年以上先の大学費用を“育てる”
投資に税制優遇がある制度としてはNISAとiDeCoがありますが、iDeCoは老後資金用のため教育資金では使い勝手が悪いです。
ですからまずはNISAを検討しましょう。
2024年スタートの新NISAは生涯非課税枠1,800万円。
つみたて投資枠(長期分散)+成長投資枠の併用が可能となっています。
教育目的ならつみたて投資枠でインデックス型の投資信託を中心に考えると良いでしょう。
なお、NISAは未成年が口座を開設できません。
ですから当面は親名義でということになります。
なお、未成年向けの「こどもNISA(仮称)」は検討段階にはあります。
ただし、まだ報道・提言レベルで、制度化は未確定です(今後の税制大綱等に注目)
投資商品イメージ
世界株式インデックス(オルカン)等の低コスト分散が基本です。
高校期が近づくにつれ、変動が少ない債券・現金比率を段階的に厚くする“グライドパス”が安全策かも。
学資保険のメリット/デメリットを素直に整理
もう一つの選択肢として学資保険があります。
メリット・デメリットをみておきましょう。
メリット
強制力があることはメリットでしょう。(半ば“保険料”として積立)
強制貯金的に活用ができます。
もう一つが親に万一時の払込免除という保険的メリットですね。
デメリット
個人的には学資保険はあまりおすすめしていません。
それはデメリット部分が強いからです。
具体的には途中解約で元本割れしやすい、インフレへの追随力が低い、流動性が低いというデメリットがあります。
保険会社も株等で運用した分をお渡しする形になりますが、自分たちの取り分があるから当然、利回りで考えると低くなってしますのです。
その分、満期まで持てば元本補償だったりするのですが、ローリスク・ローリターン感が否めません。
それならNISA等で自分で運用した方がお得なケースが多いのです。
また、生命保険の相談動向でも説明不足・解約返戻金の認識齟齬などの相談が目立ちます。
実際、学資保険の元本割れ紛争も国民生活センターADRの事例に見られます。
契約前に返戻率・解約返戻金の推移・特約の有無を必ず確認をしましょう。
家計に“強制力”が必要・死亡保障も兼ねたいなら候補にいれても良いとおもいますが、率の良い長期積立(NISA)と併用し、過度に比重を高めないのが失敗しないコツですね。
児童手当の“満額積立”シミュレーション
児童手当は、0〜2歳:月1.5万円、3歳以上〜高校生年代:月1万円(第3子以降は3万円)。支給は偶数月に前月まで分をまとめてです。 (2024年10月拡充反映)
もしそれを全額教育資金として運用したらどうなるのかをシュミレーションしてみましょう。
拠出額
0~2歳(36か月)×1.5万円=54万円
3歳~高校生年代(180か月)×1万円=180万円
→ 計234万円
運用結果
運用なし:234万円
年1%で月積立運用:約257.8万円
年3%で月積立運用:約315.4万円
(当サイトで定率積立の将来価値を計算。利回りはあくまで仮定です)
これだけでは到底たりませんが、運用しない場合と比較して81.4万円増えています。
GPIFは年4.3%の利回り
投資をやったことない人からすると年3%のイメージは湧きにくいと思いますが、日本で年金を運用しているGPIFの利回りは2025年度第1四半期までで年+4.33%の利回りとなっています。
ですから年3%って結構現実的な数字なんですよ。
ちなみにGPIFの運用を真似るのはかなり容易です。

使い道別の現実解:幼少~小学校は“現金重視”、小~中は“児童手当の一部をNISAで育てる”
高校期は“現金化”の3段ロジックにすれば計画は破綻しにくいでしょう。
制度や税制優遇の“使い分け”
その他使える制度の使い分けを見ていきましょう。
祖父母からの教育資金贈与(非課税)
まずは祖父母からの教育資金贈与です。
対象:直系尊属→30歳未満の孫・子
期限:2026年3月31日までに契約等(延長措置後)。
上限:1,500万円(うち学校等以外は最大500万円まで。合算で2,000万円非課税ではない点に注意)。
実務:金融機関の教育資金口座/信託で領収書管理。使い残し・贈与者死亡時の扱いに税務注意。
奨学金
JASSO(貸与)は第1種(無利子)・第2種(有利子)は固定/見直し方式を選択。
第2種の上限利率は制度上3%(実勢はもっと低位が多い)。
家計・学力基準や給付型との組合せも確認。
給付奨学金/授業料等減免は家計基準が細かいので公式ガイドを必ずチェック。
国の教育ローン(日本政策金融公庫)
目安上限350万円(要件で450万円)、固定金利2.85%(2025年6月時点)。
条件により0.4%優遇など。金利は変動するため公式ページの最新を確認。
奨学金(低コストの長期資金)+教育ローン(入学金や初年度の資金ショート対策)を必要最小限で使うのがポイント。
借入は卒業後キャッシュフローで返せる額に限定しましょう。
教育資金を貯める際の注意点と“あるある”失敗例
次に注意点と失敗例をみていきましょう。
インフレリスク
これから一番考えないといけないかもしれないのがこれかもしれません。
インフレリスク
現金だけだと実質目減りとなります。
長期資金は分散投資でヘッジし、新NISAのつみたて投資枠を核にするのがおすすめ。
学費もインフレで上る可能性大ですしね。
投資のやりすぎ(元本割れ)
投資は波があります。
大学入学前にリーマン・ショック級の大暴落が来る可能性もゼロではありません。
“大学入学3年前”を切ったら値動き資産を縮小するのがおすすめ。
流動性不足
学資保険の中途解約は元本割れリスクがあります。
契約前に返戻表と諸費用を必読
制度誤認
未成年の新NISA不可(親名義で運用)
児童手当は偶数月支給。
口座着金のたびに自動積立設定で“先取り”するのがおすすめ。
まとめ
今回は「教育資金の貯め方|高校・大学の学費目安とNISA等の制度活用」と題して教育資金の話をみてきました。
まとめるとこんな感じですね。
・児童手当の口座を“教育専用”にして、偶数月の着金→即・自動振替(定期預金 or 特定のサブ口座)。
・新NISA(親名義)で毎月つみたてを設定(世界分散インデックス等/教育資金サブ口座で見える化)。
・高校期3年前から現金化。必要ならJASSO給付/貸与や国の教育ローンを最小限で併用。
“教育資金”はゴールが明確な資金。
学年カレンダーに沿って「現金⇄投資」の比率と制度の申請時期を前倒しで決めておけば、焦らず・迷わず・取りこぼさずに走り切れます。
がんばって貯めていきましょうね。
NISA始めるならSBI証券がおすすめ。