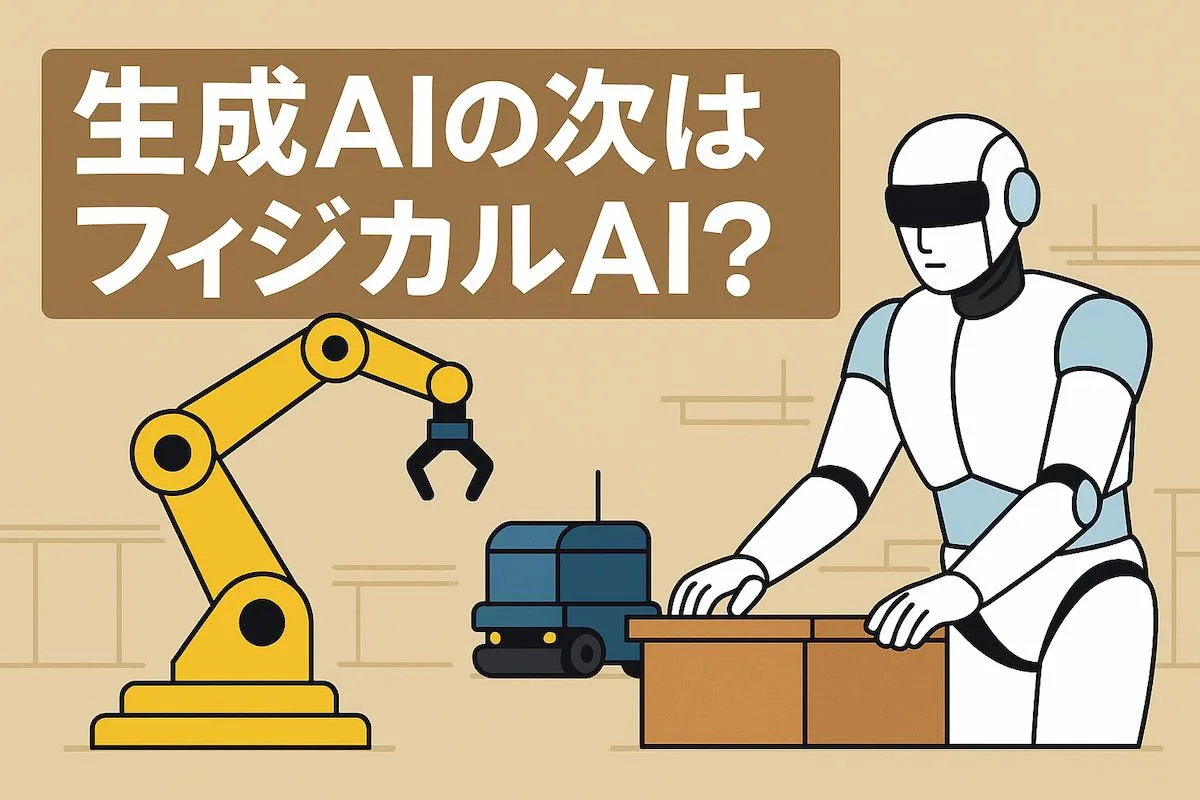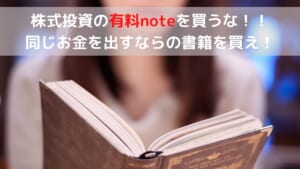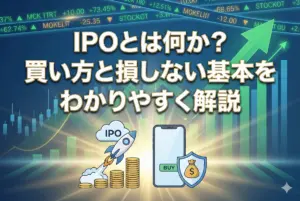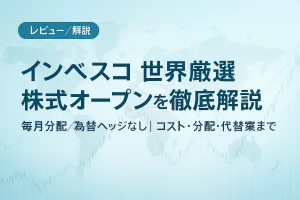先日、ソフトバンクグループがスイスのABBからロボット事業を買収する合意を発表しました。
総額は約53.75億ドル、ABBがロボティクス事業を会社分割したうえで全株式をソフトバンク側が取得するスキームです。
ABBは産業用ロボットの分野で世界4位の企業なんですよ。
この買収に端を発して話題となっているのが「フィジカルAI」です。
今回はフィジカルAIについてわかりやすく解説していきます。
フィジカルAIとは
まずはフィジカルAIとはなにかについて解説していきましょう。
フィジカルAIは、カメラや各種センサーで周囲を“見て・理解し”、状況に応じて“判断・動作”までやり切るための仕組みです。
文章や画像を生み出す生成AIに対し、フィジカルAIは三次元の空間や物理法則を前提に「自律行動」を生みます。
代表例がロボットや自動運転ですね。
たとえば、倉庫で荷物を素早く仕分ける、工場で段取り替えを自動でこなす、病院で検体を運ぶ、建設現場で資材を運搬する、といった実務です。
学習は強化学習や高精度シミュレーションを活用して“仮想空間で数万回試してから”現実へ持ち込むのが基本形になりつつあります。
NVIDIAはこれを「Generative Physical AI(生成フィジカルAI)」と整理し、仮想空間が学習の訓練場とデータ源を兼ねる、と位置づけています。
フィジカルAIが投資テーマとして取り上げられるのは以下の2点の要素が大きいです。
需要の高まり
まず、挙げられるのが生成AIが広げた「知の自動化」の次に、「作業の自動化」への需要が高まっていることです。
製造、物流、建設、ヘルスケア、リテールなど、いずれも人手不足に直面しています。
特に先進国の人口減、生産年齢減は共通事項ですからね。
また、人出不足以外にも安全性の確保、そして多品種少量への対応が重なり、ロボット導入のハードルは「必要性の高まり」によって下がっています。
実際、世界のロボット導入は長期的に増加基調で、2024年の新規導入は54万台規模。日本は設置台数で世界2位の市場を維持しつつ、稼働台数や輸出でも重要な地位を占めています
技術の進歩
次に挙げられるのが、技術の進歩です。
特に大きいのが、学習を現実ではなく仮想空間で進められるため、かつてより開発サイクルを速く回せるようになったことでしょう。
この部分はかなり大きいです。
前述の生成フィジカルAIですね。
また、クラウドとエッジ、GPUと専用アクセラレータ、基盤モデルとロボティクスOSといったレイヤーが整い、部品の寄せ集めではなく“スタックとしての産業”が見え始めています。
そのタイミングに目をつけた孫さんはさすがとしか言いようがありません。
生成AIとの違い
生成AIが得意にしてきたのは“知の自動化”でした。
一方フィジカルAIは“作業の自動化”。
一番大きな違いは「物理世界でミスが許されにくい」点にあります。
生成AIでよく発生するハルシネーション(それぽい嘘)のような現象は基本的に許されないのです。
ですから、単なる精度の話ではなく、安全規格への適合、停止・再開の手順、ライン全体での段取り、保守サービス網、顧客の生産計画との整合――こうした“現場の作法”を身につけている企業が強いのです。
NVIDIAが示すように、シミュレーションという“仮想の現場”で学習を回し、現場への展開を速める発想が主流になるほど、GPUとロボットの両方に資金が流れる可能性が高そうです。
フィジカルAIの実装像
当面は「危険・重労働・単純反復」など置き換え効果と安全性が両立しやすい領域から普及が進みことが予想されます。
工場の協働ロボットによる段取り、物流倉庫の入出荷、空港・病院の搬送、建設現場の自律搬送などがその例ですね。
単体販売で終わらず、稼働率を高める保守契約やリモート監視、性能アップのソフト更新まで含めた“長い収益”が乗りやすいのが特徴です。
その後は徐々に複雑な分野に進出していくものだと思われます。
フィジカルAI関連銘柄を整理してみた
次にフィジカルAI関連銘柄について考えてみましょう。
フィジカルAI関連の銘柄はかなり幅が広く、掲載しているメディアによってかなり異なっているんですよ。
今回はそのあたりを整理してみましょう。
フィジカルAI関連銘柄を大きく分けると、頭脳に当たる上流(学習・シミュレーション・GPU)、ライン最適化やロボットOSで囲い込む中流(ロボットOS・デジタルツイン・制御)、据付・保守まで抱える現場側の下流(実機・SI・保守)、そして部品・センサー、通信等の横串となります。
それぞれ分けて整理してみましょう。
上流:GPU・シミュレーション基盤
まずは上流部分です。
ここでも本命はNVIDIAが挙げられます。
NVIDIAは、生成AIの学習だけでなく、物理を織り込んだ3Dシミュレーションやデジタルツイン(仮想工場)を束ねる要となっています。
フィジカルAIでは“仮想空間で技能を身につける”過程が重要で、GPU需要がクラウドから工場・倉庫・病院へと裾野を広げる可能性があります。
他にもAMDやArmは、学習・推論双方の計算基盤で存在感を高めています。
推論の電力効率やエッジ側での処理がカギになると、CPU/GPU/専用アクセラレータの“適材適所”が進みます。
ここは技術進化と価格性能の勝負で、NVIDIAの優位をどこまで崩せるかが中期テーマとなりそうです。
シーメンス、ダッソー・システムズ、ANSYSなどは、設計〜製造のデジタル連携や物理シミュレーションを担い、ロボットの段取り時間短縮に効きます。
特にデジタルツインは“試作を現場でなく仮想空間で回す”要で、フィジカルAIの量産に直結します
中流:OS・制御・遠隔運用
ロボットOSや統合制御、遠隔監視の分野は、特定企業への“囲い込み”が強くなりやすい層です。
ここは非上場企業も多いのですが、ロックウェル・オートメーション、シュナイダーなどのFA(工場自動化)大手も、AI連携の中核を握る動きが強まっています。
トヨタ自動車はWoven CityやTRI(トヨタ・リサーチ・インスティテュート)を軸に、移動・生活・エネルギーが混ざる実環境で「認識→計画→制御」を安全規格や運用設計まで含めて統合するのが強みです。
これはまさに中流の仕事で、デジタルツインや運用OS、ライン最適化の設計思想が問われます。
そのうえで、自動運転シャトルやサービスロボット、工場自動化の適用など現場側の実装にも踏み込むため、下流にもまたがります。
日立製作所も世界トップのフィジカルAIの使い手となるべく動いているようです。
具体的には、米JR Automationの買収でロボットSIの海外展開を取り込み、さらにKyoto Roboticsの3次元ビジョンなど“目と頭脳”の要素を抱き合わせ、製造・物流のデモラインや案件で「認識→計画→制御→据付・保守」を一気通貫で回せる体制を固めています。
こちらも中流から下流をまたいでいる感じですね。
下流:実機メーカー・SI・保守(国内)
日本が強いのは下流の部分ですね。
今回のソフトバンクによるABBのロボット事業の買収で、産業用ロボットの世界上位5社のうち、4社が日本企業となります。
産業用ロボット世界1位のファナックは、工作機械や電子部品の生産ラインで幅広く使われるロボットを展開し、信頼性と保守の強さが持ち味です。
協働ロボットの拡充や、ソフトによる段取り効率化はフィジカルAIの受け皿になります。
産業用ロボット世界3位の安川電機はモーション制御とロボティクスの両輪で、溶接・塗装など“現場の定番”を押さえています。
フィジカルAI分野で富士通、NVIDIAとの協業を検討しているとの報道もでていますね。
富士通はNVIDIAとチップからサービスまで含んだ「フルスタックAIインフラストラクチャ」の構築を目指し、戦略的協業を拡大することを発表しています。
川崎重工は自動車などでの実績が厚く、産業用ロボットから医療ロボット(手術支援)まで裾野が広いのが特徴です。
三菱電機はFA総合力が強く、ロボット単体より“ライン全体の最適化”で稼ぐポジションです。
産業用ロボット世界5位のデンソーも東芝や東京科学大学と共同研究するなどフィジカルAIの分野に力をいれはじめています。
ダイフクは“モノの流れ”を自動化するマテハン(倉庫内の自動搬送・保管・仕分け)の世界大手で、倉庫や空港、工場の自動化に不可欠です。
ソフト・据付・保守まで抱き合わせる“長い収益”が乗りやすい構造です。
下流:実機メーカー・SI・保守(海外)
ABBはロボット事業をソフトバンクへ売却するため、売却後のABB本体は電化・自動化などの中核に専念する形となります。
ロボット純粋プレイとしてのABBはソフトバンク傘下へ移る、というのが今回のポイントです。
産業用ロボット世界2位の中国企業KUKA(Midea傘下)は上場外ですが、欧州の自動車分野で強いプレゼンスがあります。
フィジカルAIの分野では中国がかなり先行しているという話もありますね。
米国ではロックウェル、欧州ではシーメンス、シュナイダーが“ライン最適化”を軸にロボティクスとAIの橋渡し役を担います
テスラは自社工場という現実の現場を持ち、ヒューマノイドのOptimusや工場内自動化といった“動くプロダクト”の内製を運用しています。
今後それらを横展開する可能性もありそうです。
横串:部品、センサー、通信
ソフトバンクグループは、データセンター構想やAI半導体の調達網と、今回のロボティクス事業を束ねられる点が強みです。
生成AIとフィジカルAIを両輪で回すには、学習と配備の往復を支える計算基盤が不可欠で、ここでの投資余力が活きてきます。
SMCやハーモニック・ドライブ・システムズ、THKなど部品の横串は、ロボット台数とともに裾野が広がる“波及の受け手”です。
キーエンス、オムロンはセンサー・制御の雄で、視覚・安全・検査の高度化に切り込んでいます。
エッジAIカメラや検査の自動化は、フィジカルAIの“目と耳”を強化する発想と相性が良い領域
まとめ
今回は「生成AIの次はフィジカルAI?:ソフトバンクのABBロボット買収で話題の実世界AIの本命領域」と題してフィジカルAIについてみてきました。
「フィジカルAIとは」を一言でいえば、AIが“知識をつくる”段階から“行動をつくる”段階へ踏み込むための要です。
ソフトバンクがABBロボティクスを取り込む意味は、AIの頭脳と現場の筋肉をまとめて握り、学習→配備→保守の循環を速めることにあります。
投資家としては、上流・中流・下流のどこで“長期の反復収益”が積み上がるかに注目し、一次情報(IR、IFR、メーカー資料)で地道に裏取りを続けることが重要でしょうね。