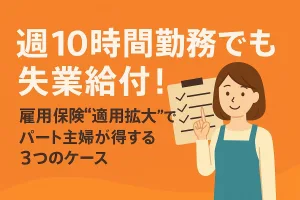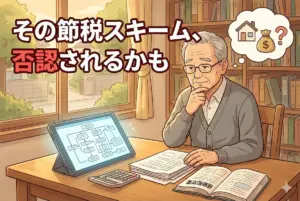2026年、労働基準法が約40年ぶりに大幅改正される見通しです。
1987年に「週40時間制」や「裁量労働制」が導入されて以来の大改革となるこの改正は、働き方の根本を見直す内容を含んでいます。
テレワークの普及、副業・兼業の拡大、そして労働者の健康確保への意識の高まりを受け、現行法が想定していなかった働き方に対応するための改正が進められているのです。
本記事では、厚生労働省の「労働基準関係法制研究会報告書」をもとに、2026年労働基準法改正のポイントと施行時期、そして私たちの収入・キャリアに直結するポイントを、感情論ではなく経済的な視座から解説していきます。
労働基準法改正2026年はいつから施行されるのか
まず、もっとも気になるスケジュール感について整理しましょう。
いまどこまで決まっているのか
現時点で決まっている流れは、ざっくり次のとおりです。
- 2024年1月:厚労省が「労働基準関係法制研究会」を設置
- 2025年1月:同研究会が報告書(改正の方向性)を公表
- 2026年:通常国会に労働基準法改正案が提出される見込み
- 2027年4月施行と見込む民間解説が多い
早ければ2026年4月からとの予想もありましたが、現在は2027年4月からとなる感じの流れですね。
まとめると
2026年:国会で法改正を決める年
2027年以降:順次施行されていくイメージ
と捉えた方が現実的です。
法改正の正式決定には国会での審議が必要であり、現在の少数与党では修正や施行時期の変更もありえます。
「労働基準法改正 2026 いつから?」への答え
2025年11月時点での答えを、あえて一文でまとめるとこうなります。
「2026年に法案が成立すれば、早ければ2027年4月から施行が始まる見込み。ただし内容も施行日もまだ確定ではない」
そのうえで、既に方向性として挙がっている「7つのポイント」を押さえておけば、会社員・フリーランス・投資家いずれの立場でも、先回りして準備しやすくなります。
なお、本件は2026年の通常国会への提出を見送ったとのこと。
ですから内容も、時期も未定になりました。
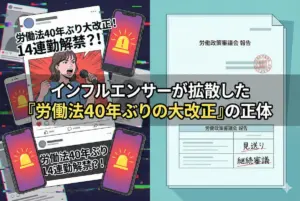
「40年ぶりの大改正」と呼ばれる理由
労働基準法は1947年に制定されて以来、労働者保護の基本法として機能してきました。
1987年には「週40時間制」や「裁量労働制」の導入を含む大改正が行われましたが、その際も約10年にわたる検討が重ねられました。
現行の労働基準法は、昭和22年(1947年)に制定されたものがベースとなっており、「工場で働く労働者」を守ることを主眼に置いてきました。
しかし、現代はどうでしょうか。PC一台でどこでも働けるテレワーク、時間ではなく成果で評価されるべきクリエイティブ職、そして副業・フリーランスといった多様な働き方が一般化しています。
「時間管理」から「健康と成果の管理」へ。
このパラダイムシフトに対応しなければ、日本企業の生産性は上がらず、結果として働く個人の賃金も上がらないという危機感が、今回の改正の背景にはあるのです。
今回の改正が注目される理由は、単なる条文の修正ではなく、「労働者」の定義や「事業」の概念といった法の根幹部分にまで踏み込んだ議論が行われている点にあります。
デジタル技術の発展やコロナ禍を経て急速に変化した働き方に対応するため、法律そのものの整備が必要だと認識されていう感じですね。
労働基準法改正で議論されている7つの主要ポイント
厚労省の研究会報告書では、企業実務に直結する論点として、次の7項目が整理されています。
- 連続勤務の上限規制(14日以上連続勤務の禁止)
- 法定休日の明確な特定義務
- 勤務間インターバル制度の義務化(原則11時間)
- 有給休暇の賃金算定で「通常賃金方式」を原則化
- 「つながらない権利」に関するガイドライン
- 副業・兼業者の割増賃金算定ルールの見直し
- 週44時間特例の廃止(週40時間に一本化)
それぞれ簡潔に見ていきます。
1.連続勤務の上限規制(14日以上連続勤務の禁止)
現行の労働基準法では、法定休日として1週間に少なくとも1日の休日を付与することが義務付けられています。
一方で「4週間を通じて4日の休日を付与」すれば週休1日制の適用を受けない特例も認められています。
この4週4休の特例を理論上適用すると、最長で48日間の連続勤務が可能になってしまいます。
たとえば、8週間のうち第1週の最初に4日間、第8週の最後に4日間の休日を設ければ、間の期間は連続して勤務できる計算になるのです。
一方、精神障害の労災認定基準では「14日以上の連続勤務」が強い心理的負荷として扱われるため、健康リスクが非常に高い状態とも言えます。
そこで報告書では、
- 特例を「4週4日」→「2週2日」に見直す
- 「14日以上の連続勤務は禁止」というラインを設ける
という方向性が示されています。
ブラック企業に痛手
長時間労働に依存している職場では、シフトや人員配置の抜本的な見直しが避けられないテーマです。
これは、企業に対して「人員配置の余裕」と「業務の標準化」を強制するものです。
ギリギリの人員で回しているブラック体質の企業は、この規制により人件費コストが増加、あるいは業務停止のリスクを抱えることになります。
一方で、働く側にとっては、過労死リスクという「人的資本の毀損」を防ぐための重要なセーフティネットとなります。
2.法定休日の明確な特定義務
多くの企業は週休2日制ですが、「どちらが法定休日で、どちらが所定休日か」を明確にしていないケースが少なくありません。
現行法では、週1日以上の休日は義務化されているものの、どの曜日を法定休日に特定するかの義務はないんですよ。
しかし、休日に働いたときの割増賃金の扱いは、法定休日かどうかで変わるため、線引きが曖昧だとトラブルの火種になります
そこで報告書では、
- 法定休日を事前に特定すること
- シフト制の場合は勤務表や就業規則で「基本パターン+例外」を明示すること
など、休日ルールの明確化が提言されています。
3.勤務間インターバル制度の義務化(原則11時間)
勤務間インターバル制度は、終業時刻から次の始業時刻までに一定時間の休息を確保する仕組みで、2019年からは「努力義務」として導入されています。
ただ、導入企業はまだ2024年時点での導入実績はわずか5.7%にとどまっているという調査もあり、十分に普及しているとは言えません。
そのため、報告書では、
- 勤務間インターバルを義務化
- 原則のインターバル時間を11時間とする(EUなど海外の水準を参考)
という方向性が示されています。
夜遅くまで残業した翌朝は、始業時刻を遅らせる運用などがセットで求められるイメージです。
ダラダラ残業ができなく
逆に言えば残業代で稼いでいた層にとっては、一時的に収入減となる可能性があります。
しかし、長期的には「時間当たりの単価」を上げない限り、収入が維持できない構造になります。
これは、「ダラダラ残業」からの脱却を意味し、自身のスキルアップに時間を投資できた人だけが勝てるゲームへとルールが変わることを示唆しています。
4.有給休暇の賃金算定における「通常賃金方式」の原則化
有給休暇を取ったときの賃金の出し方は、現在3パターンあります。
- 平均賃金方式
- 通常賃金方式
- 標準報酬日額方式
このうち平均賃金方式や標準報酬日額方式だと、日給・時給労働者が不利になるケースがあり、格差が問題視されています。
そこで、
有休取得時の賃金は、原則「通常賃金方式」で支払う
というルールに一本化する方向で検討が進んでいます。
これにより、有給休暇を取得しても通常の勤務日と同じ賃金が支払われることになります。
5.「つながらない権利」に関するガイドラインの策定
「つながらない権利」とは、勤務時間外のメールや電話、LINEに応答しない権利のこと。
フランスなどではすでに法律で位置づけられている国もあります。
日本労働組合総連合会が2023年に実施した調査によると、「勤務時間外に部下や同僚、上司から業務上の連絡がくることがある」と回答した人は72.4%に上りました。
また、「勤務時間外の連絡を拒否できるならそうしたい」と答えた人も72.6%でした。
報告書では、
- 勤務時間外にどこまでの連絡が許容されるか
- どのような連絡は拒否できるのか
といった点について、社内ルール作成を促すガイドラインを整備することが提言されています
6. 副業・兼業者の割増賃金算定ルールの見直し
現行の労基法では、事業場が違っても労働時間は通算するのが原則で、そのうえで割増賃金も通算時間をもとに計算する建て付けになっています(労基法38条)。
そのため、両方の労働時間を合算して法定労働時間を超えた場合、後から労働契約を締結した事業主が割増賃金を支払う義務を負います。
しかし、複数企業の労働時間をまとめて管理し、割増賃金をどこがいくら支払うか調整するのは、実務的にはかなり大変です。
そのため、企業が副業・兼業を認めにくい要因とも指摘されています。
そこで報告書では、
- 健康管理のための「労働時間通算」は維持
- ただし割増賃金の通算管理は原則として廃止
という方向性が示されています。
副業をする本人の健康管理と、企業の実務負担のバランスを取りに行く改正、とイメージしていただくとわかりやすいと思います。
7. 週44時間特例の廃止(すべて週40時間に)
ごく一部の業種・小規模事業場には、「週44時間」まで法定労働時間を延長できる特例が残っています。
ところが、厚生労働省が2023年に実施した調査では、特例対象事業場の87.2%がこの特例を利用していないことが明らかになりました。
そのため、「役割を終えた」と判断し、
法定労働時間はすべての事業場で週40時間に一本化
「40年ぶりの大改正」で議論されているその他の重要テーマ
今まで見てきた7つの項目は盛り込まれる可能性が高いと思われますが、他にも議論されているテーマがあります。
そちらも確認しておきましょう。
労働者の定義の見直し(プラットフォームワーカー・フリーランス)
現行の労基法では、労働者は「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義されています。
しかし、ウーバーの配達員やクラウドワーカーなど、プラットフォームを通じて働く人たちの扱いが、この定義では十分にカバーできていないのではないか、という問題意識があります。
報告書やSmartHRの解説では、海外の「ABCテスト」なども参考にしながら、労働者性の判断基準を見直す必要性が指摘されています。
フリーランス・ギグワーカーにとっては、自分が「本当は労働者として扱われるべきなのか」が、今後ますます重要な論点になっていきます。
事業単位の見直し(テレワーク時代の「どこの事業場の人か」問題)
これまで労基法は「事業場ごと」に適用されるのが原則でしたが、テレワークの普及で、「勤務地」や「所属事業場」が曖昧になっています。
こうした変化を踏まえ、企業単位でのルール作りや、複数事業場をまたいだ労働時間管理のあり方も見直しの対象とされています。
「新しい労働時間制度」とホワイトカラーへの適用
もっとも議論が白熱しているのが、いわゆる「ホワイトカラー・エグゼンプション(適用除外)」に近い概念や、裁量労働制の適用拡大です。
現在は限られた専門職や企画職にのみ適用されている「時間ではなく成果で評価する(残業代が出ない代わりに、時間の使い方が自由)」制度を、より広い職種へ適用しようとする動きです。
デロイト トーマツなどの調査機関や経団連も、ジョブ型雇用への移行とセットでこの議論を推進しています。
もしこれが汎用的な職種に解禁されれば、あなたの給与明細から「残業手当」という項目が消え、代わりに「職務給」や「業績給」の比重が高まることになります。
会社員・フリーランス・企業(投資家)にはどう影響する?
ここからは会社員、フリーランス、企業(投資家含む)にどのような影響があるのかを考えて見ましょう。
企業(投資家)にとっての影響
まず法改正により、労働時間の管理や健康確保の基準が厳格化されます。
これに対応できない企業、つまり「長時間労働でしか利益を出せないビジネスモデル」の企業は、法的リスクと採用難というダブルパンチを受けることになります。
とくに小売・外食・介護・物流・宿泊など、シフト勤務と長時間労働に依存している業種は、人件費増か人員不足のどちらかを迫られやすい構造となっています。
一方で、いち早く「時間あたりの生産性」を高め、柔軟な働き方を制度化した企業には、優秀な人材が集まります。
労働時間の見える化や情報開示も議論されており、「長時間労働が隠しにくい時代」になりつつあります。
求人・採用の場面でも、「法改正への対応状況」「勤務間インターバルの有無」などが、企業選びの指標になっていくでしょう。
厳しい言い方になりますが、今回の法改正は「ゾンビ企業の退出」を促す側面があります。
法改正に対応するコストを支払えない、あるいは管理能力のない企業は市場から退場を余儀なくされるでしょう。
投資家としては、有価証券報告書の「人的資本」に関する記載や、離職率、有給取得率などの非財務情報をこれまで以上に注視する必要があります。
会社員への影響
会社員にはメリットとして
- 14日以上の連続勤務禁止や勤務間インターバル義務化により、睡眠時間と連続休息が確保されやすくなる
- つながらない権利のガイドライン整備で、「夜中のチャット」「休日の電話」が減る可能性
- 有給休暇の賃金が「通常賃金方式」に統一されれば、非正規の人が有休取得で不利になるケースが減る
というのがあります。
つまりワークライフバランスが取りやすくなるということですね。
一方で、注意点としては、
- シフト制・繁忙業種では、残業の上限や休日取得がより厳密に管理される分、「この日はどうしてもお願い!」が通りにくくなる
- 労務管理が厳しくなることで、成果ではなく時間で評価される感覚が強まる職場も出てくるかもしれません
など、「働きすぎ防止」と「柔軟さ」のバランスがポイントになりそうです。
それに伴い残業代などが減る可能性もあります。
フリーランス・副業ワーカーへの影響
フリーランスやギグワーカーにとっては、次の2点が特に重要です。
労働者の定義見直し
実態として社員に近い働き方をしているフリーランスは、将来的に「労働者」と認定されるリスクとチャンスの両面があります。
契約書や実際の指揮命令関係を見直しておくことが、法改正前からのリスク管理になります。
副業・兼業の割増賃金ルール見直し
本業+副業で働く人にとって、「どこまでが自分の自己責任の働き方で、どこからが企業の責任か」という線引きがクリアになる方向です。
一方で、労働時間の通算管理は残る方向なので、「週何時間働いているか」を自分でも把握しておく習慣がより大事になります。
まとめ
ここまで、「労働基準法改正」をテーマに、その影響と対策を見てきました。
- 施行は2027年4月が濃厚:準備期間はあとわずかです。
- 残業代は「不確実な収益」になる:時間外労働の規制強化や裁量労働の拡大により、残業代ありきの家計設計は破綻します。
- 「時間」から「成果」へのシフト:ダラダラ働くことは許されなくなり、短時間で成果を出すスキルが資産になります。
- 副業解禁の波に乗る:労働時間通算の見直しを見据え、自分で稼ぐ力を育てましょう。
法律が変わるということは、ゲームのルールが変わるということです。ルール変更を嘆くのではなく、新しいルールの中でいかに有利に立ち回るか。
今日からできることは、自分の働き方を「時給」ではなく「付加価値」で捉え直すことです。
「どうせ先の話」と流してしまうか、「40年ぶりのルール変更」をチャンスと捉えて、働き方や投資スタンスを一段アップデートするかで、数年後の差はかなり変わってきます。
この記事を、情報収集と整理のたたき台として使っていただければうれしいです。