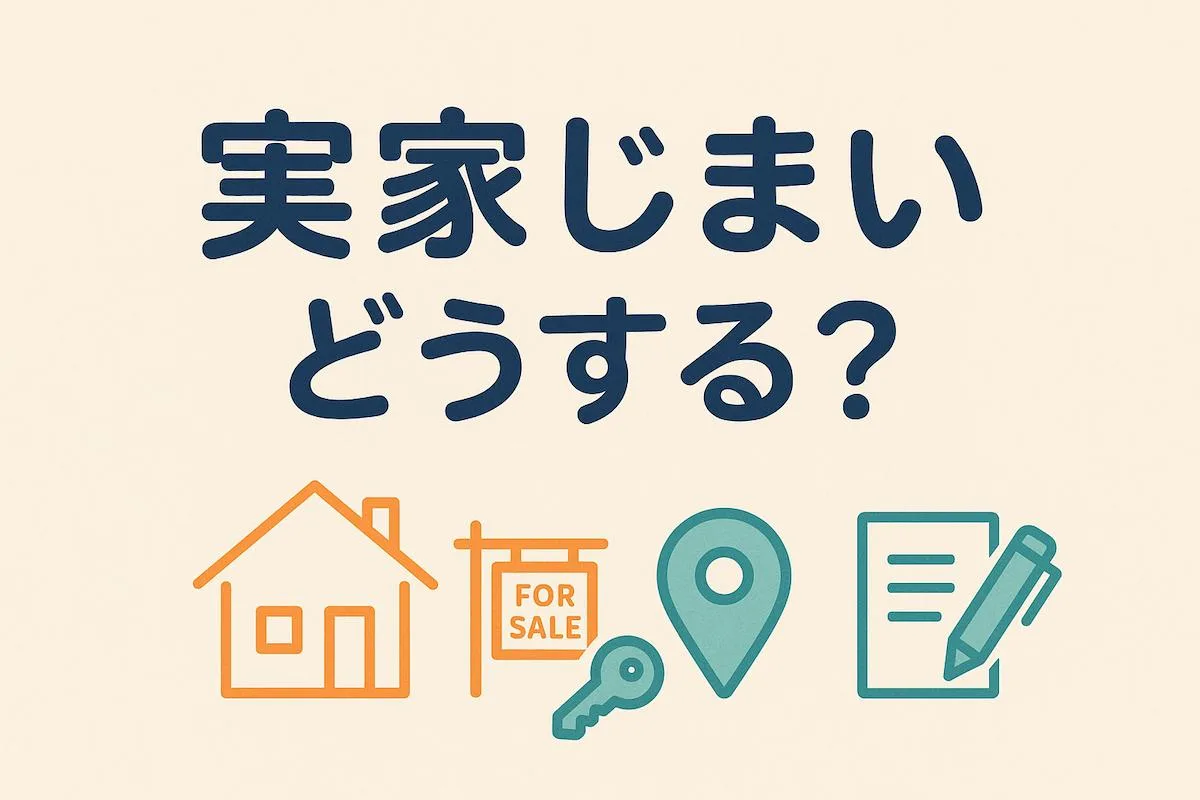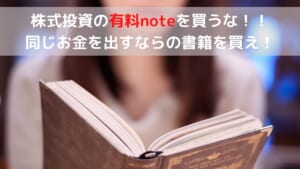最近、よく聞く話があります。
実家の土地や家をどうするべきなのか?というものです。
うちもそろそろ考えないといけない時期に来ているとは思いつつも手つかず・・・
そこで今回は実家の土地、家をどうするとよいのか?という論点を整理してみました。
「実家の家と土地」で取り得る5つの選択肢
まずは実家の家と土地をどうするか?で取りうる選択肢を見ていきましょう。
住む
まず1つ目は自分たちが住むという選択肢。
勤務や家族の事情で実家居住に合理性があるとか、学区・通勤・介護動線の相性が良いようなケースは選択肢になり得るでしょう。
土地の購入代や家の建設費が浮くため生活基盤が安定するというメリットがあります。
ただし、古い家の場合には改修・耐震費用が当然かかりますし、固定資産税・保険・維持費が恒常化します。
暑さ、寒さも今の家とは違いますのでそこらあたりはよく考える必要がありますね。
相続税では小規模宅地の特例(居住用 最大80%評価減)の検討余地があります。
誰がいつまで住むかで可否が変わるため、早めに要件確認をしましょう。
土地だけ使うという選択肢も
家には住まず、親の土地に家を建てるという選択肢もあります。
こちらもメリット・デメリットがあります。
詳しくはこちらの記事でまとめておりますので合わせて御覧ください。

貸す(賃貸・定期借家・一部民泊など)
次は貸すというパターンです。
中長期で“住まないが手放しも難しい”という場合には候補に上がるでしょう。
収入化の余地が生まれますのでそのあたりは大きなメリットですね。
ただし、原状回復・空室・近隣対応や事故・災害時の責任など運用負担があります。
また、その場所によっては需要がそもそもないというケースも。
借り手が見つからなければそもそも貸せないですからね。
売る(現況/耐震適合後/解体後の「更地売り」)
次は売ってしまうというパターンです。
相続人の誰も使わないとか、遠距離で管理が困難といったケースに選ばれやすいですね。
また、相続の際に資産の再配分をしやすくするというのも大きなメリットになります。
ただし、これも場所によっては需要がそもそもないというケースもありますので、すぐ売れるとは限らないという部分もあります。
マンションの場合は比較的売りやすいですが、戸建ての場合はなかなか苦労するという話も聞きますね。
特例
なお、売却する場合には特例があります。
- 「相続空き家の3,000万円控除」(譲渡所得から控除)
- 対象時期:平成28年4月1日〜令和9年(2027)12月31日の譲渡
- 代表的要件(抜粋):昭和56年5月31日以前新築/区分所有でない/相続後に住居・事業・貸付に使っていない/耐震適合にして売却 or 解体して土地売却/譲渡対価1億円以下/期限は相続開始から3年経過日の属する年末まで 等
- 相続人3人以上での譲渡は控除2,000万円(2024/1/1以降)
売却パターン
売却もやり方がいろいろあります。それぞれメリット・デメリットがありますのであらかじめ検討したいところです。
- 現況売り:そのまま売るってことですね。最短・現金化が早い。価格は抑えめ
- 耐震適合後:耐震リフォームしてから売るというパターンです。コストはかかるが対象者が広がりやすい
- 解体・更地化:買い手は付きやすいが、固定資産税の住宅用地特例が翌年以降外れる可能性も。着工時期を含め税負担の試算を
保留し、情報収集(空き家バンク)
一旦、保留にして情報収集するという選択肢もあります。
合わせて動くと損をする可能性がありますから、地域需要を見定めたいといったケースでは有力な選択肢となるでしょう。
例えば空き家バンク、空き地バンクなどに登録だけしておくというなんてことも考えられます。
このあたりの運営は自治体差が大きいので、掲載から成約までの運用フローを確認をおすすめします。
手放す(相続土地国庫帰属制度)
手放すという選択肢もあります。
ニーズがない地域でかつ、遠隔地であれば有力な選択肢になりえるでしょう。
具体的には相続土地国庫帰属制度というのを利用する形です。
相続や遺贈で取得した土地に限定されますが、申請手数料1筆14,000円+負担金(地目・面積等で算定)でりようできるとのこと。
ただし、不承認事由も多く、事前相談が前提となるようです。
実家の放置が駄目な理由
上記の5つの選択肢以外に取られがちなのが放置です。
これは悪手なんですよ。
具体的には以下の点で問題となります。
・相続登記の義務:相続で不動産を取得を知った日から3年以内に登記が必要。怠ると10万円以下の過料の可能性。
・住所等変更登記の義務化:変更から2年以内。違反は5万円以下の過料。
・空家法による管理不全空家:勧告で住宅用地特例が外れ、固定資産税の負担増。命令違反で過料(50万円以下)の恐れ
・相続空き家の3,000万円控除の期限(2027年12月31日)
過料となってしまう可能性があるのです。
実家じまい:ケース別・判断フローチャート
なかなか、難しい判断ですが以下の点を確認しましょう。
- 借金あるか不明 → まず通帳・保証・税滞納を洗い、必要なら相続放棄 or 期間伸長へ(3か月)。
- 使う人がいる? → 住む/貸すの前提で改修費・管理計画を数字で
- 使わない+売れそう? → 相続空き家特例の適否と締切(3年経過日の属する年末/2027年末)を逆算。
- 売れない・持続不能 → 国庫帰属制度の要件・費用・代替策を比較。
- 共通:相続登記(3年)と住所等変更登記(変更後2年)は確実に
最初にやるべき“3つのマスト”
まず最初にやりたいのは以下の3つのことです。
相続関係の確定と相続登記
遺言の有無→法定相続情報一覧図→相続登記(3年以内)。
分割が未確定で間に合わない場合は相続人申告登記で申出人のみ義務履行みなしに。
最終的には本来の相続登記が必要。
債務調査と相続放棄の検討
3か月以内が原則。
難しければ期間伸長を申立て。
カード・保証・税滞納など負の資産の把握は最優先。
管理体制の仮置き
ポスト投函・雨樋・雑草・越境・害獣・損壊の定期点検、火災保険の見直し。
管理不全空家の認定は税負担直撃リスク。
「売る」判断の要点と実務フロー
次に売るという判断をする際の良い点と実務の流れをみていきましょう。
まず特例の適否を診断
まずは特例を確認します。
ポイントは以下の部分
・物件の築年(S56.5.31以前)
・区分所有でない
・相続後未使用
・耐震適合 or 解体
・1億円以下
・期限(相続開始から3年経過日の属する年末まで)
・相続人3人以上なら控除2,000万円。
これらをチェックリスト化して逆算しましょう。
価格と工期の意思決定
現況売り・耐震適合・解体の3案で、工期と税制適用の締切から逆算して検討しましょう。
更地化は翌年以降の税負担増(住宅用地特例外れ)になりやすい点も視野に入れるのも良いでしょう。
また、解体もそれなりに費用がかかるのでその見積もりも早めにするのをおすすめします。
売却の実務フロー
実際に売却するとなると大まかな流れは以下のとおりです。
- 査定(机上→訪問)
- 媒介契約(一般/専任/専属専任)
- 販売活動(ポータル・囲合/レインズ登録)
- 売買契約(手付・付帯設備・境界)
- 引渡し(残代金・鍵/抵当抹消)
- 確定申告(特例の計算書・添付書類をミスなく)
「貸す、住む」場合の落とし穴
次は貸す、住むという場合の話です。
結構落とし穴があるんですよ。
外観・安全管理・耐震
屋根・外壁・庭木の劣化は管理不全空家に波及します。
勧告で住宅用地特例外れ→固定資産税3倍程度のケースも(自治体資料の周知)。
管理委託の費用対効果を検討しましょう。
自分が住む場合でも耐震や断熱などリフォームをしないと快適に暮らせないケースが多いためそのあたりの部分は検討する必要が出てきます。
賃貸の法務・実務
設備事故・近隣トラブル・入退去時精算などいろいろあります。
賃貸は事業であり、保険(施設賠償等)の見直しもセットで考えるべきです。
私は敷金で裁判しましたが、適当な対応をしているとそういうケースも出てくる可能性があります。

空き家バンク
国交省の全国版バンクは広域での露出に有効。
ただし現地の自治体運用フローで成約難度が変わる。
まずは掲載条件と実績を確認。
「手放す」――相続土地国庫帰属制度の現実味
次は手放す場合です。
相続土地国庫帰属制度のポイントは以下のとおり。
- 狙い:相続土地の所有者不明化の抑制と管理負担の軽減
- 入口要件:相続・遺贈取得の土地に限定/工作物・土壌汚染・通路状況など不承認事由を細かくチェック
- 費用:申請手数料1筆14,000円+負担金。負担金は地目・面積・管理水準等で算定。事前相談→申請→審査が標準ルート。
- 向き・不向き:極端な遠隔地/分筆が要る複雑地形/境界不明確などではハードル高。売却・寄附・等価交換との比較検討表を作って意思決定を。
よくあるQ&A
次によくある質問を見ておきましょう。
相続人どうしの話し合いが長引いて、3年に間に合わなそう…
A. 相続人申告登記で、申出人本人は義務履行みなしにできます(最終的には本来の相続登記が必要)。
全員分を行えば全員がみなし履行に。
更地にしたら税金が高くなるって本当?
A. 住宅がある土地には住宅用地特例(課税標準の1/6・1/3)が効きます。
更地化や勧告で特例が外れると負担が増えるため、解体の時期と売却タイムラインを事前設計しましょう。
「管理不全空家」って何をしたら該当?
A. 放置すると特定空家になり得る状態(破損・草木繁茂・衛生悪化等)。
勧告で住宅用地特例が外れる可能性があります。
命令違反は50万円以下の過料の恐れ。
「国庫帰属」は万能?
A. いいえ。
不承認事由が多く、申請手数料1筆14,000円・負担金も必要。
まずは売却・寄附・等価交換を含め総合比較を。
税制面で知っておきたいポイントは
A. 実家の土地、建物に関連する税制のポイントを纏めておきましょう。
・固定資産税の住宅用地特例:小規模200㎡以下1/6、超過分1/3が基本。管理不全空家・特定空家の勧告で解除
・相続空き家の3,000万円控除:2027/12/31まで。要件は築年・用途・耐震/解体・1億円以下・期限など。相続人3人以上は2,000万円(2024/1/1〜)。
・小規模宅地の特例:居住用 最大80%、貸付事業用 50%など区分と上限面積あり。誰が引き継いで住むか/貸付の開始時期等で可否が変わる。
まとめ
今回は「実家の家と土地問題。実家じまいどうする?相続登記と空き家3000万円控除・国庫帰属まで実務ガイド」と題して実家の家と土地について考えてみました。
実家の家と土地は、「情」の問題に見えて実は期限管理の勝負です。
3か月(放棄)/3年(登記)/2027年末(空き家控除)/住所変更2年
この4つの締切と税制の“要件”を軸に、住む・貸す・売る・手放すを数字で比べれば、結論は自然と見えてきそうですね。