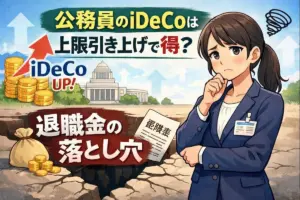個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)はかなりお得で良い制度です。
その反面、株式投資などの資産運用などの経験がないとかなりわかりにくく難しい制度でもあります。
そのため「お金に生きる」でもかなり力を入れて記事を書いてきました。
しかし、記事がありすぎてどこをみれば良いのかわかりにくいという意見があります。
そこで今回はこのページをみれば個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)のことはすべてわかるという完全ガイド(まとめ記事)を作成しました。
このページをみていただければ個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の始め方から、どこの金融機関で始めたらいいのか、どの商品を選んだらいいのか、そして60歳を超えてからもらう時どうすればよいのかまで辞書的に網羅してわかるようになっています。
ぜひブックマークやはてぶをして必要な時に活用してください。
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)ってなに?
まずは個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)とはなにか。どういうメリットがあるかです。
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)とは
個人型確定拠出年金(iDeCo)は簡単に言えば自分の老後生活のために老後資金を自分で作るための制度です。
具体的にはこんな感じの流れになっています。
60歳までの間に自分で決めた金額を積み立てをする
↓
その積み立てたお金で投資信託や定期預金、保険などの商品を選択して運用
↓
60歳以降にその運用した資産を受け取ることができる。
国民年金や厚生年金と合わせた年金制度の上乗せ部分を自分で運用できる制度として考えると良いでしょう。

個人型確定拠出年金(iDeCo)のメリット
個人型確定拠出年金(iDeCo)には大きく分けて3つのメリットがあります。
特に大きいのが1の節税効果ですね。払えば払うだけ所得控除(小規模企業共済等控除)となり、住民税と所得税の節税効果があるのです。
個人型確定拠出年金(iDeCo)の隠れメリット
表立ったメリット以外に隠れたメリットもあるんですよ。


個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の専門用語
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)にはいろいろな専門用語があります。
iDeCo特有なもの、投資の世界の用語、税金や社会保険の用語などなど・・・
それらをまず勉強したい方はこちらの記事を御覧ください。
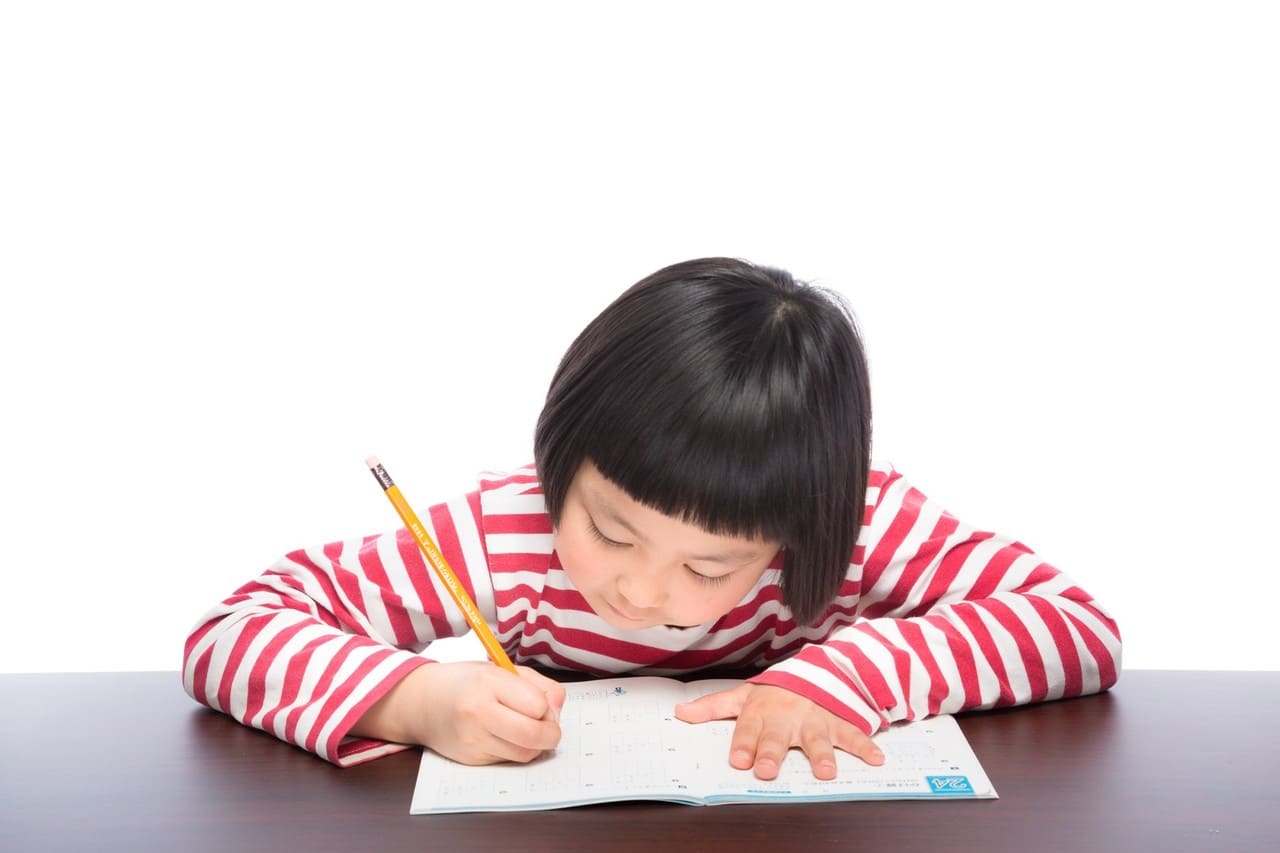
個人型確定拠出年金(iDeCo)を始める前に本で勉強したい方
個人型確定拠出年金(iDeCo)も投資ですからある程度勉強してから始めたほうが良いのは事実です。
そこで私がオススメするiDeCO(個人型確定拠出年金)を始める前に読んでおきたい本3冊をご紹介します。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。

個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)をやらない方がいい人、やったほうがいい人
個人型確定拠出年金(iDeCo)をやらないほうがよい5つのパターン
実はiDeCoに加入しないほうがよい人もいるのです。
結論から言えば個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)のメリットがあまり受けられない方にはおすすめできません。特に節税効果です。効果があるのは税金を納めている人に限られます。
当然ですよね。税金納めてないのに節税もないです。
ですから無職の方、住宅ローン控除のある方などは要注意です。自分がどのくらい所得税や住民税を納めているのかをまず確認してみましょう。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。
この記事を読めばあなたがそもそも「個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)を始めるべきか否かがわかります。

個人型確定拠出年金(iDeCo)のデメリットも知っておこう
個人型確定拠出年金(iDeCo)ももちろんメリットだけの制度ではありません。デメリットもあるのです。つまり、個人型確定拠出年金(iDeCo)は人を選ぶのです。
銀行や証券会社、ファイナンシャルプランナーなどはポジショニングトークが多くあまり悪い面(デメリット)を説明しないケースが多くなっています。
ですから、デメリットの方が大きい方が個人型確定拠出年金(iDeCo)を始めてしまうと「騙された!!」とか「失敗した」とか「こんなはずでは・・・」となるのは確実です。始める前にデメリットも知っておきましょう。


国民年金基金とどちらに入ればよいのだろう。
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)と同じ枠で選択をすることになる制度として国民年金基金という制度があります。
そう。優香がCMしているアレです。会社員の方は加入できませんが、自営業の方は国民年金基金と個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)のどちらに入ればよいのか悩まれる方が多いです。
これも考え方次第なんですよね。個人的には個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)のほうがおすすめですが・・・
国民年金基金とどちらがよいのかはこちらの記事を御覧ください。

個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の加入条件
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)に実はそもそも入れない人もいるのです。ここでは加入条件に関する記事を見てみましょう。
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)は2017年から、法改正により加入範囲が拡大されました。
これまでの加入対象者に加えて、企業年金加入者、公務員共済等加入者、国民年金の第3号被保険者(専業主婦等)の方も、基本的には個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)に加入することができるようになりました。
つまり、ほんとんどの方は加入できるのですが、ちょっとややこしいルールもあるのです。
国民年金の未納がある場合
国民年金の未納がある場合に入れない可能性があるんですね。詳しくはこちらの記事をご覧ください。自分が個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の加入できるのか否がわかります。

海外勤務、海外留学中の方
海外勤務や海外留学の予定のある方は要注意です。
iDeCoは基本的に国民年金の加入が前提となった仕組みです。
海外在住となると国民年金(厚生年金)の対象から外れてiDeCoの加入が認められなくなる可能性があるのです。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。

企業型確定拠出年金に入っていた方
確定拠出年金は個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の他に勤め先の企業が掛金を拠出する企業型確定拠出年金(企業型DC)があります。そのうち企業型確定拠出年金は、掛けてくれていた会社を退職や転職すると加入資格を失います。
次の会社も企業型確定拠出年金がある場合、そのまま移行手続きをとる方が多いですが、そうでない場合放置されてしまうケースが多いのです。
そんな方はもったいないですから個人型に移行するのがおすすめです。詳しくはこちらの記事を御覧くださいね。73万人も放置してしまっている方がいるんですよ。

会社が認めてくれない場合も・・・
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)に加入するためには会社員の方なら会社に書類記入してもらう必要があります。しかし、断わられてしまうなんてことも・・・断られた原因として考えられる可能性としては
・担当者の知識不足
・加入手続きが面倒でやりたくなかった
おそらくこの2点あたりでしょう。ほとんどの場合、ちゃんと説明すれば理解してくれるはずなのですが・・・事前に対策を講じて置きましょう。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。
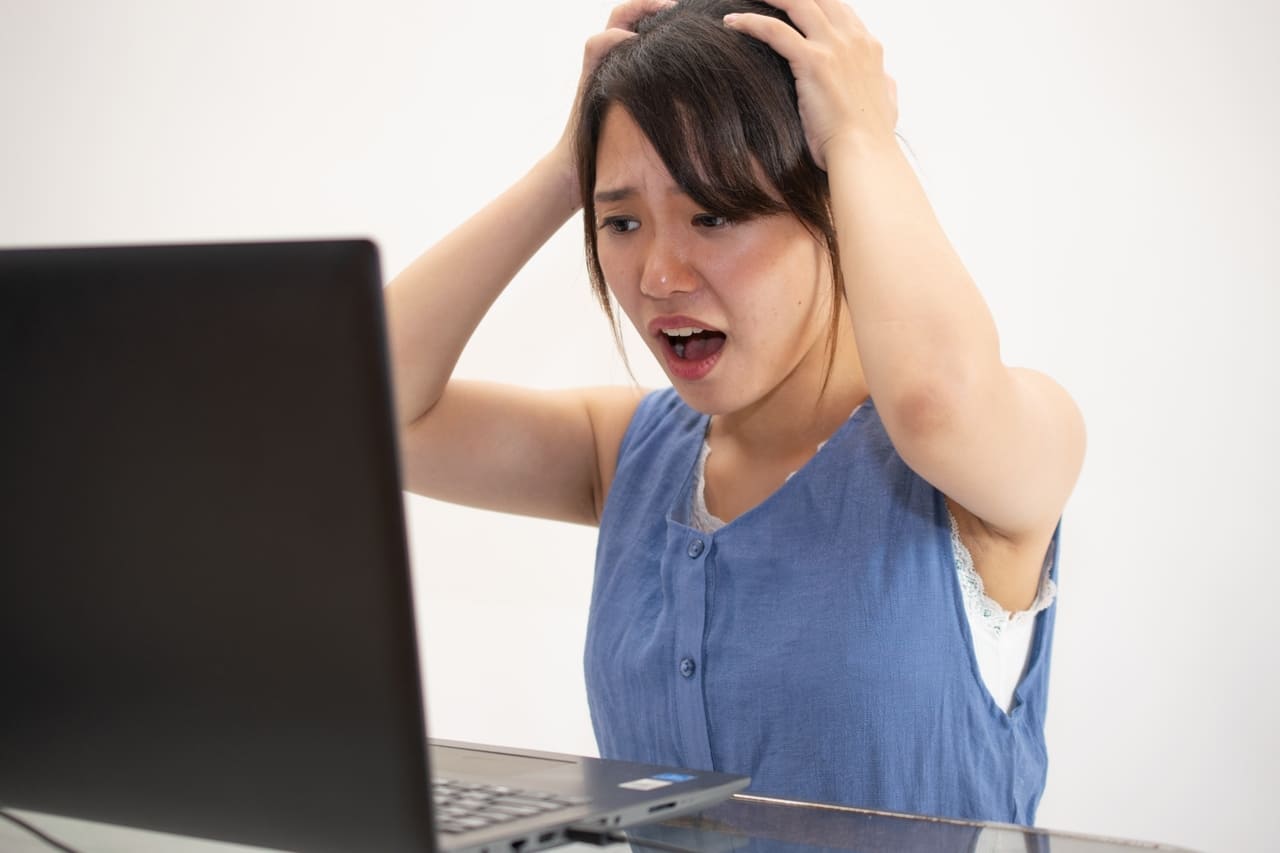
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)でどのくらい儲かるのか?
普段投資などをやってない方からすると個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)はちょっと怖いところがあるでしょう。
初めての投資となるからです。
節税効果だけでも利回り30%も
すでに説明しましたが個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)には節税効果と売却益が非課税という大きなメリットがあります。
この二つを考えるとかなりの利回りが期待できるのです。
例えば課税所得金額が650万のサラリーマンの場合でみてみましょう。
個人型確定拠出年金(iDeCo)に月5,000円積み立てたとします。
すると年間で60,000円の掛け金です。
それがそのまま全額所得控除となり18,000円もの節税となります。
(6万円✕30%)所得税率20%、住民税10%で計算
年間60,000円積み立てると所得税と住民税で18,000円(所得税20%の場合)の節税効果が生まれます。
つまり、率にすると30%もの利回りが節税効果だけで得られるのです。この効果は税率により異なりますので給料や所得が大きい人ほど効果があります。
また、運用は非課税です。
例えば30歳から月5,000円積み立て、かなり固く運用して平均年3%の運用をしたとしましょう。するとこれだけの運用益を得る計算となります。
積立金額(元金)1,800,000円(年間60,000✕30年)
運用益1,113,684円
合計金額2,913,684円
1,113,684円もの利益が得られるんですね。その部分の運用益に税金は掛かりません。
3%が多すぎるだろ!って突っ込まれるかたもみえるでしょうが、3%というのは国民年金などを運用している日本最大の運営機関であるGPIFの過去からの年あたりの平均収益率がそれくらいです。
GPIFの過去からの収益率(年率)は3.18%。リーマンショックなどの時期を含めてもこれだけで運用できているんですよね。
GPIFはアセットアロケーションを公開していますのでそれを真似していればこれくらいの収益率が得られたことになります。
節税効果と運用非課税。この二つの効果はかなり大きいものがありますね。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。

個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の利回りの実際
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)は自分で運用する投資信託などの商品を選択できます。
ですからどの投資信託を選択したかによって運用成績はぜんぜん変わってくるのです。
ですが他の人がどれくらいか知りたいですよね。
企業年金連合会が2019年2月に発表した「確定拠出年金実態調査」の結果によると2017年度の運用利回りを平均すると3.1%の利回りとなっています。GPIFくらいの利回りなんですね。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。他の方がどれくらいの利回りで運用できているのかがわかります。

個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)はどこの金融機関で始めればよいのか
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)を始めるならまずは金融機関を決める必要があります。
しかし、たくさんあってどこにしたらよいのかわからない方も多いでしょう。簡単に決めてしまう方もおおいかもしれませんが、個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の場合、金融機関ごとの違いがとても大きいですから慎重に選びたいところです。
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の金融機関を選ぶ際のポイントから見ていきましょう。
大きなポイントは2つです。
口座管理料が無料
まず1の観点からみると選択肢は8社(SBI証券、マネックス証券、楽天証券、松井証券、イオン銀行、大和証券、au、カブドットコム)しかありません。
この7社はすべて口座管理手数料が無条件で無料です。(みずほ銀行のように条件付き無料のところは他にもありますが・・・)
手数料は投資の成績に一切関係なく必ず掛かるお金ですから極力少ないほうがよいですし、
できれば無料がよいです。長いこと積み立てることになりますのでこの差は大きいです。ですからこの7社から選択するのがベストでしょう。
取扱商品
取扱商品も金融機関により大きな差があります。つみたてNISAとは違い金融庁がルールを持って選別しているわけではありませんから地雷商品も多く含まれてしまっています。
ですから選択した金融機関によってはかなり儲けるのが厳しいということもありえます。
ちなみに前述の口座管理料が無料の7社は商品も優良なのを取り揃えています。
特におすすめなのはSBI証券(セレクトプラン)、マネックス証券、楽天証券、松井証券かな。
SBI証券、マネックス証券、松井証券は「eMAXIS Slimシリーズ(イーマクシススリム)」を取り揃えていますし、
楽天は自社ブランドの楽天・全世界株式インデックスファンドや楽天・全米株式インデックスファンドの取扱があり評価が高いですね。
おすすめの金融機関は下記記事を御覧ください。

個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の商品の選び方
他の人はどんな商品を選んでいるのか
実際、みなさんがどんな運用商品を選択しているのかは統計データとして公開されています。
興味深いのは預貯金や保険の元本保証の商品を選んでいる方が半分以上いることですね。
直近の2017年3月現在でも預貯金38.6%、保険26%が選ばれています。
合計して64.6%となっています。投資信託への投資が35%しかないんですね。
詳しくはこちらの記事をを御覧ください。

定期預金や元本保証商品はおすすめしない
前述したように64.6%の方が選択されている預貯金や保険の元本保証の商品。私は個人的におすすめしません。
それは手数料負担などを考えると目減りしてしまうからです。節税効果はそれでもありますが・・・
詳しくはこちらの記事を御覧ください。

どうしても定期預金や元本保証が良い方はこちらの記事も合わせて御覧ください。少しでも手数料負担を減らせます。

失敗しない商品選択の方法
自分たちで商品を選択してく運用しなければならないため投資初心者には少しハードルが高いのも事実です。
しかし、個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の商品選びは実はコツさえつかめばそこまで難しいものではありません。
まずはこちらの記事で流れや考え方を抑えましょう。

アセットアロケーションを考える
アセットアロケーションをどうするかで投資結果の9割が決まると現代ポートフォリオ理論では言われています。
アセットアロケーションとは資産配分のことです。どの資産にどれだけ配分するかを考えるのです。
投資の言葉に
卵は一つの籠に盛るな
という格言があります。つまり分散させなさいってことですね。
リスクを分散させるために複数の商品に投資をするのが長期投資の基本となります。そのためにもまずはアセットアロケーションを考えることが大事なのです。
アセットアロケーションの考え方について詳しくはこちらの記事を御覧ください。

おすすめ投資信託
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)で買える投資信託は金融機関ごとにバラバラになっています。
そのため、どこの金融機関で始めるのかもどの投資信託を扱っているのかというところも重視したほうがよいでしょう。
おすすめ投資信託は以下の商品です。参考にどうぞ。

金融機関ごとのおすすめ商品とポートフォリオ
それでは具体的な選択した金融機関ごとのおすすめ商品とポートフォリオを見ておきましょう。
SBI証券のおすすめ商品とポートフォリオ
SBI証券はたくさんの取扱商品がありますから、選択するのは楽しいのですが大変でしょう。
セレクトプラン、オリジナルプランそれぞれのおすすめ商品とおすすめポートフォリオはこちらを御覧ください。

マネックス証券のおすすめ商品とポートフォリオ
マネックス証券はeMAXIS Slimシリーズが購入できるのがポイントですね。
eMAXIS Slimシリーズさえ選んでおけばそれでOKな感じもします。マネックス証券のおすすめ商品とおすすめポートフォリオはこちらを御覧ください。

松井証券のおすすめ商品とポートフォリオ
松井証券はあえて商品を絞っているのが特徴です。
SBI証券のセレクトプランやマネックス証券と同じくeMAXIS Slimシリーズがラインナップされています。松井証券のおすすめ商品とおすすめポートフォリオはこちらを御覧ください。

楽天証券のおすすめ商品とポートフォリオ
楽天証券は楽天ブランドの楽天・全米株式インデックス・ファンドや楽天・全世界株式インデックス・ファンドが買えるのがポイント高いですね。楽天証券のおすすめ商品とおすすめポートフォリオはこちらを御覧ください。

イオン銀行のおすすめ商品とポートフォリオ
イオン銀行も銀行では唯一運営管理機関の手数料を0円としてます。
また、イオン銀行は窓口も多いことから相談しやすいのが強みですね。
詳しくは下記記事を御覧ください。

大和証券のおすすめ商品とポートフォリオ
大和証券は大手証券で唯一運営管理機関の手数料を0円としてます。
それだけ個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)に力を入れていると言えるでしょう。店舗がそこら中にあることがかなりの強みですね。詳しくは下記記事を御覧ください。

カブドットコム証券のおすすめ商品とポートフォリオ
カブドットコム証券はKDDIアセットマネジメント株式会社(au)と組んで4月27日に新規参入したばかりとなります。
他との違いとしてはポイント付与制度がありますね。詳しくは下記記事を御覧ください。

auのおすすめ商品とポートフォリオ
かなり意外なauも個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)に参入しています。
運営管理機関の手数料を0円は当然としてポイント付与など新しい試みが注目ですね。詳しくは下記記事を御覧ください。

その他金融機関のおすすめ商品とポートフォリオ
その他金融機関のおすすめ商品とポートフォリオはこちらをご覧ください。

個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)でいくら積み立てればよいの?
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)でいくら積み立てればよいの?これはiDeCoを始める人みなさん迷うところだと思います。
まず個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の毎月の掛け金上限は以下のとおりです。
第1号被保険者(自営業など)68,000円
第2号被保険者(企業型DCなし)23,000円
第2号被保険者(企業型DCあり)20,000円
第2号被保険者(DBあり、公務員)12,000円
第3号被保険者(主婦など)23.000円
この上限内で掛けることができます。ただし、下限は5,000円ですね。
例えば自営業者などは毎月5,000円から68,000円まで選択することができるってことになります。(後述する付加年金に加入すると上限は67,000円)
具体的にいくら賭けるのかは基本的には自分の懐具合に相談してもらうしかないんです。
しかし考えなければ行けないのが60歳まで引き出せないってことですね。
つまり、使わくても大丈夫な金額とする必要があるのです。
また、この上限は引き上げ要請が各所からでていますのでもしかしたら将来的には上る可能性があります。
いくら積み立てればよいのかは下記の記事を参考にどうぞ。


個人型確定拠出年金で節税する方法
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)には節税効果があります。しかし、単に加入して掛け金を拠出しただけで自動で節税されるわけではありません。年末調整もしくは確定申告をする必要があります。それぞれ見ておきましょう。
個人型確定拠出年金の年末調整の書き方
年末調整は所得税などを確定させる方法です。毎年11月〜12月ごろに会社から紙を配布されて記入して提出すると思います。あれですね。なんか難しそうですが、個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)分についてはかなり簡単です。ちょっと記入するだけで終わります。
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の年末調整についてはこちらを御覧ください。

個人型確定拠出年金の確定申告書の書き方
次に確定申告です。サラリーマンの方などで年末調整を会社が行ってくれる方で他に特別な事項がなければ確定申告はいりません。
しかし、自営業の方や年末調整で個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の手続きを忘れた方などは確定申告しないと税金の節税はできません。
こちらもそれほど難しくありませんよ。詳しくはこちらの記事を御覧ください。

節税額を確認する方法
実際の個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)による節税額の確認方法は結構簡単です。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。

個人型確定拠出年金を受け取るとき
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)はかなりお得な制度なのですが、受け取るときにはちょっとした罠があります。そこをちゃんと理解していないと損をしてしまうなんてことも・・・
受け取り方は大きく分けて3パターンあります。
一時金で受け取る
年金で受け取る
一時金と年金の併用で受け取る
基本的には退職金控除内で収まる分については一時金で受け取るのがトクですね。ただし、会社から退職金をたくさんもらえる方などはちょっとした工夫が必要となります。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。

運用管理機関を変更する
おすすめの金融機関を前述しましたが、それ以外の手数料が高い運用管理機関を利用している場合には変更したいというニーズも高いです。変更には手数料が掛かりますので慎重に。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。

また、SBI証券の旧プランを使っている方がセレクトプランに変更する方法についてはこちらの記事を御覧ください。私が実際に変更しております。

個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)加入中に転職したり退職
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)加入者は転職や退職する時に少し考えなくてはならないことがあります。それは個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)に手続きが必要なことです。
いろいろなパターンがあります。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。

個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ) の申し込み先が倒産したらどうなる?
結構心配される方が多いのがこれです。個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)はとてもよい制度だけど実際に運用したお金を引き出せるのはかなり先になります。
そのため申込先の金融機関が倒産なんてなったらどうなるだろうという疑問をお持ちの方も多いんですね。
結論から言えば心配いりませんってことです。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。

個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の投資先を変える方法
当初しっかり運用方針を決めている方でも運用していると、運用成績により少しずつ当初のアセットアロケーションとズレが生じて来てしまいます。それを調整するリバランス(資産の再配分)が必要になるケースもあります。
逆に当初にしっかり運用方針を決めてない方でも「あれ?思ってたのと違う」とか、転職して年収が変わったとか、結婚してライフスタイルが変わったなどで運用を見直す必要が生じてしまうときがあるでしょう。
また、魅力的な投資信託が新規導入されたりしたときも入れ替えたくなりますね。
そんなときに武器になるのが「スイッチング」と「配分変更」です。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。

個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)は解約できるのか?
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)は一時的に損失がでて解約したいと思ってたりしたとしてもあまり解約を考えるよりは手数料が安い、運用商品が有利な会社に移すとか運用商品を見直すなりをおすすめします。
それでもどうしても解約したいと考える方は以下の記事を御覧ください。
かなり特殊な場合でしか基本的に解約はできません。そのことをしっかり理解してから加入しましょうね。

個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)はいつ始めればよいのか?
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)が大変お得な制度という認識を持っていてもなかなか始める踏ん切りがつかない方が少なからずおみえです。
・どのタイミングから始めればよいのか迷っているうちに過ぎてしまった
・大暴落が来るのを待っている

個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の年代別の使い方
20代の個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の年代別の使い方
20代で加入する際は運用が40年近くとかなり長期となりますのである程度のリスクをとっても問題ないでしょう。ですからあまりリスクを取りたくない場合でも元本保証の定期預金等は個人的におすすめしていません。期待値が高い株式などがよいでしょうね。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。

30代の個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の年代別の使い方
30代で加入する際は運用が満年齢の60歳までですから加入年齢にもよりますが30年近くとかなり長期となります。
それなりの長期となりますのでリスクはある程度は取れるということになりますね。基本は20代と同じです
詳しくはこちらの記事を御覧ください。

40代の個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の年代別の使い方
40代で加入する際は運用が20年近くとかなり長期となります。こちらもある程度リスクをとって運用してもよいかもしれませんね。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。

50代の個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の年代別の使い方
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)は期待値の高い株式などのリスク商品を選択するのがベストですが50代で加入する際はそのリスクが高くなるのです。
例えば55歳で加入して58歳でリーマンショック並の大暴落がきてしまうと上がった時期もほぼ経験せず下がった株が戻す前に満了となってしまう可能性があります。
そのため、あまり投資期間がない50代の方は株式やリートなどではなく債券などのリスクが低めの商品を選択されるのをオススメします。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。

個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)に関連する制度について
他にも個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)に関連する制度などの記事を見てみましょう。
中小事業主納付制度(iDeCo+)
中小事業主納付制度とはその名前の通り、個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の掛け金を中小事業主が納付できるようにする制度です。簡単に言えば従業員に変わって会社が個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)の一部掛け金を払ってくれるってことです。
詳しくはこちらの記事をどうぞ

選択制確定拠出年金
選択制確定拠出年金制度とは企業型確定拠出年金制度の一種です。通常の企業型確定拠出年金制度は会社が掛金を払う仕組みとなっています。それが従業員が加入(拠出)するかを選択できるんですね。
拠出を選択する→企業型確定拠出年金制度へ加入(将来受け取る)
拠出を選択しない→今受け取る

マッチング拠出(企業型確定拠出年金)
マッチング拠出とはその企業型確定拠出年金の会社が払ってくれる掛金に自分で上乗せできる仕組みのことです。
こちらもメリットもデメリットもありますから加入は慎重にしましょう。その企業型確定拠出年金の扱っている商品次第ですね。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。

付加年金
自営業者など加入できる方は限られますが、対象の方にぜひおすすめしたいのが付加年金です。
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)との併用が可能となっています。(個人型確定拠出年金の掛け金上限が67,000円と1,000円減りますが)
付加年金について詳しくはこちらの記事を御覧ください。

小規模企業共済
こちらも個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)と併用が可能な制度です。
小規模企業共済は簡単にいえば中小企業者の事業主や個人事業の事業主が自身の退職金を作るための制度
国が作った経営者のための退職金制度といえばわかりやすいかもしれません。
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)と同じく小規模企業共済等控除を受けられますのでこちらを併用することで節税効果はさらに高まります。
小規模企業共済について詳しくはこちらの記事を御覧ください。

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)
ちょっと毛色は違いますが中小企業倒産防止共済も使い方によってはおすすめです。
取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐことが目的として作られました。
最大の特徴は掛け金が所得控除ではなく損金や必要経費に参入できることです。
ただし、小規模企業共済や個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)と違い受け取るときの税優遇がありませんのでどちらかというと税の繰り延べという意味合いが強い制度ではあります。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。

個人年金
民間の保険会社も個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)と似た商品を販売しています。
それが個人年金です。ただし、これあまり良い商品すくないんですよ。
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)との併用はありだとは思いますが、まずは個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)を優先しましょう。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。

トンチン年金
こちらも民間の保険です。個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)と少し毛色は違いますが老後に備えるという点では同様の商品です。
大きく個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)と違うのが終身年金であるってことですね。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。

つみたてNISA
個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)と同じくつみたて投資が非課税で行える制度につみたてNISAというものもあります。
こちらは個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)と違い所得控除はありませんが、そのかわりに引き出しがいつでも可能です。
将来必要となる資金が多い方はこちらも選択肢に入るでしょう。両方併用している方も多いですね。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。

まとめ
今回は「個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)完全ガイド。始め方から、金融機関や商品の選び方、もらい方までこれをみればすべてOK」と題して個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)を始めてからお金をもらうまでに必要となりそうな知識を総ざらいしてみました。
基本的には個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)はかなりお得な制度です。
この記事を熟読していただいて興味を持たれた方には少額からでも構いませんのでぜひ加入していただきたいですね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。