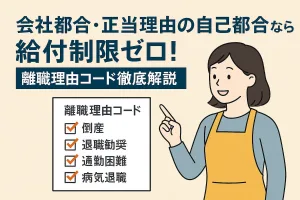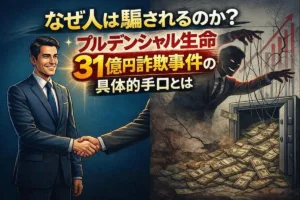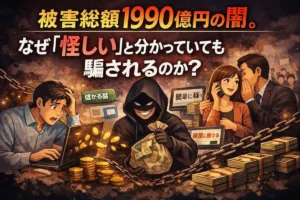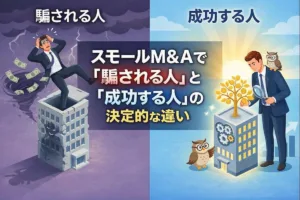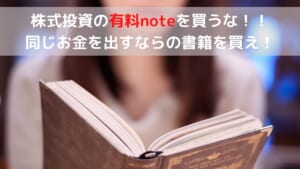最近、スタートアップ界隈で急激に増えていると言われているのが業務委託です。
人件費や社会保険負担、消費税を抑えたい企業、場所や時間に縛られず働きたい個人のニーズが重なり、求人現場で「正社員ではなく業務委託で」という提案が珍しくなくなりました。
ですが、契約形態の違いは受けられる保護とリスクを大きく変えます。
厚生労働省は、契約の名称ではなく実態で「労働者性」を判断すると明確に示しています。
実態が「指揮命令下の労働」なら労基法が適用され、名称が業務委託でも違法(偽装請負)となり得ます。
今回はそんな業務委託の話をみていきましょう。
業務委託と正社員の違い
まずは業務委託と正社員の違いを確認しておきましょう。
労働法の適用と契約の性質
正社員(雇用契約)は労働基準法・労災保険法・雇用保険法などの保護対象です。
業務委託(請負・委任:民法)は原則これらの適用外です。
立場的には自営業者、フリーランスなんですよ。そのため、時間管理や割増賃金の保護がありません。
退職金も基本的にありません。
しかし、実態が労働者性を満たせば労基法が適用されます
指揮命令関係という決定的な線引き
仕事の断る自由、勤務時間や場所の拘束、会社の指揮監督、報酬の労務対価性などを総合して労働者性を判断します
社会保険・雇用保険・労災保険の違い
正社員は条件を満たせば雇用保険や健康保険・厚生年金の適用が前提です。
業務委託は原則それら社会保険の対象外で、自身で国民年金・国民健康保険に加入します(※前述のように業務委託という名目で契約していても実態が労働者なら別)。
なお、業務委託は労災も対象外ですが、2024年11月1日施行の「フリーランス新法」と並行して整備が進み、フリーランス(業務委託)向けに労災保険の特別加入の対象・手続き案内が拡充されています。
業務上のケガに備えたい方は検討をするとよいでしょう。
業務委託のメリット・デメリットを冷静に比較
それでは業務委託にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょう?
メリット(年収と裁量を取りに行く戦略)
単価の上振れや時間・場所の裁量、仕事を選べる独立性は魅力です。
ただし、偽装請負のような業務委託のケースだと、実際は普通の正社員と変わらないのでこの部分はほぼありません。
ちなみに会社側からすれば業務委託は社会保険の負担軽減(正社員なら半額会社負担)、消費税の削減(業務委託者が消費税課税事業者なら払った報酬も消費税が含まれる扱いで消費税納税額の削減に繋がる)、雇用調整がしやすい(首を切りやすい)、残業手当や有給休暇が不要などのメリットがあります。
会社側にメリットが多いのが業務委託契約というわけです。
デメリット(見落としがちな「失うもの」)
業務委託契約のデメリットはかなりあります。
まず、怪我などでの休業時の補償・有給・残業代の不在、社会保険の自己負担、失業給付なし、退職金なしは、景気の谷や病気の時ほど重くのしかかります。
健康保険は国民健康保険に自ら加入する事になりますが、会社員の入る健康保険と比べて会社負担がありませんので割高で補償も少ないのです。

また、正社員と違って契約を切られるリスクも高いんですよ。
それでいて失業給付もないという不安定さ。
さらにインボイスがはじまったこともあり、業務委託者には消費税課税事業者になることを要求されることが多くあります。
そうなれば、消費税を納税しなくてはならなくなります。
さらにさらに業務委託は年末調整対象外で、自ら確定申告も必要です。
慣れてない方はこのあたりも地味に大変なんですよ。
「業務委託はひどい/やめたほうがよい」と言われる背景
多くの転職サイトなどで業務委託はやめたほうがよいと注意が促されています。
その背景をみておきましょう。
偽装請負につながる実態
勤怠打刻・上司の指示・会社PCで常駐・専属拘束・成果でなく時間給
こうした運用は派遣や雇用に近い実態で、偽装請負と判断される可能性が高いです。
会社側は正社員で雇うよりも業務委託のほうがメリットがありますので、そちらに誘導するケースもあります。
参考:厚労省の「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」は判断基準を具体化しています。
支払遅延・減額・やり直しの強要
前述したように正社員は労働基準法に守られていますが、業務委託はそれがありません。
そのため、支払遅延などの不利益が生じることもあるんですよ。
つまり、立場がかなり弱いのです。
ちなみにフリーランス新法(正式名:特定受託事業者に係る取引の適正化等法)は、受領日から原則60日以内の支払義務、報酬の不当減額や返品・買いたたきの禁止、募集情報の的確表示などを定めています。
違反があれば公取委・中小企業庁・厚労省が所管。
業務委託の見抜き方
それでは業務委託の見抜き方はどうすればよいのでしょう?
ポイントをご紹介します。
内定後に業務委託へ切替提案が来たら
雇用条件通知書の提示を求め、雇用での採用可否をまず確認。
労働者性が出る運用(時間指示・場所拘束・専属義務)を前提にしていないか、すり合わせましょう。
基本的に正社員と同じような働き方、報酬なのに業務委託という条件なら受けない方が吉だと思われます。
契約書に必須の確認ポイント
業務委託を結ぶなら契約書をしっかり確認しましょう。
取引条件の明示
業務内容・成果物・検収方法・報酬額・支払期日(受領から原則60日以内)・再委託時の30日以内支払まで記載が必要です。
未定事項は理由と決定予定日の明示が要件。
募集情報の的確表示
氏名・住所・連絡先・業務内容・場所・報酬が欠けた募集は違反の可能性。
SNS求人も対象です。
競業避止・秘密保持
競業避止は期間・地域・対象業務の限定が合理性のポイント。
発注者の優越的地位の濫用は独禁法上の問題にも。
報酬設計とインボイスの合意
報酬の詳細も確認しましょう。
税込/税抜表示、インボイス登録の有無、経過措置の取り扱いを書面で合意。
今まで見てきたように社会保険や福利厚生に大きな違いがありますから、正社員と比較してかなり高い報酬でないと割にはあいません。
その部分もしっかり意識しましょう。
「業務委託 やめたほうがよい」典型例
業務委託をやめたほうがよい例をみておきましょう。
事実上のフルタイム常駐+時間給+上長の人事評価
これは雇用に極めて近いです、
偽装請負の恐れがあり、残業代や割増の未払いリスクにも直結します。
低単価+経費自己負担+支払遅延の常態化
買いたたき・不当減額・やり直し強要は新法の禁止行為。
契約前に検収・修正回数・遅延時扱いまで詰めてください。
住宅ローン・クレカ・各種審査に不利な設計
収入の安定性が問われる審査では、正社員と比べてかなり不利になりやすいのが実務感覚。
将来設計と生活防衛費を厚めに。
それでも業務委託を選ぶなら——失敗しない進め方
それでも業務委託を選ぶなら以下の点を意識してみましょう
まずは「二刀流」で試す
現職を続けながら期間限定の準委任(時間単価)や小さな請負で相性を見る。
副業の業務委託も新法の保護対象になり得ます。
保険と年金は先回り
国民年金・国民健康保険の切替、労災特別加入の可否、所得補償保険の検討。
雇用保険の失業給付は原則使えない前提で資金計画を。
単価の設計は「手取り逆算」
「社会保険の事業主負担がない」分、表面的な手取りの見かけに惑わされず、可処分所得と可処分時間で比較を。
インボイス登録の有無も含め税コストでブレないように。
まとめ
今回は「就活、転職で「業務委託」を提案されたら気をつけて|正社員との違い・やめたほうが良いケース・見抜き方」と題して業務委託の話を見てきました。
正社員と業務委託の違いは、受けられる法的保護・社会保険・失業給付・税務対応を根本から変えます。
契約の名称より実態を常にチェックし、支払期日・禁止行為・募集表示など新法の守りも味方につけましょう。
迷ったら一次窓口に相談し、将来の選択肢を狭めない着地を選んでください。