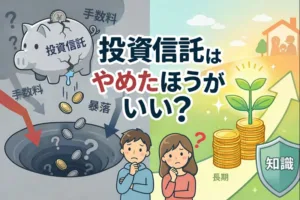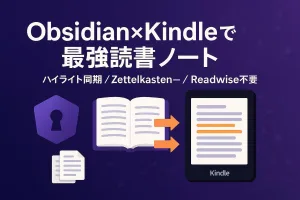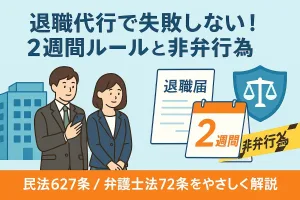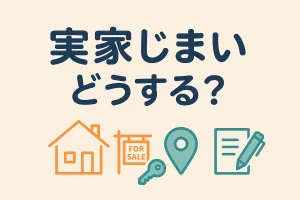最近、SNSなどでJ-FLEC認定アドバイザーを名乗る人を見かけるようになりました。
J-FLEC認定アドバイザーってなんだ?って疑問に思ったので調べてみました。
すると意外とちゃんとした制度だったんですよ。
そこで今回は私と同じようにまったく知らない方のためにJ-FLEC認定アドバイザーとはなにかについて解説します。
J-FLEC認定アドバイザーとは:中立的な家計・資産形成アドバイスを可視化する制度
先に結論から言えばJ-FLEC認定アドバイザーはJ-FLEC(金融経済教育推進機構)が、特定の金融機関や特定商品に偏らない中立的な立場で家計や資産形成のアドバイスを行う人を「認定・公表」する仕組みです。
制度の趣旨は、相談者が中立性の基準を満たす助言者を見つけやすくする“見える化”にあります。
J-FLECは金融庁所管の認可法人ですから、国がお金のアドバイスできる人を認定する制度みたいな感じですね。
経営で言えば「認定経営革新等支援機関」みたいな扱いでしょうか。
制度の背景:法的根拠とガバナンス
法的根拠はJ-FLECは「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づく認可法人(所管:金融庁)です。
2024年4月に設立され、官民一体で金融経済教育を推進します。
2024年8月に設立式典(首相出席)が行われ、国の金融リテラシー政策の柱として位置づけられています。
公表リストと人数の推移
2024年10月23日、認定アドバイザーのリストとプロフィールが初公表。2024年10月21日時点で637名が認定済みと金融庁が周知しています(J-FLECサイトから検索可能)。
以降も徐々に登録され2025年6月末時点で、累計1,290名とのこと。
金融庁との関係は?
J-FLECは金融庁所管の認可法人として設立。
制度の節目(認定者公表など)は金融庁が公式サイトやXで周知しています。
J-FLEC(金融経済教育推進機構)は、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき、2024年4月に設立された認可法人です。
設立にあたっては、金融広報中央委員会(事務局:日本銀行)、全国銀行協会、日本証券業協会が発起人となりました。幅広い年齢層に向けて、国民各々のニーズに応えた金融経済教育の機会を官民一体で届けていきます。
出典:金融庁 金融経済教育について
つまり、金融庁が金融教育のために設立した外郭団体ってことでしょう。
J-FLEC認定アドバイザーの登録要件、合格率は?
それではどのような方がJ-FLEC認定アドバイザーに登録できるのでしょう?
認定要件の骨子
J-FLEC認定アドバイザーは2024年8月26日からJ-FLECサイトで募集を開始しています。
認定の要件は以下の5つです。
1.次のいずれにも該当しないこと
・金融商品の組成・販売等を行う金融機関等に所属している
・金融商品の組成・販売等を行う金融機関等から、顧客に対するアドバイスの信頼性・公正性に影響を及ぼし得ると考えられる報酬を得ている
2.家計管理、生活設計、NISA・iDeCo等の資産形成支援制度、金融商品・サービス、消費生活相談等に関するアドバイスを提供するために有益な資格(CFP®、AFP、FP技能検定(2級以上)、外務員(1種)、弁護士等の士業、消費生活相談員など)及び一定の業務経験(原則として当該資格に関するもの)を有すること
3.法令諸規則違反等による、刑事罰、処分その他の措置を受けていないこと
4.反社会的勢力ではないこと
5.その他、金融経済教育推進機構が不適当と認めた者でないこと
要はどこかからお金をもらっていたり、紐づいていないか。(中立か)
関連する資格や経験を持っているのかということですね。
お金の相談といえばファイナンシャルプランナーという国家資格はありますが、保険や住宅ローンなど自身の利益に走る人も多いのが実情なので、このような公平なアドバイスをする人という制度ができたのかもしれません。
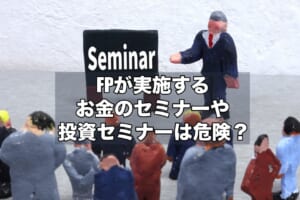

認定プロセス:書類審査、面接
認定プロセスは申込→書類審査→面接審査という段階的審査が行われる運用が案内・実例として示されています。
面接もあるんですね。
ちなみに「認定経営革新等支援機関」は書類審査のみで面接はありませんでした。
合格率は?「落ちた」という報告も
公表された合格率データは現時点で確認できません。
一次情報(J-FLEC公式・金融庁公表資料)には合格率の明示はないんですよ。
合格した人が15%〜20%程度だろうとか書いている記事を見かけましたが、その根拠の明示はありませんでした。
ただし、認定者数が公表されており、制度は審査付きの“認定”であることがわかります。
応募者数がわからないので合格者は算定もできない感じですね。
書類審査、面接双方とも「落ちた」という報告は何人も見ましたので、応募すれば必ず認定されるものではなく、合格率も高くはなさそうな感じです。
何が“中立”なのか:できること/できないこと
それではJ-FLEC認定アドバイザーはなにができるのでしょう?
できること(制度の目的に沿う行為)
ライフプラン・家計管理・資産形成制度(NISA・iDeCoなど)・基本的な金融商品理解・消費生活相談に関する教育的・中立的なアドバイスができることとなります。
ポイント:販売・勧誘の現場から“切り離された”教育的助言を制度として明確化しているのがJ-FLECの特徴です。
できない(もしくは抑制される)ことの例
逆にできないこととしては、特定の個別金融商品の推奨・販売行為や、金融機関等からの利害関係で中立性を損なう助言。
J-FLECの周知資料では、個別具体の税額計算や個別商品に踏み込む相談は対象外の注意喚起がなされています(関連するFSA英語版広報の注意書き)。
税理士法なども関係もありますしね。
また、
自身が運営している媒体(ホームページ、ブログ、SNS、メールマガジン、自身が開催するセミナー等)を通じて不特定多数の者に対して金融経済に関する情報発信を行う場合には、予めその媒体及び概要についてJ-FLECへ届け出なければならない。
出典:J-FLEC J-FLEC認定アドバイザーになるには
とのルールがあるようです。
個人的にはこの部分が嫌なので、条件的には登録できる可能性がありそうですがやめておきます・・・って感じですね。
メリットと限界(投資家視点)
一投資家からしてこの制度にどのようなメリットと限界があるのかを考えてみましょう。
メリット
メリットとしては以下の3つでしょう。
- 中立性の明確化:金融機関や販売インセンティブから独立した立場で、教育的助言が受けられる。
- 検索・可視化:資格・実務・得意分野等が事前に確認でき、ミスマッチを減らせる。
- 官民一体の品質担保:法に基づく認可法人による制度設計で、最低限の中立性フィルターが働く。
一番大きいのは中立性が明確化されていることでしょうね。
限界・注意点・デメリット
- 個別商品の推奨は原則対象外:実際に銘柄や保険商品の具体推奨が欲しい場合はIFAや販売会社のFP等、別スキームの専門家が適する場面も。
- 合格率や審査基準の詳細は非公開:数値の透明性は限定的。最終的には個々人の経験・倫理観・コミュニケーションの質を面談で見極める必要
具体的な銘柄、商品の推奨が欲しい方も多いと思いますので、中途半端なアドバイスになりそうな部分もありますね。
あとは合格率などの発表もありませんので、レベルの担保が保有資格くらいになっているところもちょっと心配。
私も30時間程度の勉強で受かったそれほど難易度の高くないFP2級でも認定要件は満たせるんですよね。
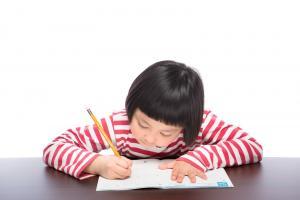
ただし、CFPの人とかでも「落ちた」という報告をしていましたので、面接でしっかりそのあたりは確認しているのかもしれません。
課題
また、課題としては知名度アップが挙げられるでしょう。
私のようにそれなりにお金の話にアンテナを張っているものでも存在を知らなかったんですよ。
金融庁でそういう案がでているのは知っていましたが、気づいたら始まっていたという笑
J-FLEC認定アドバイザーという名前もわかりにくいので、一般の方への周知がうまくいかないと絵に書いた餅で終わってしまう形になりそうです。
アドバイザー側の視点:資格者が目指す価値
それではアドバイザー側からみるとこの制度はどうなのでしょう?
私も社会保険労務士とFP2級の資格を持っているので、認定要件はクリアできそうですのでちょっと考えてみました。
社会的信用
“販売から距離を置いた教育”で社会的信用を可視化されるというのが一番のメリットになりそうです。
FPのイメージにある保険を売りつけられそうというイメージがこの制度の登録者はない形ですからね。
FPや社会保険労務士、税理士等の基礎資格+実務の上に、中立性のフィルターを通過した事実が公表されることはメリットになりそうです。
昔、オリエンタルラジオの中田氏がファイナンシャルプランナーを信じるなと動画を出して話題になったこともあります。
結局この話の趣旨は「自身のお金儲けのポジショニングトークだから信じるな」というものでしたが、それが払拭される部分があるってことになります。

セミナー等の登壇機会
J-FLECは講師派遣やイベント等のハブ機能を担い、地域に根差した教育機会の拡大を掲げています。
J-FLEC認定アドバイザーになればそのようなセミナー等での登壇機会はありそうです。
まとめ
今回は「J-FLEC認定アドバイザーとはなにか?仕組み・要件・合格率・金融庁との関係を徹底解説」と題してJ-FLEC認定アドバイザーについて考えてみました。
投資が「はじめて・ひさしぶり」の人にとって、誰に相談すべきかは最大のボトルネックです。
J-FLEC認定アドバイザーは、販売と切り離された教育的助言を受けられる入口の公的標準となりそう。
一方で、個別商品の推奨や具体的節税の計算は制度の外に置かれているため、必要に応じてIFAや販売会社の専門家と使い分けるのが賢明です。
まずは公式検索で、目的×得意分野の相性から一人を見つけ、行動KPIに落とす相談を組み立てていきましょう。
J-FLEC公式サイトの「認定アドバイザー検索」で、都道府県、保有資格、得意分野などから絞り込み可能です。プロフィール(経歴・得意分野・報酬目安・評価など)の公表が進められています。