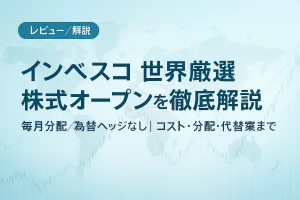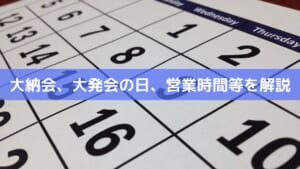日経平均が過去最高値を34年ぶりに更新しました。
かなり長い間かかりましたね笑
しかし、実際に株を買っている人からすると日経平均の上がり方と実際の自分のもっている株の上がり方、なんだか連動してない感じはありませんか?
日経平均が大きく上げたのに持ち株はぜんぜん上がっていない。自分の銘柄選びが致命的にだめだったのか・・・って思っている方もいるでしょう。
実はこれには大きなカラクリがあるためなのです。
今回は日経平均と自分のもっている株が連動していない理由についてみていきます。
日経平均株価は日本株全体の動きを示しているわけではない
それではなぜこのような実際の持ち株や感覚と日経平均株価は大きく相違する日があるのでしょうか?
これは簡単です。
名前の印象から日経平均株価は日本株全体の動きを示していると思っている方が多いですが、そうではないからです。
特に株式投資初心者の方や株式投資をやっていない方に多い勘違いですね。
日経平均株価とは
それでは日経平均株価とはどんな指標なのでしょうか?
まず日経平均とは東証プライム市場(元東証一部)に上場する銘柄のうち225社を日本経済新聞社が独自の基準でピックアップしてそれを元に15秒ごとに平均を出した株式指標です。
ちなみに225社は定期的に入れ替えが行われています。
つまり、そもそも225社だけが対象の株式指標ですべての銘柄が対象ではないんですよね。
さらにこの225銘柄の選び方の基準もちょっと曖昧で批判が多いところであったりもします。
225社は下記のサイトをみるとわかりやすいですよ。
日経平均株価の計算方法は簡単に言えば単純平均である
もう一つ押さえておきたいのが日経平均株価の計算方法は簡単に言えば単純平均であることです。
225銘柄の株価を全部足して225で割って平均を出しているイメージです。
実際には分割や増資などを加味しているため225で割っているのではなく除数という数値を使っているためちょっと違いますがニュアンスは同じです。(実際の計算式は225銘柄の株価の合計÷除数)
そのため225社それぞれ均等に影響をもっているわけではなく、株価の変動の影響が銘柄によって大きく違います。
単純な平均ですから特に株価の金額が大きい株価の高い値がさ株の影響を大きく受けます。
例えば日経平均株価の影響力が高いことで有名なのが東京エレクトロン、ファーストリテイリング(ユニクロ)、ソフトバンクですね。
日経平均株価は一部の銘柄の影響(寄与度)が大きすぎる
上記のように一部の銘柄の影響力がかなり大きな日経平均ですから、それらの銘柄を大きく買えば数値はある程度操作できてしまうんですよね。
実際に暴落時の買い支え的なときには日経平均の影響度が高い銘柄は高く、他の銘柄は暴落しているようなケースはよくあります。
ですから政府やかなり大きな機関が仕掛ければある程度の操作も可能な指標であるともいえます。
実際にファーストリテイリングの大株主に日銀がいたりします・・・
ちなみに今回の上げは東京エレクトロンの寄与がかなり大きいですね。
日経平均株価はかなり歪な株式指標である・・・
日経平均はせっかく225社の株価から算出しているのに一部の銘柄の影響力が大きすぎてしまってちょっと歪な株式指標となってしまっているんですよね。
しかも、計算方法が単純計算ということで株価が高い銘柄の影響が大きすぎるという問題があります。
日経平均株価は日本全体を示す指標どころかなにを示しているのかよくわからない株式指標で歪としかいえません・・・
日経平均株価と自分の持ち株が連動しない理由
今まで見てきたように日経平均株価はほんの一部の銘柄の影響度が強すぎる指標です。
そのため日経平均株価が上がっていても自分の持ち株が連動しないというのは当然といえば当然です。
ですからタイトルに有るように日経平均株価は大きく上げているのに自分の持ち株が上がらないというのも普通にありえるでしょう。
つまり、日経平均が上がっている=日本株の調子がよいってわけではないのです。
逆に日経平均が下がっていても同様のことが言えます。
日経平均株価の動きとは関係なく、自分の持ち株の動きを常にチェックして下降トレンド入りしていないか変化はないのかを見ておくことが重要なのです。
日経平均株価はそういう特徴のある株式指標だという認識のもとに参考程度と考えればよいでしょう。
TOPIX(トピックス)とは
日経平均株価と同じような株式指標でTOPIXというものがあります。
TOPIXは東証プライムに上場している全銘柄の時価総額加重平均をとした株価指数です。
日経平均と違って東証プライム全銘柄をみることになります。また時価総額を加重平均しています。ある意味日経平均株価の問題を解消しているんですよね。そのため日本株全体の動きを見るならばTOPIXの方がおすすめですね。
実際に投資家では日経平均よりTOPIXを重視している人が多いです。
ただし、東証プライムに上場している全銘柄といっても東証一部に上場してすぐにTOPIXに反映されるわけではありません。ルールがありますのでそのあたりは押さえておきたいところです。
詳しくは下記の記事を御覧ください。
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://ideco-ipo-nisa.com//7023]
アメリカの株式指標
参考までにアメリカの株式指標についても見ておきましょう。
NYダウ(ダウ平均)
まずはニュースなどで一番取り上げられるNYダウです。
アメリカで最も古い株価指数であり、ダウ・ジョーンズ社がアメリカ市場に上場している代表的な30銘柄を選び、その株価の平均値に特殊な修正を加えて算出されます。日経平均株価の255よりさらに狭い30社の指標となります。
S&P500
アメリカの株式指標でもう一つ有名なのがS&P500です。アメリカのスタンダード・アンド・プアーズ社が定めている株価指数です。ニューヨーク証券取引所、NYSE MKT、NASDAQに上場している銘柄から、代表的な500銘柄を選定し、その株価から算出されます。
時価総額でアメリカの株式市場の約80%をカバーしています。NYダウと違い時価総額の80%を占めていますのでアメリカ全体の株式の状況を見るときにはこちらが使われます。
ナスダック
最後はナスダックです。こちらはアメリカのIT系企業が多く上場するNASDAQ(ナスダック)に上場している全銘柄を対象とする株価指数になります。
GAFA(グーグル、アップル、フェイスブック、Amazon)など世界的なIT企業がNASDAQに上場していますので影響力はとても大きい指標になります。
まとめ
今回は「日経平均が過去最高値を更新。しかし、自分の持ち株が上がっていない理由を知っておこう。」と題して日経平均株価と持ち株が連動しない理由についてみてきました。
名前のイメージでミスリードされてしまいますが日経平均株価は日本経済全体を示す指標ではなく一部の銘柄の影響力が非常に大きな指標であるってことはぜひ知っておきましょうね。
お知らせ:You Tubeはじめました。
You Tube「お金に生きるチャンネル」をはじめました。
You Tubeでも少しでも皆様のお役に立てる動画を定期的に発信していきますのでチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。
最後まで読んでいただきありがとうございました。