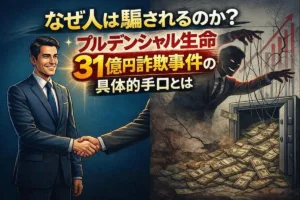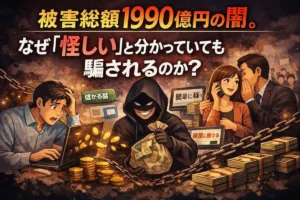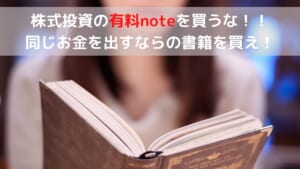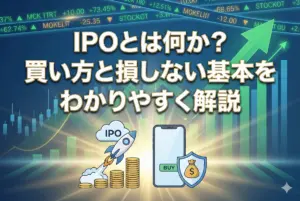ニデック(旧・日本電産) の株価が急落し大きな話題となっています。
大型株でストップ安はかなり久々ですからね・・・
「不正会計?」「不適切会計?」という言葉が独り歩きしがちな局面ですが、まずは一次情報で何が公表され、株式市場で何が起きたのかを事実ベースで整理します。
今回はニデックが発表した第三者委員会の設置、報道で伝えられた疑義の具体像、そして株価急落の背景を確認したうえで、投資家が今日から取るべき対策を段階別にまとめていきましょう。
ニデックにいま何が起きているのか
それではまず現状でている一次情報をまとめておきましょう。
第三者委員会の設置と発端の事象
ニデックは2025年9月3日、外部の弁護士・公認会計士で構成する第三者委員会を設置したと発表しました。
発端はグループ会社ニデックテクノモータの中国子会社(浙江)における一括値引き(約1,000万元≒2億円)の会計処理に関する疑義で、調査の過程で評価減の時期を恣意的に検討していたとも解釈し得る資料が他のグループ会社にも見つかったため、経営陣関与の有無も含め調査対象としています。
株価の反応
発表翌営業日の2025年9月4日、株価は22%超下落でストップ安と、上場来でも記録的な急落となりました。
日経225採用銘柄のストップ安は久々であるということも話題になりました。
直近までの「会計・コンプラ関連」の火種
ニデックは2024年5月に子会社の売上過大計上に起因する過年度修正(2期合計で約6700万ドル規模)を公表。
さらに2025年6月にはイタリア子会社を巡る原産地申告の誤り・通関対応の調査に関連し、有価証券報告書の提出期限延長を得ています。
今回の「会計疑義」とは別事象ながら、足もとで会計・コンプライアンスの論点が連続している点は事実です。
ニデックってなんなのさ?
そもそもニデック(旧・日本電産) って名前は聞いたことあるけどなんの会社かわからないって方も多いと思いますので簡単に解説しておきましょう。
ニデックは世界的な総合モーターメーカーです。
HDD用スピンドルモータなどの精密小型モータから、車載向けのE-Axle(EV駆動ユニット)、家電・産業用モータまで「回るもの・動くもの」を幅広く手掛けています。
投資家としては、収益貢献の大きい車載・精密小型・産業の3領域を押さえ、のれん・在庫・評価減の潜在論点がどこに集中しているかを意識しておくと、今回の調査結果の読み解き精度が上がります。
「ニデックってなんなのさ」というCMで知名度向上を狙っていました。
報道で示される論点の読み方
今回の報道かなりややこしいので理解がしにくい方も多いともいます。
少し前にオルツの不正会計疑惑がありましたので、それと同様に考えている方も見えます。
それとはかなり毛色は違いますので、少し論点を解説しておきましょう。

一括値引き・割戻しの会計処理
中国子会社での仕入値引きに伴う戻しをどう会計処理したか、期間配分と帰属年度が焦点です。
さらに社内調査で、資産の評価減(減損・評価損)の時期を恣意的にコントロールした疑いに関する資料が複数見つかったとされ、範囲(どの会社・どの勘定科目まで波及するか)が最大の注目点になります。
あくまでもいま出てる情報では2億円の会計処理上の問題で、オルツのような大半の売上が架空だった話とはだいぶ違うんですよ。
経営陣関与の可能性
問題はここ。
第三者委の調査委嘱事項には経営陣の関与・認識の有無が含まれています。
この点が立証されるかで、内部統制の有効性評価、監査意見(継続企業の前提含む)や取引所の対応の重みが大きく変わりそうです。
数年前にあった東芝の事件では経営陣は直接関与していないけど、過度な売上を上げることへのプレッシャーで下の社員がやってしまった感じでしたね。
株価急落の理由
市場は「範囲不確定」「金額不確定」「時間不確定」の三重の不確実性を嫌います。
とくに今回は管理職層以上の関与示唆や他社・他勘定への波及可能性が示されたことで、ディスカウント率が急拡大した格好です。
また、市場にはオルツの不正会計問題からの上場廃止のインパクトが残っているのも大きいでしょうね。
東証の措置と「最悪シナリオ」
それでは今後、ニデックの株はどうなっていくのでしょう?
最悪のケースも合わせて考えてみましょう。
特別注意銘柄・監理銘柄・上場廃止の基準
不適切会計や監査意見の不表明・不適正、あるいは有価証券報告書の大幅遅延等は、特別注意銘柄の指定や監理銘柄(審査中)、上場廃止の審査対象になり得ます。
基準は公開されており、内部管理体制の整備・運用が不十分で改善見込みがないと判断されると、上場廃止に至るケースもあります(一般論)。
事例:東芝不正会計で73億円の課徴金納付命令
2015年2月に証券取引等監視委員会の開示検査をきっかけに不適切会計の疑いが顕在化。
東芝は第三者委員会を設置し、同年7月20日に調査報告書(要約)を受領・公表。
第三者委による認定は1,518億円の利益過大計上(2008年度~2014年度3Q)。会社の自主チェック分を加えると累計1,562億円に達し、当該期間の税引前利益は大幅修正を余儀なくされました。
背景には、将来利益の前倒し計上や損失・費用の後送りといった会計処理が横行していた実態が示されています。
金融庁は2015年12月、73億7,350万円の課徴金納付命令(当時過去最高)を決定。
監査人・関与会計士にも懲戒や課徴金が科され、米SEC/DoJによる米国子会社への波及調査も報じられました。
事例:オルツ不正会計で上場廃止
2025年8月、AIベンチャーのオルツは粉飾決算(売上循環取引等)で第三者委報告を受け、東京証券取引所は上場廃止(8/31付)を決定。
広告宣伝費・研究開発費として資金を外部に流し、広告代理店経由で販売パートナー→オルツへ戻す“資金循環”スキームでした。
つまり、売上と広告宣伝費は架空計上だったということです。
売上の約9割が過大計上という・・・
いわゆる循環取引ですね。

これにより多くの個人株主が損害賠償請求の準備を進める事態となりました。
投資家が今すぐできる実務的対策
それでは投資家はどうすればよいのでしょう?
情報ソースを「一次」に固定する
第三者委の設置リリース(英語・日本語)と、継続開示(IR/適時開示)をウォッチ。
加えて主要報道(ロイター/FT/朝日)で市場の受け止めと新情報をクロスチェックします。
この手の話になると噂や嘘などXやヤフー掲示板でがちです。
しかし、それらは二次情報であり、一次で裏が取れない断定的な噂は避けるのが基本です
シナリオ別に「許容ドローダウン」を事前定義
シナリオ別にある程度想定しておくことも大事です。
限定シナリオ(子会社・特定勘定で限定)
影響額が相対的に軽微で、内部統制の是正計画と再発防止策が具体的であれば、信頼回復までの時間軸を見積もった中長期保有が理論上は成立します。
決して平均単価引き下げのナンピンを機械的に行わないこと。
ベースシナリオ(修正決算・内部統制評価の指摘)
過年度修正+内部統制の重大な不備が出ると、資本コスト上昇とバリュエーションのディスカウントが長期化しやすい。
保有比率の上限と時間分散のルールを明文化します。
厳しいシナリオ(経営陣関与+広範な波及)
監査意見の区分や取引所の指定が重くなると、流動性リスクが急増。
撤退基準(価格・イベント)を事前に紙で決め、日々それに従うだけの運用にします。
「第三者委報告書」の読み方を決めておく
とくに以下の5つは重要な項目となります。
- 事実認定の範囲(会社・期間・勘定科目)
- 金額影響(PL・BS・キャッシュフロー/税務影響)
- 関与の態様(現場・管理職・役員)
- 内部統制の欠陥マップ(発見・是正の仕組み)
- 再発防止策の実効性(期限・責任者・KPI)
報告書の結論だけでなく、監査人の意見(適正・限定付・不表明・不適正)や取引所の指定の動きも併読し、イベントドリブンでポジションを見直します。
財務の「脆弱ポイント」を点検
モーター事業は在庫・部材の連鎖が長く、評価減のタイミングが疑義に上がりやすい領域。
のれん・固定資産の減損テストの前提(WACC/成長率)にも注目。
セグメントと地理的曝露
車載(E-Axle等)や精密小型、欧州・中国向けの比率を、直近の決算資料で再確認し、波及時の売上・利益感応度を想定します。
資金管理とルール化
資金管理とルール化もこういう銘柄を扱う場合には重要でう。
ルールの固定化
具体的には以下のようなルールを作ると良いでしょう。※あくまで一例
- 1銘柄の最大比率(例:リスク銘柄はコアの1/2まで)
- イベント・ストップルール(第三者委報告公表/監査意見変更/指定・解除)
- 時間分散(ニュース直後の逆張り禁止/決算後の検証待ち)
「誤情報」対策
検索トレンドには他社事例が混ざりがちです。
たとえば2025年にオルツの不正会計からの上場廃止が注目されましたが、これは別企業の粉飾決算事例。
社名の似たニュースを混同しないために、コード(ニデック=6594)と公式発表のURLをブックマークしておきましょう
いつ、何を見て判断するか
今後様々な情報が出る形になりますが、どこに注目すればよいのかもまとめておきましょう。
直近(〜数週間)
- 会社IRの更新(第三者委の構成・調査範囲・スケジュール)
- 適時開示/取引所の指定の有無(特別注意・監理銘柄など)
- 主要報道の追加取材(範囲・関与・金額の新材料)
中期(〜数カ月)
- 第三者委報告書の公表と監査人の意見区分
- 過年度修正の有無・規模、内部統制の評価(改善計画の具体度)
- 資本政策(配当・自己株・社債・格付)と顧客・仕入先の反応
注:会計疑義=即・上場廃止ではありません。実際に上場維持/指定解除となる例も多数あります。一方で、粉飾が巨額・広範だった事例は上場廃止も現実化します(参照:オルツ)。「事実認定」と「是正の実行力」が分水嶺です
まとめ
今回は「ニデック(日本電産)不正会計の疑いで株価急落。背景と投資家が今すぐ取るべき対策」と題して二デックの不正会計の疑いについてみてきました。
第三者委の設置は、疑義の範囲・金額・関与を独立的に検証するためのプロセスです。
株価は不確実性へのディスカウントで急落しましたが、悪材料の範囲が限定されるのか、修正決算と内部統制の再構築が必要なのか、監査・取引所対応が厳格化するのかで、シナリオは大きく分岐します。
投資家にできる最善手は、一次情報の定点観測×事前ルール。
ナラティブではなく、イベントと数字で判断を重ねる。
これが結局いちばん強いんですよ。