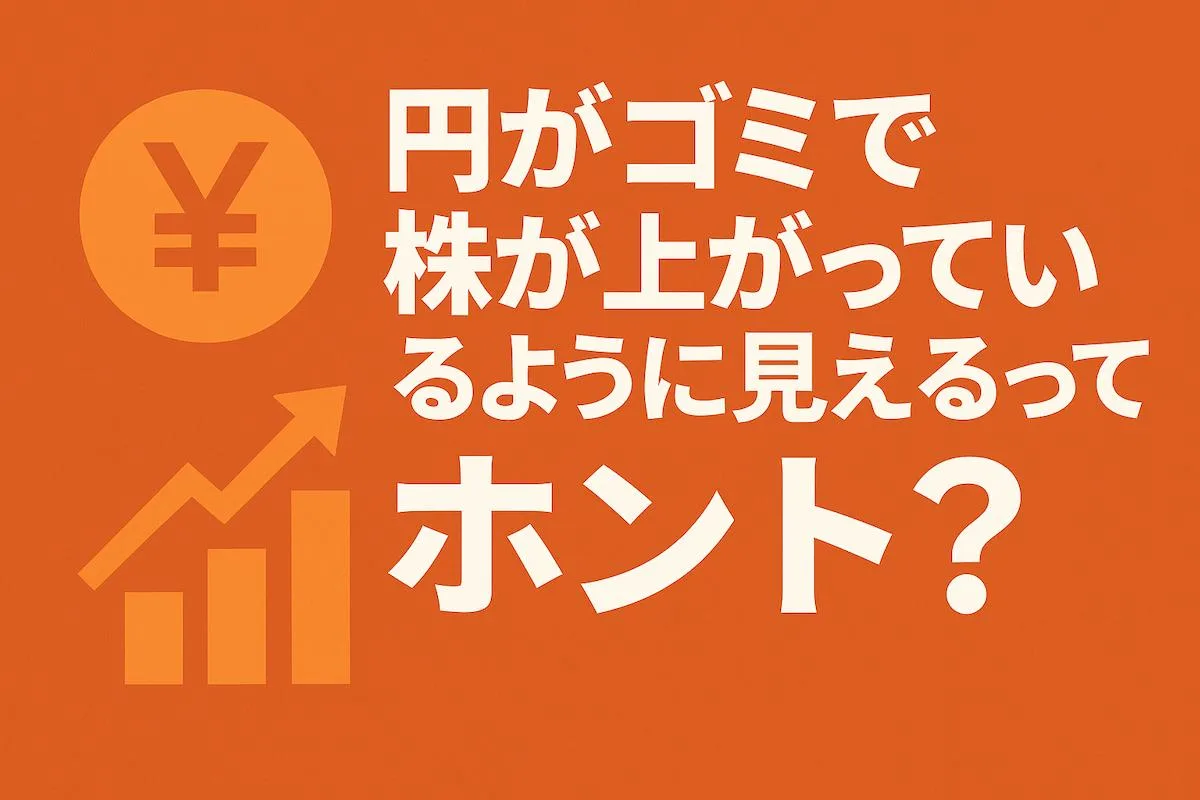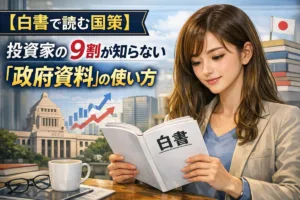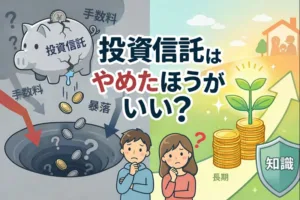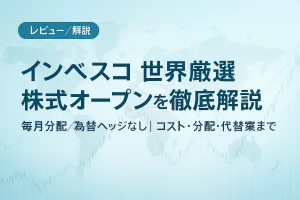ここ数年、日本円建てのチャートだけを見ると、株も金(ゴールド)や暗号資産も右肩上がりです。
SNSでは「バブルだ」「いや、円の価値が下がっただけだ」「円がゴミ化した」と二極化した議論が目立ちます。
結論から言えば、“半分正しい”です。
円安は確かに日本円ベースの資産価格を押し上げます。
しかし同時に、世界的な投資サイクル(AI関連を中心とする株高)や企業業績の改善、金そのものの需給といった本体要因も動いています。
今回はこのあたりの話を考えて見ましょう。
円の価値が下がると、何が“上がって見える”のか
まずは基本的な話から見ていきましょう。
名目価格と通貨ベースの基本
資産価格は「計測する通貨」によって見え方が変わります。
特に海外資産や国際商品(コモディティ)は外貨建ての値動き × 為替の変動の掛け算で円建てリターンが決まります。
円建てリターン ≒ (1+外貨建てリターン) × (1+為替リターン) − 1
例えば、ドル建てで+10%の上昇に、USD/JPYが+20%(円安)進めば、円建ては約+32%になります。
逆に、ドル建てが横ばいでも円安だけで円建ては上がって見えるわけです。
ゆえに「上がった理由」を語るときは、通貨効果の分離が欠かせません。
2024〜2025年の円安と「見かけの資産高」
2024年の円は対ドルで38年ぶり安値圏(160円台)をつけ、介入観測が高まる場面もありました。
2025年には一時的に円高方向へ戻る局面もありつつ、なお歴史的に円の弱いゾーンです(足元の金利差や政策見通し次第で上下)。
この局面では、円建てで見た株価や金価格が押し上げられやすい地合いになります。
「株バブル」なのか?——日本株と金の“見え方”を分解する
次に株について考えてみましょう。
日本株:高値更新は事実。ただし「円安×業績」の掛け算
2025年夏、日本株は日経平均・TOPIXともに最高値圏を更新しました。
円安は海外利益の円換算を押し上げ、業績と期待を通じて指数の上値要因になります。
一方で、円高に振れた日は押し目が生じるなど、為替と連動した繊細な値動きも確認できます。
つまり「通貨要因の上乗せ」が効きやすい相場環境であるということです。
ここで重要なのは、「円安だけで上がっているのか」「業績や見通しの改善が伴っているのか」を決算・ガイダンス・EPSで裏取りすることです。円安効果が剥落しても増益を維持できるかが、中期の上値余地を左右します。
金(ゴールド):円建て“史上高値”の背景
金はドル建てでも過去最高付近まで上昇し、円建てでは円安とのダブル効果で目立つ上昇となっています。
田中貴金属(小売価格・1g)ベースでも高値圏が続いており、直近も1万9千円台/gと歴史的水準です。
誤解しがちな点:円建てチャートだけ見ると「異常な高騰=バブル」に見えますが、ドル建て価格の上昇 + 円安の合成結果です。したがって、ドル建ての推移を併記しないと実像を誤ります。
「円の価値がなくなる」論の真偽——データで冷静に
最近、インフレで円の価値がなくなるということを言っている方が増えてきています。
このあたりの話もみておきましょう。
物価(CPI)と実質購買力
2025年夏の全国コアCPIは2〜3%台で推移。インフレは2%目標を上回っていますが、ハイパーインフレの様相ではありません。
体感的な値上がりが強いのは事実でも、「円の価値がなくなる」という表現は過度です。
東京CPIなど先行指標も2〜3%台で、足元はピークアウトの兆しと報じられています。
金利・金融政策:BOJの正常化と為替の関係
日銀は2025年に政策金利0.5%を維持しつつ、ETF・REITの売却開始というバランスシート縮小に踏み出しました。
金利差が縮む方向に動けば、理論的には円安圧力が和らぐ可能性があります(為替は金利差以外の要因でも動くため、絶対視は禁物)。

通貨要因を“はがす”3ステップ
それでは実際に通貨要因を剥がして考える方法についてみていきましょう。
ステップ1:円建てと外貨建ての二面評価
株式指数(例:日経平均)をUSD換算したパフォーマンスで併記。海外投資家の視点で“割高・割安”を補正できます。
金・原油・海外ETFも、現地通貨(ドル・ユーロ等)建ての推移を確認してから円建てに換算します。
ステップ2:業績・バリュエーションで裏取り
上昇が通貨だけなら、EPS・売上・CFと乖離しがちです。
決算とガイダンス(通期見通しの上方修正の広がり)で「本体の力」を確認。セクター別にも見ます(外需・内需・金利敏感)。
ステップ3:リスク別に“想定レンジ”を置く
為替(USD/JPY)の上下レンジを複数想定し、外需・内需・金利敏感の想定リターン帯を置いておきます。
「円高ショック時のヘッジ方法」「円安持続時の恩恵最大化策」をあらかじめ決めておくのがプロの備えです。
よくある誤解と反証
次によくある誤解について整理しておきましょう。
誤解1:「円の価値がなくなる=ハイパーインフレ」は極論
円の購買力は下がっていますが、2〜3%台のインフレ率は先進国の範囲内です。
金融政策も正常化方向に舵が切られています。したがって「紙屑化」を前提にした投資設計はオーバーアクションになりがちです。
誤解2:「株が上がっている=必ずバブル」
世界の株高は、AI投資サイクル、金利見通し、政策・関税不確実性の揺り戻しなど複合要因です。
強気相場の“初期バブル”観測はあるにせよ、即崩壊が前提ではありません。
投資家は通貨要因の上乗せも見落とさず、業績裏付けを重視すべきです。
誤解3:「現金は安全・資産は危険」という固定観念
インフレ下では現金の実質価値は目減りします。
だからといってフルインベストが正解とも限りません。
流動性の確保(生活防衛資金)と分散投資を両立させることが、長期のリスクコントロールになります。
通貨とバリュエーションを同時に織り込もう
それではこのような環境下で具体的にどのような投資手法を取ればよいのでしょう?
戦略1:外貨資産の通貨ヘッジを使い分け
- 円安の恩恵を取りにいく局面では「ヘッジなし」の比率を上げる。
- 円高反転リスクが強まる局面では、先物・為替予約・ヘッジ付き商品で部分ヘッジ。
- ヘッジコスト(スワップ・金利差)もネットリターンに効く点をお忘れなく。
戦略2:国内株は為替弾性値でセグメント管理
- 外需(自動車・電機など)は円安メリットが効きやすい一方、内需・金利敏感(銀行・不動産)は別軸で動きます。
- TOPIXコア+外需衛星の二層構造や、高配当・自社株買いを重視したディフェンシブ運用も有力です。
戦略3:金・コモディティは通貨分散+危機ヘッジ
- 高値圏では一括集中よりも積立・価格帯分散。
- 円高に振れたタイミングは押し目候補。保有の意義(通貨分散・尾リスク対策)を再確認します。
戦略4:シナリオ別の行動表
| シナリオ | 為替レンジの目安 | 株式ポジション | 通貨ヘッジ | 金・コモディティ | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| A:円安継続 | USD/JPY 150–165 | 外需比率↑・AI/輸出主導 | ヘッジなし比率↑ | 押し目待ち/積立継続 | BOJ据え置き・海外利下げ観測が材料 |
| B:円高反転 | USD/JPY 130–145 | 内需・高配当・ディフェンシブ | 部分ヘッジ↑ | 円高押しを拾う | 日米金利差縮小・期待インフレ低下 |
| C:米景気減速×日銀タカ派 | 不安定 | ベータ抑制・現金比率やや↑ | ヘッジ厚め | 分散を維持 | 企業ガイダンスとCPIを注視 |
まとめ
今回は「円の価値が下がると株は“上がって見える”?——日本株・金価格の上昇はバブルか通貨要因か【円の価値の今後】」と題して円の株の関係をみてきました。
株や金の上昇の一部は、たしかに円安による見かけの効果です。
しかし、世界の投資サイクル(特にAI関連)、企業業績の改善、金そのものの需給など本体要因も動いています。
だからこそ、通貨要因をはがして評価し、業績とバリュエーションで裏を取り、為替シナリオ別に行動計画を持つことがだいじとなります。
(1+外貨建てリターン) × (1+為替リターン) − 1。
この式を頭に入れておくだけで、SNSの“喧騒”から一歩距離を置いた投資判断ができると思います。