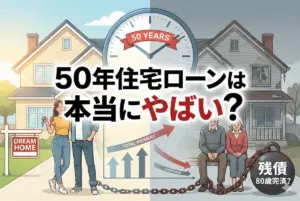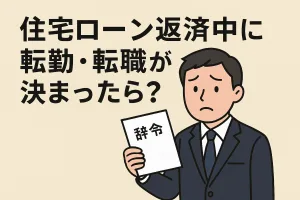日銀がマイナス金利を終了し、金利のある世界になってしばらく経ちました。
さらにインフレの影響も大きく「家」の価格はここ数年でかなり上がりました。
そのため、これから「家」を買おうとしている方はかなりハードルが高くなってきたんですよ。
そのため、一生賃貸でと考える方も増えているようですが、それもまた怖いんですよ。
家賃も上る可能性があるのです。
今回は家賃と金利の関係を見ていきましょう。
金利が上がると家賃も上がる?【結論】
先に結論から見ておきましょう。
結論から言うと、「金利が上がると家賃も必ずしも上がる」わけではありません。
ただし、お金の流れ的を考えればある程度相関して上がる可能性が高いのです。
ちなみに首都圏など需要が強いエリアの“募集家賃”は上がりやすい一方、CPI(消費者物価指数)の“家賃”(実際家賃+持家の帰属家賃)は動きが鈍いため、統計上は上がって見えにくい、というのが日本の実態です。
背景には①日銀の政策金利上昇、②住宅購入コストの上昇→賃貸需要の流入、③新規募集時に集中的に家賃が改定されやすい—という日本の賃貸市場のクセがあります。
ですからなかなか統計データに現れてくるのにはタイムラグがある点には注意が必要です。
金利と家賃の「3つの経路」
金利と家賃の関係を考えてみましょう。
大きく分けて3つの要素で連動しやすくなっているんですよ。
金利上昇→オーナーの資金コスト上昇
多くの大家さん(貸主)は不動産投資用のローンを組んでいます。
それはほとんどが変動金利なので金利上昇で返済負担は増えます。
その部分を借り主側に要求してくることは当然ありえます。
ただし、既存入居者の家賃は契約・慣行上すぐには変えにくいため、新しく募集する部屋の家賃や更新時に調整するケースが目立ちます。
金利上昇→持ち家のハードル↑→賃貸需要が強含み
日銀は2024年3月にマイナス金利を解除し、以降プラス圏での誘導しています。
2024年夏以降は追加利上げも実施され、住宅ローンや資金調達コストが上がりました。
購入に踏み切れない層が増えると、賃貸需要が相対的に強まるため、人気エリアの募集家賃は上がりやすくなります。
金利上昇→新規供給の鈍化や建築費高止まり→空室の少ない所が上がる
内閣府の短報は、新設住宅着工が揺れながら伸び悩み、建築費高止まりや金利上昇で市場が活況とは言えないと指摘
一方で東京都を中心に募集家賃の上昇が明確としています。
「供給(着工)鈍化×需要シフト」で、空室が少ない駅近・築浅は家賃が上がりやすいのが足元です。
いま日本の家賃は実際どう動いている?
それでは実際に今の日本の家賃はどうなっているのでしょう?
首都圏・主要都市は“募集家賃”が上昇基調
アットホーム・ラボや東京カンテイのデータでは、東京23区や福岡市などで2015年以降の最高値更新、複数月連続の上昇が確認できます。
シングルもファミリーも上昇しており、管理費・共益費も上がりやすいのが足元の特徴です。
CPIの「家賃」は緩慢
総務省の速報では、「家賃」や「持家の帰属家賃を除く総合」などは上昇寄与が小さめ。
CPIの家賃は「実際家賃(民営家賃)」+「持家の帰属家賃」で、帰属家賃は民営家賃の動きをほぼ流用する仕組み。
持家比率が高い日本では帰属家賃のウエイトが大きく(約15.8%)、ここがゆっくりしか動かないため、総合CPIの変動を抑える方向に働きます。
専門家からも「日本のCPIは家賃が動きづらい構造」との指摘が続いています。
そのため、生活感覚に近い「持家の帰属家賃を除く総合」という見方を厚労省も併記するようになりました。「統計をどう見るか」も大事な視点です。
金利上昇局面で家賃が「上がる物件」「上がりにくい物件」
次に上がりやすい物件と上がりにくい物件を把握しておきましょう。
上がりやすい
- 新築・築浅/駅近/人気学区など、需要が集中するエリア
- 入れ替えタイミングの部屋(新規募集)—既存入居者より価格調整がしやすい
- 共用部の光熱費・保守費が上がるマンション—管理費・共益費に波及しやすい
(※実例:首都圏の募集家賃、管理費とも上昇傾向)
上がりにくい
- 郊外で空室が目立つエリア/築古で割安感が強い物件
- 長期入居で契約条件が固いケース(法的に一方的値上げは難しい)
- 地域需要が弱く、入居者獲得に苦労する市場(空室対策が優先)
「賃貸か持ち家か」—金利があがる世界でどう考える?
次に永遠のテーマである賃貸か持ち家かについても考えてみましょう。
結論の軸は「期間・金利・流動性(身軽さ)」の3つ
お金で比べる前に、まず次の3つを考えましょう
1)住む期間:引っ越し予定や転勤の可能性を含めて「何年この街で?」
2)金利の耐性:返済が上がっても大丈夫な幅(家計のクッション)は?
3)流動性(身軽さ):売る・貸す・引っ越すの自由度をどこまで重視するか?
この3つが固まると、数字の比較(損益分岐)が一気に楽になります。
数字を揃えると迷いにくい
賃貸は家賃+共益費。
持ち家は返済だけではなく諸費用も入れます。
持ち家の“月あたり総コスト”は次のイメージです。
- 返済額(元金+利息)
- 固定資産税・都市計画税(年額を12で割る)
- 管理費・修繕積立金(マンション)または維持費見積もり(戸建て)
- 火災・地震保険(年額を12で割る)
- 購入時の初期費用の按分(仲介手数料、登記、税、諸経費を“想定居住年数”で割る)
ここまでを合計して、同じエリア・同じ広さの賃貸と比べるだけ。
ポイントは、元金返済は“貯蓄に近い”という見方ができる点。
また、住宅ローン控除が受けられるのも大きなメリット
家計の現金は出ていきますが、同額が家の“持分”になります。
したがって、利息+税・保険・維持費+初期費用の按分が“純コスト”です。
この“純コスト”が家賃を長期で下回るかを見ます。
金利が動きの影響
また、持ち家の場合には変動金利で借りている場合は、政策金利の影響を受けます。
賃貸の場合も今まで見てきたように間接的ではありますが、影響を受ける可能性があります。
そのあたりも含めて考えましょう。
まとめるとこんな感じですね。
1)住宅ローン返済(持ち家側):
変動金利は返済額に直結。
固定金利は契約時にほぼ確定。
2)購入需要と価格(持ち家側):
金利上昇→買える人が減る→価格が伸びにくくなる(出口=売却時の想定も控えめに)。
3)募集家賃・管理費(賃貸側):
オーナーのコスト増+購入見送り組の流入で、人気エリアの募集家賃や管理費が上がりやすい。
オーナーチェンジで一気に上るケースもあるので注意
ミニ事例:同条件で“10年住む”とどうなる?
例)同じ街・同じ広さで、
- 賃貸:月14万円(共益費込み)
- 持ち家:4,800万円の物件、頭金0、35年返済、金利1.2%(仮)
おおまかに
- 返済:約14.5万円/月(うち利息は初期で多め)
- 税・保険・管理修繕:合わせて2.5万円/月相当
- 初期費用の按分(10年で割る):1.0万円/月相当
→ “表面の総額”は18.0万円/月。
ただし元金返済分(たとえば初期は約7万円/月のイメージ)は持分に変わるため、“純コスト”はおよそ11万円/月。
この場合、10年の平均で見ると“純コストは賃貸より持ち家の方が軽い”計算になりやすい。
一方で金利上昇・修繕の膨らみ・売却時の値下がり次第で逆転もあり得ます。
だから期間と金利耐性の設定がカギです。
また、この計算には含めていませんが住宅ローン控除で所得税や住民税の削減効果もあります。
(注:上の数字は概算の考え方を示すための例です。実際は物件・金利タイプ・保険・税で変動します。)
「出口」が弱い物件は、買うほど身動きが取りにくい
持ち家のリスクは売る・貸すの難しさに集約されます。
- 駅から遠い・坂がきつい・人気学区外は、値下がりリスクや売却長期化の確率が上がる。
- マンションは管理状態(積立不足・大規模修繕の質)が価格に直結。総会議事録・長期修繕計画を確認。
- 戸建てはメンテ計画(屋根・外壁・給排水)が肝。年1%前後の維持費見積もりで試算を。
マンションの場合は管理組合も重要ですね。

後悔を小さくする”最終チェック
まとめると以下の点をチェックすると良いでしょう
1)金利が上がっても家計は回る?(持ち家/変動金利)
2)家賃が+5〜10%でも生活満足度は保てる?(賃貸)
3)10年基準で動かない? 動くならいつ?
4)買う物件の出口の強さ(駅近・築浅・管理良好・需給が厚い)
5)迷うなら身軽さ優先(変化が多い人は賃貸、安定なら固定多めで購入)
まとめ
今回は「金利が上がると家賃も上がる?賃貸か持ち家か?家賃と金利の関係をやさしく解説」と題して金利と家賃の関係をみてきました。
「金利が上がると家賃も必ずしも上がる」わけではありません。
しかし、その可能性も考えて置く必要はあるでしょうね。
なお、家賃の値上げ通知が来た場合の話はこちらの記事でまとめております。
合わせて御覧ください。