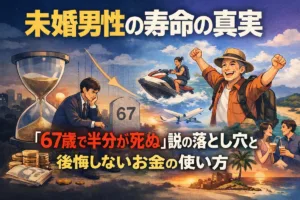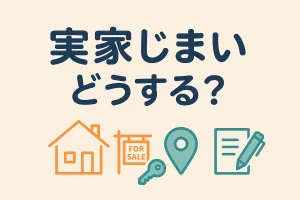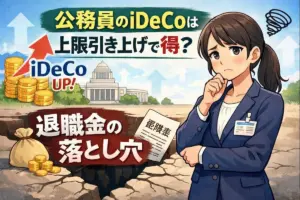国民年金や厚生年金といった公的年金の積立金を運用するGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)。2018年10月〜12月の運用損が14兆8039億円あったことから報道で叩かれていましたね。しかし、実は長い目で見るとGPIFが運用を開始した2001年からの収益率は年率換算で2.73%と波こそあれ長い目でみると収益を上げているのです。収益額は累計で56.7兆円のプラスと大きく積立金を増やしているんですよ。
これは報道の問題が大きいでしょう。下がったときは叩かれ、上がってもそれほど報道されませんので運用失敗しているイメージを持ってしまう人が多いだけなのです。
GPIFについては詳しくはこちらの記事を御覧ください。私は個人としては投資初心者こそ真似すべき投資スタイルだと思ってます。
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://ideco-ipo-nisa.com//15488]
そんなGPIFですがもう一つ批判されていることがあります。それはアベノミクスの一環で2014年から運用改革が行なわれ株式投資比率を上げたことに対してです。
今回はそんなGPIFの株式比率は本当に高すぎるのか、各国の年金運用と比較してみます。
GPIFの株式比率と各国の年金運用の株式比率を比べてみた
それではGPIFの株式比率と各国の年金運用の株式比率を比較してみましょう。
GPIFの基本ポートフォリオ
GPIFの基本ポートフォリオは下記の通り設定されています。

国内債券35%、国内株式25%、外国債券15%、外国株式25%
国内と海外合わせるとちょうど株式が50%、債券50%となっていますね
債券の方は国内が少し多めとなっています。
こちらが現在の基本ポートフォリオとなります。これは平成26年10月31日からのものでそれまでにはかなり変遷があったんですよ。
平成18年度から21年度(第1期中間目標期間)の基本ポートフォリオ
平成18年〜21年度は以下の基本ポートフォリオに基づき運用されていました。

国内債券67%、国内株式11%、外国債券8%、外国株式9%、短期資産5%
この時代では株式の比率は20%、債券が75%となっています。
ただし、乖離許容幅も設けられており国内債券+−8%、国内株式+−6%、海外債券+−5%、外国株式+−5%とされていました。
平成22年4月~平成26年10月(第2期中間目標期間)の基本ポートフォリオ
第二期この間の平成25年6月7日から大きく基本ポートフォリオが変更になりました。それが以下のとおりです。

国内債券60%、国内株式12%、外国債券11%、外国株式12%、短期資産5%
この時代では株式の比率は24%、債券が72%となっています。少しだけ株式比率が増えましたね。
ただし、乖離許容幅も設けられており国内債券+−8%、国内株式+−6%、海外債券+−5%、外国株式+−5%とされていました。
この基本ポートフフォリオであった期間は短く平成26年10月31日からは現在の国内債券35%、国内株式25%、外国債券15%、外国株式25%に変更となっています。
各国の年金運用基本ポートフォリオ
それでは次に各国の公的年金のポートフォリイオについて見ていきましょう。実は日本の株式比率50%というのはそんな飛びぬけておかしいことではないんですよ。もっと高い国はたくさんあったりします。
アメリカ:CalPERS(カリフォルニア州職員退職年金基金)
まずはアメリカです。アメリカは各州や職場毎になっていますので代表的なCalPERS(カリフォルニア州職員退職年金基金)を取り上げてみます。

債券20%、株式54%、その他資産26%
株式で54%運用しているんですね。このあたりは日本とそれほど大きく変わらないですね。日本と大きく違うのが債券の割合がかなり少なく、その分をその他資産で不動産などに運用を回していることですね。
ただしアメリカは基金によりポートフォリオがかなり違います。例えばダラス市警察・消防署職員退職金年金基金なんかはオルナティブ投資比率が56.3%となっているんですよ。オルナティブ投資とは「代替可能」という意味で株式や債券といった伝統的な資産運用ではなくヘッジファンドやコモディティ(商品)なんかの投資が含まれます。日本で言えばかなりリスキーな投資先と思われると思いますが半数をそちらに回している基金もあるのです。
カナダ:CPPIB(カナダ年金制度投資委員会)
次にカナダです。

債券17.5%、株式82.5%
カナダは非常にわかりやすく債券と株式のみです。株式比率は82.5%とかなり高くなっていますね。
ノルウェー:GPF-G(ノルウェー政府年金基金-グローバル)
最後はノルウェーです。

債券30%、株式70%
ノルウェーも非常にわかりやすく債券と株式のみです。株式比率は70%とこちらもかなり高くなっていますね。
またノルウェーの場合には不動産へ上限7%まで投資できるようになっています。
各国の年金資産運用成績の比較
各国の運用成績は以下のとおりです。株式比率が高い国のほうが波こそ大きいものの成績が良いのがわかりますね。
| 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CalPERS | 9.6% | 16.3% | 13.2% | 2.9% | -29.1% | 25.2% | 13.1% | 3.7% | 10.9% |
| CPPIB | 8.5% | 15.5% | 12.9% | -0.3% | -18.6% | 14.9% | 11.9% | 6.6% | 10.1% |
| GPF-G | 1.0% | 11.5% | 5.6% | -11.4% | -9.5% | 25.5% | 4.9% | 2.8% | 11.0% |
| GPIF | 3.4% | 9.9% | 3.7% | -4.6% | -7.6% | 7.9% | -0.3% | 2.3% | 10.2% |
| 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CalPERS | 13.7% | 6.1% | -0.2% | 10.1% | 11.1% |
| CPPIB | 16.5% | 18.7% | 3.7% | 12.2% | 11.6% |
| GPF-G | 16.6% | 34.5% | 0.8% | 12.7% | 3.9% |
| GPIF | 8.6% | 12.3% | -3.8% | 5.9% | 6.9% |
出所:年金積立金独立行政法人WEBページより
各国の年金資産の運用規模
次に運用規模を見てみましょう。平成30年3月末現在ので運用規模は以下のとおりです。(単位:兆円)
| CalPERS(アメリカ)(カリフォルニア州職員退職年金基金) | 37 |
|---|---|
| CPPIB(カナダ)(カナダ年金制度投資委員会) | 29 |
| GPF-G(ノルウェー)(ノルウェー政府年金基金-グローバル) | 110 |
| 年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF) | 156 |
出所:年金積立金独立行政法人WEBページより
日本のGPIFは他と比べてかなり大きい規模なんですよ。2017年の調べではGPIFは年金基金の運用規模では世界最大となっています。ちなみに地方公務員共済組合連合会も13位だったりします。ちなみに2位はノルウェーのGPF-Gです。
まとめ
今回は「株式比率が高すぎると批判される公的年金の積立金運用は適切なのか?各国と比較してみた」と題してGPIFの運用で株が50%あることの妥当性をみてきました。
日本はもともと株式の比率が異様に少なかっただけで他の国と比較すれば普通。もしくは少ないくらいということがわかりましたね。
今後少子高齢化でどんどん年金資産は厳しくなるでしょうからうまく運用してもらいたいものです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
フェイスブックページ、ツイッターはじめました。
「シェア」、「いいね」、「ツィート」、「フォロー」してもらえると大変うれしいです。