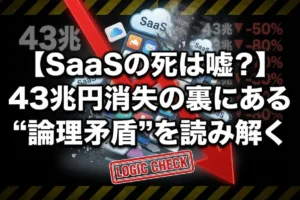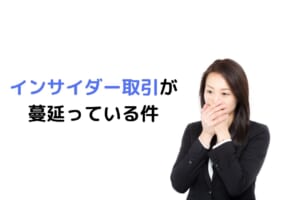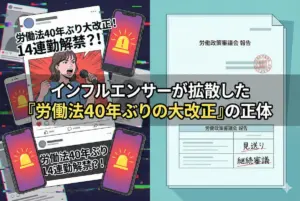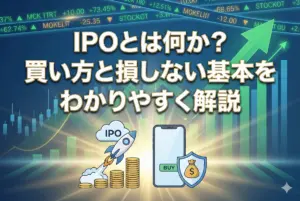X(旧Twitter)などSNSやYouTubeで、銘柄名を言わずに“ヒント”だけ出す投稿を見かけたことはありませんか?
「調べさせると煽りの効果が高い」という指摘がSNSでも語られています。
これは、情報ギャップ理論(Information Gap Theory)や自己確証バイアスで説明できる現象です。
私たちは自分の知識の“穴”を意識した瞬間、その穴を埋めたくてたまらなくなる。
好奇心が強く刺激されるのです。
投資領域ではこれがFOMO(取り残され恐怖)と結びつき、短絡的な売買につながりやすいのが難点です。
こうした銘柄の“匂わせ”は拡散力が高く、投資判断を曇らせます
今回は情報ギャップ理論で煽られない対策について考えてみましょう。
情報ギャップ理論とは(行動経済学の基礎)
行動経済学者ジョージ・ローウェンスタインは1994年、「知識の穴」に注意が向くと好奇心が生じるとする情報ギャップ理論を提示しました。
穴が大きすぎても小さすぎても動機づけは弱く、“ほどよい不確実性”で好奇心が最大化されます。
この「ほどよさ」は脳科学の実験でも裏づけがあり、自分の答えに“中くらいの自信”しかないときに好奇心がピークになり、報酬系(線条体など)が活性化しました。
つまり、情報それ自体が報酬として働くのです。
まとめ:わざと情報を欠落させる=適度な穴をつくると、人は“知りたくて”動く。
投資誘導で使われがちな「ぼやかし」テクと、なぜ効くのか
株式投資で言えば少し探れば分かる程度に銘柄のヒントを与えている状況がそれにあたりますね。
例えば以下のような手口があります(意図していないケースもあるとは思いますが)
- 伏せ字・暗号化:「◯越◯◯」「フ◯◯◯」「コア部材の“あの会社”」——検索させる余地を残す
- 限定化:「ここでは言えない」「DMで」「サロン限定」——希少性バイアスを刺激
- 追記・匂わせ:「ヒントは東証P、時価総額1,000億未満、黒字転換」——自己確証バイアス(人は自分で探した根拠を過大評価)
- 時間プレッシャー:「本日中に」「決算前に」——損失回避×FOMOを同時に刺激
なぜ効く?——上の仕掛けは情報ギャップだけでなく、希少性・社会的証明・損失回避などの行動バイアスをセットで動かすからです。
結果、検証前の“先買い”や過剰集中を引き起こしやすくなります(行動経済学の総説・解説は多数。参考:バイアスの体系的整理など)。
その他の行動経済学の話はこちらの記事にまとめてあります。

井村ファンド(Kaihou)の事例
近年、著名投資家が関与する投資商品が話題化し同様の現象を起こしているケースもあります。
たとえば、「井村ファンド」の通称で取り沙汰されることがある「fundnote日本株Kaihouファンド」は、株式会社Kaihouの投資助言を受け、fundnoteが運用する公募投信。
このファンドは月次レポートなどで投資銘柄をぼやかして表記しています。
などといった感じですね。
XやYouTubeなどでは過去の井村さんの発言、投資傾向や上記のヒントから投資銘柄を予想する人がかなりおり、その予想により株価が高騰するなど、情報ギャップ理論的な状況になっていたりもします。
おそらく、銘柄非公開なのは投資への影響を考えてのことで、それを意図してはいないと思いますけどね。
「ぼやかし煽り」に引っかからないための投資家チェックリスト
それではこのようなぼやかし煽りに引っかからないために意識したいポイントを見ておきましょう
誰が言っている?
発言者は実名・団体名が明確か?
登録の要否がある助言をしていないか(金融庁の登録一覧で検索)を確認しましょう。
そもそもXなどで儲かった自慢をしている人の大半は偽物です。(本当は儲かっていない)
何を根拠に?
目論見書・決算短信・適時開示など一次情報のURLが提示されているか。
なければ自分で探して読む。
どこに誘導?
M限定・有料サロンに誘うだけで、具体的根拠の提示がないなら黄信号。
無登録助言の温床にも。
いつの話?
期日・決算・材料の時点が曖昧なら注意。
古い情報の焼き直しは珍しくないです。
先日も某銘柄を煽っている人がいましたが、書いてある株価が数ヶ月前の金額だったんですよ。
おそらく使いまわして何度も投稿しているのでしょう。
なぜ今?
タイムプレッシャーで急がせるのは典型的。
“今日だけ”に弱いのが人の常です。
ここで一晩寝かせるのが正解。
どう損する?
上がる理由だけでなく下がる筋道も書けるか(需給・バリュエーション・事業リスク)。
どれだけ入れる?
ポートフォリオ全体の文脈に落とす(集中回避・最大ドローダウン想定・損切り規律)。
インフルエンサーの法とモラル
法的問題も確認しておきましょう。
何がアウトか(風説の流布・偽計・無登録助言)
SNSでの発信でも、投資関連は金融商品取引法の規制対象になり得ます。
- 風説の流布・偽計(158条):相場を変動させる目的で根拠のない噂や虚偽を流布することは禁止。違反すれば刑事罰・課徴金の対象になり得ます。
- 不正行為の禁止(157条):虚偽表示・重要事実の不表示なども禁止。
- 無登録の投資助言・勧誘:登録のない業者による勧誘や詐欺的行為に注意喚起が出されています。登録事業者一覧での確認が基本です
チェック先:金融庁の登録一覧(金融商品取引業者・投資助言・代理業等)。無登録リストや注意喚起ページも公開されています。
また、そもそもインフルエンサーが言ったことを全面的に信用してはなりません。
自分で考えるクセをつけましょう。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。

発信者側が注意すること
自分が発信者側なら以下の点を意識しましょう。
- “ぼやかし”ではなく、普通名詞+検証可能な事実で:例「東証P×時価総額◯◯億×営業CF黒字」のようにファクトを列挙
- 一次情報へリンク:適時開示・決算資料・目論見書
- リスクの明示:投資リスク、利益相反の可能性(保有有無・報酬関係)
- 登録の要否を確認:投資助言に該当する継続的・個別具体の助言は登録が前提
行動経済学でつくる「耐煽り」投資プロセス
今回の情報ギャップ理論のように行動経済学は世の中に張り巡らされています。
それを意識して逆に利用してやるのが良いんですよ。
以下の点を意識しましょう。
①“好奇心ピーク”を自覚する
自信が中くらいのときほど好奇心が強く、誤判断に走りやすい。
自信スコア(0〜100)を自分で付け、60未満なら即断しない
②反証検索ルール
「買い材料」検索の後に必ず“銘柄名 + リスク/不祥事/需給*で再検索。
確証バイアス対策。
③時間希少性を無効化
“本日中”投稿は強制クールダウン(24〜48時間)をルール化。
FOMO切断。
④ポジション・サイジング
リスク許容度と相関を見てサイズを決める。
上振れシナリオと下振れシナリオを対で書く。
⑤記録
買付理由・根拠URL・想定シナリオをノートに残す。
後日、根拠なき煽りだったか検証できる。
まとめ
今回は「SNSの銘柄“匂わせ”に要注意|情報ギャップ理論で煽られない投資術」と題してSNSの銘柄匂わせについてみてきました。
穴(情報ギャップ)は行動の起爆剤。
投資では誤爆になりがちです。
一次情報にあたる→登録・法令順守の確認→反証検索→ポジション設計の順で。
発信者は事実の提示とリスク明示を徹底。
“ぼやかし”で引かせる手法は法・モラル両面の地雷になり得ます。
発信者も受け取る側も気をつけたいですね。