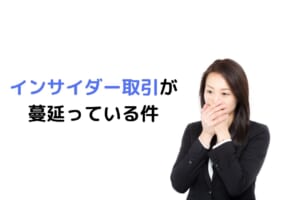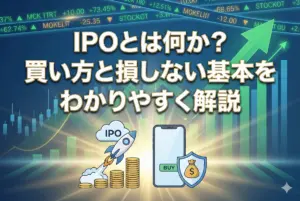株式投資をしていると、「配当落ちで株価が下がる」という現象に直面した経験がある方も多いでしょう。
配当落ちとは一体何なのでしょうか?そしてなぜ配当落ちで株価が下がるのでしょうか?
今回は、その理由を詳しく解説していきます。
そもそも「配当落ち」とは?
配当落ちとは、配当金を受け取る権利(権利付き最終日)の翌営業日に株価が下がることを指します。
株式には配当を受け取る権利がついていますが、この権利が得られる最終日の翌日以降に株式を買っても配当金を受け取ることはできません。
そのため、権利がなくなった分の価値が株価から差し引かれるために株価が下落します。
これを専門的には「理論上の配当落ち価格」と呼び、計算式は以下のようになります。
配当落ち後の理論価格=配当落ち前の株価-1株あたりの配当金
例えば、株価1,000円の会社が1株につき30円の配当を出す場合、理論的には次の日の株価は970円となります。
配当関連の用語
なお、用語がわかりにくい人も多いでしょうからそのあたりも簡単に解説しておきます。
権利付き最終日
配当を受け取る権利を得るためには、一定の「株主名簿に載る日」に株式を保有している必要があります。
日本では、決算期末や中間期末(3月末・9月末など)が権利確定日になることが多いですが、この権利確定日の2営業日前が「権利付き最終日」です。
ここまでに株式を買って持っておけば、その決算期の配当金を受け取ることができるわけですね。
権利落ち日
権利付き最終日の翌営業日が「権利落ち日」と呼ばれます。この日以降に株を買っても、
その期の配当金を受け取れる権利はもらえません。
配当落ち
権利落ち日になって配当金をもらえる権利がなくなると、理屈の上ではその分だけ株価が下がることがあります。
これを「配当落ち」と呼ぶのです。
具体的には「配当金の分だけ株価が安くなる現象」を指しており、株価が“コツン”と一段階下がったように見えるケースが多くあります。
なぜ配当落ちで株価が下がるのか?
それではなぜ配当落ち日に株価が下落するのでしょうか?ここでは、3つの理由を詳しく見ていきましょう。
権利落ちの調整
一番シンプルな理由は「配当を受け取る権利」が消失したことによる調整です。
株式市場では、企業が生み出した利益を株主に配当金という形で分配します。
配当が行われると企業の資産はその分減少します。
したがって、配当権利を失った日の株価はその配当金分だけ理論的に価値が低下することになります。
つまり、権利を得るために株を保有していた投資家が、その権利を失った瞬間から株価評価を見直すため、市場の参加者全体が調整の売買を行い、株価が自然と下落するのです。
短期的な利益目的の売却
また、権利付き最終日まで株式を保有していた短期的な投資家が配当目的で購入した後、権利確定後にすぐに売却する動きが発生します。
配当を得るために一時的に株を購入し、目的を達成したらすぐに売却する投資手法は「配当取り」と呼ばれています。
このような動きが短期的な売り圧力となり、配当落ち日には多くの投資家が一斉に売却に動くことで、さらに株価が下落する可能性があります。
心理的要因
さらに、株式市場では心理的な要素が大きく影響します。
配当落ちにより理論価格が下がると分かっているため、先回りして売る投資家も存在します。「配当落ち日は下がる」との共通認識が形成されることで、多くの投資家が前もって売りに動き、それがさらに下落圧力を強めることがあります。
市場全体が大暴落の日であれば、配当落ちによる下落幅よりさらに大きく値下がりすることも多いですね。
配当落ち後に株価は戻るのか?
ここで気になるのは、配当落ち後に株価が元の水準に戻るのかという点でしょう。
これは企業の業績や市場環境などによります。
業績が好調で今後の成長期待が高ければ、配当落ちによる株価下落は一時的なものとなり、徐々に株価が回復して元の水準を超えることもあります。
しかし逆に業績が低迷していたり、市場環境が悪化している場合には、株価が戻らず低迷したままの状態が続く可能性もあります。
お値打ちな価格で値ごろ感も
また、今までの株価よりも下がった金額となっていれば「権利落ち日には一時的に株価が下がる。ならばそのタイミングで買ったら得なのでは?」と考える投資家がいます。
もしその企業の業績がしっかりしていて、さらに長期で持っていれば配当を継続的に受けられるなら、この作戦がうまくいく可能性もあります。
配当落ちを考慮した投資戦略
それでは配当落ちを考慮するとどのような投資戦略がよいのでしょう。
配当を得るために権利付き最終日までに買う
まず、考えられるのが権利付き最終日までに買うという手法です。
配当がもらえますからね。
ただし、これはある意味「コストパフォーマンスの低い投資」になりがちです。
なぜなら、権利落ち日以降は基本的に株価が下がる可能性が高く、結果的に配当金以上に株価が下落して含み損が増えてしまうかもしれないからです。
もちろんうまくタイミングが合えば、配当金と株価上昇という両方の恩恵を受けられる場合もあります。
しかしこれはあくまで運要素が大きく、常に勝てる保証はどこにもありません。
配当落ち後に買う
逆に配当落ち後の安くなったタイミングで狙う手法もあります。
中長期的な値上がり益を狙う戦略ですね。
こちらも絶対はありません。
目先の配当よりも企業の業績やタイミングをみよう
配当を目当てに投資する場合は、その企業が長期的にしっかりと利益を上げ続けられるか、配当方針が安定しているかなどを見極める必要があります。
配当の権利だけに目が行ってしまうと、肝心の「企業の成長性」や「株価の将来性」を見逃してしまう可能性が高くなるので注意しましょう。
結局は、「配当落ちでどのように株価が動くかを冷静に把握し、無理のない投資計画を立てる」ことが大切なのでしょうね。

まとめ
今回は「「配当落ち」でなぜ株価は下がるのか?仕組みと投資のヒントを徹底解説」と題して配当落ちについてみてきました。
配当落ちで株価が下がるのは、ある意味「自然な調整」のようなものです。
権利付きの間は「配当をもらえる価値」が株価に含まれ、権利がなくなった途端にその分が切り離される、というシンプルな理屈ですね。
しかし、実際の株価はさまざまな要因によって動くため、教科書どおりに「配当金と同額だけ下がる」とは限りません。
配当をうまく活用して利益を狙う投資家もいれば、配当よりも企業の成長性やキャピタルゲイン(株価の値上がり益)に注目する投資家もいます。
どちらが良い悪いではなく、投資スタイルや目標に合った方法を選択することが大切です。
配当金に目が行きがちになる時期ほど、落ち着いて「その企業の株式を保有する根拠」を再確認してみましょう。最終的にはトータルリターン(配当+売却益)がプラスになるかどうかが重要です。
配当落ちの仕組みを理解した上で、ぜひ上手に投資判断をしてみてくださいね。