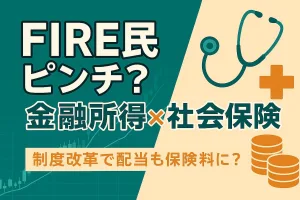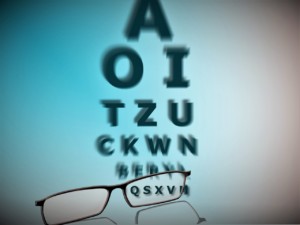参議委員選挙真っ只中ですが、各党が給付金、消費税減税を叫んでいます。
個人的にはこれにはかなり疑問を呈しているんですよ。
「消費税を下げれば物価がラクになるはず」「給付金で家計を潤したい」その気持はわかります。
しかし、そんな期待とは裏腹に、私たちの給料明細で最も重い“湿布”のように貼りついているのが社会保険料です。
本記事では社会保険料の削減こそ家計と日本経済を同時に助ける“本丸”である理由を解説します。
社会保険料とは何か?
まずは話の前提となる社会保険とはなにかについて簡単に解説しておきましょう。
健康保険・厚生年金・介護保険・雇用保険、労災保険などの社会保障制度です。
従業員の負担
そのうち、健康保険・厚生年金・介護保険・雇用保険は従業員負担分があり、年齢等によって多少異なりますが、合計約15.6%(健康保険9.98%・厚生年金18.3%を労使折半ほか)となります。
単純計算で月収30万円なら約4.7万円が毎月「見えない税」として消えるということになります。
給料天引きですからわかりにくいですが、家計負担としては消費税以上なんですよ。
ちなみに総務省「家計調査」勤労者世帯では、非消費支出17.7%の大半が税・社会保険料。
手取り減は可処分所得の伸び悩み要因となっているとのデータもあります。
また、所得税は累進課税ですが社会保険料は定率かつ上限があるため、低所得者ほど負担割合が高いということも知っておきたいところ。
年収300万円世帯:社会保険料等負担率 20%前後
年収800万円世帯:同負担率 15%前後
→ 低所得ほど負担が重い=逆進的
会社の負担
会社も従業員と折半の健康保険・厚生年金・介護保険、会社負担が少し大きい雇用保険、全額会社負担の労災保険を支払っていますので業種にもよりますが、給料とは別に16%〜20%程度の負担となっています。
つまり、会社と従業員分を合わせれば30%超の負担が発生するってことなんですよ。
さらに社会保険料のたちが悪いのが税金と違って金額がどんどん上げられるという仕組みがあるということです。
給付金・消費税減税が家計に届く仕組み
それでは各党が提案する給付金と消費税減税が家計が届く仕組みについて社会保険料と比較してみましょう。
給付金:一時金。銀行口座に振り込まれるが1回限り。
消費税減税:購入時だけの軽減。消費税10%→8%なら生活必需品中心世帯は恩恵が限定的
社会保険料:月々の固定コスト。減額すれば毎月の手取りが増え続ける。
減税・給付は「貼れば一瞬ひんやりする湿布」程度の効果です。
社会保険料削減は「痛みの根本治療」とイメージ付け。
各党の案についてはこちらの記事でまとめております。
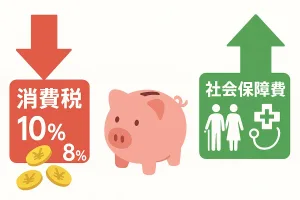
可処分所得シミュレーション(年収別・家族構成別)
それでは実際、社会保険料を削減した場合と給付、消費税を減税した場合のシュミレーションをみてみましょう。
| 年収 | 社保2%削減 | 消費税2%減税 | 給付金単身 | 給付金 2人+子ども2人 |
|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 6万円 | 4.2万円 | 2万円 | 12万円 |
| 500万円 | 10万円 | 7万円 | 2万円 | 12万円 |
| 800万円 | 16万円 | 11.2万円 | 2万円 | 12万円 |
| 1,200万円 | 24万円 | 16.8万円 | 2万円 | 12万円 |
年収300万円で大人2人、子ども二人のケースでは給付金が最もお得なりますが、その他のケースでは社会保険料を2%削減したほうが効果があるとの結果となりました。
また、4人家族・低所得帯は給付金が瞬間最大風速で大きいが、翌年以降はゼロですからトータルで見ると逆転しますね。
法人負担分と賃金抑制の関係
さらに社会保険料は企業の負担も大きいです。
これが下がれば、賃上げ交渉でよく聞く「トータルコスト」の押し下げに繋がります。
人材投資に回す原資増という波及が期待できます。
賃上げ余力の創出
非正規→正規転換促進
なんて話も期待できるでしょう。
社会保険料を下げると将来の社会保障が減るのでは?
ただし、社会保険料の引き下げにはもう一つ大きな論点があります。
それは社会保険料を引き下げれば当然ながら社会保障の部分がそのままでは維持できないってことです。
つまり、社会保険料の引き下げは社会保障の部分とトレードオフになるってことですね。
そのままの社会保障制度で社会保険料を下げるなんてむしが良い話はありません。(国債発行なんて無責任なことをいってる党もありますが)
かなり深刻な2025年問題
実は社会保険の問題はかなり前から叫ばれていました。
2025年問題です。
しかし、ぜんぜん対策がうまくいかなかったのが現状なのです。
2025年は1947〜49年生まれ約800万人の団塊世代が全員75歳以上となる時期となります。
厚生省の試算によると2025年には75歳以上の高齢者(後期高齢者)は2,197万人(日本国民の18.1%)、65歳以上の高齢者(前期高齢者)は3,657万人(日本国民の30.3%)と予想されています。
それに伴い2015年では42.3兆円(うち後期高齢者15.2兆円)だった健康保険が2025年には57.8兆円まで膨れ上がります。
高齢者は増えますが、支え手は当然減りますので、2000年には3.9人で1人を支えていたのが2025年には1.9人で1人を支える様になる状態となってしまいます。
さらにこの予想がされた当時よりも少子高齢化が進んでいますので、さらに支え手は厳しい状況に・・・
そのため、健康保険料がどんどん上がっているんですよ。
現役世代の手取りが減り、さらに少子高齢化が進むという悪循環に。
ですからこの問題を放置すれば社会保険の削減どころか“自動増加”が既定路線。
このままいけば「社会保険料の可処分所得シェア」は雪だるま式に増えるのです。

社会保障の在り方を見直す時期
つまり、今のままでは維持できない制度が社会保険なんですよ。
ですから抜本改革が必要な時期に来ているんですよ。
例えば以下のような話が出ていますね。
湿布など医療費の削減
よく問題になる湿布。
「日本が誇る医療用外用貼付剤の推進に関する議員連盟」なんて湿布の健康保険適用を守ろうなんて自民・公明・維新など超党派の議員連盟があるので手強いですが、本当にそれを健康保険で負担する必要があるのかを考える必要があります。
市販薬でいいやんって思っちゃいます。
安楽死の問題などもそうでしょう。
脳死状態で無理やりな延命で多額な医療費が使われているのが現状。
それを健康保険適用外にするという意見も出ています。
線引は難しそうですけどね。
高齢者の負担を増やす
現状、多くの高齢者は窓口1割負担となっています。(現役世代などは3割負担)
日本の多くの資産は高齢者が持っているという現状がありますが、所得が少ない(そもそも高齢なので働いていない)ため、負担が少なく済んでいるのです。
これも見直しが必要な時期に来ているでしょう。
そもそも健康保険料の利用者のほとんどが高齢者ですしね。
現役世代はほとんど使わない健康保険料がどんどん上がってしまっている現状なのです。
今回の自民党が提案してる給付金で増額対象となっている住民税非課税世帯の問題も絡んでくる話になります。
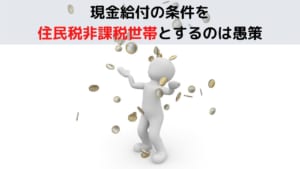
選挙で社会保険料を訴えると負ける
上記ふたつの案は正直、小手先の対処療法に過ぎません。
必要なのは抜本改革。
ただし、難しい問題があります。
選挙で年金や健康保険料の問題を取り上げると負けるんですよ。
人口の3割が高齢者です。
投票率が高いのも高齢者。
高齢者の負担が増える社会保険改革案は受けが悪い。
社会保険料が削減されても働いていない高齢者にはあまり関係がない。
むしろ社会保障が削られて損をする可能性の方が高いです。
一方、消費税減税や給付金なら得をします。
高齢者の多くが住民税非課税世帯ですからプラスの給付も受けられる。
そうなれば当然厳しい選挙になってしまうんですよ。
消費税減税や給付金よりもやるべきことは社会保険の改革とわかっている政治家は多いとは思いますが、自分の首が掛かっていて動けないという・・・
このあたりは本当に難しい問題です。
数少ない社会保険料の問題に真っ向から向き合っている音喜多元議員のこの投稿などをみると、高齢者の当事者意識はかなり薄いですからね・・・
案の定、音喜多元議員は社会保険料について訴えているので情勢は厳しいようです。
私は東京の選挙区民でないので投票できないのが残念でなりません。
まとめ
今回は「今やるべきことは社会保険料改革――消費税減税・給付金より重要な理由」と題して社会保険料改革について考えてみました。
消費税減税も給付金も一時的な“湿布”。
しかし社会保険料の恒久的な引下げは、毎月の手取りと企業競争力を同時に底上げします。
「湿布だけでは治らない痛み」を放置するか、根源治療に踏み出すか――決めるのは私たち一人ひとりの選択です。