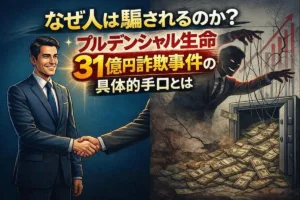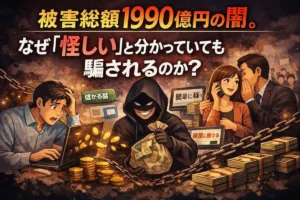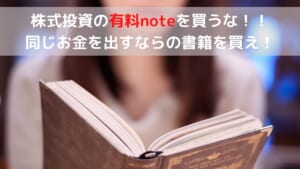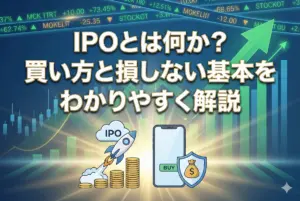経済安全保障や少子高齢化による財政悪化が叫ばれる中、公明党が参院選公約に掲げた「日本版ソブリン・ウェルス・ファンド(政府系ファンド)」構想に個人的に注目しています。
GPIFの運用ノウハウを活用し、外貨準備や国有資産を積極運用すれば、国民生活や株式市場はどう変わるのでしょうか?
本記事でポイントを分かりやすく解説します。
ソブリン・ウェルス・ファンドとは?
ソブリン・ウェルス・ファンド(SWF)とは、政府や中央銀行が国の資産を長期運用する投資ファンドです。
他国では実現した成功事例がいくつもあります。
世界の事例
最大規模はノルウェーの政府年金基金グローバルで約1.7兆ドルの運用残高を誇ります
原資は原油収入(ノルウェー)、外貨準備(中国SAFE)、年金積立金(カナダCPP)など多様。
運用益は
- 将来世代への資産継承(ノルウェー)
- 国民への給付(クウェート)
- 産業投資・雇用創出(シンガポールのテマセク)
など国ごとに目的が異なります。
投資対象は株式・債券・インフラ・PEファンドなどに分散され、各国の経済政策と連動している点が特徴です。
日本版SWF構想の経緯と背景
公明党が参院選公約で「日本版SWF創設」を提案。「財政を育て、政策実現の財源を創出する」と明記。
党政策ビラでも「国の資産を計画的に運用し、新たな財源を生み出す仕組み」として解説しています。
現在、公明党は与党になりますから実現可能性はそれなりにありそうです。
背景には
- デフレ脱却後も続く慢性的な財政赤字(国債残高GDP比250%超)
- 約1.27兆ドルの外貨準備(主に米国債)が低金利で眠る現状への問題意識
- 日本版SWF創設を巡る議論は民主党政権(2009–12年)でも浮上したが実現に至らず。今回の公約は再浮上と言える。
参議院選挙のためだけの話でないと願いたいところですが・・
円安局面で外貨準備をドル建てのまま運用すれば為替リスクを抑えつつ収益拡大が期待できる一方、米国債売却が外交カード化する懸念もあります。
政府系ファンドを創設する目的
創設する目的はいろいろ考えられます。
| 目的 | 期待される効果 | リスク |
|---|---|---|
| ① 新たな財源創出 | 運用益を子育て・年金財源に充当 | マーケット下落時の含み損 |
| ② 経済成長投資 | 国内スタートアップ・インフラへの直接投資 | 政治介入による投資効率低下 |
| ③ 為替・資産の分散 | 外貨準備の運用多様化でリスク分散 | 地政学リスク・対外政治圧力 |
| ④ グリーン・DX推進 | 脱炭素・AI等の国家戦略投資 | 長期回収案件の評価難 |
海外SWFは資源収入の代替財源化が主流ですが、日本の場合は「少子高齢化×財政赤字」の課題解決をめざす点がちょっと他の国とは違うところ。
政府系ファンドを「経済安全保障の司令塔+長期投資家」として位置付ける構想です。
GPIFの実績と教訓
おそらくこの話が国会で議論されだすと「損を出したらどうするのだ!」といった反対意見が多数でることは目に見てえています。
しかし、日本には成功事例があるんですよ。
年金を運用するGPIF(年金積立管理運用独立行政法人)です。
GPIFの過去の運用実績は以下の通り。
| 指標 | 2024年度単年度 | 過去20年累計 |
|---|---|---|
| 運用収益率 | 0.71% | 年率4.2% |
| 収益額 | +1.7兆円 | +120.0兆円超 |
出典:GPIF業務概況書会見資料(2025年7月4日)
さらに直近2024年10〜12月期には+10.7兆円(+4.31%)の四半期利益を確保し、総資産は258.7兆円に到達しました
4半期でたまたま赤字になるとマスコミが大騒ぎして、儲かっているときはなにも言いませんので、赤字のイメージの方が多いみたいですが、実は年金の運用はかなりうまくいっているんですよ。
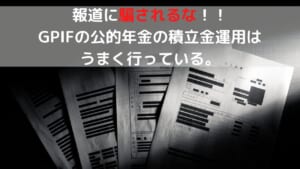
教訓
GPIFはいくつもの教訓を与えてくれています。
・長期分散+低コストが最強
・透明性と説明責任が政治的干渉を抑制
・市場に与える影響力(売買インパクト)を重視した段階的リバランス
特に個人的に大きかったと思うのが基本ポートフォリオを以下のように公開。
実際の銘柄もすべて公開していることです。
これにより政治家の介入をしにくくしているのです。
ちなみにGPIFの運用は個人投資家も真似をすることは容易だったりします。
詳しくはこちらの記事を御覧ください。

財源・運用スキームとGPIFから学ぶべき点
ここからは実際どのような財源、運用スキームになるのかを予想してみましょう。
運用原資候補
まず、運用原資は以下のようなものが考えられます。
・外国為替資金特別会計(外為特会):1兆ドル超の米国債を保有
・日本郵政、JTなど国有株の追加売却
・日銀ETF・REITの売却
・国債の発行
どれも実現は可能ですが、いろいろな影響がありそうな内容ばかりです。
難しい判断がでてきそうではあります。
運用主体の選択肢
運用主体もいろいろな候補が考えられます。
・新設独立行政法人
・日銀子会社化(NBIM方式)
・GPIFとの連携ファンド(共通リスク管理基盤)
個人的にはGPIFとの連携ファンドが一番良いと思いますけどね。
ガバナンス
ガバナンスの部分は難しいところになります。
・専門家委員会による長期ポートフォリオ策定
・国会・会計検査院への報告義務
・ESG・スチュワードシップ責任の明文化
GPIFの成功要因である低コスト運用・パッシブ比率の高さ・徹底した透明性は、そのままSWFに移植可能です。
逆に政治的銘柄指定や高コストアクティブ投資の乱発は失敗の教科書となりそうです。
癒着の温床とならないようにしてもらいたいところですが・・・
日本経済・資本市場へのインパクト
それでは日本版ソブリン・ウェルス・ファンド(政府系ファンド)が実際にできた場合の日本経済へのインパクトについて考えてみましょう。
株式市場の需給改善
まず大きいのが株式市場への影響です。
・年間数兆円規模の新規買い需要
・TOPIXのガバナンス改革に追い風
特にTOPIX採用銘柄など大型株にはプラスとなりそうです。
ただし、原資が日銀ETFの売却だった場合は往って来いとなりますが笑
日銀ETFの処分は影響が大きすぎるため、その受け皿として今回の話がでているという可能性もありそうですが。
スタートアップ資金の厚み
政府系LP参入でVCファンド規模が拡大し、ユニコーン創出確率が上昇という可能性もあります。
ただし、政府系のベンチャーファンドはうまく行っているとは言い難いですけどね・・・
金利・為替への波及
金利や為替への影響も当然あります。
特に運用原資を米国債売却とするなら為替への影響はかなりありますね。
ただし、米国債の金利はトランプ政権の弱点の一つとも言われていますので、トランプ関税を含めて駆け引きとなりそう。
国際的プレゼンス
ノルウェー基金に次ぐ規模になれば、グローバル投資家の議決権行使で日本の声が強まる可能性もあります。
GPIFと合わせれば日本の影響力はかなり大きくなりますね。
投資家・企業・個人への影響
個人投資家にも当然影響はあります。
| ステークホルダー | 想定メリット | 想定リスク | 今からできる対策 |
|---|---|---|---|
| 個人投資家 | 株式市場のリスクプレミアム低下で資産形成チャンス拡大 | 市場に追随し過剰リスクを取る可能性 | 積立NISA・iDeCoで長期分散継続、TOPIX採用銘柄に投資 |
| 企業経営者 | 政府系ファンドからの直接出資・社債需要 | ガバナンス要求の高まり | 情報開示・IR強化 |
| 機関投資家 | 共投資機会・ESG協調エンゲージメント | 競合による利回り低下 | 差別化戦略(オルタナティブ・インパクト投資) |
| 政策担当者 | 財源多様化・社会保障負担緩和 | 政治介入で失敗すれば批判集中 | 独立ガバナンスの法制度整備 |
まとめ
今回は「日本版政府系ファンド創設で株式市場への影響は?株価上昇に期待」と題して日本版ソブリン・ウェルス・ファンドについて考えてみました。
日本版ソブリン・ウェルス・ファンドは「財政再建+成長投資」の二兎を追う壮大なプロジェクトとなります。
成否の鍵は【①長期分散】【②低コスト】【③独立ガバナンス】の3点
GPIFの成功体験を踏襲しつつ、スタートアップ投資などのビジョンも欠かせません
まだ公明党の一公約に過ぎませんので実現の可能性はわかりませんが、もし現実のものとなるなら「オルカン」や「S&P500」だけでなく日本株の積立投資で市場の長期成長を取り込むということも検討してみても良いかもしれませんね。