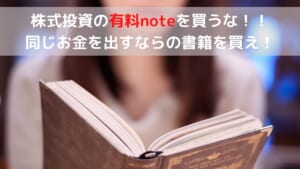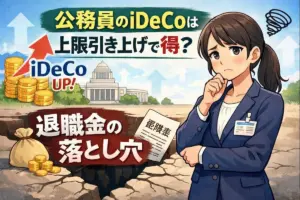「もっと稼がなきゃ、増やさなきゃ」「老後が不安だから貯めなきゃ」。気付けば“いつか”のためにお金を蓄えること、お金を増やすこと自体が目的になっていませんか?
特に株式投資界隈に多い気がします。
私も元々そのタイプだったのですが、最近考え方が大きく変わりました。
『DIE WITH ZERO』という本を読んでからです。
著者ビル・パーキンスは、「人生のゴールは“お金を残す”ことではなく“体験を最大化する”ことだ」と説きます。
昔から「天国にお金は持っていけない」といいますしね。(地獄の沙汰も金次第という言葉もありますが)
本記事では同書のエッセンスを日本のデータと最新研究を交えながら噛み砕き、「全財産使い切る=豊かな人生」を実現する実践ステップを紹介。
“お金”“時間”“健康”の3資源を最適配分し、“ゼロで死ぬ”までの方法について検討してみます。
なぜ今“DIE WITH ZERO”が注目されるのか
まずは今回の話の前提となるDIE WITH ZEROの内容を見ていきましょう。
DIE WITH ZEROの基本メッセージ
DIE WITH ZEROで言いたいことをかなり簡単にまとめると以下のとおりです。
・お金は目的ではなく“人生経験”というリターンを生む手段
・体験は“記憶配当”を生み、時間とともに価値が複利で高まる
・死ぬ瞬間の通帳残高をゼロに近づけることが、人生効用の最大化
DIE WITH ZEROの9つのルール
具体的にはDIE WITH ZEROでは以下の9つのルールが示されています。
| ルール | 具体的アクション例 |
|---|---|
| ポジティブな人生経験を最大化せよ | “今年のバケットリスト”を毎年更新 |
| 経験への投資は今すぐ始めよ | 20代から旅行・留学に資金を振り向ける |
| ゴールはゼロで死ぬこと | 遺産ではなく「生前贈与+経験」を設計 |
| 使えるツールはすべて活用 | 社会保険・年金・投資の複利を組み合わせ |
| インパクトが大きい時に子ども・慈善へ渡す | 子どもが独立前に教育資金を贈与 |
| オートパイロットで生きるな | 5年ごとに“人生決算”を行う |
| 人生を“季節”で区切れ | 体力がある30代までにバックパッカー経験 |
| 資産拡大に“潮時”を設けよ | 60歳で運用リスクを段階的に縮小 |
| 失うものが少ない若いうちに大胆に挑戦 | キャリアチェンジ・起業は40代前半までに |
あなたが30歳で行った世界一周の思い出は、60歳になっても語れる“配当”を生みます。
詳しいニュアンス等は実際に読んでみることをおすすめします。
コロナ後に加速した“貯め込み”
総務省の家計調査によると、2人以上世帯の平均貯蓄残高は2024年に1,984万円と過去最高。
貯蓄は積み上がるのに、使う時間=健康寿命は有限。
お金が余るリスクは、老後資金不足と同じくらい深刻なんですよ。
自分が亡くなるときには子どもは高齢者
ちなみに令和5年簡易生命表では平均寿命が男性81.09年・女性87.14年。
子どものために財産を残すと言う方も見えますが、平均寿命くらいまで生きると自分が亡くなるころには子供は自立して中年以降です。
下手したら子供も高齢者だったりするんですよ・・・
高齢者で大金をもらっても・・・ってのが正直なところでしょう。
貯蓄に回るだけがオチです。

日本人の貯蓄・寿命データで読む「使い切る」現実味
それでは実際使い切るという話になったときに現実味はあるのでしょうか?
以下の点を考えてみてください。
貯蓄ピークは60代後半
定年前後で資産額が最大化する一方、経験価値は体力低下と反比例します。
若い頃の経験と高齢になってからの経験では同じ内容でも価値が大きく違うんんですよ。
寿命と健康寿命のギャップ
平均寿命は延びても、健康寿命との差は男性8.7年・女性12.1年前後と言われます(厚労省統計より試算)。
つまり、実際に元気で経験できる期間は意外と短いということです。
高齢者の“使い残し”問題
金融資産が最も多いのは70代以上。
しかし消費額は現役世代の7割弱。
“老後に取っておく”だけでは体験の旬を逃し、お金の効用が急減します。
お金と幸福度の最新エビデンス
2023年に発表された行動経済学の創始者として知られるカーネマンとキリングスワースの共同研究では、
「収入が増えるほどウェルビーイングは上がり続けるが、増加率は逓減する」
つまり、ある程度まではお金が幸福を買いますが、お金→体験変換の効率を意識しないと、「ただ数字が増えるだけ」になりがちということです。
お金があるから幸せってわけでもないんですよ。
以前、残クレアルファードの話を書きましたが、貯金はないけどいろいろな経験を繰り返す残クレアルファード人の方が、お金をためていく人よりも幸福度は高いのではないか?という話もあったりしますね・・・

全財産を使い切る3ステップ実践法
それでは全財産を使い切る方法を具体的に見ていきましょう。
ステップ1:ライフイベントを“タイムバケット”化
DIE WITH ZEROではツールとして、本書では、タイムバケットを紹介しています。
まず、年齢を5年ごとに区切り、死ぬまでに実現したいと思っているリストを書き出し、それぞれを実現したい時期のバケットに「やりたい体験」「必要資金」をマッピング
子育て・介護など不可避コストも同時に配置
ステップ2:体験のROI(記憶配当)を数値化
次にやりたい体験を数値化します。
例えばこんな感じですね。
| 体験 | 費用 | 満足度(10点) | 記憶配当年数 | ROI* |
|---|---|---|---|---|
| 30歳でバックパッカー | 100万円 | 9 | 50年 | 4.5 |
| 75歳で豪華客船 | 300万円 | 7 | 5年 | 0.12 |
*ROI=(満足度×配当年数)/費用
この計算式でわかるように若いうちに経験をしたほうが記憶配当が高いためROIは高くなります。
こうすることで人生のどの時期にその体験を行ったほうがよいのかが見えてくるはずです。
ステップ3:キャッシュフロー&リスクマネジメント
あとは実際のお金の話です。
以下の点を考える必要があります。
長寿リスク=公的年金+終身年金でヘッジ
早死リスク=生命保険で家族を守る
インフレリスク=株式・REIT等で成長取り込み
使い切り計画=60代で“資産ピーク”到達をゴール設定
あとは生前贈与・寄付などの計画もしておきたいところ。
税金・保険・相続を味方に
その際に税金面、保険などをうまく使うことも重要ですね。
特に生前贈与の税金面のルールは必ず意識しておきたいところです。
| 分野 | ポイント | キーワード |
|---|---|---|
| 税金 | 教育資金一括贈与非課税1,000万円枠を活用 | 生前贈与 |
| 保険 | 長寿年金(変額終身年金型)で“使い切り”をサポート | 長生きリスクヘッジ |
| 相続 | 遺言信託+家族信託で“争続”コストを削減 | 相続分割の柔軟化 |
お金を使い切る戦略は、「使う時期」「残す相手」を先に決めることが重要。
エンディングノートなども用意しておくことが重要です。
よくある誤解Q&A
この手の話をすると誤解されることも多いのでよくある話を見ておきましょう。
資産ゼロで死ぬなんて無謀
リスク管理(保険・年金)を前提に“最適残高ゼロ”を目指す感じですね。
実際にきれいにゼロになるのは難しいと思いますが。
子どもに遺産を残さないのは不孝
前述したように平均年齢まで生きていれば、そのときの子どもはすでに自立して高齢者です。
早死リスクを考え生命保険などでヘッジをして、インパクトが大きい若い時期に生前贈与する方が合理的。
投資しないと資産が減る
目的は資産最大化ではなく体験最大化です。
資産最大化を目指すならずっと投資をしていた方がよいですが、複利を考えると亡くなる時が資産の最大の状況という不合理な状況になります。
それよりも使う方にフォーカスしたほうがよいという考え方です。
必要利回り=支出計画次第
まとめ
今回は「死ぬまでにお金を使い切るという考え方 — “DIE WITH ZERO”で人生のリターンを最大化する」と題して死ぬまでにお金を使い切る話を見てきました。
天国にお金は持っていけません。使わずに貯め込むのは、燃料タンクを満タンにしたまま旅を終えるようなものです。
“全財産使い切る”人生をデザインしていくという考えもありだと個人的には思います。
私の考え方を大きく変えたこちらの本。興味を持った方はぜひ手にとって見てください。