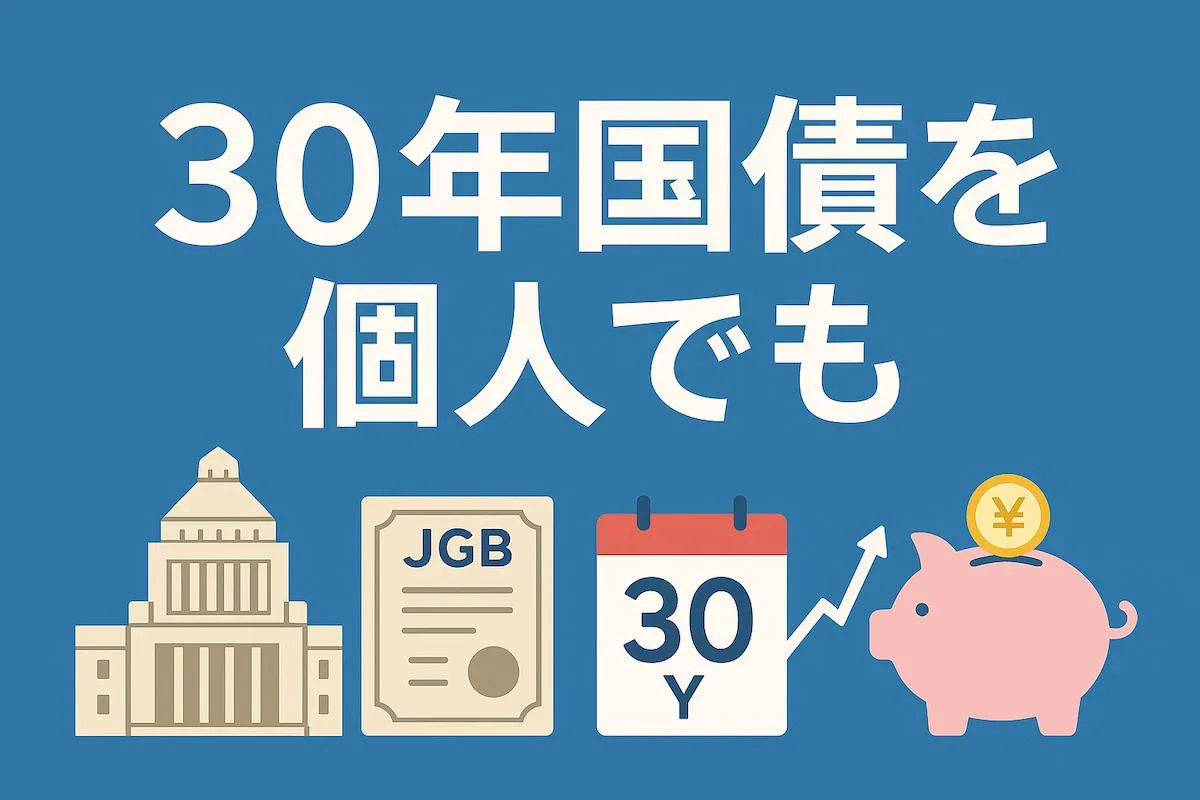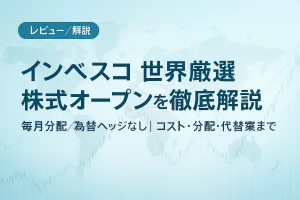最近、30年国債の利回りがかなり高くなっています。
2025年9月16日時点で3.23%あるんですよ。
そんな30年国債。買いたいと思っても個人向けに販売はされていないんですよ。(既発は個人でも買えるケースも)
しかし、買える方法があります。
「iFreeHOLD 日本国債(JGB2056)」という投資信託を買えば間接的にではありますが購入できるのです。
さらに投資信託のメリットである100円から1円単位での購入が可能。(通常、国債は5万円単位)
今回はiFreeHOLD 日本国債(JGB2056)について詳しく見ていきましょう。
iFreeHOLD 日本国債とは何か
それでは具体的にiFreeHOLD 日本国債についてみていきましょう
単一銘柄を“満期まで”保有する投資信託
iFreeHOLD 日本国債(JGB2056)は、設定当初に残存期間が30年程度の固定利付日本国債“1銘柄”に投資し、信託期間内はそのまま保有する設計です。
分散ではなく集中。
投資家は小口で「満期に向け額面100へ収れんする債券価格の軌跡」に乗るイメージ、と大和アセットは説明しています。
債券は満期まで持てば元本が返ってくるというメリットがあります。(発行体に問題が生じなければ)
しかし、複数の債券を買う投資信託になると金利が上がっている局面では価格が下がってしまうことが多く、そのメリットを消してしまっていました。
そのため、債券を買うなら投資信託よりも、直接債券を買う人が多かったです。
こちらの商品は、個人向けには発売されていない超長期の国債を1銘柄買って、そのまま保有するということですからそのデメリットを消してくれます。
いわゆる債券持ち切り運用型というやつですね。
参考:当シリーズのコンセプトは「債券投資をもっと自由に。最後まで1つの債券を保有し続けるシンプルな投資戦略」。
投資対象と“いま”の参考利回り
現在の投資対象は2056年3月20日償還の超長期日本国債(40年・第9回)。
2025年9月12日時点のクーポン0.4%/利回り3.05%/価格47.62円が、同ファンドの「参考指標」として掲示されています(ファンド自体の成績ではない)。
信託報酬等のスペック
信託報酬:年0.1265%(税込)
信託財産留保額:0.05%(売却・換金時に基準価額から控除、ファンド内に留保)
購入時手数料:主要販売会社では徴収なし(現時点)
基準価額・純資産:2025/9/16 基準価額10,071円、純資産3.55億円(設定間もないため小型)
決算:毎年9月20日/分配方針は成長重視、分配なしもあり得る(初回計算期間は2026/9/20まで)
国債を買って保有しているだけにしては信託報酬が高い気もしないでもないですが、債券の投資信託全体でみれば低めなコストとなっています。
コストは保有期間のトータルで利回りを押し下げる点に留意が必要です。
NISA成長投資枠対象
本ファンドはNISA成長投資枠の対象です。
100円から1円単位での取引が可能で、「超長期国債の値動き」を少額・非課税枠で取りに行けます。
SBI証券・楽天証券・マネックス証券など主要ネット証券で取り扱いがあります。
30年国債の金利推移と注意点
30年・40年といった“超長期ゾーン”の金利は、景気・インフレ期待や需給(発行計画・年金・生損保の買い姿勢)に鋭敏です。
昨今はかなり高い利回りで推移しています。
2025年5月末には財務省が超長期の発行減額観測と報じられた局面で、30年利回りが一日で約▲0.185%低下(国債価格上昇)するなど、ボラティリティは比較的高め。
投資タイミングの巧拙が基準価額に与える影響は小さくありません。
なお、日次の主要年限金利は財務省の“国債金利情報(CSV)”で公開されており、30年の長期的な推移確認に役立ちます。
ポイント:利回りが上がる=価格は下がる。残存が長いほど下落幅(上昇幅)も大きい
超長期はデュレーションが長く、コンベクシティも大。金利低下局面では価格が大きく戻りやすい一方、上昇では含み損に耐えられるかが勝負どころです。
直接「30年・40年国債」を個人で買うのと何が違う?
投資信託で国債を買うのと直接買う場合の比較を考えてみましょう。
最低投資額・売買のしやすさ
個人向け国債として30年、40年ものは発売されていませんが、店頭では既発の30年・40年国債を個人でも買うことは可能です。(ネット証券等でもたまに見かけます)
しかし、国債は額面5万円単位など最低ロットが重たいのが一般的。
一方でiFreeHOLDは100円から1円単位。
税制(NISAの非課税効果)
NISA口座なら分配金・譲渡益ともに非課税。
対して、特定口座で債券を直接保有すると利子・譲渡益ともに20.315%課税。
同じ金利でも手取りが変わるため、NISA枠の有効活用は実務上の差になります。
超長期の国債と非課税期間が無制限になった新NISAは相性が良いですね。
コスト・スプレッドの透け方
ファンドは信託報酬+解約時0.05%の留保額がある一方、基準価額(+留保額)が売買価格として明確。
個別債の店頭売買は提示スプレッドや手数料が価格に内包され見えづらいことも。
“見えるコスト”か“見えにくいスプレッド”かの選択でもあります。
ただし、長期で持つ場合には信託報酬分だけ投資信託が不利にはなりそうです。
個人向け国債(変動10/固定5・3)との使い分け
個人向け国債は「変動10年/固定5年/固定3年」のみ。
30年“個人向け”は存在しません。
個人向け国債は元本額面100で中途換金制度あり(所定の控除あり)で、価格変動リスクを極小化した商品です。
利回りは現状1%程度となっており、30年ものと比較すると低くはなっています。
利回りが低くても安定を取りたい場合は個人向け国債がおすすめですね。

債券投資のリスクを腹落ちさせておこう
国債だから安心と考える方も多いでしょう。
実際そうなのですが、知っておいた方がよいリスクもあります。
途中の含み損/含み益は大きい
超長期は金利の動きで価格インパクトが非常に大きいです。
途中では大きな含み損(含み益)などが生じている可能性もあるんですよ。
満期まで持てば元本は理屈として正しいですが、途中解約なら評価差は実現します。
流動性リスク
解約集中や市場急変時には期待価格で売れない/解約停止・支払遅延の可能性が明示されています。
超長期の板厚が薄い局面は現実に起こり得ます
再投資リスク
クーポン(0.4%)の再投資収益は利回りにわずかに効きます。
ファンドコスト控除後の実効利回りを常に意識しましょう。
よくある誤解Q&A
この商品は誤解が多い感じですのでありそうな話をみておきましょう。
Q1:「満期まで持てば確実に年3%で回る」?
A:いいえ。掲示の3.05%は“対象債の参考”で、ファンドの実行利回りではありません。
信託報酬(0.1265%/年)等で投資家の取り分は目減りします。
本ファンドの初回計算期間は2026/9/20までなので、今の時点での実際の利回りは不明です。
Q2:「個人向け国債とどちらが安全?」
A:元本価格が動かない個人向け(変動10/固定5・3)の方が価格面の安定性は高い。
iFreeHOLDはブレは大。
Q3:「途中で売っても大丈夫?」
A:信託財産留保額0.05%がかかり、その時点の基準価額で売却。
金利上昇時は損失が出る可能性。
解約集中や市場急変時の流動性リスクも目論見書に明記。
まとめ
今回は「30年国債を個人でも。iFreeHOLD 日本国債で超長期利回りを最大化」と題してiFreeHOLD 日本国債についてみてきました。
NISAで“超長期の金利低下リスクプレミアム”を狙いたい方や、他の債券・株式との逆相関狙い、最後まで持ち切る覚悟がある方には向く商品です。
ただし、コスト・留保額・流動性・途中解約リスクを理解し、金利見通しに過度に賭けない。
個人向け国債や短期金利商品と役割分担をするのがおすすめです。