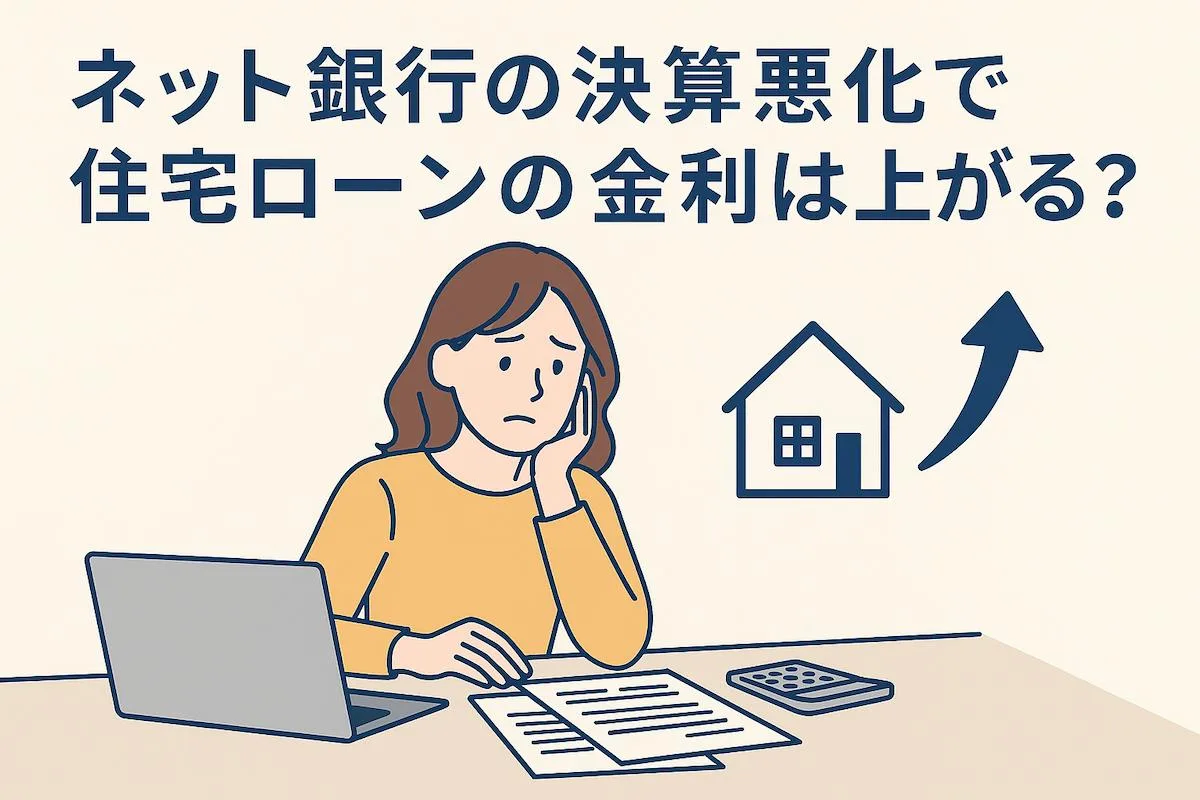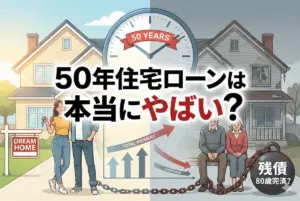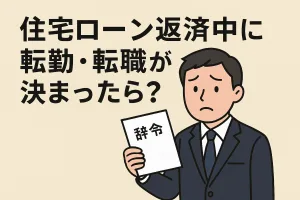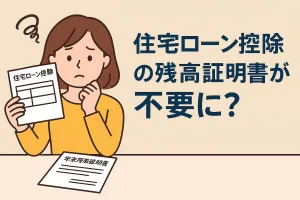2025年に入り、ネット銀行を中心に四半期決算の減益が目立ちます。「金利のある世界」では銀行は儲かるはず……という常識に反して、なぜネット銀行の収益が鈍っているのか。
そして、それは住宅ローン金利(とくに変動金利)にどう跳ね返るのか。
今回はネット銀行の減益の理由、短期プライムレート(短プラ)と変動金利の連動、見直し時期、今後のシナリオまで整理していきます。
ネット銀行の決算はなぜ悪化しているのか
それではなぜネット銀行の決算が悪化しているのかから見ていきましょう。
住宅ローン依存モデルの逆風
主要ネット銀行や流通系銀行の2025年1Q決算は減益が相次ぎました。
背景にあるのは、収益柱だった住宅ローンの伸び悩みとマージン圧縮です。
金利上昇で本来は利鞘が広がるはずが、預金の調達コストの上昇や、新規貸出の競争激化・インフレによる住宅価格上昇による需要減速が同時進行したためです。
調達コストの上昇という新常態
特に大きいのが預金の調達コストですね。
マイナス金利の時代との大きな違いとなってきています。
2024年夏以降、普通預金や定期預金の金利引き上げが相次ぎ、預金コストが構造的に上昇。
都市銀・信託銀も短期プライムレートの引き上げが続きました。
マイナス金利でお金の調達をしまくって低金利の住宅ローンを広く提供するというビジネスモデルは大きく変えないといけない時期に来ているのでしょう。
個別決算の実例
それでは実際の各ネット銀行の決算状況をみていきましょう。
ソニー銀行
2026年3月期1Qは経常利益2,982百万円(前年同期比▲51.3%)。
銀行部門の経常利益は▲51.7%と大幅減。
住信SBIネット銀行
2026年3月期1Q(2025/4–6)は経常収益 413億円(前年同期比+26.0%)/経常利益 78.6億円(同▲13.2%)
四半期純利益 55.4億円(同▲10.5%)。増収減益
auじぶん銀行
2026年3月期1Qの経常利益2,231百万円(前年同期5,907百万円)と減益。
PayPay銀行
2026年3月期1Qは経常利益が前年同期比で減益
楽天銀行
2026年3月期1Q(2025/4–6)は経常収益 575.0億円(前年比+40.8%)/経常利益 239.4億円(+56.8%)/親会社株主に帰属する四半期純利益 168.3億円(+54.1%)とこちらは好調。
楽天銀行はもともと住宅ローンにあまり力を入れてなかったんですよ。
それでも変動中心の自社住宅ローンのローン手数料は伸び悩み、一方でフラット35(固定)取扱い増で補う構図となっています。
住宅ローンの変動金利はなにに連動しているのか?
多くの方が興味をもっているのが住宅ローンの変動金利の動向です。
変動金利はなにに連動しているのかご存知でしょうか?
変動金利=短期プライムレート連動が原則
多くの銀行の変動金利は「短期プライムレート」に連動します。
「短期プライムレート」とは
銀行が最優良の企業(業績が良い、財務状況が良いなど)に貸し出す際の最優遇貸出金利(プライムレート)のうち、1年以内の短期貸出の金利を「短期プライムレート」(略して「短プラ」)といいます。
出典:SMBC日興証券 初めてでもわかりやすい用語集 より
短期とは1年以内、プライムは「最優遇」を示します。
つまり、金融機関が優良な貸付先に1年以内の短期貸付をする際の金利ってことですね。
なお、この「短期プライムレート」は日銀の政策金利にほぼ連動する形となっています。
そして短期プライムレートに少し上乗せした金利で各金融機関が住宅ローンの基準金利を設定します。
商品で言えば基準金利が定価です。
そこから独自に定める優遇金利(値引きみたいなもの)である金利引下げ幅を引いて、借入金利を提示・決定しているのです。
一般に4月・10月の半期ごとに住宅ローンの適用金利へ反映されます
住信SBIネット銀行の例
例えば先日、NTTドコモに買収された住信SBIネット銀行の住宅ローン変動金利は短期プライムレートを基準に、毎年4/1・10/1に適用金利を見直しとなっています。
住信SBIネット銀行の短期プライムレートは2.175%(2025年4月1日適用)。
基準金利は年3.275%(2025年9月時点)
住宅ローン金利は年0.698%~年3.275%となっています。(2025年9月時点)
短期プライムレートに連動しない銀行も
ただし、ネット銀行やJAなど短期プライムレートではなく独自ルールで決定している金融機関も結構あります。
ソニー銀行の例
例えばソニー銀行では以下の独自ルールになっています。
- ソニー銀行では、市場での金利スワップ手法を活用し、毎月基準金利を決定します。
- ソニー銀行で毎月決定する基準金利は、資金コスト(住宅ローンの貸し出し資金をソニー銀行が調達するために必要なコスト)や営業コスト、および収益を加味して決定されます。最も大きな変動要因は資金コストで、このコストは変更日前数ヶ月における銀行間で取引されている金利の動向や、国債の利回りの動向など、該当する期間の指標と連動して上下します。
出典:ソニー銀行 金利変動リスクなどに関する説明書
なお、ソニー銀行独自の判断で決定している基準金利が2.307%。(2025年9月時点)
住宅ローン金利は年0.797%~年2.307%となっています。(2025年9月時点)
楽天銀行の例
楽天銀行も独自ルールですね。
新規ご融資基準金利は、市場金利等をもとに楽天銀行が決定し、毎月15日以降に、翌月分の基準金利を楽天銀行ウェブサイトでお知らせします。
出典:楽天銀行 商品詳細説明書
なお、楽天銀行独自の判断で決定している基準金利は1.643%。(2025年9月時点)
住宅ローン金利は年0.993%~年1.643%となっています。(2025年9月時点)
その他のネット銀行の金利決定ルールはこちらの記事でまとめております。合わせて御覧ください。

短期プライムレートは今どうなっているか
それでは短期プライムレートはどうなっているのでしょう?
日銀の政策転換と短プラの上昇
2024年に日銀がマイナス金利を解除、その後政策金利は0.5%程度へ。
主要銀行の短期プライムレートは1.475%→1.625%(2024/9)→1.875%(2025/3)へと少しずつ上昇。
直近の住信SBIネット銀行の短プラは2.175%(2025/4)と上昇基調が続いています。
ちなみに短プラは2009年以降下記の数字でほとんど変わっていなかったんですよ。
最頻値:1.475%
最高値:1.725%
最低値:1.475%
それがマイナス金利を解除したことで大きく流れが変わった形ですね。
4月・10月の見直しタイミング
短プラの改定が複数回あっても、住宅ローンの適用金利は4/1・10/1にまとめて反映される設計が一般的です(銀行により異なる)。
固定金利は「長期金利」に左右されやすい
ちなみに固定金利は10年国債利回りなど長期金利に連動。
2025年夏には新発10年国債が1.6%台に達する場面もあり、固定は変動金利よりも先行して上がりやすい地合いです。
今後のシナリオ:変動金利は上がるのか
それでは今後変動金利はどうなっていくのでしょう?
シナリオA:年内据え置き
政策金利が0.5%程度で維持されれば、短プラも当面は現状水準がベース。
2025年10月の見直しでは、4~9月の短プラ改定を集計して反映。
大幅な上げ材料が乏しければ、据え置き~小幅上昇の蓋然性。
ただし、前述のようにネット銀行の収益が悪化していることから、短プラではなく独自のルールで金利を決めているところは上げてくる可能性があります。
シナリオB:年内に追加利上げ
エコノミスト調査では2025年Q4に追加利上げの見方が優勢(あくまでコンセンサス)。
実施されれば短プラのさらなる切り上げ→2026年4月の適用金利へ反映がメインシナリオとなります。
結論:短期は「10月見直し」で小幅上振れの余地、中期は「次の利上げの有無」が鍵。銀行ごとに連動指標や反映ルールが異なる点にも要注意
変動金利が上がると家計インパクトはどれくらい?
例えば35年・3,500万円・元利均等の場合に変動金利があがったらどれくらいのインパクトになるのかをシュミレーションしてみました。
以下は金利以外の条件一定とした概算です(返済方式・優遇幅・団信等で実額は変わります)。
- 金利0.70% → 月々約94,000円
- +0.25%pt(0.95%)で+約4,000円/月
- +0.50%ptで+約8,100円/月、+1.00%ptで+約16,600円/月
それなりのインパクトとなりますね。
なお、変動金利には5年ルール/125%ルール(多くの銀行)があります。
しかし、返済額の変化は抑えられても利息負担は増えうる点に注意
詳しくはこちらの記事を御覧ください。

乗り換えた方がよい?後悔しない“次の一手”
それでは多くの方が悩まれる金利が上がる期間の次の一手を考えてみましょう。
金利タイプの再点検
金利による違いはあらかじめ確認しておきましょう。
- 固定:先に上がりやすいが支払いの確実性を買う選択。返済比率が高め・家計のクッションが薄い世帯に向く。
- 変動:短期は据え置きの可能性も、中期は政策金利次第で上振れ余地。繰上げ余力があり、リスク許容度が高い世帯向き。
- ミックス(固定+変動)で心理的損失回避と金利上振れのリスク分散を両立。
イメージとしては変動金利は金利が上がるリスクを個人が取る。
金融機関のリスクは低いので、その分金利は安い。
固定金利はリスクを金融機関が取る。
個人のリスクは低い。
その分金利が高いという感じなんですよ。
ですから変動金利で借りるなら金利が大きくあがるリスクが爆発しても対処できるように、資金を確保するなど準備はしておく必要はあると思いますね。
「見直し月」前後の行動
10月見直し前後は、金利タイプ変更・固定特約・借換えの打診を先回りで。
審査~実行に数週間かかるのが通常。
借換えの判断軸
借り換えの検討もよいでしょう。
ただし、考えないといけないポイントがあります。
手数料です。
同じ銀行で変動から固定への切り替えでも11,000円くらいとられるところが多いです。
また、銀行を変えて借り換えしようとすると事務手数料+登記等の手数料がかかりますのでそのあたりも勘案して検討しましょう。
諸費用込みの実質金利差が0.3~0.5%pt以上なら初期費用回収のメドが立ちやすいと思います。(期間・残高次第)。
フラット35等の全期間固定金利は、長期金利が落ち着いた局面を待って検討しましょう。(すでに先行して高くなっている)
生活防衛としてのキャッシュ設計
半年~1年分の生活費バッファの確保。
こまめな部分繰上げ返済で利息負担を削るのも有効です。(金利上昇局面に強い)。

よくある誤解を整理
次によくある誤解を整理しておきましょう。
ネット銀行の決算が悪い=金利が上がる?
決算が悪いから金利が上がると短絡的に考えるのは禁物です。
多くの銀行は短プラの動き+自社の優遇幅調整で金利を決めます。
短プラ自体は政策金利連動となっています。
ですから銀行の四半期の業績よりも、政策・市場の持続的なトレンドの方が影響力は大きいです。
ただし、短プラの連動ではなく、独自ルールのネット銀行などでは、業績によっては変更になる可能性があります。
ソニー銀行などは「資金コストや営業コスト、および収益を加味して決定」と書いてありますしね。
また、短プラ連動の銀行でも業績が悪ければ、新規客の優遇幅を縮小する可能性はありそうです。
変動は“毎月”上がる?
多くは4/1・10/1の年2回。
ただし銀行により仕様差があり、商品ごとに連動指標も異なりうる。
固定はもう手遅れ?
固定は長期金利次第。
直近は上昇圧力が強かったが、政策や国債買入方針・海外金利で上下します。
今後も政策金利があがることを予想するならそのタイミングで固定に乗り換えるのも手です。
まとめ
今回は「ネット銀行の決算悪化で住宅ローンの金利は上がる?——変動金利の見直し時期と短期プライムレートの行方」と題してネット銀行の決算悪化と住宅ローンの金利について考えてきました。
金利の動向は専門家でも間違えるまくる予想は困難なものです。

金利が上がっても大丈夫なように準備をしておくことが大事でしょう。
とくに短プラ連動でない、ネット銀行で変動金利の住宅ローンを借りている場合は決算状況を見ると少し怖いところがありますね。
心配な方は借り換えを検討するのも一つの手でしょう。