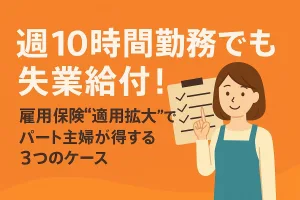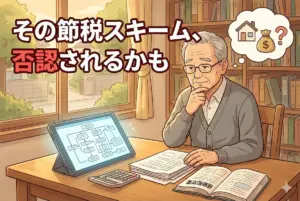2023年10月から様々な分野で変更が入ります。
かなり重要な変更もありますので知らないことが無いようにチェックしておきましょうね。
インボイス制度の導入
まず、2023年10月からの変更で最も大きいと思われるのがインボイス制度のスタートです。
簡単に言えば消費税のルールが厳しくなるんですよ。
大きな影響を受けるのは事業者ですが、間接的に消費者も影響を受けることになります。
今までの消費税のルール「帳簿保存方式」
事業者が納める消費税額の計算方法をかなり簡単に説明すると以下の形となっています。
お客さんから預かった消費税ー自分たちが払った消費税=納付する消費税(本則課税の場合)
例えば10万円で商品を仕入して(消費税8,000円)、20万円で商品を販売(消費税16,000円)で販売したとすると16,000-8,000=8,000となり、8.000円分消費税を納税することになります。
上記計算の「自分たちが払った消費税」のことを仕入税額控除といいます。
いままで仕入税額控除は「帳簿保存方式」という帳簿及び取引先が発行した請求書の保存をしていることが要件となっていました。
簡単に言えば、請求書などをちゃんともらって保存しておいて、帳簿にもちゃんと記帳しておきなさいってことですね。
その「帳簿保存方式」がインボイス方式に変更になるのです。
つまり、仕入税額控除のルールが変わるよってことですね。
これからの消費税のルール「インボイス方式(適格請求書等保存方式)」
インボイス制度が導入されると上記の仕入税額控除のルールが変わります。
仕入税額控除を受けるためには帳簿と適格請求書(インボイス)の保存が必要となります。
また、適格請求書(インボイス)の発行及び副本(控え)の保存が義務付けられます。
さらに、適格請求書(インボイス)にはインボイス専用の番号である事業者登録番号、軽減税率対象品目である旨、適用税率、税額の記載が義務付けられます。
今までのルールも請求書の保存が義務でした。
何が変わっているのかと言えば簡単に言えば請求書のルールがより厳しくなったということと、請求書を発行する側も発行及び副本の保存が義務となったことです。
具体的には以下のような請求書が必要となります。

インボイス制度:適格請求書
出典:国税庁「消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます」より
インボイスは課税事業者しか発行できない
インボイス制度最大のポイントは適格請求書(インボイス)の発行は課税事業者しかできないという点にあります。
適格請求書(インボイス)を発行するためには事業者登録番号が必要です。
しかし、事業者登録番号は課税事業者にしか発行されません。
つまり、免税事業者は適格請求書(インボイス)の発行ができないのです。
インボイスの発行ができないとどうなる?
それでは適格請求書(インボイス)の発行ができないとどうなるのでしょう?
簡単に言えば取引先が仕入税額控除できなくなり、取引が終わる可能性が大ってことです。
例えば前述した例を元に考えて見ましょう。
10万円で商品を仕入して(消費税8,000円)、20万円で商品を販売(消費税16,000円)で販売
16,000-8,000=8,000となり、8,000円分消費税を納税することになります。
仕入れ先が適格請求書を発行してくだされば上記の納税となります。
しかし、仕入れ先が適格請求書(インボイス)の発行できない免税事業者ならばこうなります。
16,000-0=16,000となり、16,000円分消費税を納税することになります。
つまり、免税事業者と取引をすると消費税分損することになってしまうんですよね。
そうなれば普通は免税事業者と取引をやめようか、という話になる可能性が高いでしょう。
消費税事務への対応
もう一つが消費税事務への対応です。
そもそも消費税の納税事務がかなり大変ですから一定の規模の事業までは納税を免除するという目的で免税事業者となっていたのです。
その事務を今後は対応せざる得なくなります。
適格請求書(インボイス)の発行はもちろん必要となりますし、保存も必要となります。
受け取った適格請求書(インボイス)の保存や経理処理もかなり大変となるでしょう。
基本的に仕訳も税率ごとの区分が必要となりますしね。
また、すぐに実施されるのかわかりませんが、インボイス制度を骨抜きにしないために簡易課税を廃止するという動きもあるようです。
その辺りを考えると事務作業はかなり煩雑化することが確実なのです。
もともと課税事業者となっているフリーランス、個人事業主、副業の方であってもこの点はかなり大きな影響かもしれません。
最近はfreee![]() やマネーフォワードクラウド
やマネーフォワードクラウドといった会計をAIを使ってかなり簡単にするサービスも出ていますのでその辺りを活用していくしかないでしょうね。
消費者も間接的には影響を受ける可能性
まず、仕組みだけ考えれば消費者はインボイスの導入で直接の影響はありません。
インボイスが導入されても消費税率が変わるわけではありませんからね。
もらえるレシート等の書類が詳細に書かれるようになるってことくらいです笑
しかし、間接的には影響を受ける可能性があります。
まず、多くの免税事業者は今まで納めなくてもよかった消費税を負担せざる得なくなるでしょう。
今まで納めていなかった消費税は利益部分であったので、それがなくなります。
免税事業者がインボイス導入前と同様の利益を得るためには値上げせざる得なくなります。
値上げすれば当然消費者にも影響が出てくるのです。
また、免税事業者以外もインボイスが始まると多くの事業者の事務負担が増えます。(特に本則課税事業者)
事務負担が増えればそれは価格に反映される可能性があります。
つまり、これも値上げ圧力となりかねないのです。
インフレで様々な価格が値上がっている最中ですが、インボイスの導入でそれが加速する可能性がありそうです。
ふるさと納税のルール変更
次はふるさと納税です。
ふるさと納税の返礼品ルールが2023年10月から再び改悪されることになりました。
これにより返礼品のお得度が少し落ちることになりそうです。
費用割合に受領書発行費なども含める
まず、ふるさと納税に使う経費は「寄附金額の5割以下」とするとされている基準が設けられています。(うち返礼品は寄付額の3割以下)
その割合計算にカウントされる経費が増えることになりました。
具体的には今まで返礼品の価格(調達費)や送料、広報費などが対象でしたが、今後はワンストップ特例事務や寄附金受領証の発行などの付随費用も含めて計算される事になりました。
これら費用は3.9%くらいとの予想ですから少なからず影響はありそうです。
自治体としては経費を圧縮するか、返礼品の質を落とすという選択となってきますね。
中にはこの手の業務もふるさと納税ポータルサイトなどに外注をしている自治体もあるとのことですから、その場合はかなりの金額となりそうです。
そうなれば当然、返礼品の質がかなり落ちてしまうでしょう。
地場産品のルールが厳格化
次は返礼品の対象となる地場産品のルールがより厳しくなります。
具体的には「加工品の熟成肉」と「精米」です。
ステマ規制のスタート
次はステマ規制です。
ステマ規制とはステマ法とも呼ばれ正式には景品表示法の法改正により「ステルススマーティング」が違反になるということを指しています。
ステルスマーケテイングとは
ステルスマーティングとは広告であるにもかかわらず、広告であることを隠す手法のことを指します。
インフルエンサーなどが広告と告げずに、お金や商品をもらってこの商品良いんですよなんて言ってるのをみたこともあるかたも多いと思います。
それらが景品表示法で規制される形となります。
あらゆる表示媒体が対象
なお、景品表示法は、商品又はサービスについて行うあらゆる表示媒体が対象です。
ですからインターネット上のWEBページ、ブログ、SNS投稿、ECサイトのレビュー投稿、5CHなどの掲示板の投稿などはもちろん対象となります。
また、新聞、テレビ、ラジオ、雑誌などの表示についても対象となります。
今までかなりやばい広告などもありましたが、この規制で減ってくれると良いですね。
規制対象となるのは広告主
なお、今回のステマ法の規制対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)側です。
インフルエンサー、アフィリエイター、ブロガーなどが規制されるわけではなく、広告主が規制対象となるのです。
なお、今回の規制の対象とならないのは以下のような場合です。
まとめ
今回は「2023年10月から変わることまとめ。インボイス、ステマ規制、ふるさとの納税の見直しなど」と題して2023年10月から変わることをまとめてみました。
大きな改正がいくつかありましたね。
また、まだ詳細が発表されていないのでここには載せていませんが、「年収106万の壁」問題を解消すべく、2023年10月より、企業向けに最大50万円の助成金をスタートする旨を表明しています。
情報をキャッチしておきましょう。
お知らせ:You Tubeはじめました。
You Tube「お金に生きるチャンネル」をはじめました。
You Tubeでも少しでも皆様のお役に立てる動画を定期的に発信していきますのでチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。
最後まで読んでいただきありがとうございました。