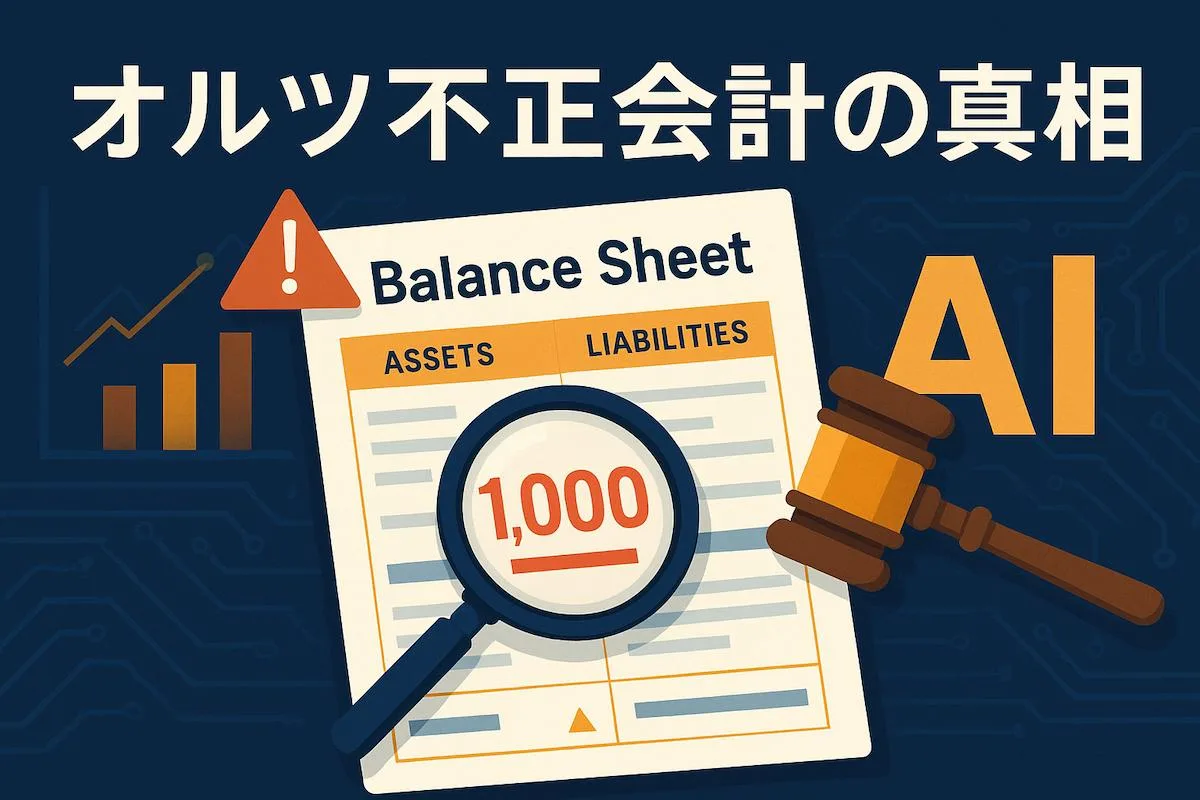「AI銘柄の星」と注目されテレビなどのマスコミで何度も取り上げられていたオルツ(260A)は、上場からわずか半年で“粉飾決算疑惑”の渦中となりました。
2025年4月に第三者委員会を設置した同社は、7月25日に調査報告書を開示し、過去決算の売上高の大半が架空だった事実を認めました。
本記事では▼報告書の要点 ▼3カ月前に公開した筆者の分析記事との答え合わせ ▼投資家として何を学ぶべきかを、専門用語をかみ砕きつつ解説します。
追記:オルツは上場廃止かつ民事再生の申請をしたとの報道です。
詳しくはこちらの記事を御覧ください

オルツ不正会計問題の概要(過去記事のおさらい)
まずはオルツの不正会計問題の概要から見ておきましょう。
※過去記事のおさらいとなります。

不正会計の予兆は決算書にも現れていた。
過去記事では、売上が5年で100倍近く膨張する一方、営業キャッシュフローが恒常的にマイナスである「キャッシュフローと売上の乖離」と「売掛金回転期間」と特定販売パートナーへの集中、広告宣伝費の急増から読み取れた「循環取引の可能性」を指摘し、売上の大幅修正リスクを警告しました
第三者委員会の設置と上場後初の決算延期(2025/4/25)
決算短信の遅延は“最後の赤信号”と表現しましたが、結果的にその通りでした。
株価暴落
株価は570円から大暴落となりました。
第三者委員会調査報告書の主なポイント
それでは実際に発表された第三者委員会の調査報告書の内容を見ていきましょう。
| 期間 | 売上高計上額(B) | 過大計上影響額(A) | 過大計上比率 |
|---|---|---|---|
| 2021/12期 | 9.6億円 | 7.4億円 | 78.2% |
| 2022/12期 | 26.6億円 | 24.3億円 | 91.3% |
| 2023/12期 | 41.1億円 | 37.4億円 | 91.0% |
| 2024/12期 | 60.6億円 | 49.8億円 | 82.3% |
| 累計 | — | 119.1億円 | — |
出所:オルツ「第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」2025/7/25
不正会計の手口の概要
具体的な手口は以下のとおり。
循環取引型の売上水増し
広告宣伝費・研究開発費として資金を外部に流し、広告代理店経由で販売パートナー→オルツへ戻す“資金循環”スキームでした。
つまり、売上と広告宣伝費は架空計上だったということです。
このあたりは決算書上でも「キャッシュフローと売上の乖離」、特定販売パートナーへの集中、広告宣伝費の急増に現れていますね。
AI GIJIROKUの未稼働アカウント計上
実際には利用されていない有料アカウントを受注扱い。
内部統制の形骸化
上場前後に急拡大した取引を社内監査部門が把握できていなかった。
市場へのインパクト
市場へのインパクトもそれなりにありそうです。
監理銘柄(審査中)指定。
東証は同日付で監理銘柄(審査中)指定
PTSで暴落
日経報道も「売上の最大9割が過大計上」と大きく報じ、株価はPTSで前日比▲40%まで急落。
すでに折込済かと思いましたが、これだけ下げるってことは報道が間違えだったとか、たいした問題ではなかったという発表を期待して買ってた人がそれなりにいたのかもしれません。
過去記事の「当たっていた点」「修正が必要な点」
ちなみに過去記事の指摘と比較してみましょう。
| 観点 | 過去記事の主張 | 報告書での結論 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 営業CFの赤字継続 | 売上拡大と乖離=要注意 | 循環取引で実質キャッシュ創出なし | 的中 |
| 売掛金膨張 | 回収リスクを警戒 | 実際に架空販売で回収不能分あり | 的中 |
| 取引先依存 | 特定パートナー依存が高い | 一部販売パートナーが水増し取引の中心 | 的中 |
| 研究開発費の増大 | 投資フェーズと判断 | 研究開発費も“迂回資金”に流用 | 再評価が必要 |
| ストックオプション大量発行 | 希薄化リスクのみ指摘 | オプション発行直後に疑惑発覚→ガバナンス問題 | 再評価が必要 |
研究開発費も迂回資金に使われてたのは想定外でしたが、それ以外は概ねあたっていましたね。
新たに判明した事実とその意味
今回新たに判明した点についてもみておきましょう。
上場申請時の有価証券届出書にも虚偽記載
上場時の有価証券報告書の時点で虚偽記載の可能性が指摘されています。
今後は上場審査の厳格化と引受証券の責任問題に発展する可能性があります。
また、91%を超える売上過大計上を見抜けなかった監査法人シドー、主幹事大和証券の責任も問われる可能性もあるでしょう。
広告宣伝費の98%超が架空循環
成長ドライバーとされたマーケ費が実態を伴わず、事業モデルの根底が崩れる
IRの説明責任
利用企業9,000社突破といった“KPI”が実態を伴わなかったことが露呈。信頼失墜は長期化。
投資家視点で見る今回の教訓
それでは今回のオルツの事例から投資家サイドは学べば良いのでしょう?
営業キャッシュフローと売上の乖離を必ず見る
売上が伸びても現金化できていない場合は粉飾の初期シグナル。
損益計算書だけでなく、キャッシュフロー計算書もかならず見ましょう。
同じく粉飾決算で問題になったグレイステクノロジーでもこの予兆はでていましたね。
売上高成長と営業CFの逆行は黄信号です。
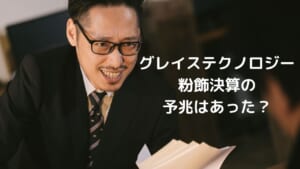
売掛金回転日数と取引先集中度をチェック
架空売上は売掛金として蓄積しやすいです。
とくに特定パートナーに偏った売掛金は要警戒。
今回のオルツは特定の販売先が少数で大半を占め、なおかつ調べると異業種だったんですよ。
特定科目の急増
特定の科目が急増しているのも要注意(今回は広告宣伝費)
一般的には循環取引に使われるのは仕入や広告宣伝費など損益計算書の科目が多いですが、過去にはソフトウェアを計上している企業もありました。
ですから貸借対照表もみないと駄目ですね。
IR資料と第三者情報をクロスチェック
IRのKPIは客観データが伴うか?
SNSや業界メディアの声も参考に。
SNSではオルツの疑惑は結構出てたんですよ。
「上場直後×急成長×赤字」の組み合わせは要デューデリ
特にグロース市場では内部統制が成熟していないケースが多い。
粉飾決算は税務上では余分に税金を払ってくれているだけですから、税務署から指摘は基本ありません。
そうなると外部のチェックは監査法人のチェックがほとんどです。
今後は監査法人がどこなのかという観点も重要になりそうです。
まとめ
今回は「オルツ不正会計の真相と答え合わせ|第三者委報告で学ぶ投資リスク」と題してオルツの第三者委員会の発表があったので過去記事の答え合わせでした。
数字は嘘をつかないが、嘘つきは数字を使う。
第三者委員会報告で“9割水増し”が証明され、財務三表の基本チェックの重要性が改めて浮き彫りになりました。
今後は訂正後決算・上場維持審査・訴訟リスクが株価を左右します。
短期的にはボラティリティが高く、損切りルールの徹底が肝要となりそうです。
「期待のAI銘柄」が一転して監理銘柄。
この事例は、“ストーリー”より“数字と仕組み”を信じるべきだと私たちに教えてくれる反面教師ですね・・・
粉飾決算についてもう少しよく知りたい方はこちらの本がおすすめです。