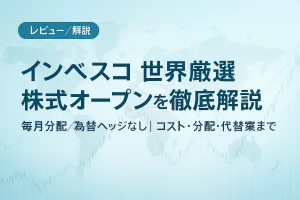「債券より高い利回りが欲しい。でも株ほど値動きが激しいのは不安」
そんな投資家のニーズに応える形で、日本初の日々で設定・解約可能なプライベート・クレジットファンドが登場しました。
ファンド名は「SBI オルタナティブ・ハイインカム・セレクト・ファンド(年4回決算型)」。
非上場企業向け融資という“オルタナティブ投資”の一種を、少額から手軽に組み入れられる画期的な仕組みです。
本記事では、プライベートクレジット市場の基礎からファンドのメリット・リスク、購入方法までを投資家目線で徹底解説します。
プライベートクレジットとは
まじは今回の話の前提となるプライベートクレジットとはなにか?というところから見て言いましょう。
定義
銀行や公募債を介さず、ファンド等が直接企業に貸付を行う“非公開ローン市場”。
それがプライベートクレジットです。
非公開ローンや担保付き債権などで構成されています。
高いインカム収益を源泉とする優れたリターンと、プライベート資産特有の安定した値動きが期待されています。
市場規模
世界の運用残高は約2.1兆ドルに達し、過去10年で約4倍に拡大しています。
低金利時代の代替投資として世界的に急拡大しているとのこと。
つまり、かなり伸びている市場であるってことですね。
国内の状況
日本でも2024年以降リテール向けプライベートクレジット投信が相次ぎ誕生。
機関投資家中心に需要が高まりつつあるとのこと。
ただし、現時点ではオルタナティブ資産に投資を行う投資信託は、最低投資額500万円以上で、月1回の基準価額と購入申込み、四半期解約で解約代金は数週間後の支払いなど、解約の上限設定も含めて、流動性が低く、かつコストの高さを考えるとかなりハードルが高かったんですよ。
ソーシャルレンディングとの違い
なお、いろいろ問題があったソーシャルレンディングと「貸付ビジネス」という点は同じですが似て非なるものです。
違いをざっくりまとめるとこんな感じです。
| 比較項目 | ソーシャルレンディング(融資型クラウドファンディング) | プライベートクレジット(ダイレクトレンディング) |
|---|---|---|
| 資金の流れ | インターネットプラットフォーム経由で個人投資家 ➜ ファンド ➜ 中小企業・不動産案件 | 専門運用会社が組成するファンド ➜ 主に未上場の中堅〜大型企業 |
| 投資商品 | 案件単位(1万円前後から)/期間は 3 か月〜3 年程度 | 投資信託・インターバルファンドなど/5 年以上が一般的 |
| 想定利回り | 年3〜10%(案件・事業者で差が大きい) | 年7〜10%前後(ローン・シニア担保付きでスプレッド確保) |
| 主な規制 | 第二種金融商品取引業(FIEA)登録が必須 – 金融庁指導で情報開示強化中 | 投資信託法・海外ファンド規制+機関投資家向けの監督枠組み |
| 借り手規模・用途 | 小規模事業者や不動産 SPV 等、銀行融資が届きにくい領域 | 企業価値 2〜20 億ドル程度のミドルマーケット企業が中心 |
| 流動性 | 途中解約不可(満期まで待つ)/セカンダリー市場なし | ファンドのルール次第(日次換金型も登場)だが基礎資産は非流動 |
| 情報開示 | 案件概要は公開されるが貸付先匿名組合が多く透明性に課題 | 四半期 NAV・コベナント開示など機関投資家水準のレポート |
| 代表的リスク | 貸し倒れ・運営会社倒産・情報非対称 | バリュエーションの遅延・流動性低下・企業レバレッジ上昇 |
| 市場規模 | 国内残高は数千億円規模で横ばい | 世界で約2.1兆ドル、5年で倍増ペース |
簡単にいえば規模の違いです。
ソーシャルレンディングは“案件型”のミニファンド。
クラウドファンディング感覚で少額投資し、償還まで資金を預けっぱなし。
ソーシャルレンディングはポンジスキームまがいの不祥事も起き、貸し倒れ・運営会社破綻が投資家損失の主因でした。
そのため、金融庁は登録業者かどうかを必ず確認するよう呼びかけています。
プライベートクレジットは機関投資家向けに発展してきた“私募ローン市場”。
近年は投資信託経由でリテールにも解禁されてきました。
ソーシャルレンディングで問題が多発したので、「貸付ビジネス」というとイメージは悪いですが、プライベートクレジットの方が比較的規模の大きい企業に、リスクが分散されて貸付されており、安全性は高そうです。

SBI オルタナティブ・ハイインカム・セレクト・ファンド(年4回決算型)とは
それでは今回の本題である「SBI オルタナティブ・ハイインカム・セレクト・ファンド(年4回決算型)」について詳しく見ていきましょう。
概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | SBI オルタナティブ・ハイインカム・セレクト・ファンド(年4回決算型) |
| 設定日 | 2025年9月9日(予定) |
| 投資対象 | パブリック・クレジット、プライベート・クレジット |
| 主要投資ファンド | KKR クレジット・インカム・ファンド(KKC) SPDR ブラックストーン・シニアローン ETF(SRLN) フランクリン・シニアローン ETF(FLBL) ジャナス・ヘンダーソン・B-BBB CLO ETF(JBBB) SPDR SSGA IG パブリック&プライベートクレジット ETF(PRIV) |
最近流行りの海外のETFに投資をする投資信託ということですね。
主要投資ファンド
投資ファンドについてもご紹介しておきましょう。
| ティッカー | ファンド正式名 | 主な投資対象 | 分配利回り* | 総経費 | AUM(純資産) | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KKC | KKR Credit Income Fund | 欧米のシニアローン+ハイイールド債+プライベートクレジット | 8.4%(現行利回り) | 1.1% | 約A$23億 | プライベート案件への直接パイプを確保し、9%超のYTMで高インカムを狙う |
| SRLN | SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 米ドル建てファーストリ・エン・シニアローン | 7.68%(30日SEC) | 0.70% | 69.9億USD | 変動金利なので金利上昇局面のクッション。AUM最大で流動性◎ |
| FLBL | Franklin Senior Loan ETF | レバレッジド・ローン(BB〜B中心) | 6〜7%(直近分配ペース) | 0.45% | 11.9億USD | SRLNより小粒だがコストが低くアクティブ運用で差別化 |
| JBBB | Janus Henderson B-BBB CLO ETF | BBB〜BB級CLO債券トランチ | 7.92%(12か月分配) | 0.48% | 13.6億USD | 投資適格すれすれのCLOでスプレッドを上積み。分散効果大 |
| PRIV | SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF | IG社債+プライベートクレジット(Apollo提携) | 5.32%(YTW) | 0.70% | 1.45億USD | 投資適格×プライベートのハイブリッド枠でディフェンシブ補完 |
*利回りは2025年7月末データ。分配頻度はいずれも“毎月”ですが、KKCのみオーストラリア上場 CEF のため為替リスクはAUD→USD→JPY経由で乗ります。
どれもかなり高い利回りとなっているんですよ。
手数料
| 区分 | SBI オルタナティブ・ハイインカム・セレクト・ファンド(年4回決算型) |
|---|---|
| 実質信託報酬 | 年1.5204%程度 |
| 購入時手数料 | 購入価額に3.3%(税抜3.0%)を上限として、販売会社が独自に定める率 |
| 信託財産留保額 | なし |
信託報酬は1.5204%程度と他の投資信託と比べると高めです。
組入れETF平均0.57%+国内投信コスト0.95%という計算です。
ちなみにプライベートクレジット市場の投資信託として先行して「アレス・プライベート・クレジット戦略ファンド」という商品がありますが、年1.39%+ファンド年1.25%+成功報酬。「ブラックストーン・プライベート・クレジット・JPYファンド(毎月)」は年2.669%+成功報酬となっています。
それらと比較するとかなり安くなっていますね。
なお、購入時手数料は3.3%上限となっていますが、おそらくSBI証券などネット証券なら0円かと思われます。※購入前に確認してください。
利回り
| 項目 | 本ファンド | 先進国社債ETF | 国内REIT |
|---|---|---|---|
| 想定利回り(分配込年率) | 7〜9%※ | 3〜4% | 4〜5% |
| ベータ(株式相関) | 0.3〜0.4 | 0.6〜0.7 | 0.7〜0.8 |
| 実質コスト | 1.5%前後 | 0.1〜0.2% | 0.3〜0.5% |
※利回りレンジは投資対象ETFの直近分配実績から試算。市場環境で変動。
利回りは債券やREITと比べるとかなり高くなっていますね。(過去のデータですが)
株式との相関関係が低いのも分散先としてはメリットになりそうです。
知っておきたいメリット・デメリット
本ファンドはかなり尖った商品となります。
メリット・デメリット(リスク)はあらかじめ知っておきましょう
メリット
主なメリットは以下の通り。
- 分散効果:伝統的債券・株式と低相関でポートフォリオ安定化。
- インカムゲイン重視:四半期分配でキャッシュフローを可視化。
- 低ベータ:経済ショック時でも価格変動が比較的小さい傾向。
- 少額から投資可:従来500万円以上必要だったプライベートクレジットに少額からアクセス可能
このファンドはメインで利用するというよりも伝統的債券・株式と相関関係が低いという特徴や経済ショックでの価格変動が少ないことを活かした分散狙いが主な使い方となりそうです。
デメリット(リスク)
次はデメリットです。
ほとんどSBI オルタナティブ・ハイインカム・セレクト・ファンド(年4回決算型)独自のデメリットというよりもプライベートクレジット市場のリスクという感じですね。
| リスク | 内容 | 対応策 |
|---|---|---|
| 流動性 | 上場ETF経由とはいえ基礎資産は非公開ローン。市場ストレス時にスプレッド拡大。 | 解約タイミングを分散、流動資産比率を確保 |
| デフォルト | 米プライベートクレジットのデフォルト率は3〜5%に接近との見方。 | 分散投資・シニアローン中心で優先債権を確保 |
| 評価手法 | 非上場資産はマーケットプライスが乏しく、公正価値評価にブレ。 | NAV乖離を注視、目論見書で算定方法を確認 |
| レバレッジ規制 | 海外ETFが内部レバレッジを用いる場合、規制変更で収益性低下の恐れ。 | ポートフォリオETFの開示資料を定期チェック |
取り扱い証券会社
取り扱い証券会社は
となっています。
購入時手数料の書き方を見る限り、他社にも開放すると思われます。
公募投信扱いのため一般の方も購入可能です。
まとめ
今回は「『SBI オルタナティブ・ハイインカム・セレクト・ファンド(年4回決算型)』爆誕。少額からプライベートクレジットへ投資可能に」と題してSBI オルタナティブ・ハイインカム・セレクト・ファンド(年4回決算型)についてみてきました。
ポイントは「高インカム×日次流動性」。
従来のプライベートクレジットへ投資する投資信託と比べハードルが一気に下がったという部分が大きいですね。
かなり面白い投資信託かと思いますが、まずは資産全体の数%以内を目安に試験導入し、値動きや分配パターンを見極めるのが無難かもしれません。