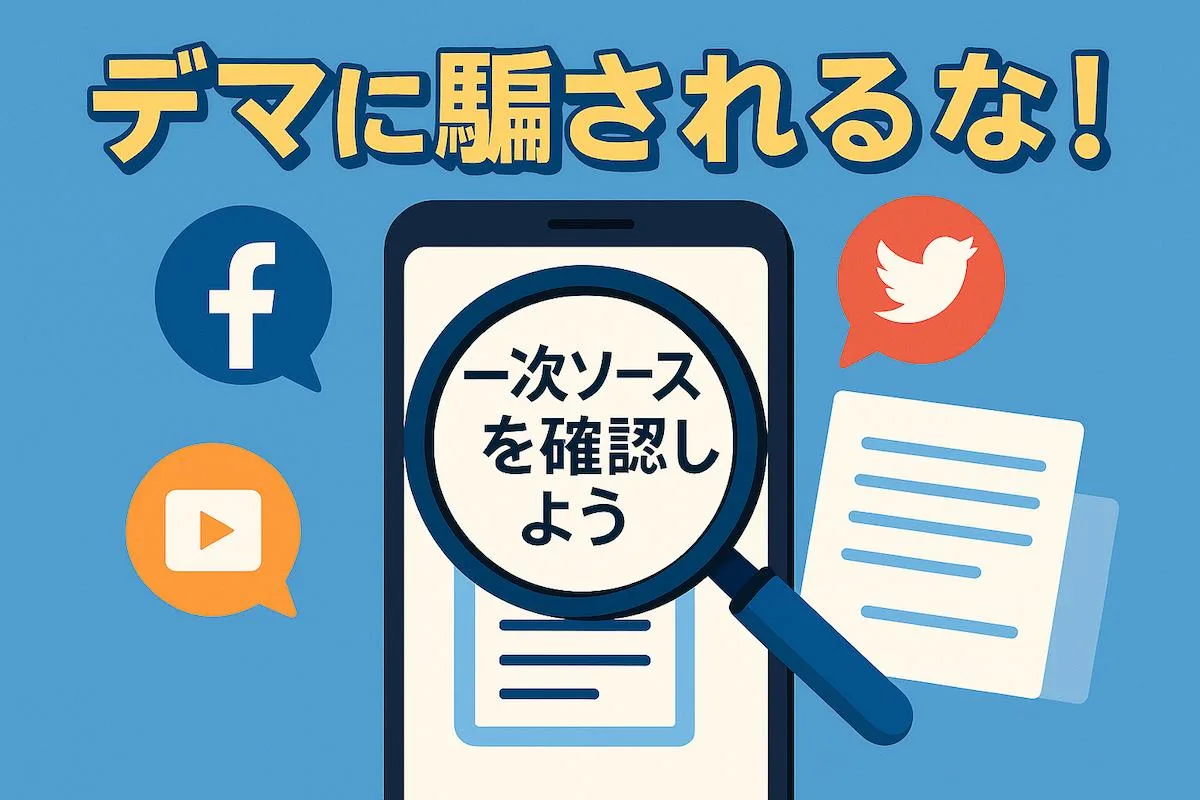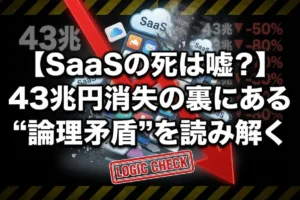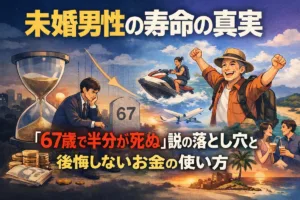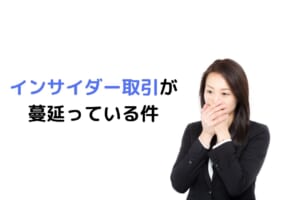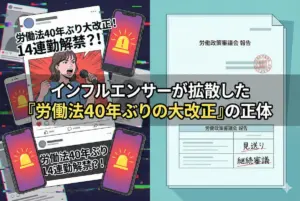SNS のタイムラインを眺めていると、刺激的な見出しや迫力ある画像が秒単位で流れてきます。
ところが 2025 年 5 月に内閣府が実施した調査では、回答者の約 50 % が「SNS で見聞きした 15 件の誤情報のうち 1 件以上を正しいと信じた」ことが明らかになりました。
デマといえば最近は選挙で話題ですが、政治の世界だけではなく、金融や経済の話でもデマ情報がかなり出回り騙されてしまう人もかなり出ているんですよ。
つまり “情報の大洪水” 時代では、私たち全員が誤情報へ踏み出すリスクを抱えています。
そこで鍵となるのが 「一次情報の確認」。
この記事ではデマが生まれ拡散する仕組みをひもときつつ、“一次情報確認術” を徹底解説します。
読み終える頃には、あなたも 自分で真偽を見極めるファクトチェックの達人 です。
デマが拡散する 3 つのメカニズム
まずなぜデマが拡散されるのかのメカニズムを抑えておきましょう。
エコーチェンバー現象
最近のSNSのアルゴリズムは「あなたが好む情報」を優先表示します。
同じ意見ばかり浴びると、異論を遮断する “エコーチェンバー” が完成。
結果としてデマでも「周りが言っているから本当だ」と錯覚しがちです。
政治関連や新型コロナなどのデマはこのエコーチェンバーによるものが大きいと言われています。
バイラルアルゴリズム
SNS は「いいね」「リツイート」「コメント数」「保存数」など反応が多い投稿を拡散させる設計。
怒りや不安を煽る誤情報はエンゲージメントが高く、真偽より “拡散力” が勝つ瞬間があります。
つまり、目立ちたい、バズりたいがためにデマを流すという動機もなりたつのです。
権威バイアスと “専門家の言葉”
肩書・フォロワー数が立派だと、人は無意識に信用度を上げます。
たいそうな肩書があると信じてしまいがちですが、そもそもSNSは自分で肩書をいくらでも名乗れます。
肩書ではなく 根拠 があるかを見極めましょう。
肩書がそもそもウソの可能性も考慮入れておきたいですね。
株関連のデマアカウントはほとんどプロフィールがウソばかりだったりします。
一次情報(一次ソース)とは何か ─ 二次・三次情報との違い
デマに対抗するためには一次情報にあたるのが一番だと言われてます。
そもそも一次情報とはどのようなものなのでしょう。
一次情報(Primary Source)
一次情報(一次ソース)とは当事者・公式機関が発表した元データや原文のことです。
一番はじめの情報ってことですね。
例えば政府統計、企業の IR 資料、裁判所判決文などがそれに当たります。
二次情報
2次情報とは一次ソースを引用・要約した報道記事や解説ブログ、動画などです。
最近は偽画像や動画がかなりリアルに作れるようになったため、ウソが混ぜ込まれることも散見されます。
三次情報
二次情報をさらに SNS やまとめサイトが再拡散したものを3次情報といいます。
ポイント:情報が「一次 → 二次 → 三次」と離れるほど、誤解や省略が混入しやすい。
一次情報の探し方(一次情報さがし方)
それでは一次情報はどのように探せばよいのでしょう?
ブックマーク管理
まずは信頼できる公的機関はフォルダ保存し “一次情報リスト” を作成するのがおすすめです。
発表主体の公式サイトを検索
省庁名+「PDF」「プレスリリース」で絞り込みで検索をかけるのも良いでしょう。
統計ポータルを活用
e-Stat、IMF、世界銀行などの公的な統計ポータルも活用できます。
学術データベースを使う
Google Scholar で論文タイトル→出版社 PDF が一次ソース。
AIはハルシネーションに気をつけて
最近はAIを使って情報を調べる方が増えています。
とても便利なんですが、ハルシネーションといって、AIが実際には存在しない、あるいは間違った情報をそれっぽく生成してしまう現象があるんですよ。
つまり、AIがデマの発信源なんてこともあり得るのです。
これには気をつける必要がありますね。
一次情報を見抜く 5 ステップ
それでは出ている情報の一次性を見抜くためにはどうすればよいのでしょう?
以下の5つを確認してみてください。
1. 発信主体の確認
URL のドメインが go.jp / ac.jp / who.int など公的かをチェック。
2. 日付と版の確認
同じ資料でも改訂版が存在。
最新ファイルか “Last updated” を確認。
3. 引用元リンクの追跡
記事から一次情報へのリンクがあるか。
なければ検索で突き止める。
4. 文脈の検証
統計の 母集団・期間・単位 が自分の課題に合うかを読む。
5. クロスチェック
複数の一次情報を突き合わせ、一致しない場合は保留または追加調査。
実例で学ぶデマとファクトチェック
それでは実際に最近あった実例を見てみましょう。
7月5日の大震災
まず、ここ最近で一番大きな話題となったのが7月5日の大震災の話です。
これは下記のマンガの話がSNS等で大きく拡散されたことによるものなんですよ。
作者自身は煽るつもりもなく、自身が見た夢の話を書いただけらしいのですが、夢の見た日と2025年の同じ日(7月5日)に震災が起こると編集で断定して書いたことで世界中で大きな影響に。
実際に中国や台湾からの旅行客が減るという大きな現象にまで発展してしまったのです。
気象庁・地震学会は根拠なしと否定しましたが、その状況は変わらず。
作者の竜樹諒(たつき諒)さんが本当に伝えたかったことを自費出版するという事態にまで発展しています。
生活保護世帯の 1/3 が外国人
最近大きな話題となったのが「生活保護世帯の 1/3 が外国人」というもの。
これもかなり回っていました。
実際は生活保護を受給している全世帯のおよ2.9%が外国人らしいのですが、、全体の受給世帯数は約165万という1カ月分の数値なのに対して、受給する外国人世帯数の方は12カ月の延べ数(約56万)で対比して「生活保護世帯の 1/3 が外国人」との話が出回ったのです。
具体的な数字もあったので信じた人も多かったデマですね。
「数字はウソをつかない。しかしウソつきは数字を使う」という言葉を思い出したい事例です。
三峡ダム決壊
また、少し前ですが、中国にある水力発電ダムである「三峡ダム」が決壊の危機にあるというデマが流れたこともあります。
決壊すれば多くの人が被害にあい中国の経済が死ぬ。
そして世界経済が死んで株が暴落するというのです。
実際株にも大きな影響がありましたね。
中国政府や自治体が否定するも騒動は収まりませんでした。
最近ではAIで偽画像や偽動画の作成も容易ですから、今後もこの手の話は増えてくると思われます。
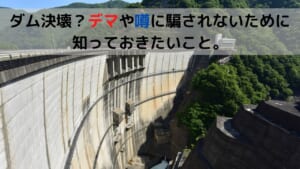
今日からできる対策
それではこのようなデマを信じてしまわないためにどうすればよいのでしょう?
拡散前の 30 秒ルール
- リンクをタップして全文を読む
- 出典の有無を確認
- 自分の感情(怒り・恐怖)が煽られていないか振り返る
特に重要なのが出典までしっかり確認することですね。
最近は新聞社もいい加減なので新聞社や雑誌の記事でも出典を確認することは重要です。
ちゃんと自分で一次情報を確認して本当だと判断できたものだけ拡散するようにしましょう。
信頼できる情報源リスト作り
また、信頼できる情報源を確認しておくことも重要です。
あらかじめリスト化しておくと便利ですね。
- 省庁・自治体/プレスリリース
- 国際機関(WHO、IMF など)
- 専門メディア(科学・法律系ジャーナル)
- 公認ファクトチェック団体(FIJ、AFP など)
まとめ ─ 情報の時代を賢く生き抜く
「デマは 100 回シェアされる前に 1 回の検索で止められる」。
私たち一人ひとりが 一次ソースを確認する習慣 を身につければ、誤情報の連鎖は必ず弱まります。
まずは “30 秒の立ち止まり” から始めてみましょう。
この記事が、あなたの 情報リテラシー強化 の第一歩となれば幸いです。